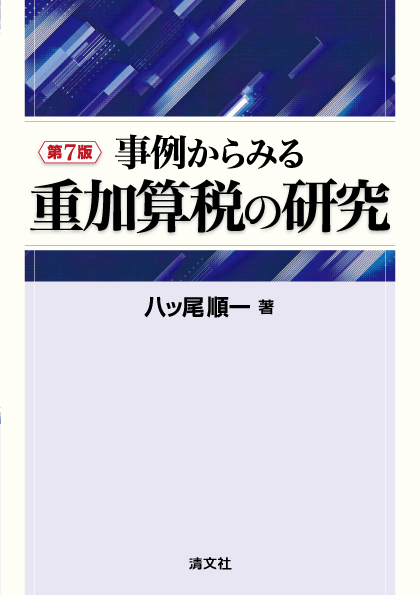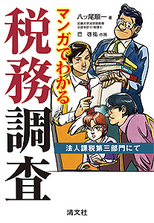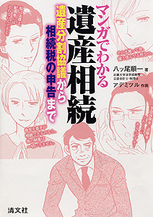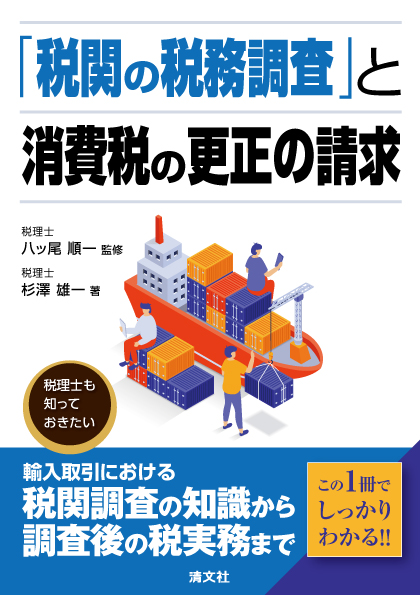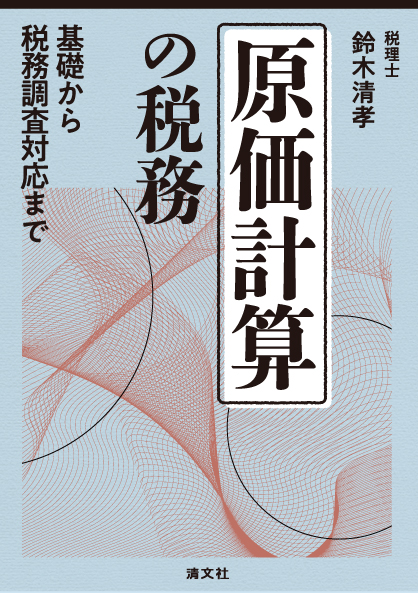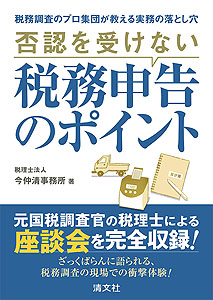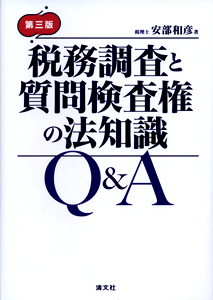改正国税通則法、施行後1年を検証する
~税務調査は変わったか?
【前編】
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
はじめに
平成25年1月1日から改正国税通則法が施行され、1年が経過した。
この改正では、法施行後における税務調査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、その施行前である平成24年10月1日から事前通知、修正申告等の勧奨の際の教示文の交付手続等が「先行的取組」として実施されているが、改正国税通則法に基づく新しい税務調査制度が実施されて以降、税務調査の現場において、税務当局や納税者にどのような影響を及ぼしているのか、2回に分けて検証することとする。
本連載の構成
1 税務調査の実地件数に対する影響
2 事前通知の法定化
3 物件の提示・提出(以上、今回)
4 留置きのケース(以下、次回)
5 印紙税の調査
6 調査終了後~申告是認・修正申告の勧奨・更正処分
1 税務調査の実地件数に対する影響
国税庁の平成24事務年度(平成24年7月から25年6月)の各税目の実地調査件数は、3割程度減少していると公表されている。すなわち、所得税の実地調査は、6万9,974件(前年9万8,687件)であり、前事務年度から3割減少している。
この減少の要因としては、「①1件当たりの調査日数増加(1件当たり1.3日増加)」や「②国税通則法の改正による研修や事務量の増加」が挙げられている。
法人税の実地調査も前事務年度より27.4%減少して、9万3,000件となっている。法人税の調査1件当たりの日数は2.6日増加し、11.7日となっている。
これらの減少原因は、国税通則法の改正による理由附記の範囲の拡大や法令遵守に係るチェック項目の増加による事務量の増加、改正国税通則法の研修などが挙げられている。
また、相続税の実地調査の件数も12,210件と、前事務年度に比べて1割強減少している。これは、改正による影響で事務量が増加し、さらに調査1件当たりの平均日数が13.9日(前事務年度12.7日)に増加したことが原因となっている。
相続税の実地調査の件数が減少していることから、国税庁は、平成26年1月から、所得税調査で行われている納税者に文書を送付し申告書の見直しを促す取組み(簡易な接触)を実施することになっている。
このように、所得税、法人税そして相続税の実地調査の件数は、国税通則法の改正によって、確実に減少しているのである。
2 事前通知の法定化
国税通則法74条の9では、
税務署長等は、国税庁等又は税関の当該職員に納税義務者に対し実地の調査において第74条の2から第74条の6までの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
として、調査に際し、事前通知をする旨を定めている。
法定化された「事前通知事項」は、次のとおりである。
① 実地の調査を行う旨
② 調査開始日時
③ 調査開始場所
④ 調査の目的
⑤ 調査の対象となる税目
⑥ 調査の対象となる期間
⑦ 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑧ 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
⑨ 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
⑩ 調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項
⑪ 事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、当該事項に関し調査ができる旨
これらの「事前通知事項」の通知は、原則として、納税義務者と税務代理人(税務代理権限証書を提出した税理士等)の両者に対して行うことになる。
国税庁は、事前通知を行う際に、当該職員に対し、納税者が理解しやすく丁寧に説明すべきと指導していることや、当該職員がこのような対応に不慣れで、ナーバスになっているためなのか、当該職員が電話等で事前通知を行う際には、間違えないように、文面を機械的に読み上げることが多い。
また、税理士に事前通知を連絡するとともに、納税者に対しても同様に連絡することになっている。従前は、税務代理人に調査の連絡をすれば、税務代理人にその旨を納税者に伝えることを依頼すればよかったのであるが、改正国税通則法では、双方に直接連絡することが求められている。
もっとも、納税者から事前通知の詳細を税務代理人から聞く旨の申立てがあれば、納税者に対しては、実地調査を行う旨のみ通知すればよいことになっている。
このように、事前調査の法定化(実質的にはその内容は変わらないのであるが)だけでも税務当局の手間が従前と比べ増えていることは明らかである。
3 物件の提示・提出
国税通則法74条の2では、
国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
と規定している。
ここでいう「物件の提示」とは、「当該職員の求めに応じ、遅滞なく当該物件(その写しを含む)の内容を当該職員が確認しうる状態にして示す」ことをいい、「物件の提出」とは、「当該職員の求めに応じ、遅滞なく当該職員に当該物件の占有を移転すること」をいう。
また、「必要があるとき」については、具体的な判断基準を法令等で明確に示すことができないことから、最終的には、その調査を担当している税務職員の判断によらざるを得ない。
しかしながら、事務運営指針において、
調査について必要がある場合において、質問検査等の相手方となる者に対し、帳簿書類その他の物件の提示・提出を求めるときは、質問検査権等の相手となる者の理解と協力の下、その承諾を得て行う。
として、当該職員に対し、相手方の理解と協力の下で実施することを指導している。
このような物件の提示・提出は、従前と大きく変わるものではないが、事務運営指針等でその運用を具体的に文言化されると、当該職員は自ずと、物件の提示・提出を行う際には慎重にならざるを得ない。また、税務調査に非協力的な納税者等のケースでは、物件の提示・提出を拒否され、説得することに(従前以上に)時間を要することも予想される。
そうすると、結果的に冒頭で述べたように、税務調査の日数が増えることになるのである。
〔凡例〕
事務運営指針・・・調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
(了)