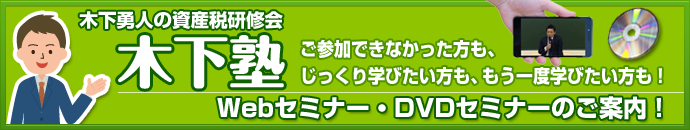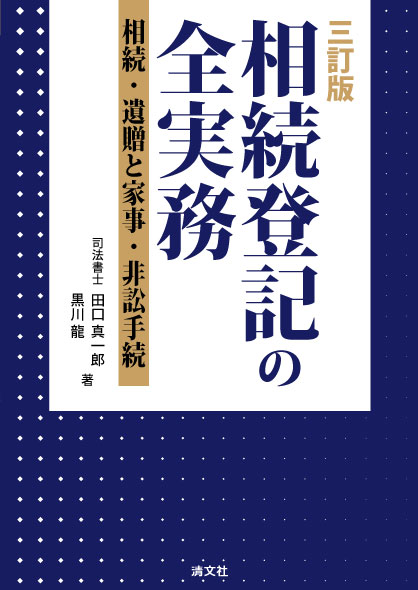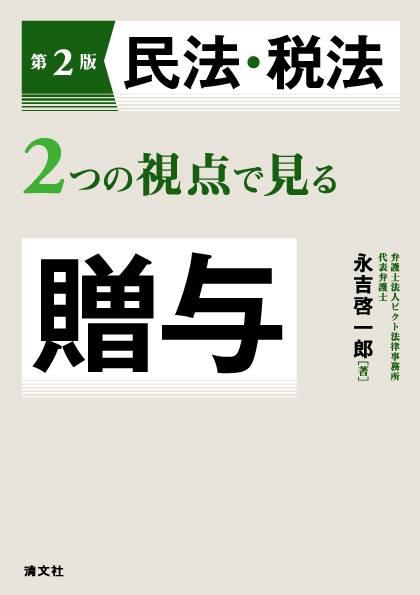《相続専門税理士 木下勇人が教える》
一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法
【第1回】
「特別寄与料に関する今後の相続実務と事前コンサル」
公認会計士・税理士
木下 勇人
1 民法改正による新設規定
現行民法では、被相続人の介護や看病などに尽くした「相続人」のみ、その貢献により被相続人の遺産の増加又は維持に貢献したと認められる場合、遺産分割に際して、相続分を増加させる「寄与分」の制度が存在する。つまり、相続人でない親族(例えば長男の嫁)が被相続人の介護や看病に尽くしても、現行民法上は遺言がない限り、相続財産を取得することはできない。
しかし、民法改正における「特別寄与料」の新設により、寄与した親族(相続人を除く6親等内の親族と3親等内の姻族。以下、「特別寄与者」という)は相続人に対して特別寄与料を請求できることになった(本制度の施行日は2019年7月1日)。
2 相続税申告実務における影響
(1) みなし遺贈
平成31年度税制改正により、この特別寄与料について、被相続人から遺贈により取得したものとみなし、相続税を課すこととされた(相法4②)。
(2) 2割加算の適用
上記(1)のとおり、みなし遺贈により財産の取得者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者となるため、相続税額につき2割加算の対象となる(相法18)。
(3) 支払う相続人側の処理
相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除する(相法13、21の15)。
(4) 修正申告・更正の請求等の「特則」対象
相続税法上で定められている修正申告や更正の請求等の「特則」の対象に、「特別寄与料を被相続人から取得した場合」が加わり(相法31②、32①七、35②五)、改正民法と合わせ、本年7月1日以後に開始した相続から適用されることとなった。更正の請求期間は、他の特殊事情が生じた場合と同様に、特殊事情が生じた日の翌日から4ヶ月以内となる。
3 相続手続における影響
(1) 各種書類への署名押印
特別寄与者には、あくまで相続人に対する特別寄与料の請求権のみ認められており、遺産分割協議には参加できない。つまり、遺産分割協議書への署名押印はないが、相続税申告書への署名押印は生じる。
(2) 特別寄与料の請求手続
特別寄与料の金額は、請求者と相続人との協議にて決定されるが、協議が整わない場合等は相続が開始したこと及び相続人を知った時から6ヶ月又は相続開始の時から1年以内に限り、家庭裁判所に審判の申立てを行うことが可能である(改正民法1050)。
特別寄与料を請求するためには、被相続人の介護や看病などに尽くしたエビデンスを残すことも実務上必要になるため、生前からの意識的な対応が望まれる。
4 特別寄与料に対する生前対策
税理士が「相続税申告」実務において留意すべき事項は上記2のとおりとなるが、あくまでこれは特別寄与者による特別寄与料の請求とその支払が生じた場合における対応である。つまり、事後的な処理に過ぎない。
検討すべきは、①特別寄与料を請求する特別寄与者の心理的負担、②特別寄与者が相続税申告書に署名押印することによる財産開示の可能性である。つまり、①特別寄与者が特別寄与料を相続人へ請求するということは親族間で遺恨を残すことになり、特別寄与者本人にも心理的に負担となる。また、②相続財産全てを相続税申告書で特別寄与者へ開示する結果となるため、相続人側からしても可能であれば特別寄与者へは未開示である方が望ましいと考える。
そこで、税理士として生前にアドバイスをするならば、特別寄与者が特別寄与料を相続人へ請求しない仕組み作りの提案ではないだろうか。
仮に、遺言や死亡保険金で長男の嫁に財産を残しても②は解決できない。これに対して、被相続人から特別寄与者へ生前贈与を実行すれば、①②も解決可能となる。相続又は遺贈により財産を取得しないため、3年内贈与加算も適用されない。また、被相続人から生前に感謝の気持ちを伝えることで介護をする方、介護をされる方もどちらも良好な関係が築けると考える。
以上より、民法改正を学ぶことにより「生前贈与」の必要性を説くという視点も、相続のコンサルティングを行う立場として有用と考える。
〔凡例〕
相法・・・相続税法
(例)相法32①七・・・相続税法32条1項7号
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。