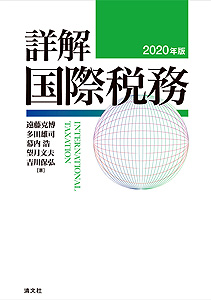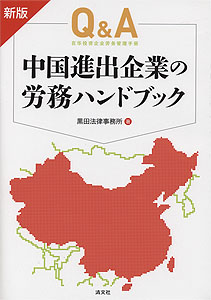『日米租税条約 改定議定書』
改正のポイントと実務への影響
【第1回】
「改正の概要及び利子所得免税」
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
1 概要
日米租税条約の改正については、昨年6月に基本合意に達したことが公表されていたが、その後、2013年1月24日に改正議定書に署名されるとともに、改正内容の詳細が明らかになった。同条約の改正は2003年以来となる。
改正の主な項目は4に掲載した表のとおりであるが、中でも重要な改正点は以下の3点である。
(1) 利子所得の源泉地国課税(税率10%)が原則として免除となったこと
(2) 仲裁制度が盛り込まれたこと
(3) 徴収共助条項の適用対象が大幅に拡大されたこと
2 発効時期
今後それぞれの国内手続(日本は国会の承認)を経て、両国間で批准書が交換されることにより効力を生ずる。
2003年の新条約締結時には、2003年11月6日に新条約に署名され、翌年3月30日に批准書が交換された。
3 適用対象・適用時期
この議定書に盛り込まれた新条約の内容は、次のものについて適用される(議定書15②)。
(a) 源泉徴収される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われ、又は貸記される額
(b) その他の租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度
上記にかかわらず、相互協議中の事案については、仲裁に移行する基準となる期間の2年の起算日は、この議定書が効力を生ずる日となる(議定書15③)。
また、情報交換、徴収共助の規定は議定書の発効日から適用する。
なお、教授免税の特典を受ける権利を有する個人は、議定書が効力を生じた後においても、それまで有している権利を失うときまで特典を受ける権利を引き続き有する。
4 改正の概要
〈日米租税条約の改正内容(平成25年1月24日署名)〉
※画像をクリックすると、PDFファイルが開きます。

5 利子所得に関する改正
(1) 原則として源泉地国免税となった
利子所得は、従来は、金融機関の得るものを除いて、利子の発生した国(源泉地国)において10%を限度税率として課税できるとされていたが、改正後は原則として源泉地国では免税となる。
例えば、日本親会社の米国子会社に対する貸付金の利子については、従来は居住地国である日本で全世界課税の中で利子所得も課税され、加えて源泉地国である米国でも10%の源泉徴収が行われ、日本における確定申告書上、外国税額控除により二重課税の一部排除を行うという仕組みをとっていた。
改正後は、米国での源泉地国課税は行われないことになるので、企業にとっては外国税額控除の申告に要する手間が省け、親会社側の外国税額控除の枠が足りないことにより二重課税が完全には排除できないという問題もなくなる。
日米双方の企業にとっては、資金のやり取りがしやすくなるという点で朗報である。
(2) 源泉地国免税の例外
次のものは、源泉地国課税の適用対象とされる(議定書4、新条約11②)。
このうち(a)は新設の規定であるが、それ以外は現行条約に同様の規定がある。
(a) 債務者若しくはその関係者の収入、売上、所得、利得その他の資金の流出入、債務者若しくはその関係者の有する資産の価値の変動若しくは債務者若しくはその関係者が支払う配当、組合の分配金その他これらに類する支払金を基礎として算定される利子又はこれに類する利子であって、一方の締約国において生ずるもの(10%限度課税)(新条約11②(a))
(b) 不動産により担保された債権又はその他の資産の流動化を行うための団体の持分に関して支払われる利子等の額のうち、法令で規定されている比較可能な債権の利子の額を超える部分(源泉地国の法令に従って課税できる)(現条約11⑨、新条約11②(b))
(c) PEに実質的に関連する利子(現条約11⑥、新条約11⑤)は事業所得となる。
(d) 利子率が独立企業間利子率を超える部分(現条約11⑧、新条約11⑥)は源泉地国において5%限度課税
〔凡例〕
・議定書・・・所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書
・条約・・・所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約
(例)議定書15②・・・所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書第15条2項
【参考】 財務省ホームページ
・「アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書が署名されました」
・「アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書のポイント」
(了)