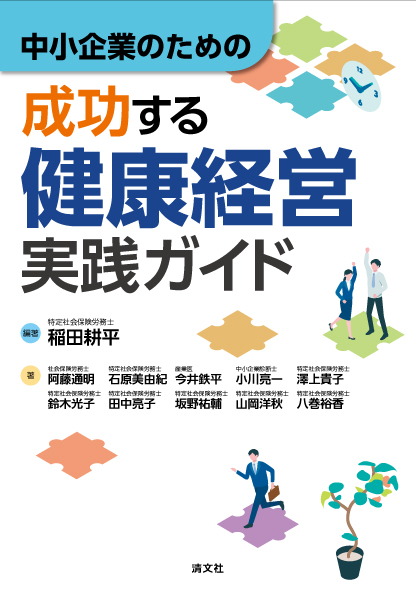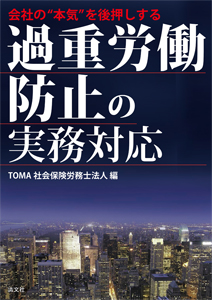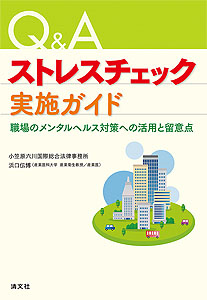社長のためのメンタルヘルス
【第1回】
「「社長のためのメンタルヘルス」の考え方」
特定社会保険労務士
第一種衛生管理者
産業カウンセラー
寺本 匡俊
◆連載開始にあたって◆
本連載は、本号から月1回、計10回程度の予定で掲載が始まる。職場におけるメンタルヘルスに関する書籍やインターネットサイトは多数あるが、その大半は、労働法の趣旨に則り、従業員の保護(メンタル不調の予防)という観点で語られている。
「業務上の理由」によると考えられる精神疾患は、労災認定される可能性があるばかりでなく、しばしば報道されるように、原因が過重労働やハラスメントとみなされた場合、労災とは別に損害賠償請求の民事訴訟に繋がるおそれもあるため、労働者保護は経営者・人事部門にとって必要不可欠な措置である。
一方で、使用者も医学的には労働者と同じ「生身の人間」である以上、多種多様なメンタル不調や、さらに診療を要するレベルの精神疾患と無縁ではない。傾向としては、社長に選ばれ、重責を担い続ける方々は、一般従業員よりも心身ともにタフであろうと考えるが、過重労働が典型例であるように、「メンタルが強いから大丈夫」というものではない。他方、予防という観点からすれば、労働者に対して行われている法定の予防措置や、福利厚生も使用者の健康保健に役立つ。
本連載では以上のような考え方に基づき、社長のためだけの特別なメニューを紹介するものではなく、労使に限らず共通してメンタルヘルスに資する方策や発想を、確認・検討する。また、職場における注意事項のみならず、メンタルヘルスは生活習慣も重要な要素であることにも言及する。
1 「社長」についての考え方
本連載のタイトルは経営トップに強く訴える効果を求めて、インパクトのある「社長」という言葉を使っている。一方、本連載では以下の理由により、「社長」はより広範な概念として用いる。例えば、経営の最高責任者が実質的には会長であることもあろうし、労働法で守られていないという意味においては、役員全般も個々人で健康管理を行う必要がある。
同様に、地方や海外の拠点のトップは、その限られた地域の企業活動においては、営業や人事など日常的に、社長に準ずる責務を負う。また、法人格はなくとも、個人事業主で従業員を雇用している場合、健康管理上は社長と同様の配慮が必要となる。
詳しくは次回の話題とするが、「社長ならではの大変さ」というものは、登記上の代表取締役ばかりではなく、上記のような事業経営に責任を有する方々が共通して背負うものがあり、本連載においては、そのような社長に準じる立場の方々も広く含めて、便宜的に「社長」と表現する。
2 「他覚」についての考え方
本項の「他覚」についての考え方も、前出の「社長」と同様、本連載に限っての発想を含んだ広範囲のものとして取り扱う。「自覚」は日常用語であるが、その対語である「他覚」は、労働安全衛生法における法律用語である。各社で行われている定期健康診断を規定した同法第66条には次のような定めがある。
(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
上掲のカッコ内にある「第66条の10第1項」にある検査とは、ストレスチェック制度のことで、これが除かれているのは、「医師による」ばかりではなく、例えば保健師でも合法であることによる。また、同条において詳細は「厚生労働省令で定める」と規定されている。この省令は、労働安全衛生規則という。次に同規則の第44条の関連個所をみる。
(定期健康診断)
第44条 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(以下、省略)
後半は省略したが、健診項目は全部で11点ある。そのうちの第1項が「既往歴及び業務歴の調査」、第2項が「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」であり、第1項及び第2項の「自覚症状」については、近年では一般に、事前に検診機関から送られてくるマークシート方式の自己申告で診断が行われている。
一方、「他覚症状」であるが、厚生労働省がホームページに公表している「定期健康診断等における各検査の概要(現状)」という資料をみると、過去の通達を引用しつつ、次のとおり解説がなされている。定期健康診断は法律において「医師による」と定められているため、ここにおいても、「医師の判断」でなされることになっている。通常、健診会場では「内診」などと呼ばれ、医師が聴診器ほかの器具による「問視診」により、健康状態を調べる。
・「他覚症状」に関するものについては、受診者本人の訴えおよび問視診に基づき異常の疑いのある事項を中心として医師の判断により検査項目を選定して行なうこと。なお、この際医師が本人の業務に関連が強いと判断した事項をあわせ行なうものとすること。(昭和47基発第601号の1)
このように法定の健康診断においては、「他覚」の「他」とは医師のことであるが、本連載は基本的に、医療にアクセスする前の段階における現場での予防を目的としている。したがって、他覚とは本人以外の上司や同僚、経営・人事や健康管理部門、広くは家族や友人まで、周囲の人たち全員を意味する。
具体的にいうと、うつ状態の前駆症状としてよく挙げられる「服装や髪型の乱れ」であるとか、簡単な文章での「誤字脱字の増加」といった、必ずしも本人が自覚していなくとも、周囲の他者が気付くような兆候も、メンタルヘルスでは重要な判断要素となる。この点は後の回でも改めて触れることになるが、労働法令では「労働者の心の健康の保持増進のための指針」にある「ラインによるケア」に類似する。
3 士業の皆様へ
本誌「Profession Journal」の読者層には、税理士や公認会計士ほか、いわゆる士業の方々が多いと聞いている。前述のように、個人事業であっても従業員を雇用している場合は、本連載における「社長」に当たるのみならず、個人のみの経営であっても顧問契約に基づく活動をしている場合、顧客の経営者に接する際に、前述した「他覚症状」のおそれを感じることもあり得る。
また、経営が多忙で自身の健康管理になかなか手が回らない社長に対し、日常的な接点があり信頼関係も築いている顧問から、メンタルヘルスを含む健康保健に関する情報提供や助言を行うことができれば、顧問契約の本業に加えて、健康管理という別の視点からも社長に、ひいては顧客の事業全体に対し役立ち得る。
このような観点から、本連載においては、健康管理とは直接関係のない分野で活躍中の士業各位におかれても活用可能な情報を提供できるように配慮する。もちろんご自身の健康管理にもお役立ていただければ幸いである。
4 最後に ~今後の連載予定について~
今後の連載概要について、今の時点の予定としては、前半に総論的な事柄、後半には各論(ただし、なるべく多くの方に共通すると思うもの)を記事とすべく準備している。総論的な事柄としては、社長ならではの大変さ(経営者に多いストレス要因)、メンタル不調とは何か(うつばかりではない)、予防の考え方などを予定している。
各論においては、例えば、すでに労働者に対し各社で実施中の労災防止やストレスチェック等において、その対象を社長にまで広げるという効率的な方法を検討いただく意義について触れたい。また、この先の動向次第であるが、時事的な課題としては、コロナ禍や、それに伴うテレワーク等におけるストレスの対処についても話題とすることも検討しており、日常の業務・生活習慣の管理にお役立ていただければと思う。
(了)
「社長のためのメンタルヘルス」は、毎月第3週に掲載します。