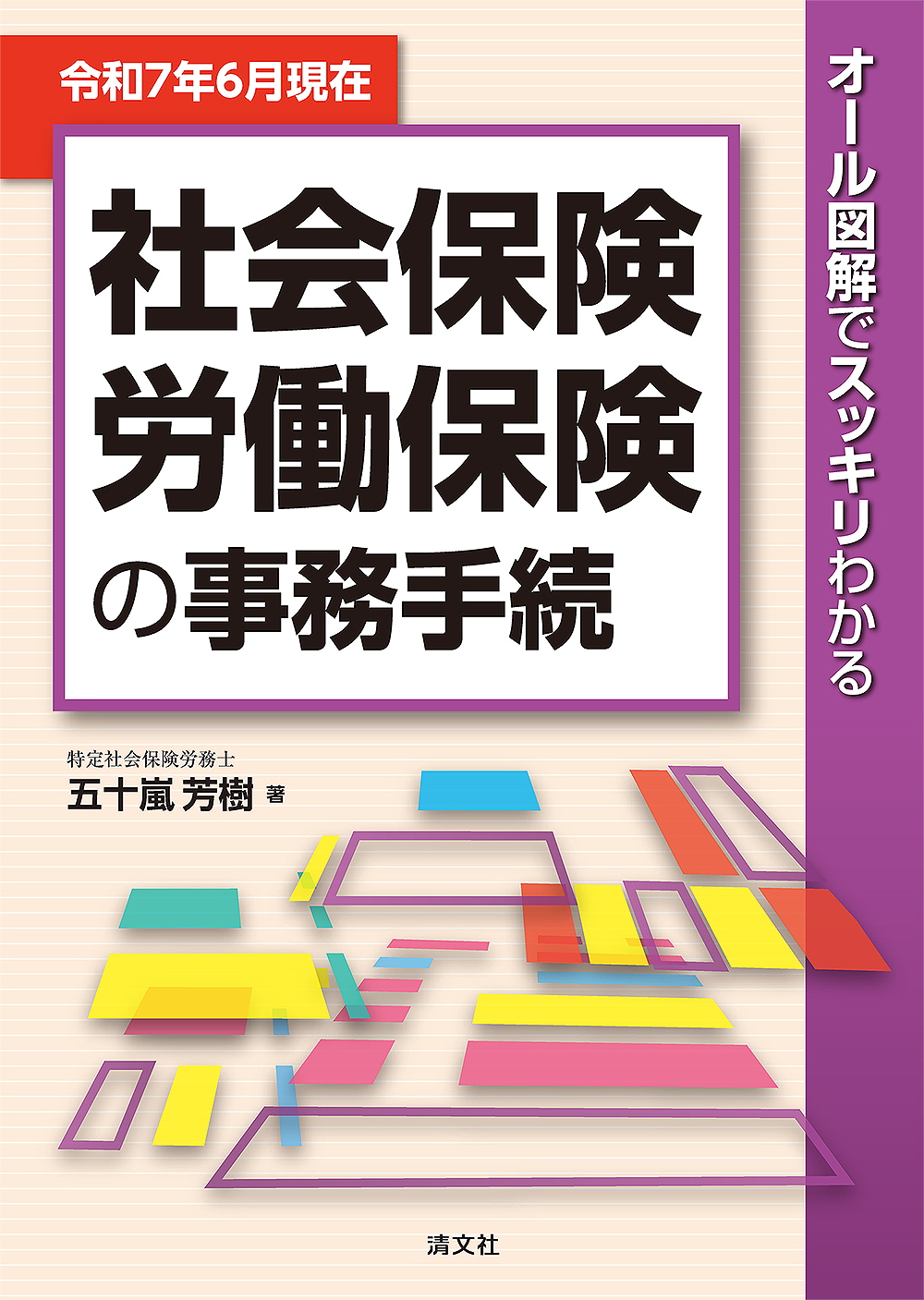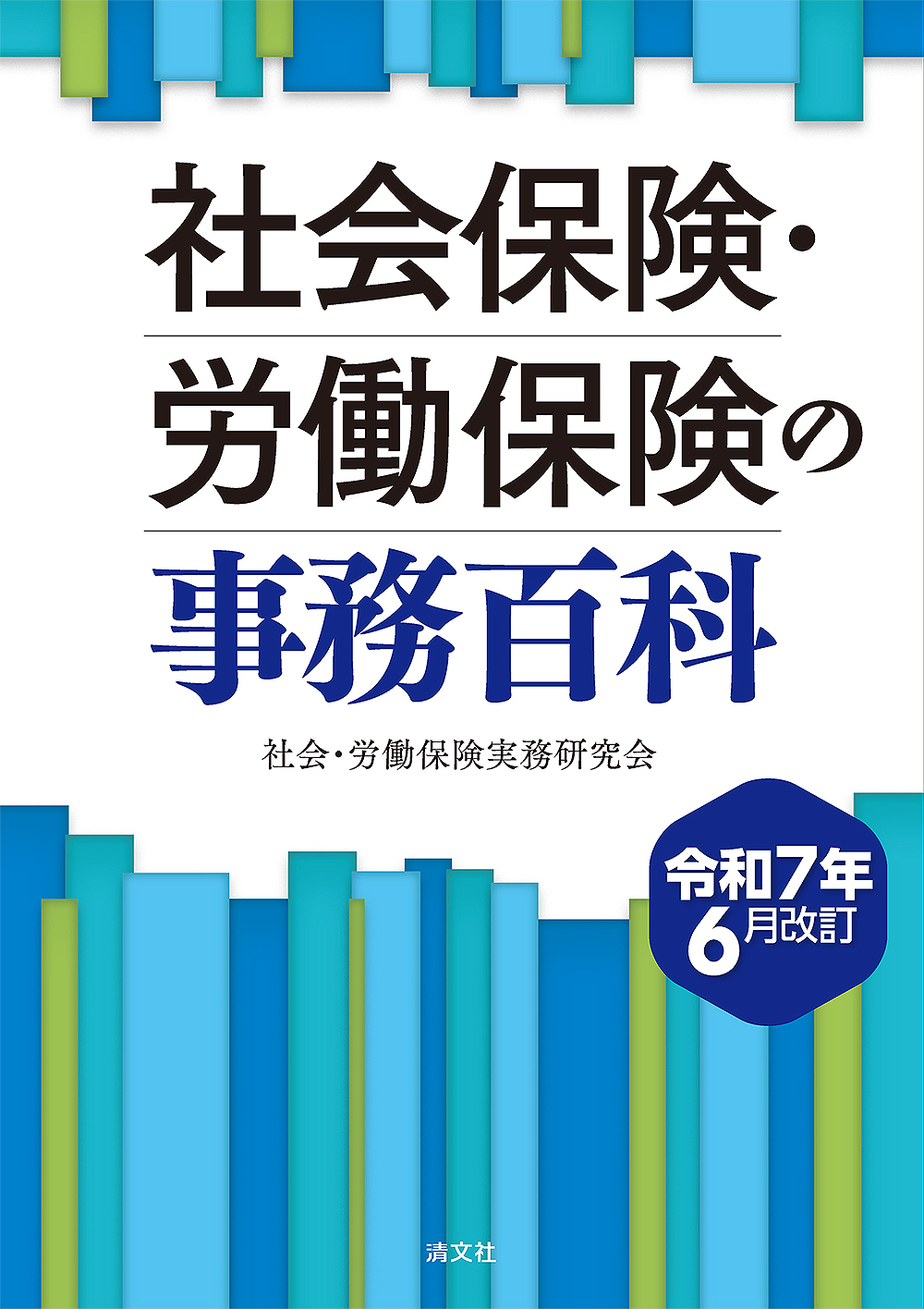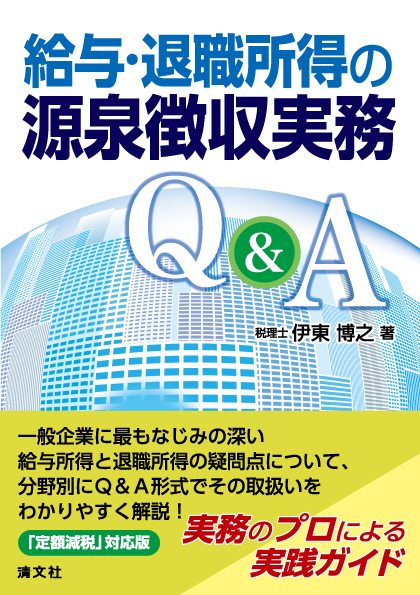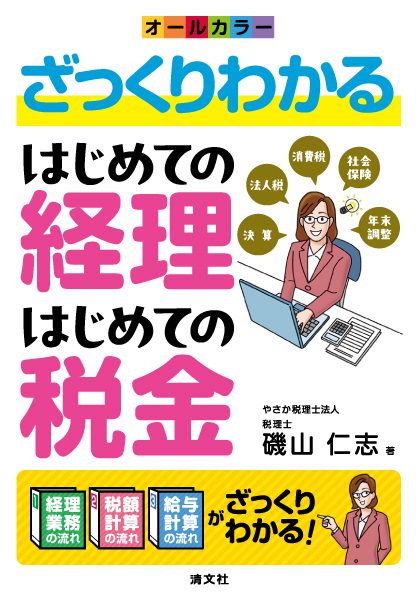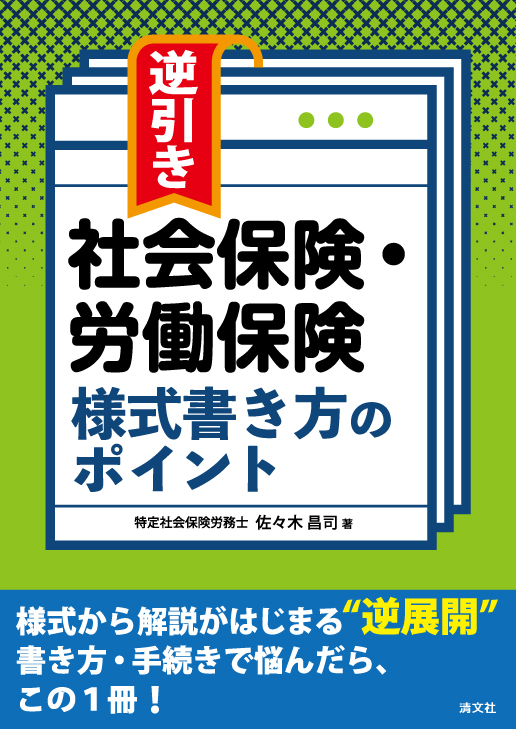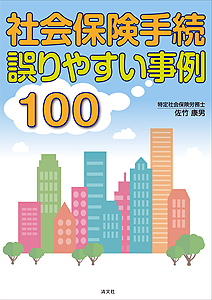賃上げ実施に伴う企業の労務上の留意点Q&A
【第1回】
「ベースアップ検討の際の3つのポイント」
~昇給原資・目的・理由~
社会保険労務士 富山 直樹
【Q】
【A】
次の3点が主な留意点としてあげられます。
① 昇給原資
② 目的
③ 理由
なお、以下で上記の留意点につきそれぞれ詳しく解説します。
●○ 解 説 ○●
① 昇給原資
例えば、筆者がクライアントの社長より「従業員Aの給料を24万円から5万円上げて29万円にしたい」と相談を受けたとする。
この場合、昇給原資は単純に5万円×12ヶ月の年間60万円では足りない。
昇給に伴い、会社が負担する保険料も増額することはご存じの方も多いだろうが、具体的にどのくらい上がるのか。東京都の一般事業会社でAが40歳未満として計算すると、今回のケースでは下記のようになる。
- 社会保険料
従前等級:240,000円 昇給後等級:300,000円 - 健康保険料会社負担分(1ヶ月)
従前:12,000円 昇給後:15,000円 - 厚生年金保険料会社負担分(1ヶ月)
従前:21,960円 昇給後:27,450円 - 子ども・子育て拠出金(1ヶ月)
従前:864円 昇給後:1,080円 - 雇用保険料会社負担分(1ヶ月)
従前:2,280円 昇給後:2,755円 - 合計(1ヶ月)
従前:37,104円 昇給後:46,285円 - 差額:1ヶ月9,181円(年間110,172円)
※上記につき2024年2月現在の保険料率にて計算
つまり、今回の内容でAの給与を月5万円昇給させると、給与のほかに社会保険料・雇用保険料の支払いだけで、年間約11万円が追加で必要となる。
社長の希望は「Aの給料を5万円昇給させたい」なのか、それとも「Aの昇給原資が年間60万円あるので還元したい」なのかを正確に確認しておきたい。
もし社長の希望が、後者の「昇給原資が年間60万円あるので還元したい」であった場合、単純にAの給料を5万円昇給させると、昇給原資を上回り赤字となってしまう恐れがある。
そのため、安易に「〇〇円昇給」というのではなく、昇給原資に対して、昇給額と同時に社会保険料・雇用保険料の上昇についても留意する必要がある。
② 目的
上記質問によれば、昇給の理由は、昨今の「物価の高騰」に伴うものである。大企業でも「インフレ手当」というような形で従業員の生活を補助するために導入を進めている会社も存在する。
一時金として賞与に上乗せするような形で支給する場合は、事務作業の負担も少ない。
しかし、月額給与に手当として支給する場合は注意が必要である。
まず、就業規則(賃金規程)を改定し、インフレ手当についての記載をする必要がある。そして、インフレ手当の内容について記載をする際には「支給事由」を記載しなければならない。
具体的には「物価の高騰が落ち着いたらどうするのか」、「そもそも物価高騰の判断基準をどうするのか」といった内容である。また、一時的に支給するのであれば「その期間はいつまでなのか」といった内容も必要となる。
あくまで「物価の高騰」に伴って一時的に従業員の生活を助けることが目的であれば、一時金として賞与に上乗せするような形で支給することが、会社にとって負担の少ない方法であると考える。
また、「物価の高騰」もさることながら、そもそものベースアップを実施するにあたっても、その実施する目的をハッキリさせることが重要である。次の「③ 理由」に関係する内容なので、以下において併せて解説する。
③ 理由
上記②と続く内容であるが、結論を先に述べると、昇給の目的と理由をハッキリさせ、従業員と共有することが重要である。
わかりやすくするため、2023年に起きたスポーツの出来事で具体的に解説する。
2023年は、プロ野球において阪神タイガースが1985年以来の日本一を達成した。シーズンが始まる前に監督の岡田彰布氏は球団に「バッターがフォアボールを獲得した際の年俸査定を上げてくれ」と依頼し、その情報を選手にも共有した。
プロ野球選手は1年間の成績や1つ1つのプレーについて細かく査定がなされ、ポイントを付けられ来年度の年俸が決定する。つまり、岡田監督の依頼はその「査定項目を変更し昇給理由としてくれ」というものである。
球団及び監督としては、
優勝したい
![]()
試合に勝ちたい
![]()
作戦的に攻撃でもっと塁に出る回数を増やしたい
![]()
打つことばかりに意識を向けないで、フォアボールでも塁に出てほしい
![]()
フォアボールの査定を上げよう
もちろん優勝の要因はこの1つの項目だけではないだろうが、選手の昇給の理由と球団の目的がwin-winの関係で相乗効果を生んだのは確かである。
何よりも重要なのは、岡田監督が査定項目の変更(昇給理由)と目的を選手と共有したことで、選手のフォアボール獲得数は前年比で大幅に上昇し、目指す方向性が一致したことである。
では、一般企業であればどうであろうか。具体的な理由と目的を例として挙げるなら、次のような内容が往々にして考えられるだろう。
(1) 理由:勤続年数が一定年数を経過
目的:この先も長く勤め続けることで給与が段階的に上昇することにより、継続的な勤務を期待する。
(2) 理由:会社全体としての利益還元
目的:「安定している会社」「利益を従業員に還元してくれる会社」という認識が生まれ、継続的な勤務を期待する。
(3) 理由:物価高に対する従業員支援
目的:「従業員が幸せであってこそ、会社の幸せが実現する」等、経営理念の実現。
(4) 理由:個人の営業・売上等の成績良好
目的:成果をあげた従業員を評価することで、さらなる実績向上や周囲の職員への相乗効果を期待する。
上記のようなケースでも更に明確にするために、公務員や大企業で見られるような「『等級・号俸』による給与表を作り勤続年数ごとに昇給していくような制度を整えることで可視化する」ことや、「会社の増益や個人の営業・売上成績、仕事の貢献度に対しどのような数字で従業員に還元するのかを明示する」といった手法も有効である。
* * *
余談となるが、過去に筆者も昇給理由を示され、泣きそうなほど喜び、仕事に力が入った想い出がある。
筆者は新卒から10年間、銀行に勤めた。毎年昇給は4月1日と決まっており、必ず所属長との面談が行われていた。勤務年数による昇給に加え、日ごろの仕事に対する評価もこの場で伝えられていた。
今でも忘れられないのが8年目の面談である。通常、10年目頃までは大きな問題がなければ毎年少しずつ昇給し、職階の等級も1つずつ上がっていくような給与体系であった。
しかし、筆者は年子で子供が生まれ、前年、前々年と2年連続で育児休業を取得しており、両年とも4月1日は不在であったため昇給がなく給料は据え置きとなっており、等級も同期の普通の職員と比べて2等級遅れていた。
その年も、育休から復帰したのが前年4月末であったので約1ヶ月不在にしていた期間があり、子育て時間短縮勤務も利用していたため、これまでの例からすれば昇給は望めない状況であった。しかし、結果は3年ぶりに昇給し、同じく3年ぶりに等級も上がったのである。
当時の上司のコメントは次のような内容であった。
2年間ずっと上がっていなかったし、ITスキルでの貢献度が高くて仕事も早いし、普段から一生懸命やってくれている姿は見ているから、この等級のままでいるのは相応しくないと思って、上げるように人事に申請出しておいた! 俺は子供3人を奥さんに任せっきりでなにもやってこなかったから、子育てしながらちゃんと働いているって、すごいと思うよ! 育児を仕事と考えたら倍働いているわけだし、偉いよ! これから次に続く子育て職員たちのためにも頑張ってね!
従業員にとっては、昇給の際のこのような言葉が、その後の人生に大きく残るものになることも考えられるであろう。
(了)
次回は2/29に掲載されます。