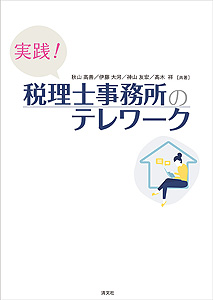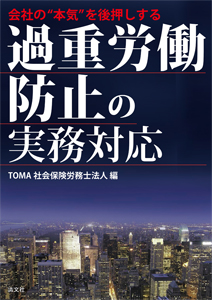残業代の適正な計算方法
【第1回】
「労働時間の基本をおさえる」
社会保険労務士 井下 英誉
1 はじめに
本連載では、「残業時間の適正な計算方法」について、5回にわたって解説する。
まず、残業代を適正に計算するうえで大切なことは何であろうか。
それは、次の式の内容を正しく理解することである。
[残業代] = [残業単価] × [残業時間]
残業代が残業単価に残業時間を乗じて計算される以上、そのどちらかの数字が間違っていれば、当然「適正」な計算結果は得られない。
労使問題として頻繁に発生する未払賃金(未払残業)トラブルは、会社が残業代を全く支払わないという理由で生じることもあるが、多くの場合は、使用者が残業単価や残業時間を正しく理解しておらず、適正な計算が行われないために起こるのである。
一方で、残業時間は労働時間の一部であるから、労働時間を正しく理解していなければ、残業時間を正しく理解することはできないともいえる。
したがって、本連載では、第1回で「労働時間」を取り上げ、第2回以降で残業時間や残業単価等について解説を行うこととする。
2 労働時間の原則と例外
労働基準法では32条から32条の4において、労働時間の原則的取扱いと例外的取扱いを定めている。
【原則的取扱い(32条)】
① 休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
② 休憩時間を除き、1日について8時間を超えて労働させてはならない。
【例外的取扱い】
① 1ヶ月単位の変形労働時間制(32条の2)
労働組合又は労働者の過半数代表者との書面による協定、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。
② フレックスタイム制(32条の3)
就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、労働組合又は労働者の過半数代表者との書面による協定により、必要な事項を定めたときは、1ヶ月以内の清算期間として定められた期間を平均して1週間当たりの労働時間が週40時間を超えない範囲内において、1週間において40時間又は1日において8時間を超えて、労働させることができる。
③ 1年単位の変形労働時間制(32条の4)
労働組合又は労働者の過半数代表者との書面による協定により、必要な事項を定めたときは、対象期間(1年限度)として定められた期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。
3 時間外労働の考え方
労働基準法では、32条(32条の2から32条の4を含む)の規定に定める時間を超えて労働させることは原則禁止されている。
しかしながら、下記の36条の要件を満たし、就業規則等で「労働者に時間外労働を行わせる」旨の定めがある場合は、32条(32条の2から32条の4を含む)に定める時間を超えて労働させることができる。
《労働基準法36条で定められている要件》
① 労働組合又は労働者の過半数代表者と書面による協定(36協定)が締結されること
② 書面による協定(36協定)を労働基準監督署に届け出ていること
4 労働時間の適正な把握
労働基準法では、前述のように労働時間について規定を設けているため、使用者は、労働時間を適正に把握し、適切に管理する責任を負っていることは明らかである。
使用者が講ずべき労働時間の適正な把握のための措置としては、次のものがある。
① 始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
② 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
ア 使用者が自ら現認することにより確認し、記録する。
イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する。
③ 自己申告制により始業・終業時刻を確認及び記録を行う場合の措置
上記②の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講じること。
ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行う。
イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施する。
ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じない。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払い等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認する。
④ 労働時間の記録に関する書類の保存
労働時間の記録に関する書類について、労働基準法109条に基づき、3年間保存すること。
⑤ 労働時間を管理する者の職務
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等、労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。
次回からは、残業時間の考え方、集計方法等について解説する。
(了)