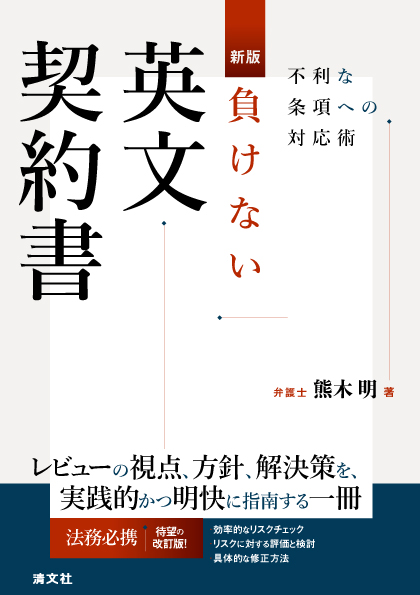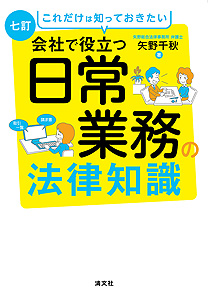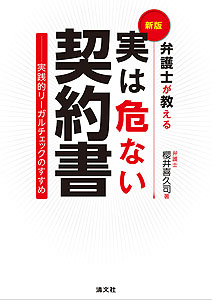法務・会計・税務からみた循環取引と実務対応
【第2回】
「法務からみた循環取引」
弁護士・公認不正検査士 下尾 裕
1 法務からみた循環取引の知識が必要になる場面
法務からみた循環取引の知識が必要となる場面は、主に循環取引の破綻時において、当事者が自らの直接の取引先に対して、未払の売掛金等を請求する場面である。そこで、本稿では、循環取引に基づく請求の可否の判断枠組み及びこれを前提とした具体的な裁判事例について、解説を行う。
なお、本稿においては、契約目的物の現実の引渡し等又はその最終需要者(エンドユーザー)が存在することを指して「実需」という用語を用いる。
2 循環取引に基づく請求の当否に関する判断の枠組み
(1) 循環取引に基づく請求の法的根拠
循環取引は、二当事者間の取引が順次連鎖して円環を構成しているものであり、複数の契約の集合体であることから、循環取引に基づく請求についても、個々の契約が請求の根拠となる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。