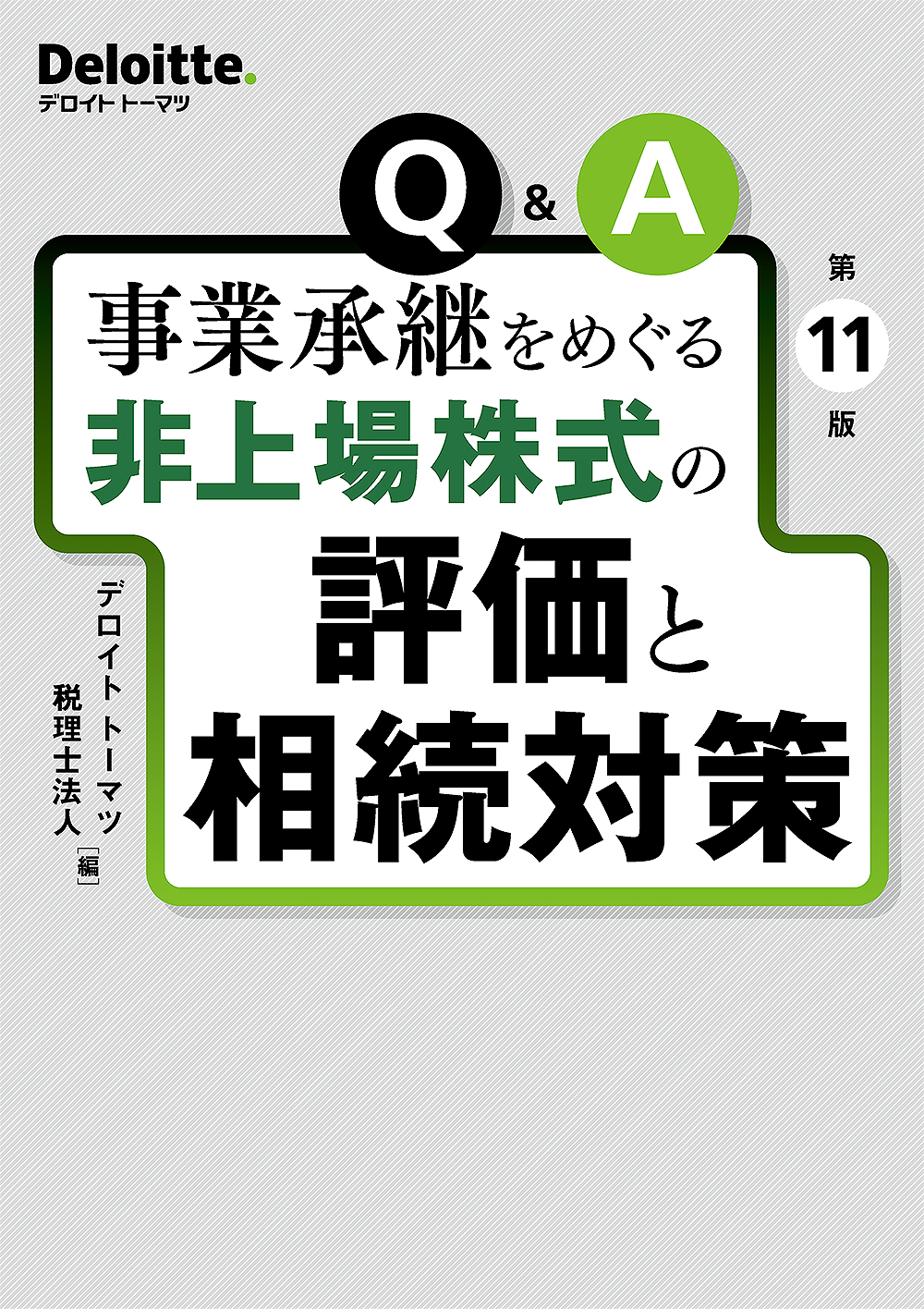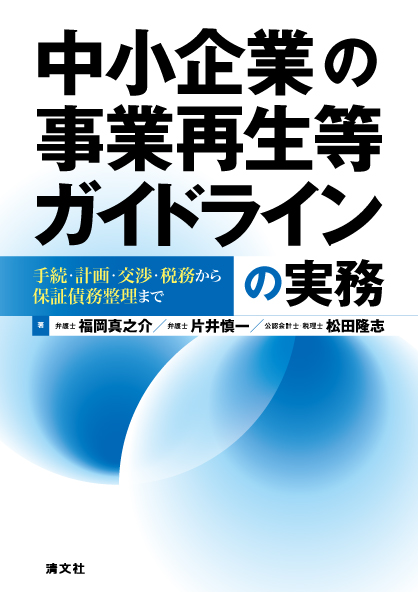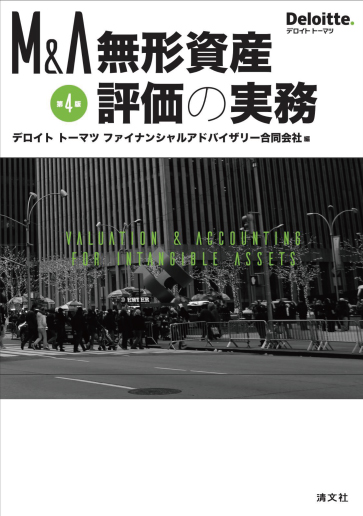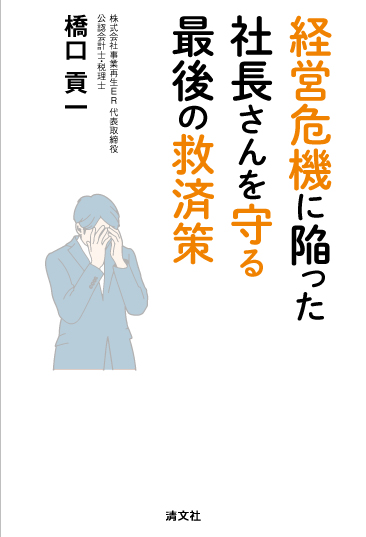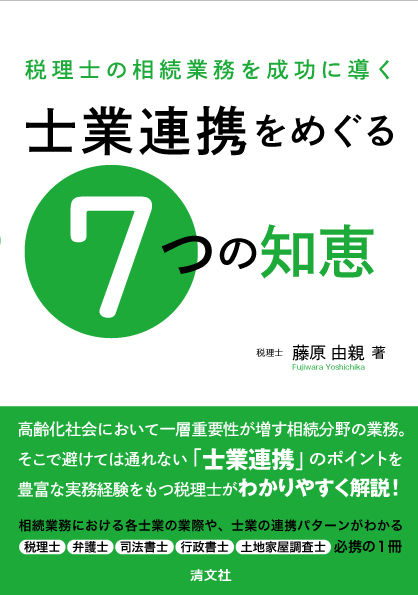〈“2025年問題”を前に知っておきたい〉
3つの事業承継方法とそれぞれのメリット・デメリット
【前編】
株式会社M&A総合研究所
企業提携部 主任
JMAA認定M&Aアドバイザー
税理士有資格者 松木 雅彦
国内企業の9割以上を占める中小企業・小規模事業者は、技術や雇用の担い手として日本を支える重要な存在です。
最先端技術や伝統技術を有する企業も多いですが、近年は経営者の高齢化が進み、事業承継が重要な課題とされています。
1 中小企業における事業承継の現状
2020年1月末に日本政策金融公庫が公表したアンケートでは、後継者が決まっていると回答した中小企業はわずか12.5%、後継者が決まっていない「未定企業」が22.0%、廃業予定と答えた企業が52.6%と半数を超えており、非常に厳しい現状が分かる結果となりました。
中小企業庁は「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」の中で、2025年には70歳を超える経営者が245万人に達し、現状のままでは中小企業・小規模事業者廃業の急増で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があると試算しています(いわゆる「2025年問題」)。
このような深刻な後継者不在状況を変えるため、国は2011年から事業引継ぎ支援センター(現在は「事業承継・引継ぎ支援センター」)を設置するなど支援策を講じてきました。
2025年が間近に迫る中、国は支援策を拡充し、中小企業・小規模事業者の事業承継を強力に後押ししています。
本稿では、この2025年問題を前に、中小企業・小規模事業者のオーナーに加え、事業承継の相談を受ける立場となる税務顧問の方が知っておくべき3つの事業承継方法とそれぞれのメリット・デメリットを2回にわたって紹介します。
2 親族内承継~事業承継方法①~
親族内承継は中小企業・小規模事業者の事業承継で最も活用されており、経営者の子など親族を後継者として事業を引き継ぎます。
帝国データバンクの「全国企業「後継者不在率」動向調査(2021年)」では、2021年の事業承継のうち、先代経営者との関係性で親族内承継を選択した企業が38.3%と最も高い割合となりました。一方で、2017年の同割合と比較すると、3.3pt低下し、親族内承継の割合は緩やかな減少傾向となっています。
【メリット】
① 十分な後継者育成時間を確保できる
経営者の子や親族を後継者とするため、早い時期から経営者としてのノウハウを学ばせるなど、十分な育成期間を確保することができます。
子が後継者となる場合は、幼少期から将来事業を引き継ぐという意識が芽生えやすいこともメリットです。実際、他社で経験を積ませたのち自社へ入社させ、経営者に育て上げるケースは非常に多くみられます。
② 企業理念など目に見えないものの承継がしやすい
中小企業や小規模事業者の場合、経営者の方針が事業に大きく反映されますが、企業理念の承継は非常に難しいものです。
業績の良い企業であっても、企業理念がしっかり引き継がれなければ、経営方針がぶれて事業の衰退につながる可能性もあります。
大切にしてきた経営者の考え方を後継者が理解しやすいというのも、親族内承継ならではのメリットといえるでしょう。
③ ステークホルダーからの理解が得られやすい
従業員や取引先などにとって、経営者が交代するというのは大きな関心事であり、少なからず不安もあるものです。
後継者が経営者の子であれば関係先と面識があることも多いため、親族内承継は心情的に理解が得られやすい方法といえます。
④ 所有と経営の分離が起こらない
子などの親族が後継者となるため、相続が発生しても所有と経営の分離が起こりづらく、生前贈与を活用して計画的に株式や事業用資産を引き継ぐこともできます。
さらに、自社株を後継者へ集中的に承継させることによって、事業に対する意思決定の大半を行えるようになり、迅速な舵取りが可能です。
【デメリット】
① 後継者に経営者の資質があるとは限らない
後継者となる子や親族に、必ずしも経営者としての資質があるとは限りません。また、どれだけ経験を積ませても、実際に経営してみなければ分からない部分もあるでしょう。
事実、後継者に経営者としての資質がなく、親族内承継したのちにM&Aを検討するケースもみられます。
② 親族内でトラブルになるケースもある
親族内承継は相続と絡み、トラブルに発展する可能性もあります。後継者候補以外に現経営者の親族(相続人)がいる場合は他の相続人の遺留分を侵害する可能性があるため、後継者が遺留分侵害額の請求を受けないよう考慮が必要です。
現経営者の死後にトラブルが起こらないよう、遺産分割の方法などを親族内でしっかり話し合っておく必要があるでしょう。
3 従業員承継~事業承継方法②~
自社の従業員や役員を後継者として事業を引き継ぐ方法です。前出の帝国データバンクの調査では、自社の役員などを内部昇格させる従業員承継の割合は 31.7%と、親族内承継に次いで高くなっていますが、これも、前年度と比較すると減少傾向となっています。
【メリット】
① 優秀な人材を後継者にできる
自社の役員や従業員の中から優秀で経営に適した後継者を選べることが、最も大きなメリットです。親族内承継と比べると選択範囲が広くなるので、後継者候補が見つかりやすい方法といえるでしょう。
また、早い段階から事業承継の計画を立てれば、素質のある従業員を優れた経営者に育てることもできます。自社のノウハウや技術などをスムーズに引き継ぐことができるのも、従業員承継が選ばれる理由のひとつです。
② 従業員からの理解が得られやすい
従業員承継で後継者となるのは、一般的に長く勤務している従業員や経営者の右腕だった人物です。
業界の常識や社内の慣習なども把握しており、他の従業員や取引先などの関係先とも長く付き合っているため、理解が得られやすくなります。
③ 企業理念や経営方針の一貫性に期待できる
企業文化や経営方針をよく理解している人物が後継者となるので、円滑に事業を引き継ぎやすいこともメリットです。
独自の企業文化を大切にしている中小企業や小規模事業者は非常に多いものですが、社風をよく知っている役員や従業員が後継者であれば、企業文化が失われる可能性は非常に低いため、安心して事業を引き継ぐことができます。
【デメリット】
① 株式買取資金の用意が難しい
親族外承継では、後継者が自社株式を買い取る必要があります。企業価値が高ければ株式の評価額も上がるため、数千万円を超える株式買取資金が必要になるケースも珍しくありません。
後継者の自己資金で賄えない場合、銀行などからの融資を検討しなければなりませんが、個人の信用力の問題などもあり、資金調達のハードルは高いといえます。
② 個人保証や連帯保証の引継ぎリスク
中小企業や小規模事業者の多くは、銀行などから融資を受けています。事業承継の際、後継者は経営者の個人保証や、連帯保証を含めた事業に関する債務を引き継がなければなりません。
また、経営者になるということは、社会的・法的な責任を負うということでもあります。もし何か起こった場合は責任を負う覚悟も必要です。
後継者にとってはリスクや精神的な負担が少なくないため、後継者から事業承継を辞退されるケースも考えられます。
③ 所有と経営の分離が起こりうる
株式を移転せず、経営権のみを譲渡して事業を引き継ぐことも可能です。しかし、この場合は「所有と経営の分離」状態となり、後継者は現経営者の了承を得ながら事業運営をしなければなりません。
そうなれば、大胆な方向転換や改革がしにくいなどスムーズな経営が難しくなったり、支障をきたしたりすることも懸念されます。
(【後編】に続く)
【後編】は、6月29日に掲載予定です。