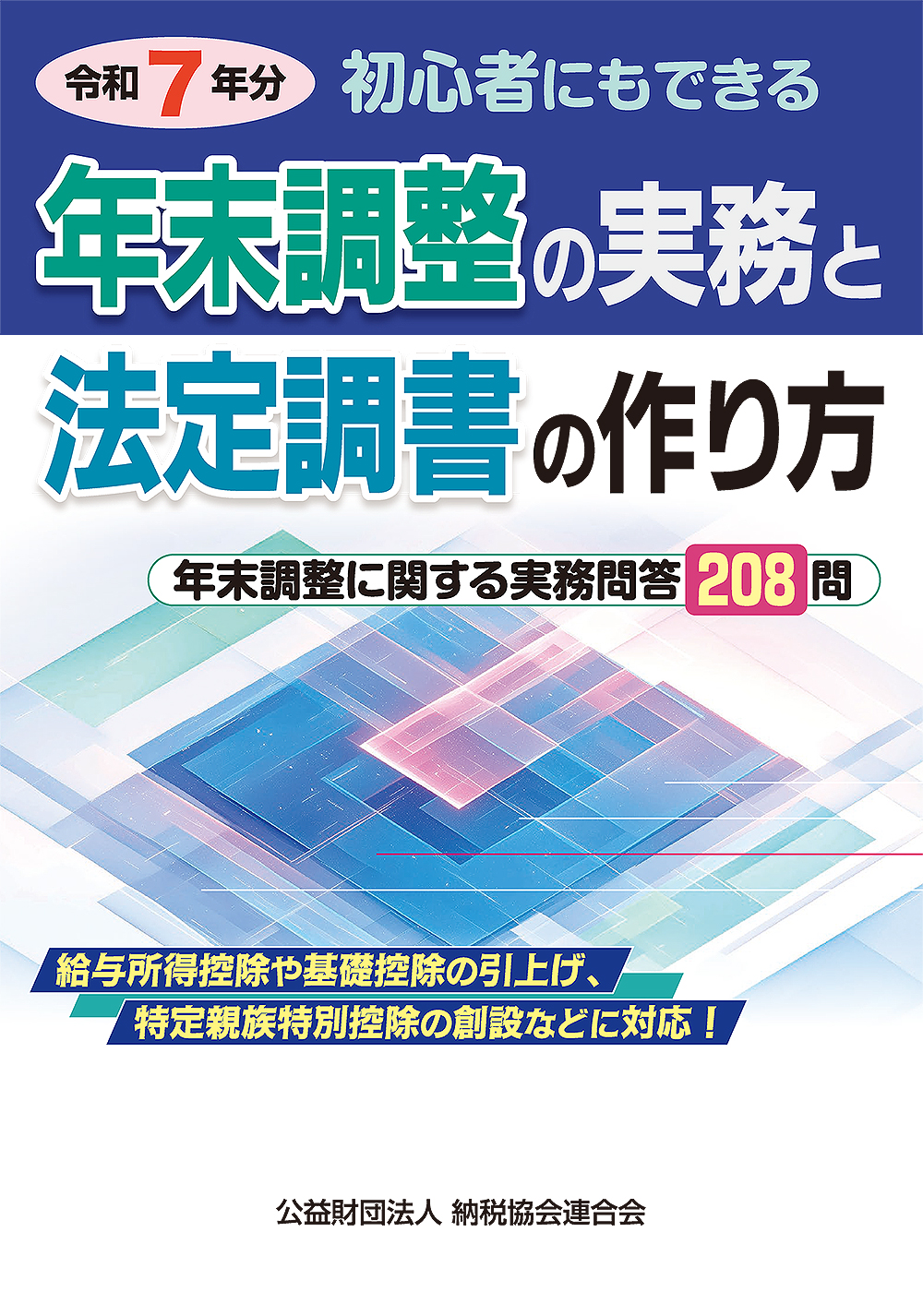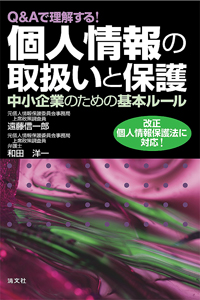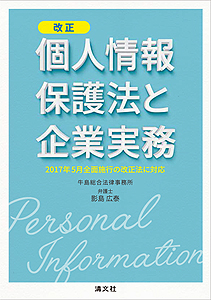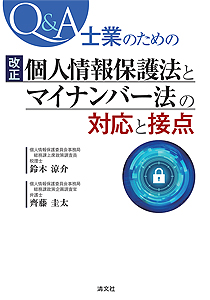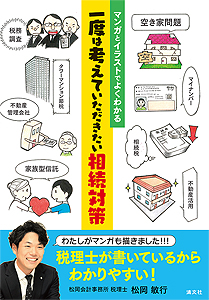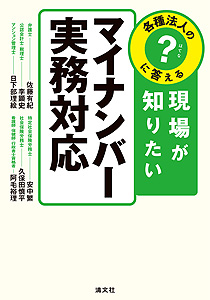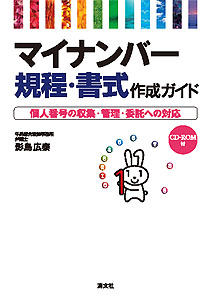マイナンバー制度と
税務手続
【第1回】
「マイナンバー制度の理解」
税理士 坂本 真一郎
【はじめに】
平成25年5月24日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)」を含む関連4法案が成立し、平成27年10月から個人番号(以下「マイナンバー」という)及び法人番号が通知され、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の3分野で利用が開始される。
マイナンバーは、導入当初は社会保障・税・災害対策分野に係る行政機関等の事務のための利用に限定されているが、マイナンバー制度においては、民間事業者が番号収集・保管という非常に重要な役割を担わなくてはならないものの、未だに特別な対策を立てていないという事業者も多い。
特に、特定個人情報(※1)の適正な取扱いに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という)では、特定個人情報の安全管理措置が義務づけられており、事業規模による対策のボリュームの差はあっても、すべての事業者が対応を行わなければならない。
(※1) マイナンバーをその内容に含む個人情報をいう。
それでは、事業者はどういったことを念頭にこのマイナンバー制度に取り組んでいけばよいのか、現時点で公開されている情報をもとに、筆者の視点から解説していきたいと思う。
【マイナンバー制度導入の目的】
番号法第1条では「マイナンバー制度導入の目的」として次の3点が掲げられており、制度を理解する上で重要な部分であるので、まず触れておきたい。
1 行政の効率化
マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等に対する行政手続において、マイナンバーの申告、申請書等への記載などが求められることとなる。国や地方公共団体等の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになると見込まれる。
例えば、市町村、税務署、年金事務所等が情報連携することにより、所得税確定申告書に記載している社会保険料控除等についての確認が容易となることや、配偶者控除及び扶養親族控除の適否も容易に確認されることが考えられる。
2 公平・公正な社会の実現
行政機関等の連携により、国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になる。
例えば、毎年税務署に提出される法定調書は、これを納税者ごとに名寄せして申告書と突合し、税務調査のための事前準備資料として管理しているが、氏名、屋号及び住所等の不一致により、同一人物に帰属するはずの情報が名寄せされずに「不明資料」として埋もれてしまうものも相当数発生している。
マイナンバー制度が導入され、申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバーや法人番号が記載されることになれば、「不明資料」は減少し、申告書等との突合をより正確かつ効率的に行うことができるようになり、所得把握の正確性が向上すると考えられる。
3 国民の利便性の向上
これまでは、市町村、税務署、年金事務所など複数の機関から証明書類等を入手し、申請書等に添付して提出するということが多々あったが、マイナンバー制度導入後は、社会保障・税務関係の申請時に所得証明、住民票など複数の行政機関等で入手し提出していた添付書類を省略でき、手続が簡素化される。
また、平成29年以降設置予定の「マイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)」サイトを通じて、自己が受けることができる行政サービス等のお知らせを受け取ることや、行政機関等が保有する自己の情報を確認し、その運用状況を監視することもできるようになる。
マイナンバー導入後は、住宅ローン控除のための所得税確定申告書の添付書類である「住民票の写し」の提出を省略することができるので、市町村窓口に出向く手間や発行手数料等の負担がなくなる。
また、平成30年にもマイナンバーを戸籍情報に紐付けすることが検討されており、実現すれば、相続税申告書の添付書類である「戸籍謄本」の提出を省略することができる。
それ以外にも、現在は国と地方公共団体それぞれ別々に提出する必要のある給与所得等の源泉徴収票、支払報告書の電子的提出について、提出先が地方税ポータルに一元化される予定となっている。
【マイナンバー制度の前提とされる事項】
前述のマイナンバー制度の目的を達成するためには、次の前提事項が必要となる。
1 付番
マイナンバーは、日本国内に住民票を有する人全員に予測不可能な番号が付番されること(悉皆性)、1人につき1つの番号が重複することのないように付番されること(唯一無二性)、「民-民-官」の関係で流通させて利用できる目に見える12桁のマイナンバー(視認性)が、最新の基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けて付番されることが必要である。
このようにして付番されたマイナンバーは、平成27年10月以降、各市町村から住民登録上の住所地宛てに「通知カード」により送付される。
また、法人等については、国税庁において、上記の悉皆性、唯一無二性及び視認性のある13桁の法人番号が付番され、平成27年10月以降、登記上の本店所在地や税務署で登録されている住所地等に、法人番号の「通知書」が送付される。
2 情報連携
1人に1つの番号が付番されても、それぞれの行政機関の持っている個人に関する情報が、マイナンバーに紐付けされなければまったく意味をなさないことになる。
マイナンバー制度は、複数の行政機関等の間において、それぞれの機関ごとに管理している同一人の情報を符号で紐付けし、情報提供ネットワークシステムを通じて、紐付けられた情報を相互に活用できることが前提である。
マイナンバー制度の情報連携の仕組みは、個人のプライバシー権への配慮や国家管理に対する懸念への対応として、個人情報を特定の機関に集約せず、必要に応じて情報の照会・提供を行うことができる「分散管理」の方法が採用されている。
3 本人確認
個人番号を提供する者が、間違いなく番号の持ち主である本人でなければ、マイナンバー制度の前提が崩れてしまう。本人確認は、成りすまし等の防止のため、個人がマイナンバーを提供する際には、その番号が正しいかを確認するとともに、提供者がマイナンバーの真の持ち主であることを確認することであり、この制度の一番重要な手続の一つである。
この本人確認は、個人番号を利用して業務を行う行政機関等(個人番号利用事務実施者(※2))と、これに関連して業務を行う民間事業者等(個人番号関係事務実施者(※3))が行う最も重要な行為である。
(※2) マイナンバーを使って、番号法別表第一で定められる事務を処理する者をいう。
(※3) 個人番号利用事務に関し、他人のマイナンバーを必要な限度で使用して事務を処理する者をいう。
(了)
「マイナンバー制度と税務手続」は、隔週で掲載されます。