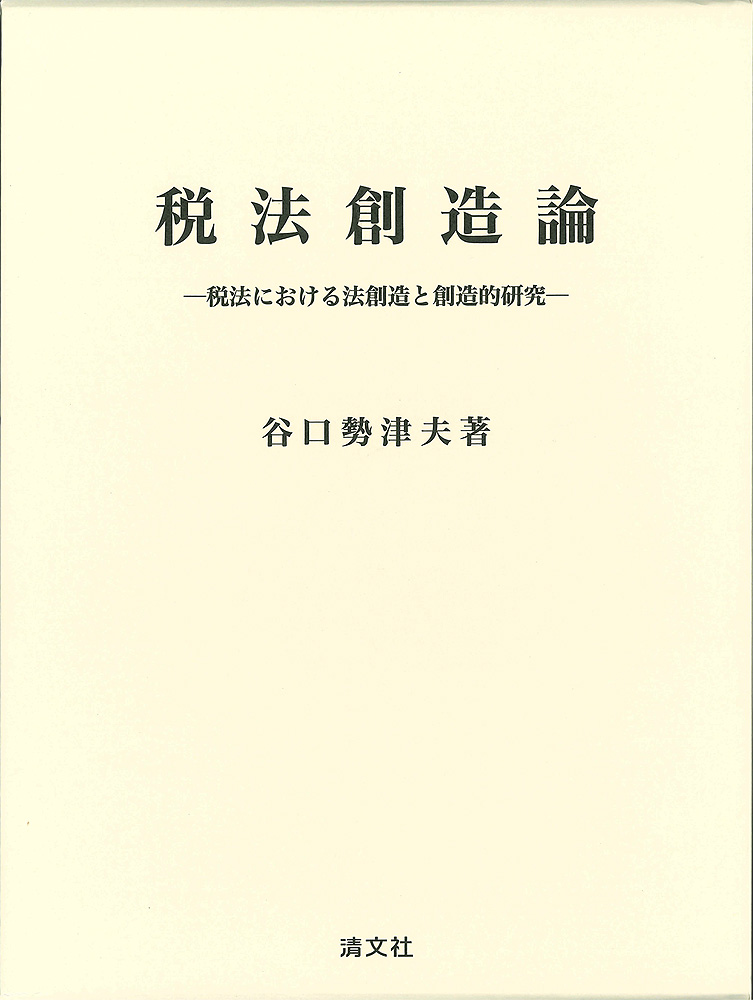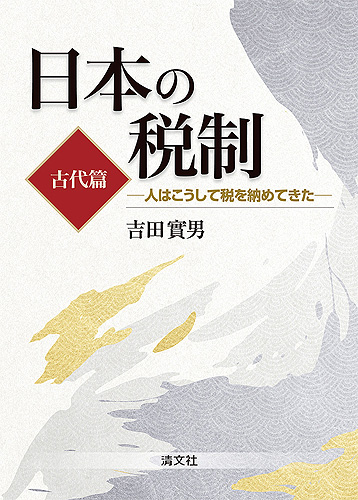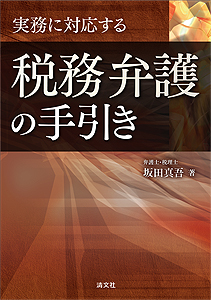税務判例を読むための税法の学び方【18】
〔第5章〕法令用語
(その4)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
(前回はこちら)
(承前)このように、「ものとする」があってもなくても意味が変わらないにもかかわらず、これを付すのは、語感や語呂から、また表現をソフトにするためであり、例外を認める余地はなく、義務を課したものである。
③ 解釈の明確化
「・・・(の規定)は、・・・に適用があるものとする」というような用例がある。
これまで述べた用例とはやや異なり、そこで問題となっているある規定が、ある場合に適用があるのは解釈上あるいは論理上当然のことであるが、解釈上の疑義を避けるために、念のために規定で明確にするという場合に使われるものである。
この場合、これを「・・・適用する」と言い切ってしまうと、本来適用のないところを、この規定で適用するようにしたという創設的意味が付加されたという解釈が生じることになりかねない。そこで、創設的意味が付加されているのではなく、念のためのものであるということを表す趣旨で、この「・・・ものとする」が使われている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。