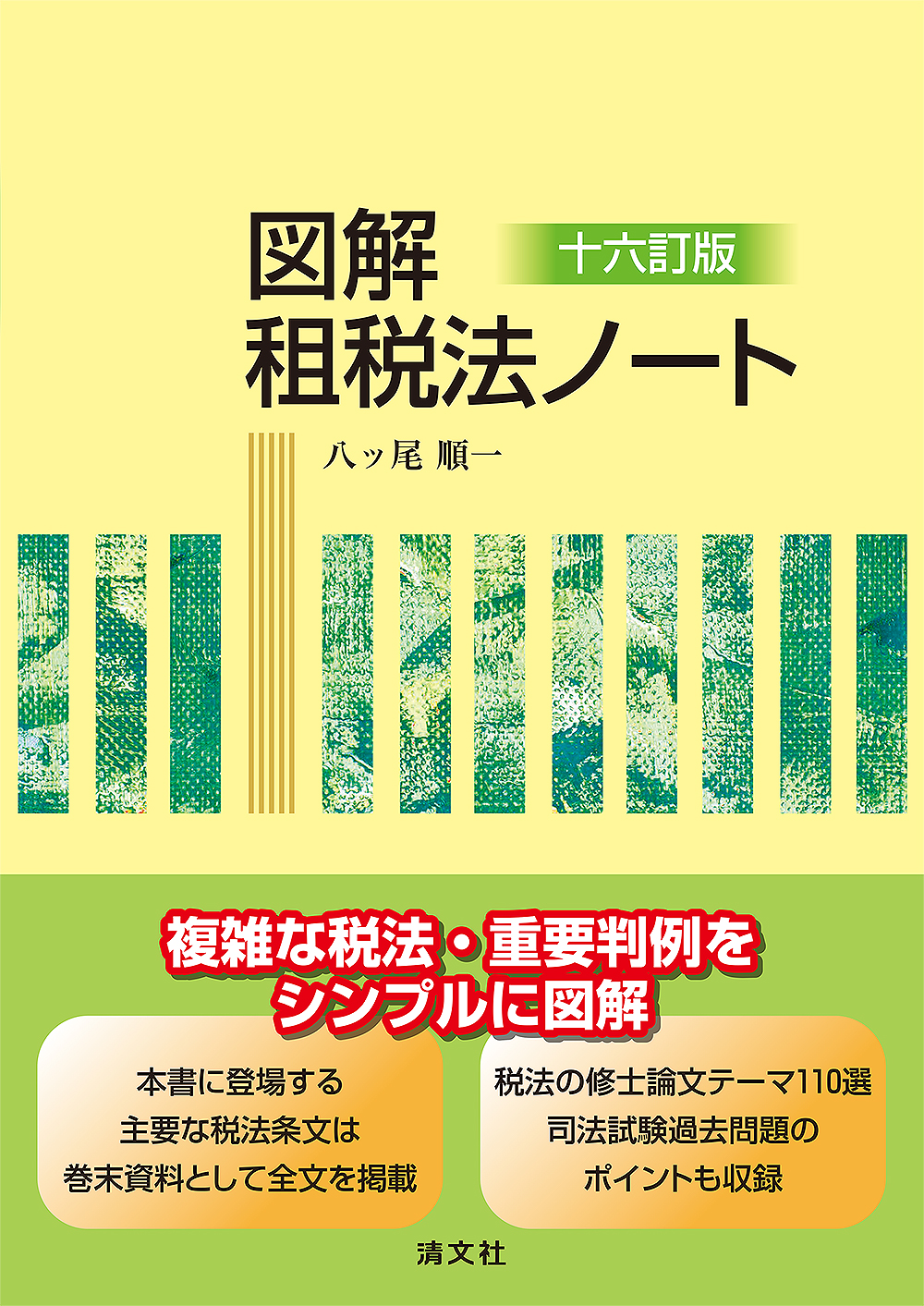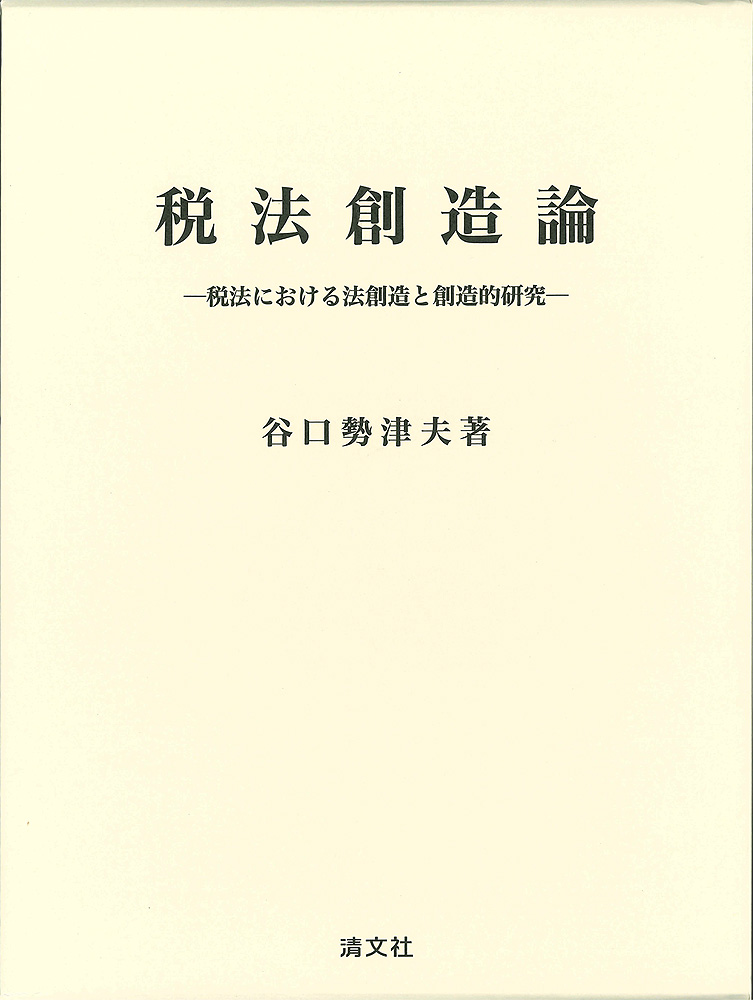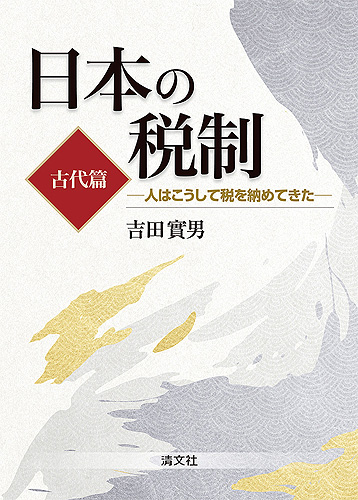税務判例を読むための税法の学び方【33】
〔第5章〕法令用語
(その19)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
11 取消・無効・撤回
前回や前々回に解説した「期限や期日を示す表現」では、単に法令用語というのみならず、民法等の他の法令による解釈をも交えて解説した。
引き続き、類似の意味を有する用語ではあるが、その意義については民法上に規定がある「取消」と「無効」について確認する。そしてこの「取消」と似た意味を有する「撤回」(この意味でありながら、かつては条文上「取消」と記されていたものもあった(改正前民法521条))についてもここで説明する。
① 民法上の意義
外形的に見ると法律上の効果を求めた法律行為ないし意思表示がありながら、法律がこれに対して直接にその効力を否定する(無効)、又は行為者にその効力を否定する事を認めている場合がある。そしてこの後者の場合においても、はじめに遡って効力を否定するもの(取消)と、はじめに遡ることはせず将来にわたりその効力を失わせるもの(撤回)とがある。
では、この差異について詳しく見てみよう。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。