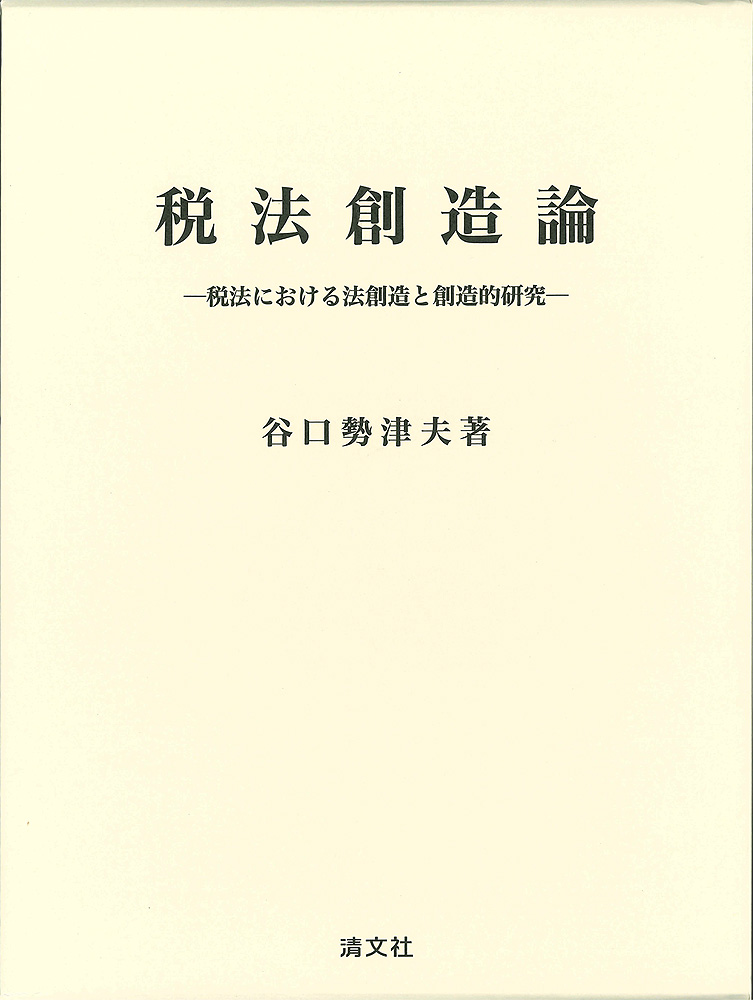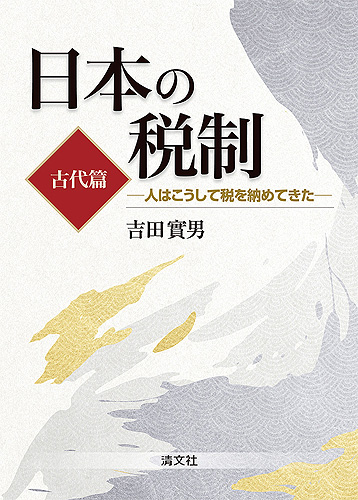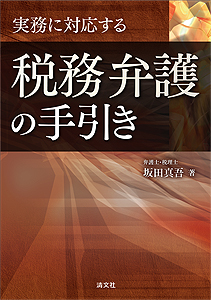税務判例を読むための税法の学び方【1】
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
〈連載のはじめに〉
これから税務判例を読むために税法を学んでいきますが、裁判例を読む前に、また裁判例の読み方を学ぶ前に、基本的なことを確認していきます。
最初に、法学概論として、法とは何かについて、また法の解釈方法等(法令用語の読み方等を含む)について確認します。
そして、裁判例の読み方を確認した後、主要な税務判例を検討していきます。
今回はその最初として、「法」とは何かについて確認していきましょう。
〔第1章〕 法(法源)の種類
はじめに
「法」は道徳などと同様、社会規範の一種である。道徳等の他の社会規範との最も大きな違いは、違反したことにより強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられるという強制力がある点である。また、行為規範となるだけではなく、裁判規範として機能するという点がある。
ではこの「法」と言った場合、「法律」と同義語であろうか。
答えは「否」である。
「法律」の成立要件は、国家により異なるが、わが国においては、国会で可決されて制定されたものを指す。では「法」として機能するものには、どのようなものがあるだろか。
そこでまず、法の種類について見ていく。
1 自然法と実定法
自然法とは、事物の自然本性から導き出される法の総称であり、人間の作った実定法の効力・拘束力の正・不正を識別する概念である。
自然法論によれば、この自然法に反する実定法は、法的拘束力をもたず、無効だと、すなわち「悪法は法にあらず」と主張される。
これに対し、法実証主義の立場からは、社会において実効的に行われている法である実定法の内容が道徳的であるか否かにかかわらず法的効力を認める、すなわち「悪法もまた法なり」と主張される。
仮に自然法論の主張を認めるにしても、何が自然法かといった判断は事実上不可能である。したがって事実上は、法実証主義の立場に立ち、実定法の分類を見ていくことになる。
2 法源
法源とは、法の形式的存在形態、すなわち、法規範がどのような形式で存在しているかをいう。
したがって「法源」という場合、法の存在形式による法の分類を指す場合もあるが、この分類の対象の範囲内か否かという意味を指す場合もある。すなわちこの分類の対象として、法的拘束力を持つものか否か=裁判官が裁判を行う際に基準となる裁判規範であるか否かという意味で使うこともある。もっとも裁判の結果に対する予測可能性から、事実上行為規範として機能することになる。
「法源性」とは、この意味における「法源」の使い方から「法規範性」の有無を指す言葉として使われている。
では次に、この形式的存在形態について見ていこう。
3 成文法(制定法)と不文法
文字・文章で表現され、所定の手続に従って定立される法を、「成文法」又は「制定法」という。これに対し、文字・文章で表現されていない形式の法を「不文法」という。慣習法、判例法、条理などがその例として挙げられる。
なお、判例法は、判決という文章が存在するが、判決文そのものが法ではなく、そこに含まれている法原則が拘束力をもつ法規範とされ、法として制定されたものではないため、不文法に分類される。
我が国では、英米と違い、成文法主義を原則とした上で、不文法も成文法を補充するものとして認められている。これに対し英米法の社会では、裁判所の判例は重要な不文法源となっている。
成文法は、体系的・論理的に整序されており、明確で安定している。したがって、社会の構成員の行動規範、裁判官の裁判規範としての明確性は高いが、法改正には一定の手続を経なければならず、時代の変化には即応しにくい。もっとも、基本的に一般的抽象的に規定されているため、立法後の社会変化に対してもある程度の適応力がある。しかし、立法当時には予測できない問題が生じた結果、成文法でなんら規定が存在しないことも起こり得る。このような場合には不文法で補充せざるを得ず、不文法に法源としての役割が求められる。
4 成文法の種類
① 憲法
国家の統治体制の基礎を定める基本法である。
憲法も国会の議決を経て制定されたものという点では他の法律と同様であるが、日本国憲法第98条に「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と最高法規性が示されている。
また第96条において「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と厳格な手続によらなければ改正できないとされている。
このように、厳格な手続によらなければ改正できない成文憲法を「硬性憲法」といい、通常の法律の改正手続と同じ手続で改正できる成文憲法を「軟性憲法」という。
② 法律
日本国憲法の定める方法により、国会の議決を経て制定された成文法をいう。
法律は国権の最高機関である国会によって制定される成文法であるから、国内法としては憲法に次で強い効力を持ち、他の国内法令に優先する。条約との関係については、条約の国会承認、憲法第98条第2項の条約遵守主義などから考えて条約が法律に優先すると解されている。
③ 規則
「規則」という名称のものは数種類あるが、これは国会以外が憲法に定められた規則制定権に基づき、作成する制定法をいい、議院規則と最高裁判所規則がある。
議院規則は、憲法第58条第2項において「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め」と衆議院及び参議院による規則制定権が定められている。なお、これも法律同様立法府の定めたものであるため法律との優劣が問題になるが、法律は国会の両院の可決等の手続により制定されたものであるため、法律が上位とされている。
最高裁判所規則は、憲法第77条において「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律も及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」と最高裁判所による規則制定権が定められている。
最高裁判所規則は、法律に優位するという説もあるが、一般には国会を国権の最高機関とする憲法の趣旨からして、法律の方が上位にあると解されている。
なお、議院規則や最高裁判所規則と法律との関係は、法律による委任がなくとも一定の事項については憲法上当然に制定することができる点において、政令や内閣府令・省令のような行政機関の制定する命令とは区別されるものである。
④ 命令
行政機関が制定する成文法の総称で、法律の実施に必要な細則や法律が委任する事項を定めるものであり、法律の範囲内において定めることができる。政令、府省令、その他の命令の3種がある。
また、内容的に分類すれば、執行命令と委任命令に分けられる(旧憲法下においては独立命令というものもあった)。執行命令とは、法律の規定を執行するために必要な細則を定める命令であり、委任命令とは、法律により委任された事項について定める命令である。
なお租税法律主義により、税に関する重要な事項(すなわち、納税義務者、課税物件、課税標準、納付の方法、納付の期日等)は法律で定めるべきであり、課税標準の計算についての技術的、専門的な事項や細かい手続的事項につき命令で定め得ると解される。
したがって、これら重要な事項は法律で命令に委任し得ず、また、法律で命令へ委任するにあたっても、委任の内容・程度が具体的・個別的であることを要し、概括的・白地的な委任は許されないと解される。
(ア) 政令
内閣が制定する成文法である。日本国憲法第73条において内閣の行う事務が定められているが、その第6号には「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」と定められている。閣議によって決定され、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署して、天皇が公布する。
(イ) 府省令
府の主任の大臣が発する成文法である府令(「内閣府令」)と各省大臣が発する成文法である省令の総称である。
内閣府令については、内閣府設置法第7条第3項に「内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。」と、省令については国家行政組織法第12条第1項に「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」と定められている。
なお、基本的には、命令のうちで重要なものは政令で、軽微なものは府省令で定めることになる。税法においては、原則、課税標準の計算に関する事項は政令(名称は「○○税法施行令」)で、細かい手続的事項については省令(名称は「○○税法施行規則」)で定めている。
(ウ) その他の命令
その他の命令として、会計検査院規則、人事院規則、人事院指令、府省の外局である委員会(行政委員会)が発する「規則」(例:国家公安委員会規則)、庁の主任の大臣又は省の外局である庁の長官が発する「庁令」(例:海上保安庁令・復興庁令。海上保安庁令は規則に準じ、復興庁令は府省令に準じる)などがある。その発する機関、根拠法、沿革などにより、政令又は府省令に並ぶか下位に位置することとなる。
(エ) 告示
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる(国家行政組織法第14条第1項)とされているが、一般的には告示そのものは法源とはされていない。
しかし、こうした告示の中には、法律又は委任命令の授権に基づいて、法令を補充する法規としての性質をもつものがある。すなわち、実質は法令の委任に基づく命令であって告示形式をとるものである。行政手続法第2条が、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 」とした上で、第1号において法令につき「法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。」と告示を含めているのは、このような例があるためである。
税法における例としては、法人税法第37条により損金算入が認められるいわゆる指定寄附金の範囲が告示によることになっている。地方税については、総務省告示及び各地方団体の長の発する告示がある。
⑤ 地方自治法規
(ア) 条例
地方公共団体が、議会の議決により、法令に違反しない限りにおいて、制定する自治立法を指す。地方税においては、賦課・徴収は地方議会の定める条例に基づいて行われなければならないとされる「地方税条例主義」によっており、地方税に関する裁判例を見るにあたっては、重要な成文法である(地方自治法第14条)。
(イ) 地方公共団体の「規則」
地方公共団体の長である首長が、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し制定するものである(地方自治法第15条第1項)。
(ウ) 地方公共団体の「規則」以外の地方公共団体の機関の定める「規則」
地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は地方公共団体の条例や規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規定を定めることができる(地方自治法第138条の4第2項)。
⑥ 条約
国家(一定の国際組織も含む)間の又は国際機関(国際連合等)による文書による合意を指し、名称は問わない。したがって、その名称は、条約のほか、憲章、協定、協約、宣言、議定書等さまざまである。憲法との関係では、その優劣につき学説上争いがあるが、法律以下の国内法令に対しては、条約が優位すると考えられている。
(次ページへ進む)
(前ページへ戻る)
5 不文法の種類
① 慣習法
慣習法とは、社会の慣行を通じて発生してきた社会生活の規範ともいうべき慣習が法規範として承認されたものをいう。
成文法中心主義を採用するわが国においては、慣習法が法源としての機能を果たすのは例外的な場合である。慣習が慣習法として認められるための要件を、「法の適用に関する通則法」第3条は「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。」と定めている。
したがって、公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反しない慣習で、「法令の規定により認められた」慣習か、「法令に規定されていない事項に関する」慣習に限られる。
② 判例法
判例とは、先例として機能する裁判例のことで、ある事件に対し下された判決の中で示された一般的規準が先例として規範化され、その後の同種の事件においても同じ内容の判決が下されるようになることから、この一般的に承認されるに至った判決(裁判所の判断)を判例(法)という。判例は、他の裁判官の法解釈を拘束することになり、一種の法規範となるので、事実上法源性を有する。
したがって、判例と裁判例は区別して呼ぶ必要がある。
なお、我が国では、先例拘束性の原理が明文で規定されておらず、また憲法第76条第3項において「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と裁判官の独立性が保証されていることから、判例は、確定的な法源とはいえないとされている。
なお、最高裁判所は、「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」は大法廷で裁判を行わなければならない(裁判所法第10条第3号)。
③ 条理
条理とは、道理・筋道のことであり、西欧では「事物の本性」ともいわれる。明治8年太政官布告103号「裁判事務心得」(民事に関する事項については、現在でも効力が残っているとされ、現在の総務省の法令データ提供システムにおいても、第3条~第5条は表示されている)の第3条において「民事の裁判に成文の法律なきものは習慣に依り習慣なきものは条理を推考して裁判すべし(原文はカタカナ)」と、条理に基づく判断を定めている。
しかし実質的な内容に関しては無いに等しいため、拘束力のある法源かどうかについては否定的な見解が多い。
なお、この第4条においても「裁判官の裁判したる言渡を以て将来に例行する一般の定規とすることを得ず」と、裁判における先例拘束性を否定している。
参考(法源性のない行政機関の内部規律)
以下のものは、所管の諸機関及び職員に対し、発せられる行政組織内の職務命令である。
したがって、これまで述べた法令等が、基本的に国家・地方公共団体職員のみならず一般国民をも拘束するのに対し、これらはあくまで国家・地方公共団体職員等を規律するものである。しかし、その内容が法令の解釈を示すためのものであれば、これら職員に遵守義務が課せられていることから、結果的にこれら職員の行政行為を通じて一般国民をも拘束する結果となる。だが法令ではないため、その適否が訴訟で争われた場合には、裁判所は法令に基づいて判断を下すことになる。したがって法源性はない。しかし、行政先例法(行政上の先例や取扱いが長年の間反覆・継続して行われているうちに、社会一般に法的確信をいだかせるようになり、慣習法として認められるに至ったものをいうとされる)の形成を認める見解もある。
① 告示
前記したように、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる(国家行政組織法第14条第1項)とされており、法令を補充する法規としての性質をもつもの(前記)と、行政機関内部の行政規則があり(そのほか、一般処分や事実行為の場合もあるが、ここでは省略する)、ここにおいてはこの後者を指す。
② 訓令
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる(国家行政組織法第14条第2項)とされており、行政機関及びその職員を対象として定める命令である。公共性が強く官報に掲載されるものと、非公表扱いのものがある。
③ 通達
訓令同様、国家行政組織法第14条第2項に基づくものである。上級機関が下級機関に対して、その機関の所掌事務について示達するため発出する公文書のことであり、法令の解釈等を示すものとして、当該法令を所管する省庁が下級機関に対して発遣することが多い。ただし、あくまで行政機関内部の文書であることから、通達で示された法令の解釈は司法の判断を拘束しないが、行政解釈を知る手段として重視される。
特に税法においては、税務通達が実務上非常に大きな影響を持っている。というのも、税に関する法令を具体的な事案に適用するにあたっては、法令の解釈が必要になるが、こうした解釈について課税庁全体における統一をはかるために通達が定められるからである。
なお、これには体系的に法令全体の解釈を示した基本通達と個別の事案ごとに示している個別通達がある。
④ 行政実例
「行政実例」とは、法令の解釈・運用について所管省庁の見解を示したもので、通達等とは異なり、都道府県・市町村からの照会に対して所管省庁が回答するという形式をとるものである。
これも通達と同じく、そこで示される解釈は司法判断への拘束力を持たないものであるが、指揮監督という関係に基づき、当該事案及び事後の同種事案において下級機関の判断を拘束する。
税務においては、地方税の取扱いにつき見解を示したものがある。
⑤ その他
インターネットによる行政機関のサイト等において、所管法令等の解釈がされることがある。税務においては、国税庁ホームページにおいて「タックスアンサー(よくある税の質問)」として回答を示しているものがある。
(了)
「税務判例を読むための税法の学び方」は、隔週での掲載となります。