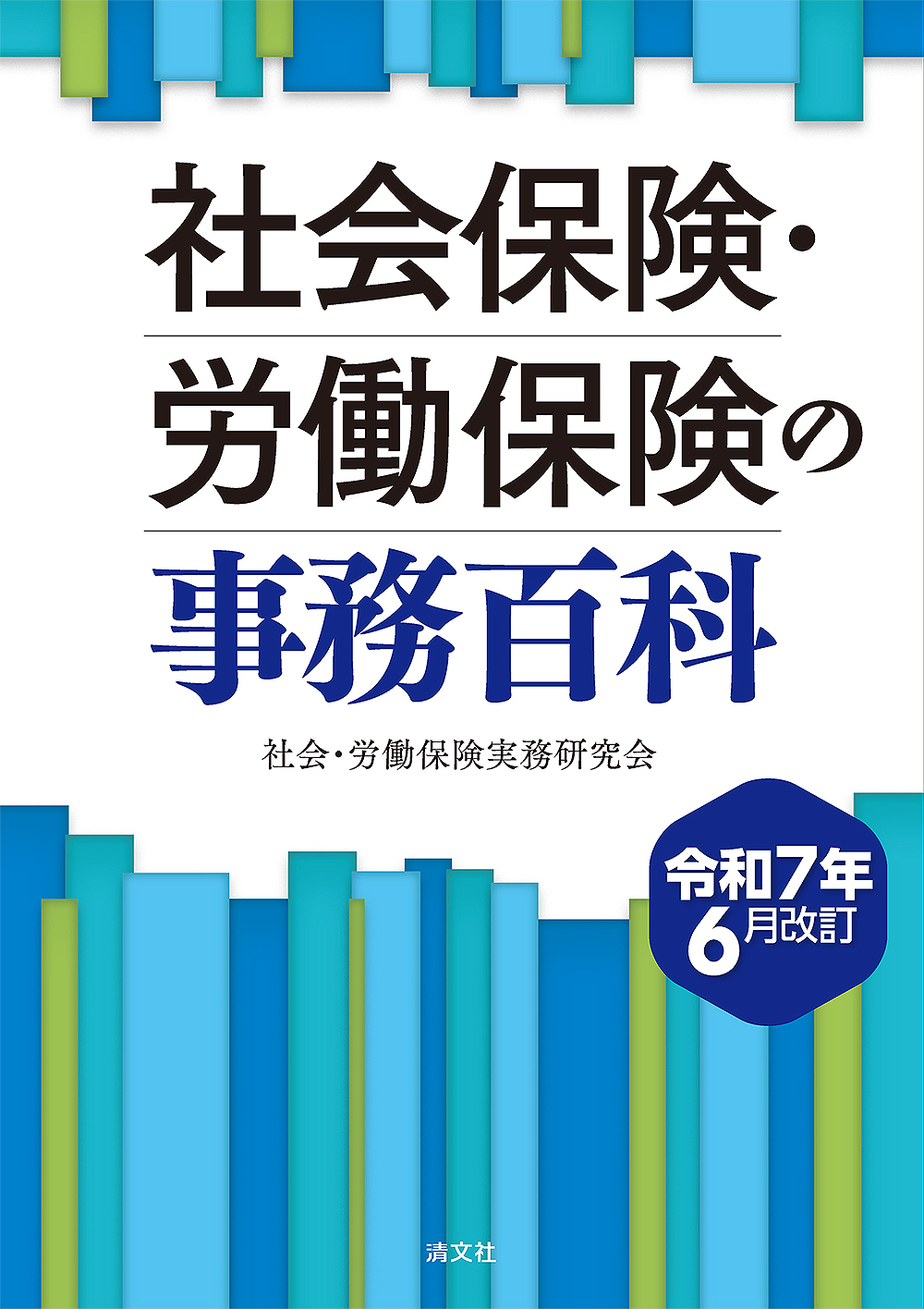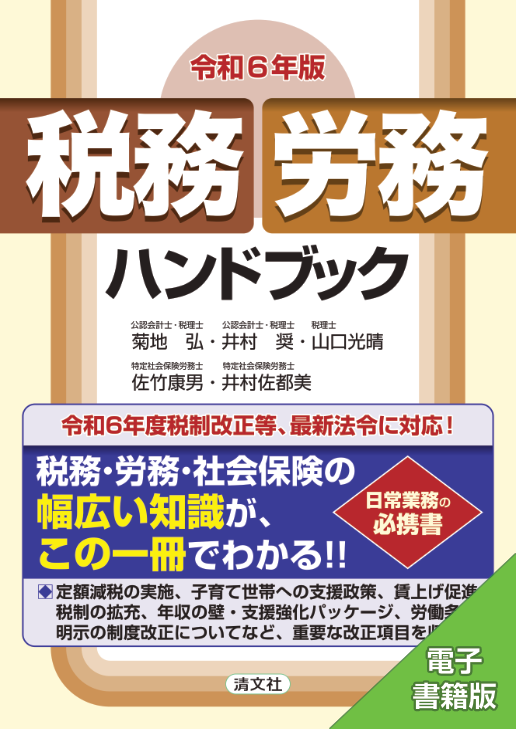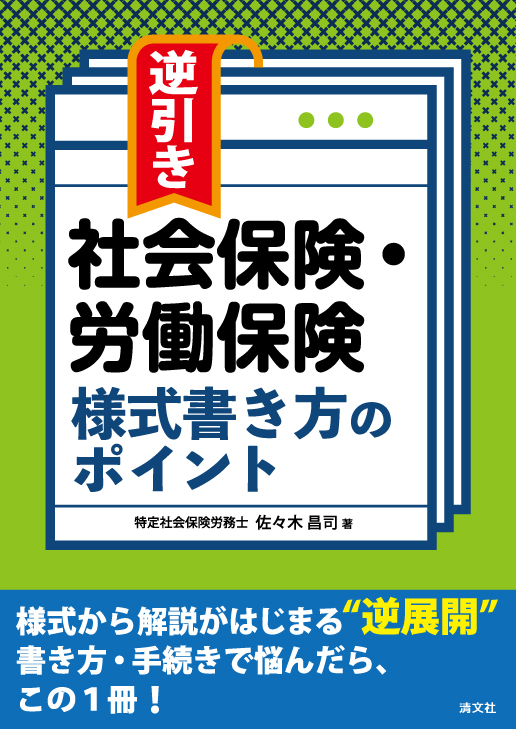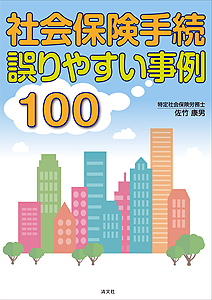最新!《助成金》情報
【第11回】
「雇用関連助成金の活用(その11)
《雇用調整助成金・障害者雇用関連助成金》」」
特定社会保険労務士 五十嵐 芳樹
《雇用調整助成金》
1 目的
この助成金は、景気変動や産業構造の変化など経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、出向により雇用を維持する事業主を助成することで、労働者の失業予防や雇用安定を図ることを目的とする。
2 対象要件
対象となる事業活動の縮小の要件は、次のすべてを満たすこと。
① 売上高又は生産量等の指標の最近3ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること。
② 雇用保険被保険者数及び受入れ派遣労働者数の最近3ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ大企業は5%を超えかつ6人以上、中小企業は10%を超えかつ4人以上増加していないこと。
③ 過去にこの助成金を受けたことがある場合は、直前の対象期間満了日翌日から1年を超えていること。
3 対象措置
この助成金の対象となる措置の概略は、事業主自らが指定した対象期間(1年間)内に行われる次のものとなる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。