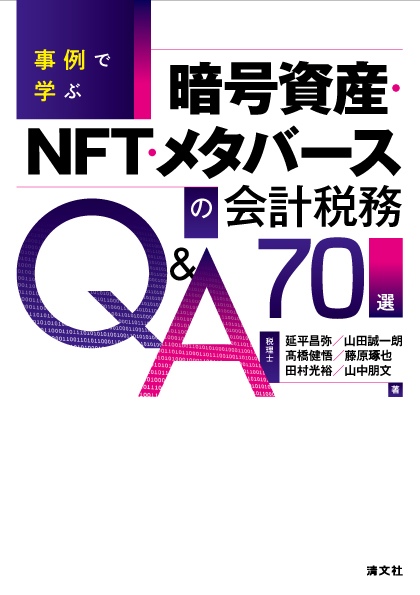〔令和元年度税制改正〕
仮想通貨に関する法人税制のポイント
【第1回】
「譲渡損益及び取得価額の算定方法」
税理士 小林 穣
ビットコイン等の仮想通貨は、個人だけでなく法人でも保有・使用することができます。
仮想通貨に関する会計・税務において、会計の面では2018年3月にASBJから「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表されましたが、税務の面では法律による定めはなく、2018年11月に国税庁から公表された「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」等をもとに実務が行われてきました。
令和元年度(平成31年度)税制改正では、これら国税庁資料で示されていた仮想通貨の譲渡損益の計算方法等が、所得税、法人税ともに税法上規定されました。本連載では、今年度改正で整備された仮想通貨に関する規定のうち法人税の関係について、そのポイントを2回にわたって解説します。
なお、日本では金融庁が中心となり、呼称を「仮想通貨」から「暗号資産」へ変更しようとする動きがありますが、本稿では「仮想通貨」を用いて解説を行います。
1 仮想通貨の譲渡損益
内国法人が仮想通貨の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額は、原則として、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入されます(法法61①)。
仮想通貨に関して譲渡損益を認識する主なケースは、次の4つがあります。
① 仮想通貨を日本円に換算(売却)した場合
② 仮想通貨で商品を購入した場合
③ 仮想通貨同士の交換を行った場合
④ 仮想通貨をマイニングにより取得した場合
(1) 譲渡損益の計算例
以下では、上記①~④ごとの譲渡損益の計算例をみていきます。
① 仮想通貨を日本円に換算(売却)した場合
保有する仮想通貨を日本円に換算(売却)した場合の所得金額は、その仮想通貨の売却金額と売却した仮想通貨の取得価額との差額になります(法法22・22の2)。
〔事例〕
1,800,000円で購入した4ビットコインのうち0.2ビットコインを100,000円で売却しました。
※仮想通貨の売買手数料については考慮しません。
【計算式】
※その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた額となります。
② 仮想通貨で商品を購入した場合
保有する仮想通貨で商品を購入した場合、保有する仮想通貨を譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その仮想通貨の譲渡価額と譲渡した仮想通貨の取得価額との差額となります(法法22・22の2)。
〔事例〕
1,800,000円で購入した4ビットコインのうち0.4ビットコインを189,000円(消費税等込)の商品を購入する際の決済に支払いました。なお、取引時における交換レートは1ビットコイン=472,500円です。
※仮想通貨の売買手数料については考慮しません。
【計算式】
※その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた額となります。
③ 仮想通貨同士の交換を行った場合
保有する仮想通貨Aを他の仮想通貨Bと交換した場合、仮想通貨Aで仮想通貨Bを購入したことになりますので、「②仮想通貨で商品を購入した場合」と同様に、所得金額を計算する必要があります(法法22・22の2)。
〔事例〕
1,800,000円で購入した4ビットコインのうち1ビットコインを10リップルを購入する際の決済に支払いました。なお、取引時における交換レートは1リップル=58,000円です。
※仮想通貨の売買手数料については考慮しません。
【計算式】
※その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた額となります。
④ 仮想通貨をマイニングにより取得した場合
仮想通貨をマイニング(採掘)により取得した場合、その所得は法人税の課税対象となります。
いわゆる「マイニング」等により仮想通貨を取得した場合、その取得価額に相当する金額の収益(時価)については益金の額に算入され、マイニング等に要した費用については損金の額に算入されることになります(法法22・22の2)。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨の取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。
(2) 適用関係及び経過措置
仮想通貨の譲渡損益の計算における改正については、平成31年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます(改正法附則12)。
ただし、経過措置として、改正事業年度(平成31年4月1日以後最初に終了する事業年度)前の事業年度において仮想通貨の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその仮想通貨の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額は、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入されます(改正法附則19①)。
(注) 契約日の属する事業年度の譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額を益金の額又は損金の額に算入している場合を除きます(改正法附則19①)。
2 仮想通貨の取得価額
(1) 原則的な取扱い
譲渡損益の計算における仮想通貨の取得価額は、購入した場合にはその支払対価に手数料等の付随費用を加算した額となります(法令118の5)。
〔事例①〕
~購入した場合~
国内の仮想通貨交換業者から、4ビットコインを1,800,000円で購入して購入時に手数料550円(消費税等込)を支払った場合の仮想通貨の取得価額は、1,800,550円になります。
なお、消費税の課税事業者(税抜経理方式を適用)である法人が、上記の取引を行う場合の購入した仮想通貨の取得価額は1,800,500円になります。
【計算式】
マイニング等により取得した仮想通貨の取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価(=益金に算入された金額)となります。
〔事例②〕
~マイニングにより取得した場合~
マイニングにより4ビットコインを取得した場合の仮想通貨の取得価額は、1,800,000円になります。なお、取引時における交換レートは1ビットコイン=450,000円です。
【計算式】
(2) 複数回にわたって仮想通貨を取得した場合の取得価額
同じ仮想通貨を複数回にわたって取得した場合の仮想通貨の取得価額の算出方法は、移動平均法又は総平均法による原価法により算出することとされています。
そして、その算出方法については所轄税務署長に届け出る必要があります(法令118の6①・④)が、届出等がなかった場合の法定算出方法は移動平均法による原価法とされました(法法61①二、法令118の6⑦)。
〔事例〕
国内の仮想通貨交換業者から、4ビットコインを1,800,000円で購入し、4ビットコインのうち0.2ビットコインを売却しました。後日さらに2ビットコインを870,000円で購入しました。
【計算式(移動平均法)】
【計算式(総平均法)】
(3) 適用関係
仮想通貨の譲渡損益の計算における取得価額の改正については、平成31年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます(改正法附則12)。
* * *
次回は、事業年度終了時の時価評価損益の算定と仮想通貨信用取引に係るみなし決済について取り上げます。
【凡例】
- 法法・・・・・・法人税法
- 法令・・・・・・法人税法施行令
- 改正法附則・・・所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則
- 資金決済法・・・資金決済に関する法律
(例)法法61①二・・・法人税法61条1項2号
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。