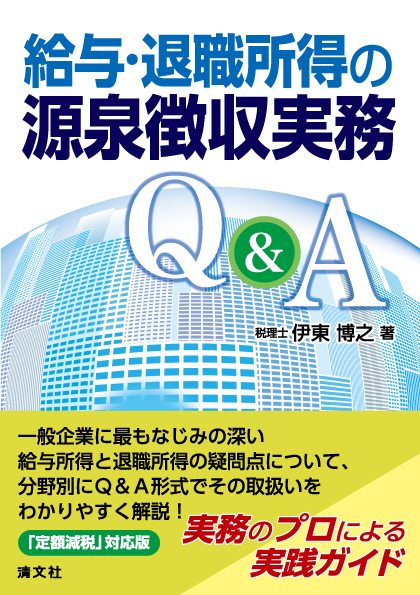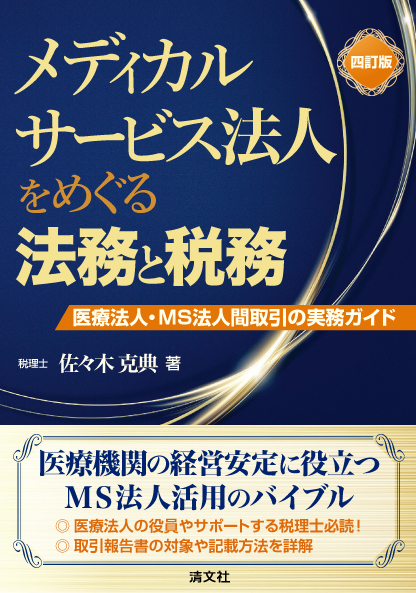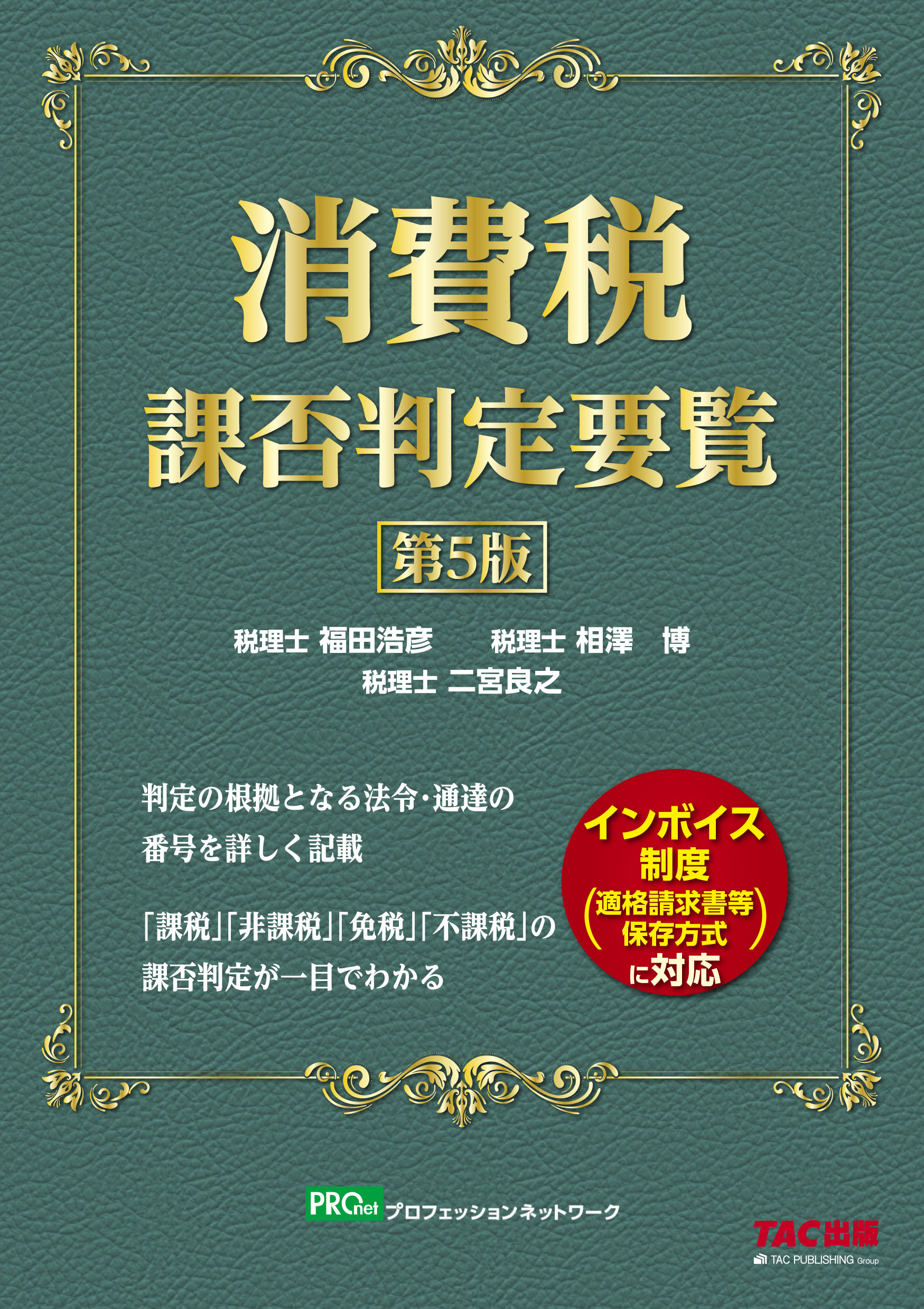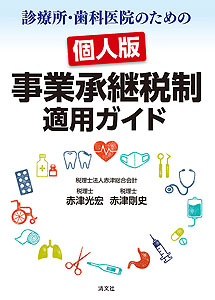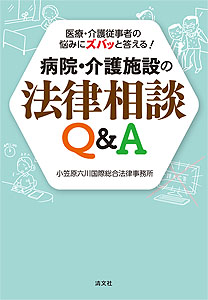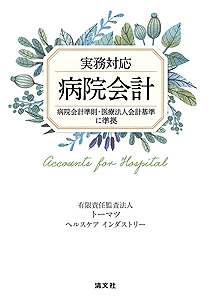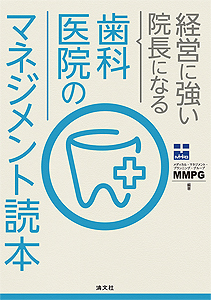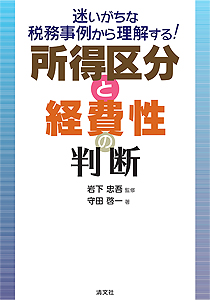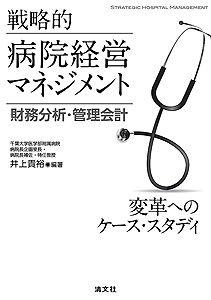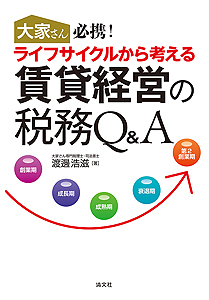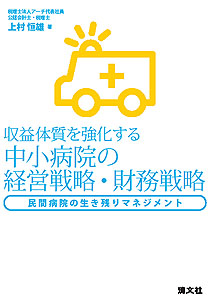〔Q&Aで解消〕
診療所における税務の疑問
【第1回】
「診療所の収入の所得区分と消費税の課税関係」
税理士法人赤津総合会計
税理士・医業経営コンサルタント
赤津 剛史
【Q】
診療所の収入の所得区分で判断に迷うものがいくつかあります。
以下の収入について、所得区分及び消費税の課税関係を教えてください。
① 自治体から委託を受けた予防接種や検診収入
② 休日夜間診療の報酬
③ 産業医の報酬
④ 原稿料、講演料
【A】
ご質問の収入について、所得区分及び消費税の課税関係は以下のとおりです。
● ● ● 解 説 ● ● ●
① 自治体から委託を受けた予防接種や検診収入
自治体から委託を受けた予防接種や検診収入は、診療所の診療に付随する行為として、自費診療収入となります。つまり、個人診療所であれば「事業所得」に計上され、医療法人であれば法人の益金に算入されます。
消費税は個人診療所、医療法人ともに課税売上として取り扱います。
② 休日夜間診療の報酬
休日夜間診療の報酬は、従事する形態によって所得区分が異なります。そのため2つのケースに分けて、以下でみていきます。
[ケース1] 地域の救急センター等で従事する場合
- 医師が自治体や一部事務組合が開設する救急センター等に赴き、休日・夜間に診療を行い、当該自治体や一部事務組合から受ける報酬は、医師個人の「給与所得」に該当します(所基通28-9の2)。
- 消費税は不課税となります。
[ケース2] 輪番制で自身の診療所で診療する場合
- 医師が自治体からの委託に応じて休日・夜間に、自己の診療所にて診療を行い、当該自治体等から受ける報酬は、「事業所得」に該当します。また、診療所を医療法人が営むときは法人の益金に算入されます(所基通27-5)。
- 消費税は委託収入として課税売上となります。
③ 産業医の報酬
「産業医」とは、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。労働安全衛生法により、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。
産業医の委託報酬は、個人診療所においては医師個人の「給与所得」に該当し、消費税は不課税として取り扱います。
一方、医療法人が事業場と産業医の派遣契約を締結し、勤務医を産業医として派遣したときは、委託収入として医療法人の益金となり、消費税は課税売上となります。
④ 原稿料、講演料
医師個人が製薬会社等からの依頼に基づき、執筆した論文等に対する原稿料及び講演をしたことによる講演料等はいずれも個人の「雑所得」になります。
また、原稿料・講演料ともに、医師個人の診療という本来の事業に関連する内容の論文や講演を行う場合には本来業務の付随行為に該当することから、消費税の課税売上に該当すると考えられます。
なお、参考までに国税庁の質疑応答事例「消費税における「事業」の定義」を以下に引用します。
【照会要旨】
消費税法上における「事業」の定義は何でしょうか。
所得税の通達では「事業」と「業務」を区分して考えていますが、消費税においては区分する必要はないのでしょうか。
【回答要旨】
消費税においては、事業者が「事業」として行う財貨・サービスの提供を課税対象としていますが、この場合の「事業」とは、「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をいいます。これは、消費税が消費者に負担を求める税であることにかんがみ、個人が消費者として行う行為を課税対象から除外するためのものです。
なお、所得税法における「事業」と「業務」の区分は、所得金額の計算上、その者が支出する費用等について必要経費として収入金額から控除できる範囲を考える場合の基準として用いられているものであり、この区分けを消費税の世界にもちこむ必然性、必要性は特にありません。消費税法にいう「事業」は、所得税法にいう「事業」よりも広い概念です。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第4条、消費税法基本通達5-1-1
(出典) 国税庁・質疑応答事例「消費税における「事業」の定義」
◆◇税務監査実務上の留意点◇◆
個人診療所及び医療法人の税務監査においては、収入の帰属先及び所得区分並びに消費税の課税判定について判断に迷う場面が多くあります。
本来は、医師個人の収入となるものが、医療法人の預金口座へ振込まれているケースも散見されます。支払い側の認識の相違により、医療法人との産業医の派遣契約に基づく支払いに源泉所得税が徴収されているという事例もあります。
経理処理にあたっては、支払い側の経理処理と整合する必要があり、請求書、支払通知書、契約書といった証憑資料の確認という基本の徹底を行い、場合によっては支払い側に直接確認をするといった一歩踏み込んだ税務監査が必要となります。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。