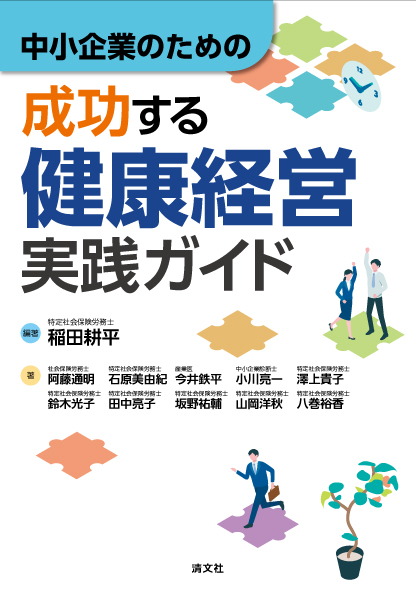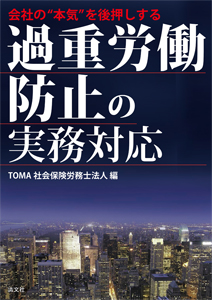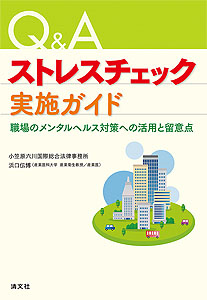義務だけで終わらせない「ストレスチェック」の活かし方
【第3回】
(最終回)
「ストレスのメカニズムから考えるメンタルヘルス対策」
特定社会保険労務士 大東 恵子
メカニズムに則った対策を
前回はストレスのメカニズムについて、説明させていただいた。12月からスタートするストレスチェックやメンタルヘルス対策について考えるとき、このストレスのメカニズムに則って進めることが重要である。すなわち、それぞれメカニズムのどこの部分に対する結果で、どの部分に対するアプローチを考えなければならないのかをしっかりと捉えることが大切である。
その上で、厚生労働省が「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の中で提唱している、
- 労働者自身の「セルフケア」
- 管理監督者による「ラインによるケア」
- 事業場内の健康管理担当者による「事業場内産業保健スタッフによるケア」
- 事業場外の専門家による「事業場外資源によるケア」
の“4つのケア”が、メカニズムのそれぞれの部分によって、それぞれの役割を果たすことで、適切なメンタルヘルス対策を進めることが可能となる。
“4つのケア”の効果
まずは、ストレスチェックによって、職場に蔓延するストレッサーにはどのようなものがあるのか、人間関係の状況はどうか、仕事の質や量は適切かなどを査定することになる。ここに何か問題があるならば、「ラインによるケア」として管理監督者による仕事量を調整し残業を無くすなどの対策が必要となる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。