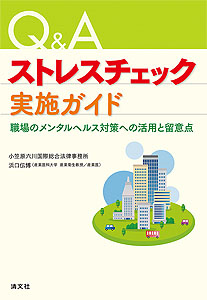改正労働者派遣法への実務対応
《派遣先企業編》
~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~
【第1回】
「期間制限への対応①」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
-はじめに-
国会で成立してからわずか19日で施行された改正労働者派遣法。成立から施行までの期間が極めて短く、改正内容の把握すら十分にできない中でスタートしたが、施行後数ヶ月が経過し、ようやくその全体を把握することができる段階となっている。今はまさにそれぞれの会社において対応策を講じている頃だと思われる。
「改正労働者派遣法のポイント」については下記の通り、本誌No.138からNo.141において確認したが、今回は、改正労働者派遣法への実務対応として、「派遣先企業」と「派遣元企業」に対象を分け、それぞれに焦点をあてて考えていきたい。
[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント
まずは、《派遣先企業編》として、派遣先企業に求められる対応内容について、5回にわたって検討する。なお、今後、次の項目を取り上げることを予定している。
【第1回】 期間制限への対応①
【第2回】 期間制限への対応②
【第3回】 均等待遇等への対応
【第4回】 労働者派遣契約等の見直し
【第5回】 研修の実施等
【第1回】及び【第2回】は、改正により新しい考え方が導入された期間制限への対応について検討したい。なお「新しい期間制限の考え方」については下記の拙稿を参照されたい。
1 「事業所」「組織単位」の特定
(1) 「事業所」の特定
「事業所」単位の期間制限では、「事業所」毎に派遣可能期間が制限され、その期間は原則3年となる。そこで、「事業所」単位の期間制限に対応するためには、ここでいう「事業所」が、自社の組織にあてはめるとどの範囲になるのかについて整理が必要となる。
「事業所」とは、以下の観点等から実態に即して判断することとされている。
① 場所的に独立していること
② 経営の単位として人事、経理、指揮監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること
③ 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること
上記について補足すると、以下の通りとなる。
① 場所的に独立していること
「事業所」の基本的な考え方となり、住所地毎に捉えることを意味する。つまり、住所地が同じであれば1つの「事業所」とし、住所地が異なれば別の「事業所」とする。
なお、同じビルの複数のフロアに入居している場合も、住所地はすべて同じと捉え、同じビルに入居している組織全体を1つの「事業所」として捉える。
② 経営の単位として人事、経理、指揮監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること
指揮命令等がある程度完結している単位を意味する。この点については、逆の視点で、経営の単位として独立性がない場合を除外する方がわかりやすい。
「経営の単位として独立性がない場合」とは、例えば、出張所やサテライトオフィス等で、規模が小さく、直属の上司は直近上位の組織に所属し、直近上位の組織にいる上司から指揮命令を受ける場合が該当する。
この場合は、直近上位の組織と出張所等の住所地は異なるが、出張所等は直近上位の「事業所」の一部として捉える。
③ 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること
この点についても②と同様に、逆の視点で、施設としての持続性がない場合を除外する方がわかりやすい。
「施設としての持続性がない場合」とは、例えば、臨時的に事業所を設置する場合が該当し、この場合もその事業所は直近上位の「事業所」の一部として捉える。
* * *
つまり、「事業所」とは、一部の例外(②③で除外されたもの)を除けば、住所地基準の組織グループであり、「事業所」単位の期間制限では、このグループ毎に派遣可能期間を管理することになる。
(2) 「組織単位」の特定
「個人」単位の期間制限では、派遣労働者「個人」毎に派遣可能期間が制限され、その期間は派遣労働者「個人」毎に同一の「組織単位」において3年となる。「組織単位」が変われば、派遣先は同じ派遣労働者を引き続き受け入れることが可能となるため、「個人」単位の期間制限に対応するためには、「組織単位」の考え方について整理が必要となる。
「組織単位」については、労働者派遣事業関係業務取扱要領で以下の考え方が示されているため、これらに照らして検討することとなる。
- 事業所等における組織単位については、法第40条の3の期間制限の目的が、派遣労働者がその組織単位の業務に長期にわたって従事することによって派遣就業に望まずに固定化されることを防止することであることに留意しつつ判断することになる。
- 具体的には、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するものであって、派遣先における組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想定しているが、名称にとらわれることなく実態により判断すべきものである。
- ただし、小規模の事業所等においては、組織単位と組織の最小単位が一致する場合もあることに留意する必要がある。
つまり、「個人」単位の期間制限では、基本的には指揮監督権限を有する組織の長を基準とするグループ毎に派遣可能期間を管理することになる。
2 意見聴取の手続き
「事業所」単位の期間制限では、「事業所」毎に派遣可能期間が制限され、その期間は原則3年となるが、意見聴取の手続きを行うことによって、派遣可能期間は3年を上限として何度でも延長することができる。
(1) 手続きの流れ
意見聴取は、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(以下、過半数労働組合)に対して、過半数労働組合がない事業所では労働者の過半数を代表する者(以下、過半数代表者)(過半数労働組合と過半数代表者を合わせて、以下、過半数労働組合等)に対して行う必要があるが、その手続きの流れは以下の通りとなる。
[Step1] 書面通知
◆会社から過半数労働組合等へ、以下の事項を書面で通知する。
① 派遣可能期間を延長しようとする事業所
② 延長しようとする派遣期間
◆意見聴取の参考となる資料(事業所の派遣労働者の受け入れの開始以来の派遣労働者数や派遣先が無期雇用する労働者数の推移等)を合わせて提示する。
[Step2] 意見聴取
◆過半数労働組合等から意見を聴取する。
[Step3] 方針説明
◆ [Step2]で過半数労働組合等が異議を述べたときは、以下の事項を説明する。
① 延長しようとする期間及びその理由
② 過半数労働組合等の異議(常用代替に関する意見に限る)への対応に関する方針
[Step4] 書面保存
◆意見聴取後、以下の事項を書面に記載して、延長した派遣可能期間の終了後3年間保存する。
① 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名
② 過半数労働組合等に書面通知した日及び通知した事項
③ 意見を聴いた日及び意見の内容
④ 過半数労働組合等に対して説明した内容
⑤ 意見を聴いて延長する期間を変更したときは、その変更した期間
⇒つまり、[Step1]~[Step3]の事項を書面で保存する。
[Step5] 従業員周知
◆[Step4]の①~⑤の事項を、従業員に法令で定める以下のいずれかの方法により周知する。
① 常時見やすい場所へ提示し、又は備え付ける。
② 書面を従業員に交付する。
③ 電子データとして記録し、従業員がその記録内容を常時確認できるパソコン等の機器を設置する。
(2) 留意点
① 手続きの実施時期
上記[Step2]については「事業所」単位の期間制限の抵触日の1ヶ月前の日(例:派遣可能期間が9月30日までであれば、抵触日は10月1日となるため、その1ヶ月前の9月1日)までに、[Step3]については「事業所」単位の期間制限の抵触日の前日(例:派遣可能期間が9月30日までであれば、抵触日は10月1日となるためその前日の9月30日)までに実施する必要がある。
なお、労働者派遣契約においては、期間制限の抵触日以降の期間を派遣期間として定めることはできないため、労働者派遣契約の更新手続き時期を考慮すると、意見聴取の手続きは、期間制限の抵触日の1ヶ月前の日までに手続き完了を目指すのではなく、かなり早い段階で手続きを行うことになるだろう。
② 異議
[Step3]における異議とは、派遣可能期間を延長することに反対する意見だけでなく、以下の意見も含まれるため、注意が必要となる。
- 延長する期間の短縮を求める意見
- 今回限り延長を認める意見
- 受入派遣労働者数を減らすことを前提に延長を認める等の条件付き賛成の意見
また、2回目以降の意見聴取の際に、再度、過半数労働組合等から異議が述べられた場合は、その意見を十分に尊重し、派遣可能期間の延長の中止や延長期間の短縮、延長しようとする派遣労働者数の減少等の対応を検討した上で、その検討結果をより一層丁寧に過半数労働組合等に説明することが必要とされている。
③ 事前準備
手続きの流れを確認した上で、意見聴取の際に必要となるものについては、準備しておくとよい。[Step1]や[Step2]で使用する書式は、労働局によってはサイト上で書式を例示しているので参考にしたい。
また、[Step5]の従業員への周知方法についても事前に決めておきたい。周知方法については上記のように法令で定めた方法による必要があるが、就業規則や労使協定等の周知でも法令に同様の定めがあるため、同じ対応をすればよいであろう。
④ 延長の必要性
意見聴取をする前に、そもそも派遣可能期間を延長する必要があるのか、検討が必要となる。つまり、派遣労働の利用は臨時的・一時的なものが原則であるという考え方を踏まえて、自社において派遣労働者の受け入れを継続すべきか、派遣労働者の受け入れをやめて新しく従業員を採用すべきか、検討した上で方針を決定する必要がある。
なお、意見聴取により異議が述べられた場合は、ここで検討した内容を過半数労働組合等に説明することになる。
* * *
【第1回】は、派遣可能期間を管理する単位の整理と、「事業所」単位の派遣可能期間を延長する場合に必要な意見聴取の手続きを確認した。
次回は、過半数労働組合がない場合に意見聴取の当事者となる過半数代表者の選出等についてみていく。
(了)