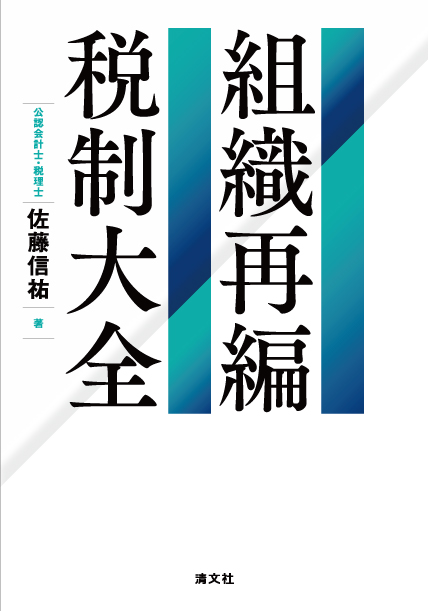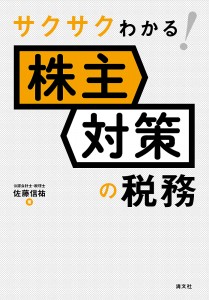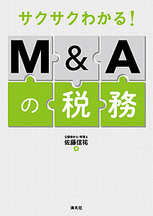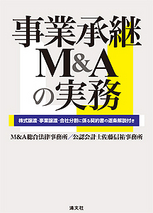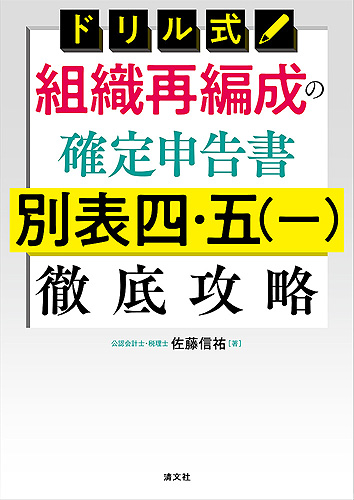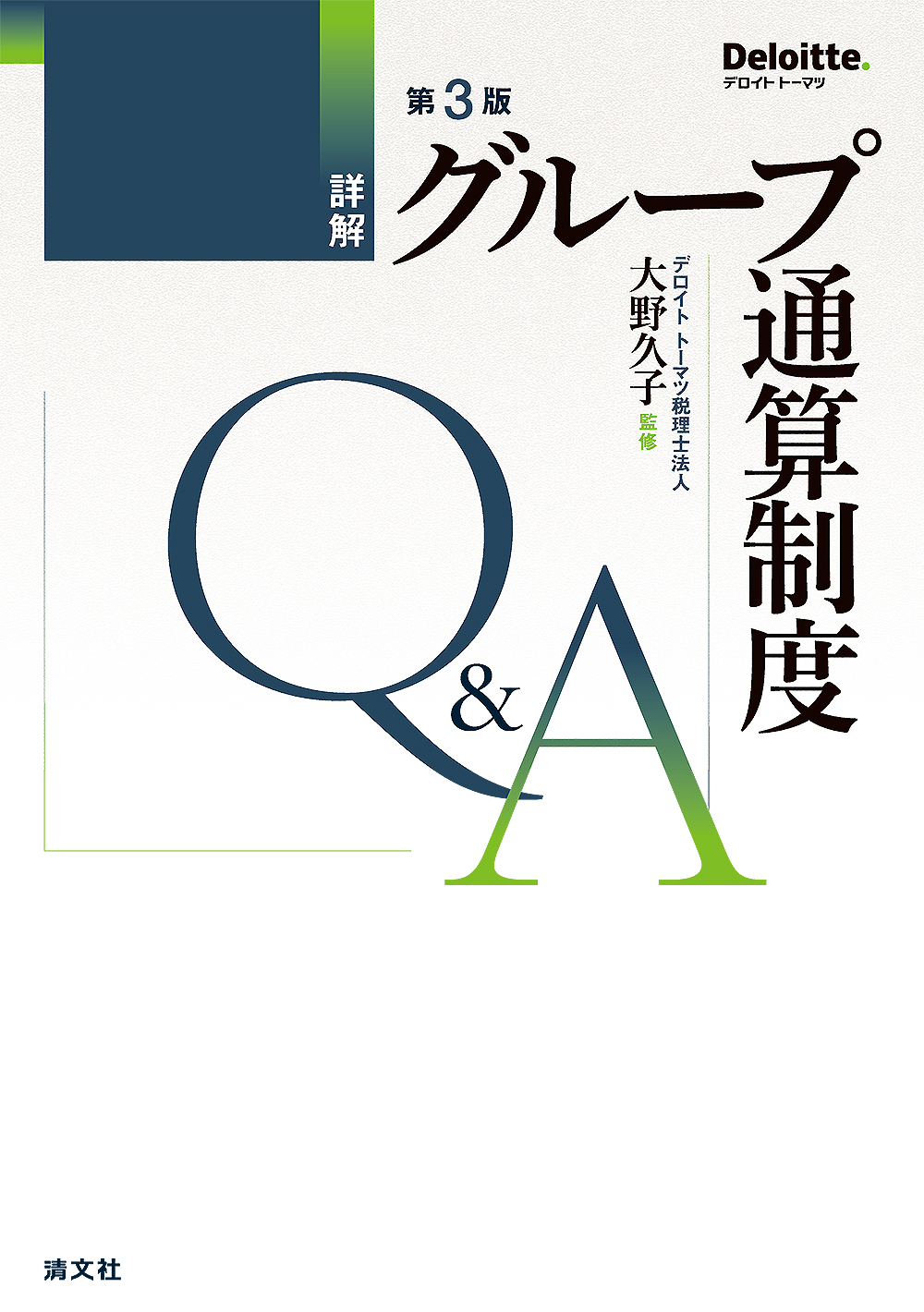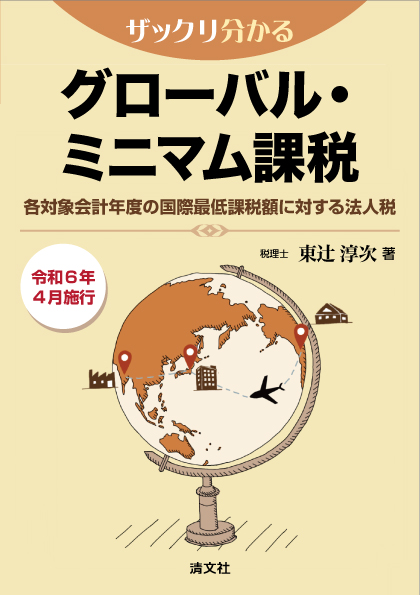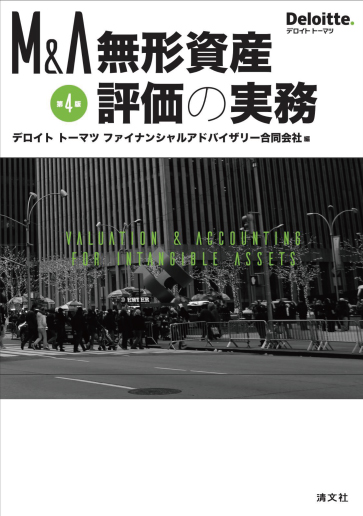〈検証〉
TPR事件 東京地裁判決
【第1回】
公認会計士・税理士 佐藤 信祐
連載の目次はこちら
1 本事件の概要
TPR事件とは、平成22年3月1日に行われた適格合併による繰越欠損金の引継ぎに対して、包括的租税回避防止規定が適用された事件である。本事件では、平成24年7月27日付けで、平成22年3月期の確定申告について更正処分を受けていたにもかかわらず、平成27年6月26日付でもう一度更正処分を受けているが、このように同じ事業年度の確定申告について2回も税務調査を受けることは稀である。
さらに、本件適格合併を行う前に、東京国税局に対して、平成14年3月から特定資本関係(現行法では「支配関係」に名称変更)が継続しているという認識で問題がないかという問い合わせをしている。その際に、包括的租税回避防止規定(法法132の2)についての回答は得られるはずはないが、その時の東京国税局の対応からして、「おそらく租税回避だとは認識していないだろう」という心証を得ていたことは推察される。
このような事情があったとしても、包括的租税回避防止規定に対するリスクが軽減されるわけでもないということで、かなり実務上は慎重に対応しなければならないことがわかる。
さらに、平成22年3月1日に行われた適格合併による繰越欠損金の引継ぎについての事件であることから、TPR事件で争われているのが、平成22年改正前法人税法に係る事件であるという点にご留意されたい。本稿でも問題視しているが、東京地裁の判旨は、平成22年度税制改正と整合しない。そうなると、現行法に当てはめたときに、TPR事件の射程がどこまで及ぶのかという点が問題になってくる。
TPR事件の特徴としては、適格合併を行う前に、被合併法人で行っていた事業を新会社に移転したという点が挙げられる。具体的には、被合併法人と商号、目的及び役員構成が同一の新会社を設立し、合併の効力発生日に、被合併法人の従業員全員が当該新会社に転籍している。さらに、合併の効力発生日に、新会社に対して、被合併法人が営んでいた事業に係る棚卸資産等を譲渡するとともに、未払費用等の負債を承継させている。このように、被合併法人が営んでいた事業、従業員が新会社に移転し、合併法人には移転していないことから、本件合併が繰越欠損金を引き継ぐための行為であり、事業目的が十分に認められないようにも思える。
しかしながら、被合併法人から合併法人に対して、被合併法人が営んでいた事業に係る工場の建物及び製造設備を引き継がせ、合併法人から新会社に賃貸している。そのため、本件組織再編が行われる前の被合併法人の貸借対照表と本件組織再編が行われた後の新会社の貸借対照表は全く別物になっていることから、事業目的が十分に認められるようにも思える。
これに対し、賃貸借の対象となった建物及び製造設備に係る減価償却費等に相当する賃料を新会社から合併法人に対して支払っているため、一見、本件組織再編に伴って新会社の損益計算書は改善されていないようにも見える。そのため、東京地裁は、新会社の損益構造の改善は、仕入価格の変更によるものであり、合併によらずとも達成可能であったとして、納税者の主張を認めなかった。
このように、東京地裁の判断は、納税者にとって厳しいものとなっており、事業目的を主張するにしても、丁寧な事実関係の積み重ねが必要になることがわかる。さらに言えば、本事件における東京地裁の判断を決定づけたのは、「裁判官の心証」と言っても過言ではない。
子会社の経営改善のための組織再編ではなく、適格合併による繰越欠損金の引継ぎを享受するための組織再編であるかのような印象を持たれるような会議資料が作成された結果、明らかに事業目的が存在する組織再編について、「税負担の減少が主目的である」と判示されずに、「法人税の負担を減少させること以外に本件合併を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事情があったとは認められない」と判示されてしまっている時点で、税務調査の段階において、事業目的が十分に認められる証拠資料をきちんと整備しておけば、異なる結論になっていた可能性はあったと言える。
2 本当に事業目的がないと言えるのか
そもそも当初案では、TPRの一部門として、原材料の調達を行う部門を新設し、新会社は人員のみを抱えた賃加工会社の形態となり、TPRから設備を貸与され、材料も支給されることとなって、原則として、利益も赤字も出ない会社になることを予定していた。このような手法は一般的であり、新会社が人員のみを抱えた賃加工会社になるのは、TPRと新会社の賃金体系が異なるからに過ぎない。
国側の主張においても、当初案については、税負担の減少目的が主目的であったと主張しながらも、旧子会社の損益を改善させるという事業目的が存在していたことは認めていることから、当初案の通りであれば、包括的租税回避防止規定が適用されなかった可能性も十分に考えられる。
その後、新会社に責任を持たせるために、減価償却費等を新会社に請求させるとともに、当該減価償却費等を加味した原価を考慮したうえで、新会社からTPRが仕入れる製品の仕入価格を見直したのである。つまり、減価償却費等を新会社に請求しながらも、仕入価格に反映させることにより、最終的に、TPRが負担した形になっている。
このような仕入価格の変更は、形式的には、新会社にコスト意識を持たせるという効果が期待されるが、実質的には、TPRがコストを負担する形になるということで、当初案通り、新会社が利益も赤字も出ない賃加工会社になるのと何ら変わらない。すなわち、一連の組織再編により、被合併法人が営んでいた事業に係るリスクとリターンのすべてが合併法人に移転されており、このような実態の変化は、合併により合併法人が建物及び製造設備を引き継がないと不可能であり、仕入価格の変更のみでこのような効果を実現させたいとクライアントから相談された場合には、ほとんどの税理士が「仕入価格が時価と異なるということで、寄附金として認定されるリスクがある」と回答するであろう。
さらに言えば、東京地裁も、受注減少に伴う赤字リスクがTPRに帰属するようになったことは認めたうえで、赤字リスクがTPRに帰属したのは、仕入価格の変更によるものであり、合併によるものではないと認定しているのである。
このように、本事件は、租税回避であると認定されるべきものとはとても思えないし、「法人税の負担を減少させること以外に本件合併を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事情があったとは認められない」というのは明らかに言い過ぎである。
結局のところ、TPR事件を参考に、租税回避として認定されないようにするためには、事業目的が主目的であるという心証をどのように与えるのかという点に尽きる。
もちろん、会議に提出される資料に税務上の効果が書かれないというのは、税務を検討せずに組織再編を行ったということで取締役の責任が問われるため、税負担減少の意図がないと主張するのは不可能である。そうだとしても、事業目的が主目的であるという会議資料を作ることは容易であるし、事業目的が主目的であるという外観を作ることも容易である。そう考えると、税務調査に耐えうる証拠書類をどのように整備していくのかという点が、租税回避として認定されないために重要であるということが言える。
このように、本事件では、包括的租税回避防止規定を適用しなければならないほど、制度趣旨に反することが明らかな取引であったかどうかという点も問題であるが、それ以前に、東京地裁が示した制度趣旨にも疑問がある。
次回では、東京地裁が示した制度趣旨について解説を行う。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。