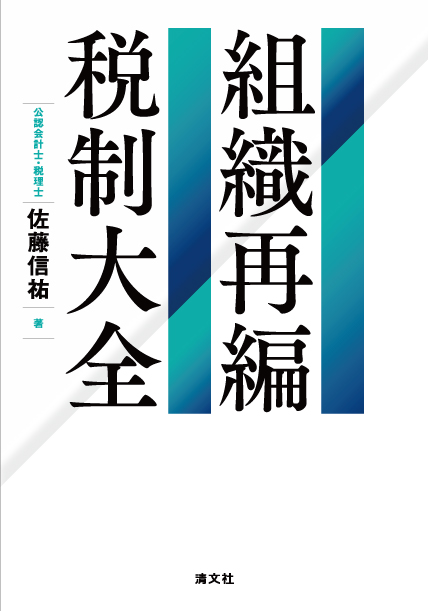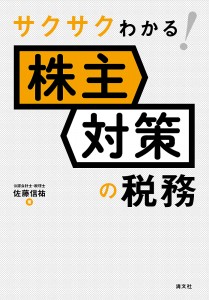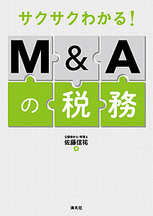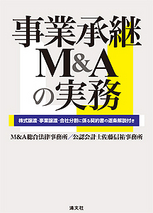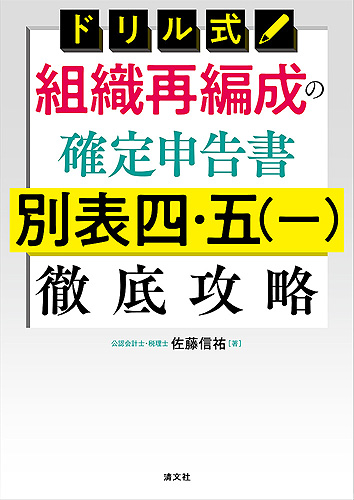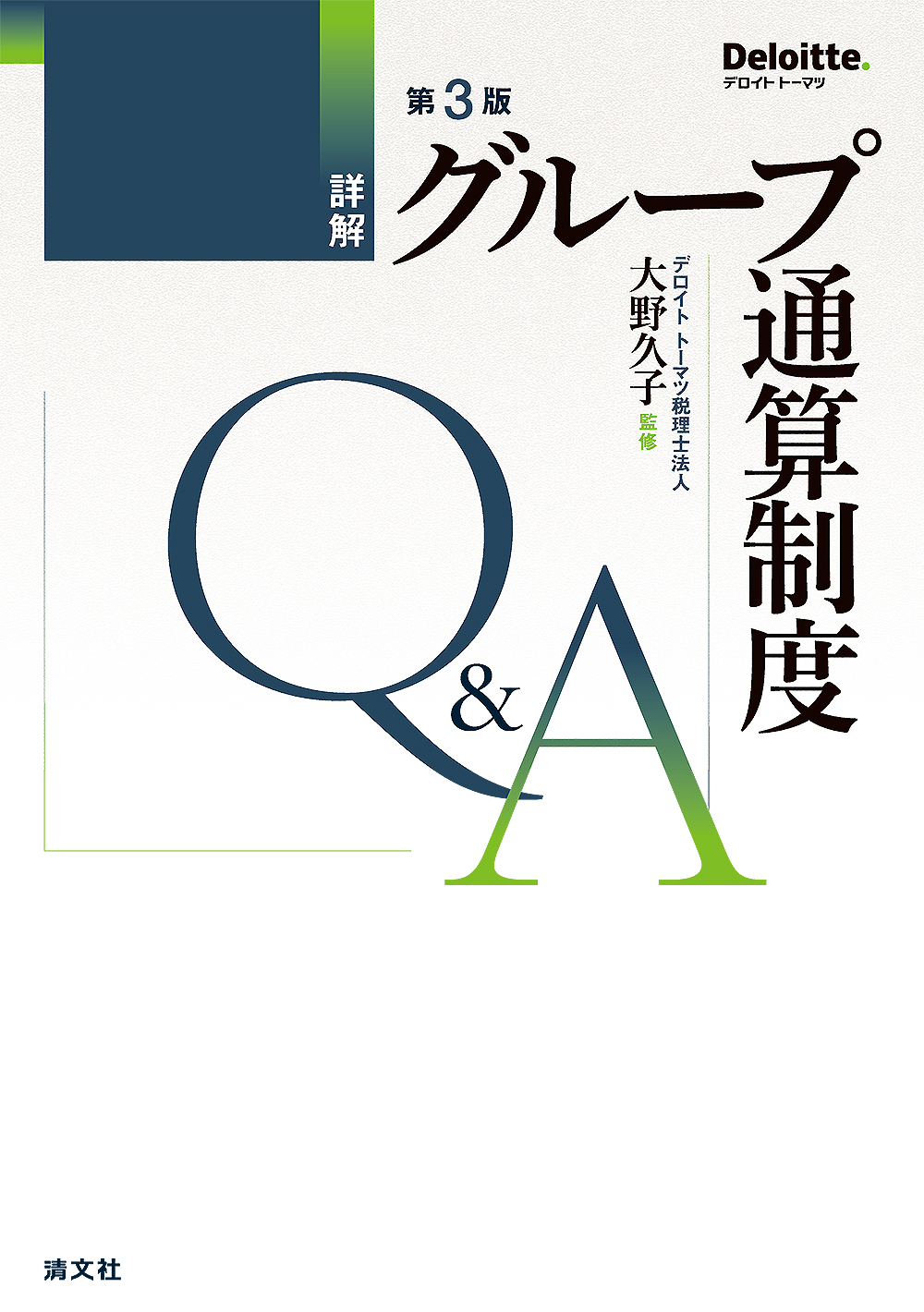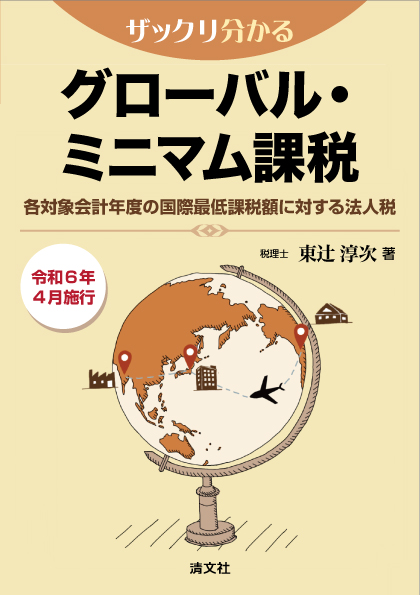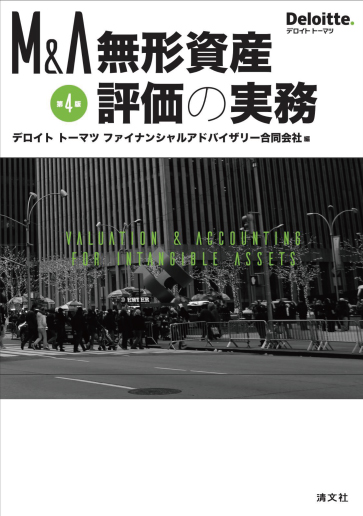〈検証〉
TPR事件 東京高裁判決
【第1回】
公認会計士・税理士 佐藤 信祐
1 はじめに
拙稿「〈検証〉TPR事件 東京地裁判決」(2019年10月に本誌掲載)で解説したように、TPR事件とは、平成22年3月1日に行われた適格合併による繰越欠損金の引継ぎに対して、包括的租税回避防止規定が適用された事件である。
すでに解説したように、TPR事件の特徴として、適格合併を行う前に、被合併法人で行っていた事業を新会社に移転したという点が挙げられる。そのため、東京地裁でも、被合併法人が営んでいた事業、従業員が新会社に移転し、合併法人には移転していないことから、本件合併が繰越欠損金を引き継ぐための行為であり、事業目的が十分に認められないと判断している。この点については、裁判官の心証によるものも大きく、判決文だけでは判断できないものも多いため、敢えて分析を行う必要もないと思われる。
これに対し、包括的租税回避防止規定(法法132の2)の適用は、制度趣旨に反することが明らかであることが前提となっているものの、そもそも東京地裁、東京高裁が示した制度趣旨に問題があるという点については、再度、分析を行う必要があると考えている。
2 TPR事件東京高裁判決(令和元年12月11日Westlaw. japan文献番号2019WLJPCA12116002)
東京高裁では、争点(1)(特定資本関係が合併法人の当該合併に係る事業年度開始の日の5年前の日より前に生じている場合に法人税法132条の2を適用することができるか否か)について、争点(2)(本件合併が法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるか否か)について争われているが、争点(1)において納税者(控訴人)の主張が認められないのは当然のことなので、争点(2)のみについて分析を行うこととする。
まず、争点(2)に対する納税者の主張は以下の通りである。
適格合併について定める同法2条12号の8では、合併法人と被合併法人間に完全支配関係がある場合は、被合併法人の株主等に合併法人株式以外の資産が交付されないことという要件(金銭等不交付要件)のみを充たせば足りるものとされ(同号イ)、従業者引継要件及び事業継続要件は必要とされない。これは、立法過程において、完全支配関係がある場合には、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」及び「組織再編成後も移転した事業が継続すること」との要件を緩和することも考えられるとされ、そのように適格合併の要件が立法化されたことによる。したがって、完全支配関係での合併では、金銭等不交付要件が唯一の税制適格要件とされているのであるから、完全支配関係での合併では、「移転資産に対する支配の継続」及び「事業の継続」は求められていないと解するほかない。仮に、完全支配関係での合併における未処理欠損金額の引継ぎにつき、「移転資産に対する支配の継続」及び「事業の継続」が求められていると解しても、完全に一体と考えられる持分割合の極めて高い法人間の組織再編成では、元々、合併当事者は経済的、実質的に完全に一体であったから、金銭等不交付要件を充たせば、「移転資産に対する支配の継続」及び「事業の継続」も充足されるとの解釈で税制適格要件が定められたものといえる。
これに対し、裁判所は、以下のように判示している。
確かに、完全支配関係にある法人間の適格合併については(法人税法2条12号の8イ)、支配関係にある法人間の適格合併におけるような従業者引継要件及び事業継続要件(同条12号の8ロ)の定めは設けられていない。しかしながら、原判決第5・3(2)が説示するように、組織再編税制は、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がなく、移転資産等に対する支配が継続する場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるということを基本的な考え方としており、また、先に組織再編税制の立案担当者の説明を引用して判示したとおり、組織再編税制は、組織再編成により資産が事業単位で移転し、組織再編成後も移転した事業が継続することを想定しているものと解される。加えて、これも原判決が第5・3(2)で説示するとおり、支配関係にある法人間の適格合併については、当該基本的な考え方に基づき、前記の従業者引継要件及び事業継続要件が必要とされているものと解され、殊更に、完全支配関係にある法人間の適格合併について、当該基本的な考え方が妥当しないものと解することはできないから、当該適格合併においても、被合併法人から移転した事業が継続することを要するものと解するのが相当である。
このように、東京高裁の判断は、東京地裁の判断とほとんど変わらないということが言える。納税者としては、「完全支配関係での合併では、金銭等不交付要件が唯一の税制適格要件とされているのであるから、完全支配関係での合併では、「移転資産に対する支配の継続」及び「事業の継続」は求められていないと解するほかない。」とまで主張したが、その前段階として、「立法過程において、完全支配関係がある場合には、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」及び「組織再編成後も移転した事業が継続すること」との要件を緩和することも考えられるとされ、そのように適格合併の要件が立法化されたことによる。」と主張したことは失敗だったように思われる。
納税者が勝訴するためには、要件を緩和したというだけに留まらず、そもそも「資産の移転が独立した事業単位で行われること」及び「組織再編成後も移転した事業が継続すること」という要件は不要であったと主張しなければならないため、以下のように主張すべきであったと考えられる。
そもそも移転資産等の譲渡損益の計上を繰り延べる企業グループ内の組織再編成は、完全支配関係での組織再編成のみとすべきところ、現に企業グループとして一体的な経営が行われている単位という点を考慮することにより、支配関係にある法人間で行う組織再編成についても、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」及び「組織再編成後も移転した事業が継続すること」という要件を付加することにより、これに含めることとしたに過ぎない。そのような立法過程を考慮すれば、完全支配関係での合併では、これらの要件は求められていないと解するほかない。
このような主張の根拠として、以下の『平成13年版改正税法のすべて』136頁の記述を挙げることができよう。
企業グループ内の組織再編成とは、100%の持分関係にある法人間で行う組織再編成と、50%超100%未満の持分関係にある法人間で行う組織再編成のうち一定の要件に該当するものとされています。移転資産等の譲渡損益の計上を繰り延べる企業グループ内の組織再編成とは、本来、完全に一体と考えられる持分割合が100%の法人間で行うものとすべきであると考えられますが、現に企業グループとして一体的な経営が行われている単位という点を考慮すれば、50%超100%未満の持分関係にある法人間で行う組織再編成についても、移転する事業に係る主要な資産及び負債を移転していること等の一定の要件を付加することにより、これに含めることもできると考えられることから、50%超100%未満の持分関係にある法人間で行う組織再編成についてもこの企業グループ内の組織再編成に含めるものとされています。
* * *
次回では、TPR事件東京高裁判決の問題点について、さらに分析を行うこととする。
(了)
次回は2020年3月19日に掲載します。