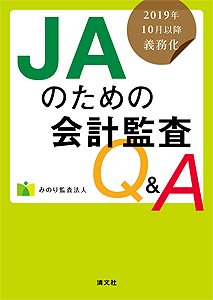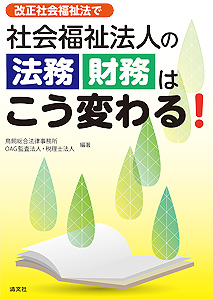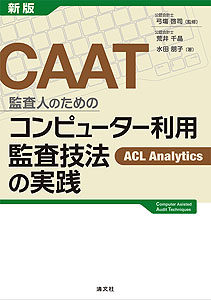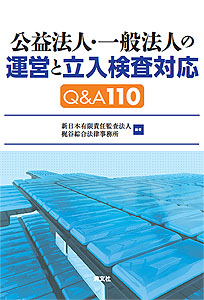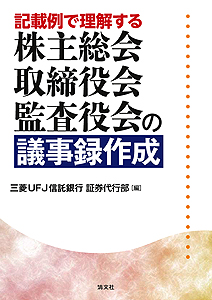訂正報告書に見る
不適正会計処理の現状(1)
大阪経済大学教授 小谷 融
1 金融庁の不適正会計に対する対応
金融庁においては、オリンパスをはじめとする相次ぐ会計不祥事で損なわれた我が国証券市場の信頼回復を目指し、次の2つの検討がなされている。
一つは、平成24年10月1日から適用されている臨時報告書提出事由の拡大だ。
オリンパスは、有価証券の損失隠しを解消するために、売上高等の小さい会社を多額の資金で買収することにより、買収費用の資産化(のれん)を図った。多額の資金を使用した子会社の取得が適時に投資家に開示されていれば、経営トップによる、長年にわたる悪質な不正会計を防げたのではないかとの指摘がある。
それを受け、臨時報告書提出事由に、売上高の小さい会社に係る高額な対価による子会社取得が追加された。
あと一つは、平成24年12月11日に企業会計審議会監査部会から公表された「監査における不正リスク対応基準(仮称)の設定について」の公開草案だ。
この公開草案によると、監査人は「目的の不明な特別目的会社(SPC)が多数ある」などの不正リスクが認識された場合には、抜打ち監査や監査時期の変更など企業が想定しにくい監査手続をとらなければならない。
また、オリンパスの監査法人の交代で引継ぎが不十分だった反省から、前任と後任の監査法人が情報を共有するよう詳細な引継ぎ義務を課している。
2 訂正報告書
有価証券報告書提出会社が過去の財務諸表に関連して不適正な会計処理を発見した場合、その財務諸表の訂正と訂正後の財務諸表に対する監査証明を付した訂正報告書を金融庁に提出しなければならない。
この2月に清文社から刊行した拙編著『不適正な会計処理と再発防止策』において、平成19年7月1日から24年6月30日までの間に提出された訂正報告書について、①提出理由、②不適正な会計処理の内容、③不適正な会計処理が行われた背景、及び④その再発防止策の検討・分析を行ったところである。
これらの傾向や分析において判明した不適正な会計処理の特徴を、2回に分けてご紹介する。
なお詳細については、同書を参照されたい。
3 上場市場別の傾向
不適正な会計処理を行ったとして訂正報告書を提出した会社は、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5証券取引所にまんべんなく見られる。
上場会社数に対する不適正な会計を行った会社の比率は、新興市場銘柄が本則市場銘柄よりも高くなっている。
その背景として、次のようなことが指摘されている。
(1) 企業の規模の違い
会社の規模が大きく、また複数の事業部門を抱えている場合、特定の部門において不適正な会計処理が行われたとしても、全社的に見ると財務上の影響は限定的なものにとどまる。そのため、金額的に重要性の範囲内に収まる。
しかし、会社規模が小さく事業部門も少ない場合や新興市場の会社の場合には、会社全体の財務へ重要な影響を与える。
(2) オーナ経営者による不適正行為
金融商品取引法に基づく内部統制制度等の整備により、上場会社の開示の正確性を担保する制度的な枠組みは、以前よりも構築されてきた。しかし、規模の小さい新興市場の会社では、管理部門が脆弱で、経営トップや稼ぎ頭の中核幹部の発言力が圧倒的なことから、不適正な会計処理やその発覚の遅れにつながる。
特に経営トップ自らが適正な開示・会計処理に対する自覚を欠く場合には、これを阻止することは事実上困難な場合が多い。
(3) ビジネスモデルが発展途上
新興市場の上場会社の中には、ビジネスモデルが発展途上である社が多い。そのような状況の中で、経営トップが、上場企業としての株価等を気にするあまり、あるいは、第三者からの期待又は要求に応えなければならない過大なプレッシャーを受けることにより、粉飾に手を染めるリスクがある。
上記1で述べた「監査における不正リスク対応基準」においては、このような不正リスク要因が「付録1」として公表されている。
4 不適正な会計処理の発覚経緯
不適正な会計処理が発覚した経緯は、個別的要素が強く多岐にわたるが、次のような類型に分類することができる。
それぞれについて、代表的な事例を掲げておく。
① 証券取引等監視委員会による立入り調査
立入り調査を受け、その調査により、過年度にわたり不適正な会計処理が行われていたとの疑義が生じたことから、証券取引等監視委員会から社内にて調査するように指示を受けた。
② 国税局の税務調査・監督官庁による調査
税務調査により、不適正な会計処理が行われている旨の指摘を受け、第三者委員会を設置して、それによる調査が開始され判明した。
③ 取引先からの照会
取引関係業者から当社経理部に支払予定のない支払いの確認と支払要請があったことから、担当社員に問い質したところ、その社員が不適切な取引の事実関係を認めたことにより発覚した。
④ 内部告発・外部告発
当社内部者から監査役会に対して内部告発があったことを受け、内部調査委員会による調査が開始され判明した。
⑤ 内部監査・社内調査
受注後工事が延期となっていた案件の仕掛原価が増加していたため、事実関係の調査を行った結果、判明した。
⑥ 子会社からの報告
子会社から不適正な会計処理を行っていた旨の報告があり、これを踏まえて社内調査を実施したところ、判明した。
(以下、次回に続く)
(了)