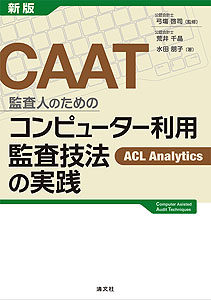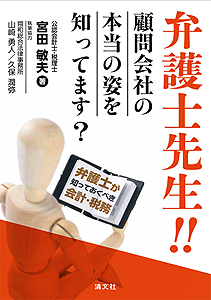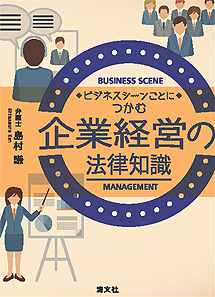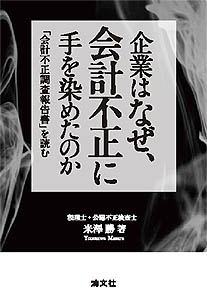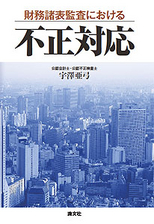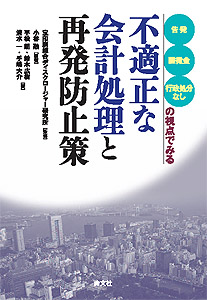〔判決からみた〕
会計不正事件における当事者の損害賠償責任
【第1回】
「エフオーアイ損害賠償請求事件第1審判決の特徴」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
-本連載の狙い-
去る平成28年12月20日、東京地方裁判所は、株式会社エフオーアイ(以下「FOI社」と略称する)の会計不正により損害を受けた個人株主らを原告とする損害賠償事件において、同社の元取締役・元監査役のみならず、主幹事証券会社についても、金融商品取引法違反による民事上の責任を認め、損害賠償を命じる判決を言い渡した。
粉飾決算を理由とする損害賠償事件において、証券会社に損害賠償を命じる判決が出たのは初めてということで、大いに注目を集めた判決であるが、同時に、本判決は、社外監査役について損害賠償を命じている点についても、話題となっている。
そこで、本連載では、本件判決とニイウスコー事件、セイクレスト事件における裁判所の判断など、複数の判決を比較考量しながら、会計不正事件の主犯・実行犯ではない当事者の損害賠償責任について、検討したい。
連載第1回目となる本稿では、まず、エフオーアイ事件第1審判決の概要を検討したい。
エフオーアイ損害賠償請求事件の概要
1 訴訟当事者
原告
- エフオーアイの株主
被告
- 被告Y1(奥村裕代表取締役社長)
- 被告Y2(上畠正和代表取締役専務管理部門長)
- 被告Y3(河野六甲取締役営業部門長)
- 被告Y4(ビノグラードフ・ゲオルギー取締役研究開発部門長)
- 被告Y5(染谷良樹社外監査役・公認会計士)
- 被告Y6(高倉正直常勤監査役)
- 被告Y7(水上浩一郎社外監査役)
- 被告みずほインベスターズ証券株式会社(被告みずほ証券)
(他の証券会社・ベンチャー・キャピタル等は省略) - 被告株式会社東京証券取引所(被告東証)
- 被告日本取引所自主規制法人(被告自主規制法人)
2 粉飾決算の内容
FOI社においては、平成16年3月期において、決算が大幅な赤字となって銀行融資を受けることができなくなることを防ぐため、被告Y1(奥村元代表取締役社長)、被告Y2(上畠代表取締役専務)及び被告Y3(河野取締役)ら役員が相談の上、見込生産をして製造を終了した6台のエッチング装置につき、実際には受注がなかったにもかかわらず、受注があったように装って架空の売上げを計上することにより、実際の売上高が7億1,941万328円であるのに、決算書類には売上高が23億2,799万9,328円である旨記載する粉飾決算を行った。
FOI社は、平成17年3月期以降も、平成21年3月期までの間、売上高を実際よりも水増しして計上する方法による粉飾決算を継続した。平成21年3月期の粉飾額は115億3,639万5,000円に及び、決算書類に記載された売上高の97.3%が架空の売上げであった。
これらの粉飾は、被告Y1(奥村元代表取締役社長)、被告Y2(上畠代表取締役専務)及び被告Y3(河野取締役)ら取締役のほか、主立った幹部職員らが共謀して行ったものであった(本件粉飾)。
上場申請から上場→上場廃止に至る経緯
1 1回目の上場申請と取下げ
- H19.5.1
被告みずほ証券、FOI社のマザーズ市場上場手続きについての主幹事証券に就任 - 8.17
被告みずほ証券公開引受部から引受審査部に対し、審査依頼 - 12.20
FOI社上場申請
⇒被告自主規制法人は上場承認日をH20.2.18と予定
- H20.2.14
被告東証ら、「注文書偽造による巨額粉飾決算企業の告発」と題する同月12日付けの匿名の投書(第1投書)を受領 - 2.18
被告みずほ証券の監査役宛てに、同月13日付けの同題名の投書が送付され、同月25日に開封。
被告自主規制法人は、第1投書を受け、FOI社の上場承認の予定を延期して追加調査を行うこととした。追加調査として、預金通帳の原本を含む帳票類の確認、FOI社の役員、従業員及び会計監査人に対するヒアリングを行った。 - 4.2
引受審査部は、第1投書についての主幹事証券会社としての追加審査を実施し、第1投書には信憑性がないものと判断 - 4.18
被告みずほ証券及び被告自主規制法人は、FOI社の上場申請につき、平成20年5月16日に承認をして同年6月18日に上場をするというスケジュールで手続を進めることを確認していたが、FOI社は、上場申請を取下げ
2 2回目の上場申請と取下げ
- H20.8.5
被告みずほ証券引受審査部は、FOI社の2回目の引受審査を開始し、追加の審査を行った結果、上場適格に問題はないと判断 - 12.1
FOI社は、被告東証に対して2回目の上場申請
- H21.5.17
FOI社が多額の売上債権を計上している取引先であるg4社が、転換社債の償還期限を1ヶ月延長するよう求めた旨の報道がされ、被告自主規制法人は、g4社に対する債権の不良債権化の懸念から、平成20年3月期を上場直前基準期とする上場は困難である旨の見解を示す - 5.19
FOI社、2回目の上場申請取下げ
3 3回目の上場申請から上場廃止
- H21.6.16
被告みずほ証券引受審査部は、FOI社の3回目の引受審査を開始し、追加の審査を行った結果、上場適格に問題はないと判断 - 8.18
FOI社は、被告東証に対して3回目の上場申請 - 10.16
被告東証は、上場日を11月20日として、FOI社のマザーズ市場への上場を承認し、対外的に公表 - 10.16
FOI社は、関東財務局に対し有価証券届出書を提出 - 11.20
FOI社、マザーズ市場に上場し、初値は1株770円
- H22.5.12
FOI社、証券取引等監視委員会から金商法違反の容疑による強制捜査を受けた旨を発表 - 5.16
FOI社、有価証券届出書及び被告東証への上場申請書類に虚偽の決算情報を記載したことを認める旨公表 - 5.21
FOI社、東京地方裁判所に破産手続開始の申立て - 6.15
FOI社、上場廃止
損害賠償責任に対する裁判所の判断
1 被告Y2(上畠代表取締役専務)、被告Y4(ゲオルギー取締役)及び被告Y1(奥村元代表取締役社長)(第5事件に限る)に対する請求について
被告Y2(上畠代表取締役専務)及び被告Y4(ゲオルギー取締役)は全事件について、被告Y1(奥村元代表取締役社長)は第5事件について、いずれも適式の呼出しを受けたにもかかわらず、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しない。
したがって、上記被告らは、当該事件についての請求原因事実を自白したものとみなされるから、原告らの被告Y2(上畠代表取締役専務)及び被告Y4(ゲオルギー取締役)に対する請求並びに被告Y1(奥村元代表取締役社長)に対する第5事件に係る請求は、いずれも理由がある。
2 有価証券届出書等の虚偽記載の有無について
(1) 被告Y1(奥村元代表取締役社長)について(第1事件ないし第4事件)
被告Y1(奥村元代表取締役社長)は、FOI社の代表取締役社長として、本件粉飾を当初から認識し、これを主導又は容認してきた人物であるから、本件有価証券届出書の虚偽記載を知っていたことは明らかである。
したがって、被告Y1(奥村元代表取締役社長)は、すべての原告らに対し、金商法21条1項1号、22条1項の責任を免れない。
(2) 被告Y3(河野取締役)について
被告Y3(河野取締役)は、FOI社の取締役として、本件粉飾に当初から関わり、これを実行してきた人物であるから、本件有価証券届出書の虚偽記載を知っていたことは明らかである。
したがって、被告Y3(河野取締役)は、すべての原告らに対し、金商法21条1項1号、22条1項の責任を免れない。たとえ被告Y3(河野取締役)が被告Y1(奥村元代表取締役社長)や被告Y2(上畠代表取締役専務)の指示又は命令によって本件粉飾に関与していたものであるとしても、上記判断は左右されない。
(3) 被告監査役らについて
被告監査役らは、いずれも、FOI社による本件粉飾を認識していなかったものと認められるから、本件有価証券届出書の虚偽記載を知らなかったものと認められる。また、被告監査役らは、FOI社の会計監査の信頼性については、一応の監査を行っていたものと認めることができる。
FOI社においては、単に財務諸表において架空の売上げを計上していたにとどまらず、取締役ら及び多数の幹部社員らが共謀し、売上取引に関する多数の書類を偽造したり、ペーパーカンパニーを設立して売掛金の回収を偽装したり、販売見込みのない製品を製造し続けるなどの大がかりな偽装工作を5年以上にわたり継続し、平成21年3月期の決算においては、実に総売上げの97%以上に上る115億円余りもの架空売上げを計上していたというのであり、取締役らのかかる違法行為は、本来監査役の業務監査によって是正されるべきものである。
被告Y6(高倉常勤監査役)は、平成16年3月期の売上げのうちに架空のものがあることを認識していたというのであり、その後、FOI社の売上げが急増したにもかかわらず売掛金の回収が進まない状況において、架空の売上げが計上されている可能性について疑問を抱き、売上げの実在性について独自の調査を行うなどの対応を執ることは十分に可能であったというべきであるが、被告Y6(高倉常勤監査役)が、会計監査人の報告を受ける以外にかかる観点から何らかの調査を行ったことをうかがわせる証拠はない。
また、被告Y6(高倉常勤監査役)は、常勤監査役であったにもかかわらず週に2日程度しか出勤しておらず、FOI社においてほぼ毎週開催されていた戦略会議にも出席していなかったのみならず、対外的には戦略会議に毎回出席していたかのように装い、議事録にかかる虚偽の記載がされていることを認識しながら放置していたというのであるから(なお、被告Y6(高倉常勤監査役)は、被告みずほ証券の引受審査における質問に対し、毎日出勤し、戦略会議にも出席している旨虚偽の回答をしている)、取締役の業務執行に対する日常の業務監査が十分であったとはいい難い。
非常勤の社外監査役である被告Y5(染谷監査役)及び被告Y7(水上監査役)は、上記のような被告Y6(高倉常勤監査役)の職務執行状況を認識していたか、容易に認識し得たと考えられるのに、これを是正するための何らかの対応を執った形跡がないところ、非常勤監査役においても、常勤監査役の職務執行の適正さに疑念を生ずべき事情があるときは、これを是正するための措置を執る義務があるというべきであるから、被告Y5(染谷監査役)及び被告Y7(水上監査役)の監査役としての職務の遂行が十分なものであったとはいい難い。
被告監査役らにおいて第1投書の存在を認識していたことを認めるに足りる証拠はないものの、監査役会において、上場申請取下げの理由について他の役員ら又は被告みずほ証券に問い合わせをするなどして調査すれば、第1投書の存在を認識することは十分に可能であったというべきであり、その上で監査役の権限を行使して調査を行えば、FOI社において粉飾決算が行われていた事実が判明していた可能性がないとはいえない。
被告監査役らについては、いまだ相当な注意を用いて監査を行っていたとは認められず、他に相当な注意を用いたにもかかわらず本件粉飾の事実を知ることができなかったことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、被告監査役らは、いずれも、金商法21条1項1号、22条1項の責任を免れることはできないというべきである。
(4) 被告みずほ証券について
第1投書を受領したことを踏まえて行った被告みずほ証券の審査が十分なものであったとはいえず、仮に第1投書を踏まえた十分な審査を行っていれば、平成20年4月頃の時点でFOI社が粉飾決算を行っていることを発見できた可能性が少なからずあったというべきである。
よって、被告みずほ証券は、本件上場に係る引受審査について、本件有価証券届出書等の虚偽記載について、相当な注意を用いたにもかかわらずこれを知ることができなかったものと認めることはできないから、原告らに対し、金商法21条1項4号及び17条の責任を負う。
(5) 被告東証について
金商法の趣旨及び被告東証と被告自主規制法人との間の業務委託契約の内容に照らせば、被告自主規制法人は、被告東証の委託を受け、被告東証とは独立した立場において上場審査の全部を行っていたものと認められ、被告東証が行う上場審査の補助者として上場審査に関与していたものではない。したがって、仮に被告自主規制法人が行った上場審査の過程において過失があったとしても、そのことにより被告東証が不法行為責任を負うということはできない。
以上の見地からすると、原告らが被告東証らの責任原因として主張する不法行為は、被告自主規制法人が行った上場審査の過程における過失をその根拠とするものであるから、これにより被告東証が不法行為責任を負担する法律上の根拠を欠くというべきである。
(6) 被告自主規制法人について
被告自主規制法人は、上場審査において、財務諸表の内容の正確性に疑いを生じさせるような事情が存在したにもかかわらず、そのような事情を看過し、追加の審査を行うことなく漫然と上場を承認したものと認めることはできないから、同被告について、投資者に対して負っていた注意義務に違反する行為があったということはできない。
したがって、原告らの被告自主規制法人に対する請求は理由がないというべきである。
本判決の特徴
上述してきたように、エフオーアイ事件第1審判決(東京地方裁判所平成28年12月20日判決)は、粉飾決算の首謀者や実行者以外の株主に対する損害賠償責任を広く認めたものとなっている。その最大の特徴は、主幹事証券と非常勤の社外取締役の損害賠償責任を認めた点にある。
それらについて、これまでの裁判所の判断との相違について、検討したい。なお、詳細な分析については、次回以降の連載を通して検討していく予定である。
1 主幹事証券の損害賠償責任を認めた判決であること
本判決は、有価証券届出書の虚偽記載に係る引受証券会社の金融商品取引法第21条1項4号、17条に基づく民事責任について判断を示したものであり、会計監査人の監査を受けた財務諸表に虚偽記載があったことを知らなかった引受証券会社に注意義務違反があったとして損害賠償責任を認めた初めての裁判例である。
責任を認めた理由については、上述のとおり、引受審査において、有価証券届出書の虚偽記載について、相当な注意を用いたにもかかわらずこれを知ることができなかったものと認めることはできないことによるのであるが、匿名の投書を理由とした2度にわたる上場申請の取下げという本事件の特殊性も踏まえ、本連載【第5回】において、裁判所の判断のポイントとなった引受審査の状況について掘り下げて検討したい。
2 非常勤社外監査役の損害賠償責任を認めた判決であること
裁判所が非常勤社外監査役の損害賠償責任を認めた論理構成は、以下のようになる。
① 取締役らの違法行為は、本来監査役の業務監査によって是正されるべきである。
② 常勤監査役は、架空売上があることを認識していた。
③ 常勤監査役による取締役の業務執行に対する業務監査が十分ではなかった。
④ 非常勤監査役は、常勤監査役の職務執行の適正さに疑念があるときは、これを是正するための措置を執る義務がある。
⑤ 非常勤監査役が、上場申請取下げの理由について調査すれば、粉飾決算の事実が判明していた可能性がないとはいえない。
よって、金融商品取引法第21条1項1号、第22条1項の責任を免れることはできないというものであった。
過去の裁判では、社外監査役については損害賠償責任を負わないと判断したものが多く、また、監査役就任時の責任限定契約に基づいて、監査役が過去の報酬を返還することによって法廷外で和解をすることも少なくないものと考えられてきた。
本判決は、常勤監査役が十分に職務を果たしていない(そのため、粉飾決算が見逃されてきた)という状況の中、非常勤である社外監査役の職務について、かなり踏み込んだ判断を行ったものであり、今後の社外監査役が職務上果たすべき「相当な注意」について、警告を与えるものであると評価できよう。
* * *
次回以降では、監査役の損害賠償責任について、先行した2つの事件判決における裁判所の判断を見たうえで、本判決との比較検討を行いたい。
(了)
「〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任」は、隔週で掲載されます。