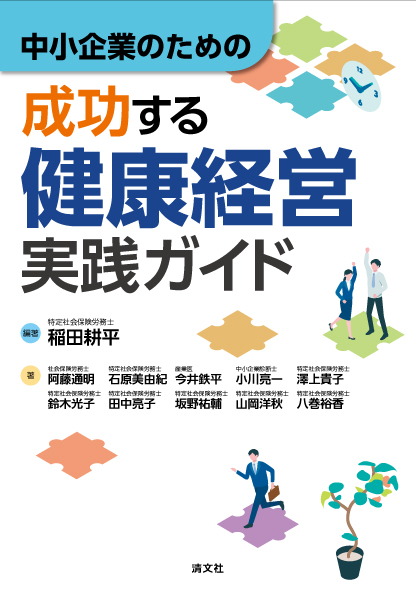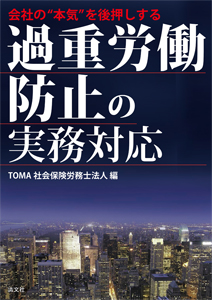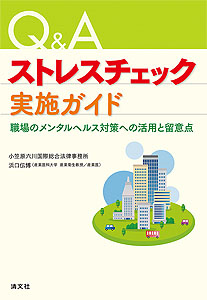義務だけで終わらせない「ストレスチェック」の活かし方
【第1回】
「メンタルヘルスの意義」
特定社会保険労務士 大東 恵子
ストレスは悪いもの?
昨今、「うつ」「ストレス」「心の病」などメンタルヘルスに関する言葉をよく耳にするようになり、誰にでも生じる身近な問題として注目されるようになってきた。国の対策においても、ご承知の通り12月からはストレスチェックの制度がスタートし、また先日の国会では、職場におけるメンタルヘルス対策の担い手として公認心理師の国家資格化の法律が可決されるなど、さまざまな対策が検討されている。
一方で企業では、安全配慮義務からメンタルヘルス対策が求められ、その対応に追われているものの、まだまだストレスに対する啓蒙が行き届かず、誤解や偏見が生じている現状も少なくない。
巷にあふれるさまざまなストレス関連本を見てみると、「ストレスのない快適な職場を」と謳われ、ストレスを完全になくそうという動きが見受けられる。もちろんストレスはないに越したことはない。ストレスによって従業員のメンタルヘルスを悪化してしまえば、集中力や注意力が低下し、仕事においてさまざまな支障が生じてしまう。休職に陥ってしまえば、その穴を埋めるべくさまざまな手立てを打たなければならず、その損失は決して少なくない。
この観点から単純に考えると、「ストレスというのは悪いもので無くせばよい」という結論に陥ってしまうが、労働においてストレスというのは必ずしも悪いものではないという点を今一度確認しておきたいと思う。
ストレスの有益制と有害性
1908年、ハーバード大学生理学研究所のヤーキーズ(R.M.Yerkes)とドッドソン(J.D. Dodson)という学者が、ストレスとパフォーマンス(生産性)の関係について研究を行い、以下のように指摘した。
ストレスには、程度が高まるにつれてパフォーマンス(生産性)や効率を向上させる特徴があるものの、ある一定値を超えると、逆にパフォーマンス(生産性)や効率を低下させ、最終的には健康にも害を及ぼしてしまう特徴がある。
例えば、
大切なプレゼンテーションを前にして、適度な緊張から集中力や注意力が高まり、プレゼンテーションが成功した。
という類のものが前者に当たり、一方、
長時間労働や時間的切迫、責任の増大などのストレスが高まると、生産が落ちたり、仕事の出来栄えが悪くなったりしてしまう。
というのが後者に当たる。
ヤーキーズとドッドソンは、ストレスの有益性と有害性の両側面を指摘し、問題は「ストレスの程度」にあるとしている。
すなわち、職場におけるメンタルヘルス対策を考えるとき、ストレスの有無ではなくストレスの「適度」な程度という観点に注目する必要がある。
「ストレス・脆弱性モデル」とは?
では、その適度な程度というのはどのようなものなのか、害を及ぼし始める境界線はどこなのかという点が疑問として挙がる。これについては容易に想像できるように、人それぞれ境界線は異なる。劣悪な環境下でも、ある人にとっては害にはならず、一方、一見するとなんでもない環境下であっても、別の人には健康を害するほどのストレスになってしまうというのは、日常でもよく見受けられる。これは、物事の捉え方など個々人のストレス耐性の程度の違いによって生じるものである。
このように、「ストレスそのものの程度」と「受け取る側の耐性の弱さ」の掛け算でストレスを捉える考え方を「ストレス・脆弱性モデル」と言う。
このモデルから考えると、人それぞれによって状況が変わってくるため、職場におけるメンタルヘルス対策としては、常日頃、職場環境のストレスの程度が高まりすぎていないかという客観的なチェックと、その環境下で働く従業員がその環境をどう捉え、健康に害を及ぼしていないかというチェックが必要になる。ストレスチェックは、この両面について有益な情報を提供するツールとして、大いに役立つものである。
ストレスチェックは、従業員の健康管理という単純な側面からだけでなく、ヤーキーズ・ドッドソンの研究からも言えるように、労働パフォーマンスをより高める環境づくりとして企業側の対策チェックとしての意味合いも含まれる。ストレスチェックを含めたメンタルヘルスについては、企業側の利益にも返ってくる、より包括的な問題としての位置づけが必要になる。
* * *
次回は、ストレスのメカニズムについて解説を行う。
(了)
【参考】 厚生労働省ホームページ