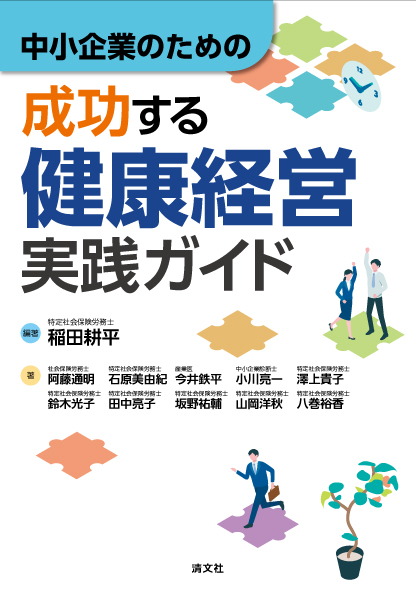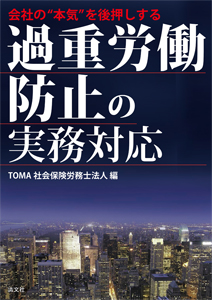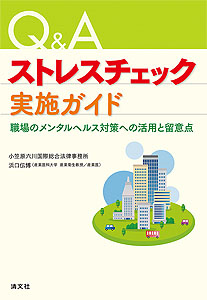会社が取り組む
社員の健康管理
【第1回】
「健康管理を規定する法令」
社会保険労務士 佐藤 信
1 はじめに
働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う脳・心臓疾患や精神障害の増加など労働者の生命や生活に関わる問題が注目され、労働環境の改善が、健康で安全な社会を作るための企業貢献として高く評価されるようになってきた。
職業性疾病や災害性疾病の予防対策はもとより、働く人の生活習慣病の予防を中心にした健康作り対策、メンタルヘルス対策を積極的に推進していくことがより大切になっている。
そこで、当連載では会社が取り組む社員の健康診断の実施方法や注意点、健康の保持増進措置、安全衛生管理体制の整備等について取り上げていくこととしたい。
2 労働者の健康管理に関する法令の定め
労働安全衛生法やその他の法令において、労働者の健康管理に関するルールが定められ、また、労働契約法では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とし、労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化している。
労働契約法には罰則がないが、安全や健康への配慮を怠った場合、
・民法709条(不法行為責任)
・民法715条(使用者責任)
・民法415条(債務不履行)
まずは会社がどのような措置を講じていくべきかを把握し、健康障害・死亡事故等が生じた後で「そのような規定があることは知らなかった」となることのないよう気を付けたい。
以下、「健康管理」について規定された主な法令を紹介していくこととする。
(1) 労働安全衛生法
作業環境の管理、健康管理、労働衛生教育等について定められているが、例えば、健康管理は、健康診断の実施項目やその結果に基づく事後措置、健康測定結果に基づく健康指導まで含めた広い内容について規定されているため、会社は「健康診断を実施している」というだけでは足りず、必要に応じ事後措置等もとっていかなければならない。
※健康診断や健康の保持増進措置の詳細については、第2回以降にて掲載予定。
(2) 労働時間等設定改善法(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)
労働時間、休日数などを設定する際に労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善することなどが定められ、事業主の責務として次の事項が掲げられている。
・事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。(法2条1項)
・事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努める(法2条2項一部抜粋)
こちらは努力規定であるが、働き方を見直しながら休暇を取得しやすい職場環境(参考:年次有給休暇の取得率は依然として5割を下回っている)や長時間労働を抑える措置を講じていくことが望ましい。
(3) 労働基準法
労働基準法では、労働時間の上限(1日8時間、1週40時間)や、確保しなければならない休日数(1週間に1日又は4週間に4日)、年次有給休暇の付与など労働条件の最低限のルールが定められている。
長時間労働は、健康障害を生じさせる要因のため、過重労働が恒常的に行われている職場では労働時間短縮、休日増に向けた施策を講じておきたい。
なお、労働時間については一定の手続により弾力的な運用(変形労働時間制という)が認められているため、業務の繁閑が見込まれる職場の場合は、変形労働時間制を採用することで繁忙期は労働時間を長めにし、閑散期は労働時間を短かく設定することも可能となる。
総労働時間の短縮策の1つとして、検討の余地があると思われる。
その他、労働基準法では次の保護規定が設けられており、母性健康管理のための措置も講じていかなければならない。
・産前、産後の休業(産前6週間、産後8週間)
・妊婦の軽易業務への転換
・妊産婦等の危険有害業務の就業制限
・妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
・妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
・育児時間(1日2回、各30分)
(4) 男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)
男女雇用機会均等法における母性健康管理の規定としては次のものがあり、上記労働基準法上の措置と併せて配慮を要する。
・事業主は、女性労働者が妊娠中及び出産後の女性労働者のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。(法12条)
・妊娠中及び出産後の女性労働者が健康診査等を受け、主治医等から指導を受けた場合は、その女性労働者が、受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。(法13条1項)
・婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等。(法9条)
第1回は健康管理に関する主な規定等について概要を触れたが、これらは法令にあわせて単に就業規則を整備しただけで実態が伴わないことも十分に考えられる。
適正に運用するためにも各労働者への周知、協力体制の構築、相談窓口の設置など、実際に健康障害の防止、健康保持増進につなげていくことを見据えた上で社内ルールの整備を進めておきたい。
次回以降は健康診断等について記載し、健康診断の内容や検査項目、具体的な実施の流れ(会社で行う準備等)について触れることとする。
(了)