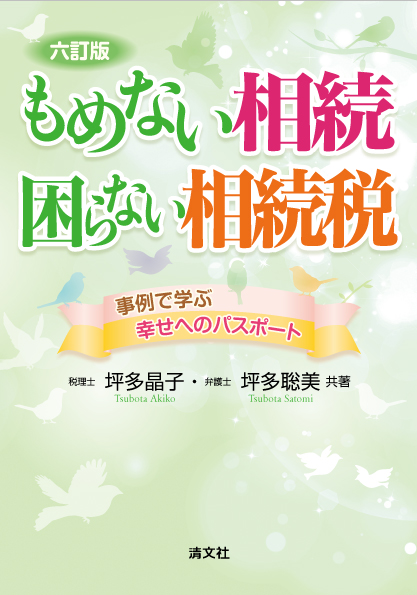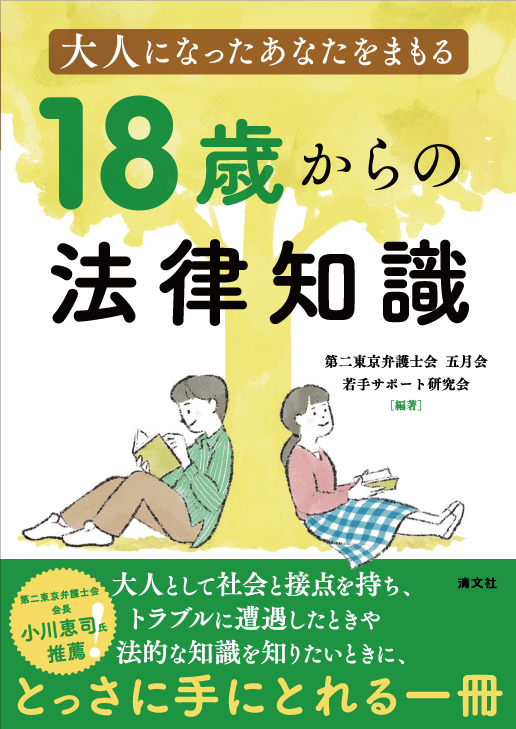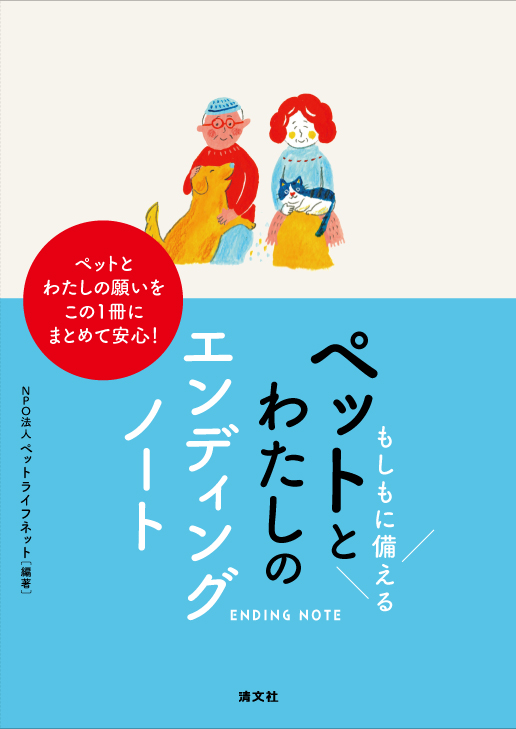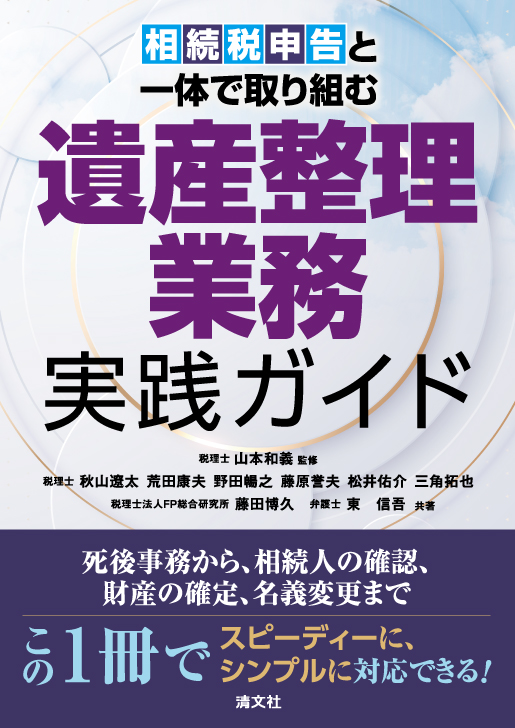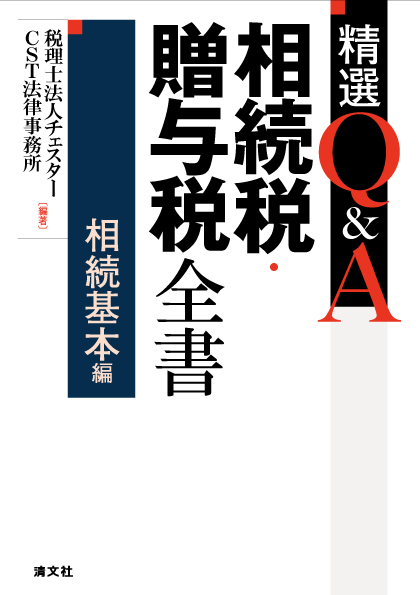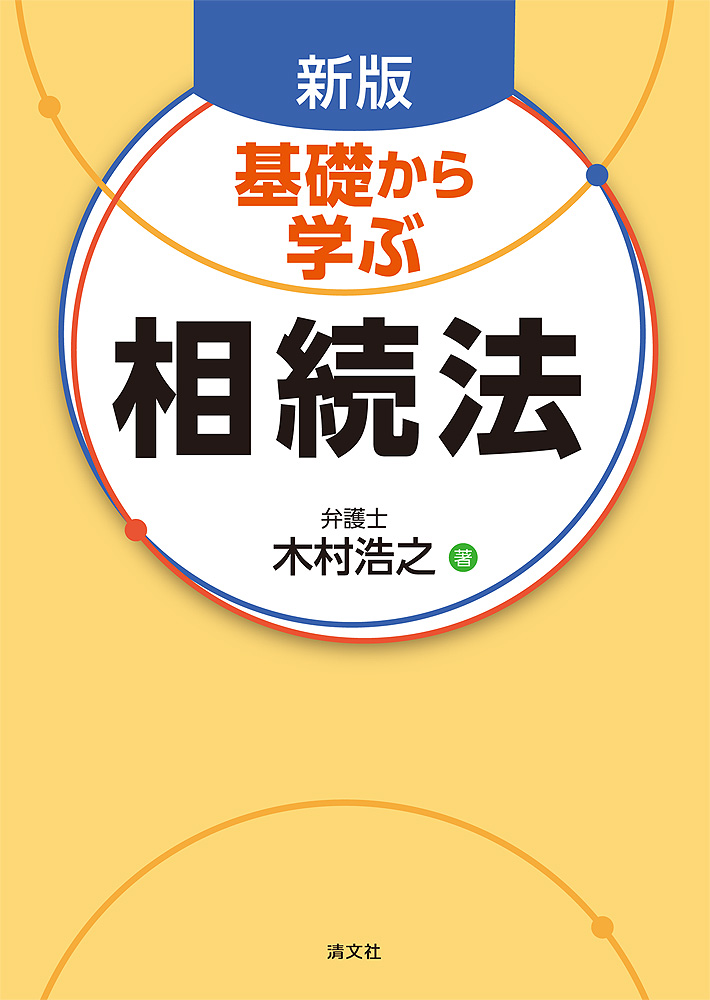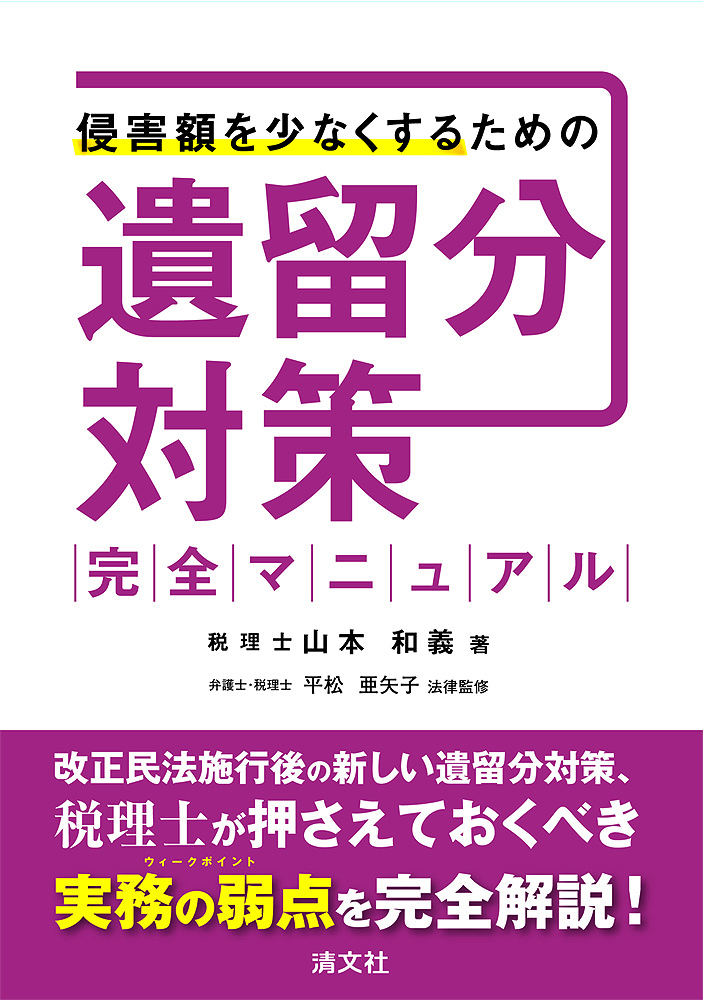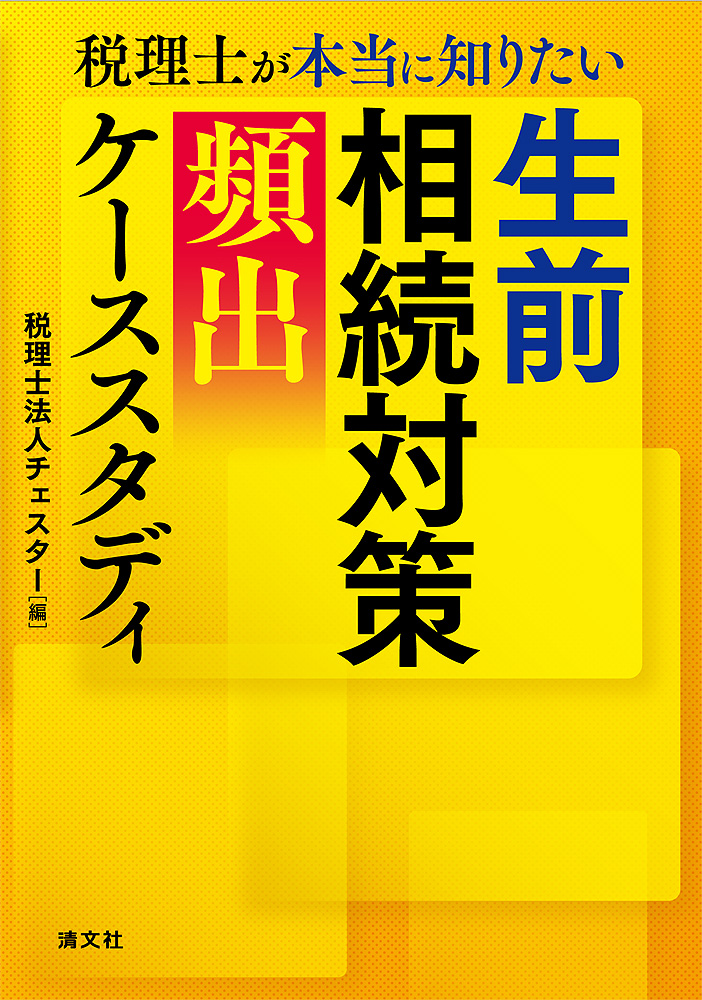養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第6回】
「外国人との養子縁組と戸籍・国籍への影響」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
外国人との養子縁組(以下「渉外養子縁組」という)を検討するに当たっては、その成立要件をどの国の法律に従って判断するかが最初に検討されなければならない。その際に適用される法律を準拠法といい、日本において準拠法を定めているのは「法の適用に関する通則法」である。
法の適用に関する通則法第31条第1項では、渉外養子縁組の成立を検討するに当たり、「養子縁組当時の養親の本国法」を準拠法とすることが規定されている。さらに、養子の本国法が養子縁組の成立について養子もしくは第三者の承諾、同意、または公の機関の許可等を必要とするときはその要件も満たすことが必要とされている(通則法31①後段)。
つまり、渉外養子縁組が成立するためには、養子縁組当時の養親の本国法のすべての要件に加え、養子の本国法上の保護要件をも満たす必要がある。さらに、日本人と外国人の夫婦が外国人を養子とする場合には、準拠法は日本法と外国人配偶者の本国法となり、養親それぞれについて、その本国法により縁組の成立要件が検討されなければならない。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。