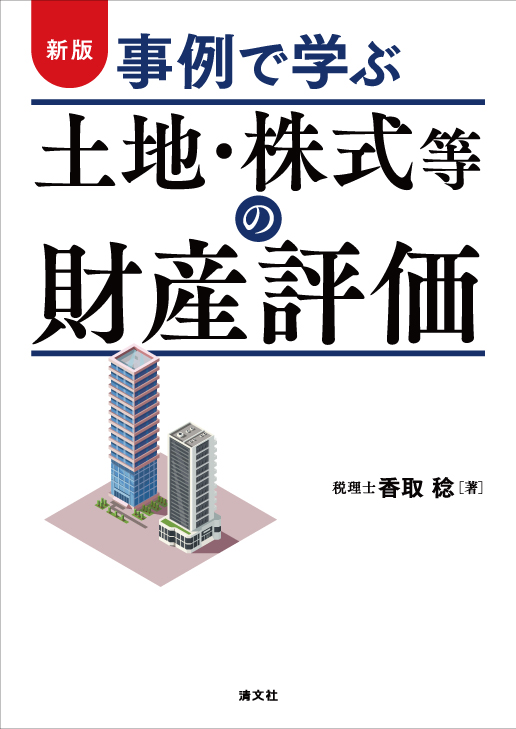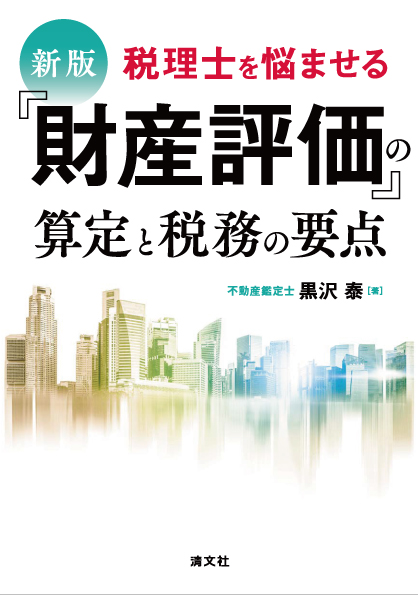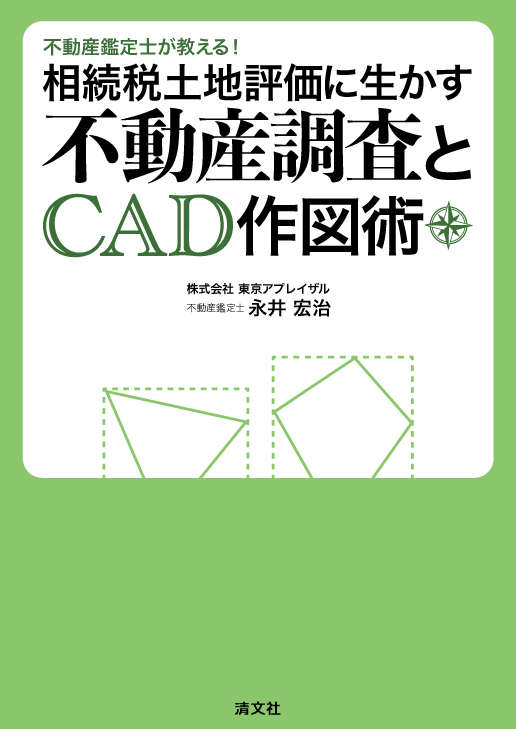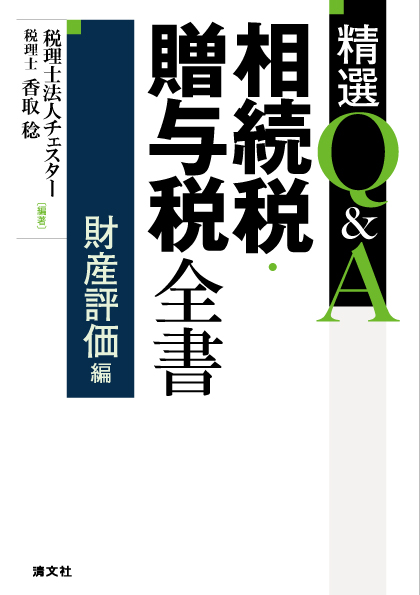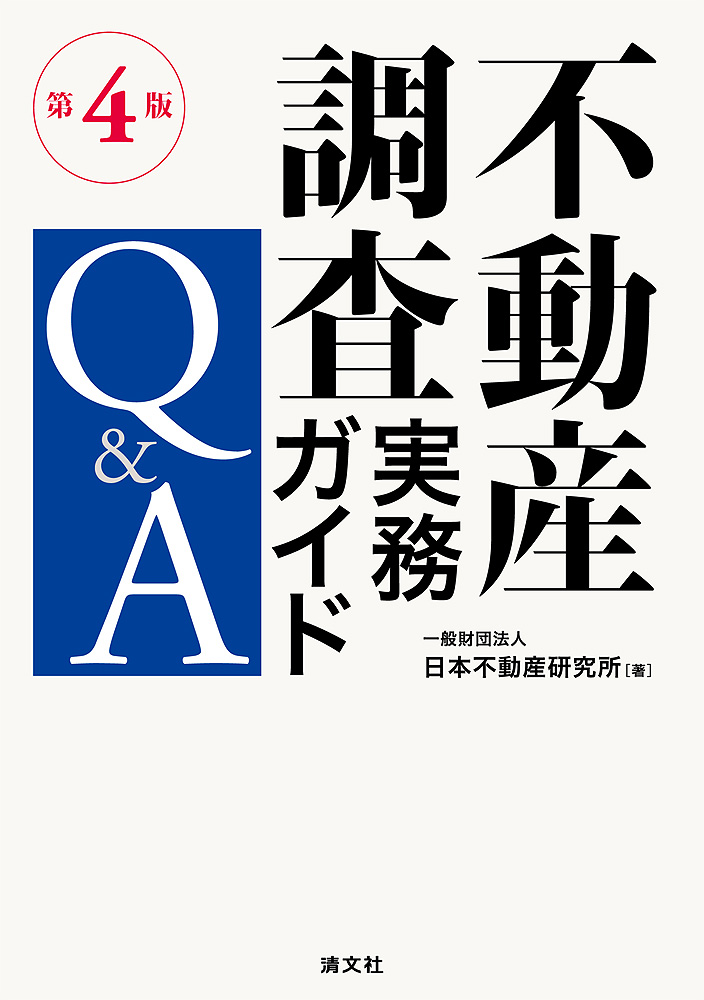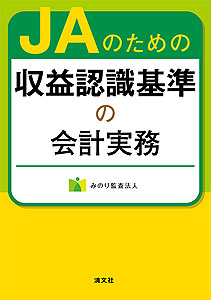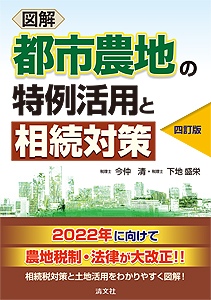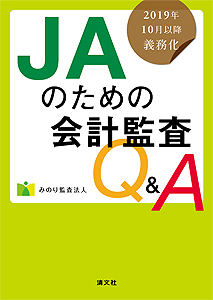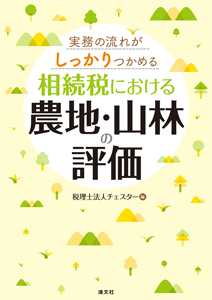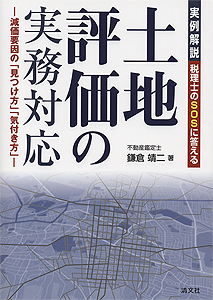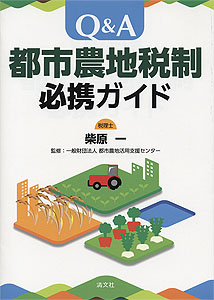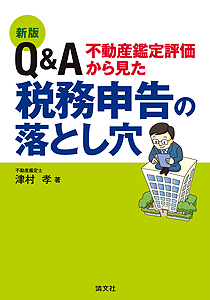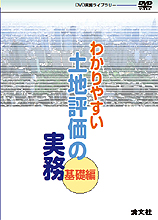税理士業務に必要な
『農地』の知識
【第1回】
「農業に関する将来の方向性」
税理士 島田 晃一
はじめに
本連載では、税理士がその業務において必要とされる「農地に関する知識」について、最新の動向を交え、幅広い観点から紹介していきたい。
1 農業を取りまく現況と今後の方向性
近年の農業環境は、農業従事者の高齢化及び後継者不足や海外の農産物との競争など岐路に立たされている。国内農業については味や安全性などの付加価値やブランド化などを推進すること、また、農地集約のための売買や貸付けなどを積極的に行うことにより大規模化、効率化を進めていくことが求められている。
行政においても農地の集約化を後押しする施策がメインになっている。それに伴い税制面においても、農地集約のための売買に関しては譲渡所得の特例措置などを設け、集約化を側面から後押ししている。これら農地の集約化のための税制面の特例については、次回以降、具体的に説明していくことにする。
また、農業従事者の高齢化及び後継者不足による耕作放棄が今後さらに増加していくことが予想される。このような遊休農地の増加に対処するため、これらの農地の第三者への売却や貸付けにより農地の維持を図ることが求められており、これは前述した農地の集約化にも繋がっていくものである。
2 都市農業に関する方向性
(1) 都市農業の特殊性と農地の維持
都市農業については、地方農業とは事情が異なる部分がある。すなわち、都市農業を営む者の多くが、農業収入が生活の糧ではなくサラリーマンが副業で休日に農作業を行ったり、以前に農地であった土地の一部を宅地化し不動産賃貸事業により主な収入を得ているのが現状である。
農地自体については、生産緑地指定を受けていれば、固定資産税・都市計画税は宅地や雑種地と比較して大幅に低く、金銭面から見た農地の維持について大きな困難を生むことは少ない。それよりも、都市農地の維持に関しては、周辺の住環境の問題それに附随するトラブルに左右される場合がある。
例えば、「風の強い日など土埃などが舞い周辺住民から苦情があった」、「農薬を使う際、臭いや住民の健康に悪影響を及ぼすといった苦情があった」などといった問題である。
これらの問題に適切に対処し、周辺住民の理解を得るということも、都市農地の維持の観点から重要なことである。
(2) 都市農業振興法の施行と税制上の措置
行政面からは、これまでの都市農業政策を転換する動きが出ている。以前から、自治体によっては、災害時の住民の避難場所や景観維持のため、ある程度の面積を有している一団の農地について、積極的に生産緑地の追加指定を行っている。また、都市部においては日常的に農業に触れあう機会がないことから、市民農園として多くの人に農業体験をしてもらうといった事業も推進されている。
これらの動きを法律的に担保するため、平成27年4月には都市農業振興法が施行され、これまでの市街化区域農地を宅地化することを前提とした方向から、都市農地としてそのまま維持する方向への転換が示された。
これは、将来の人口減少による住宅地需要の減退が避けられない見通しであること、一方で、防災拠点・景観の確保、国民の農業に対する理解・農業体験などが重視されるようになってきているという事情がある。
都市農業振興法では、第8条において、都市農業振興のための税制上又は金融上その他の措置を講じなければならないとされるとともに、第9条において「都市農業基本計画」を定めることが定められている。その後、平成28年5月に提示された「都市農業基本計画」においては、都市農業振興のための様々な施策が挙げられている。
その中で注目すべき点は、税制上の措置として、① 三大都市圏以外の市街化区域内農地(生産緑地地区を除く)における固定資産税・都市計画税納税の負担軽減、及び、② 相続税の納税猶予における農地の貸借時の猶予打切りの見直しについて言及していることであろう。
3 都市農地における農地の納税猶予適用における諸問題
相続の際、相続人が農地を売却したり、宅地に転用して賃貸住宅などを建設し農業以外の土地活用を図る事例も多いが、逆に、このまま農地として維持していこうという選択を採る場合もある。ただし、相続人がある程度の規模以上の農地を残したいという選択をしたならば、よほどの金銭的な余裕がない限り、相続税の納税猶予の適用を受ける必要が出てくる。
したがって、相続税の納税猶予に関しては、都市農地の相続を取り扱うにあたって内容を必ず理解しておく必要がある。
特に注意したい点は、前述したように、都市・地方を問わず農業従事者の高齢化が問題となっており、農地を所有していた被相続人が80代、農地を相続し相続後農業に従事する者が60代であるという事例も充分想定される。このような場合、相続後期間を置かず農業従事者が病気などで農地を維持できなくなってしまう恐れもある。その際には、原則として納税猶予は打ち切られ、猶予されていた税額及びそれに対応する利子税を納めなければならない。
ただし、市街化区域外の農地については、「特定貸付」といい、農業経営強化促進法に基づく一定の事業のために農地を貸し付けた場合、納税猶予の継続が認められる。
仮に、特定貸付が受けられない地域に農地があったり、貸付け申込み後1年経過しても特定貸付ができなかった場合には、「営農困難時貸付け」といい、重度の精神障害又は身体障害により農業の継続が困難になったことを条件として、その農地を他に貸し付けても納税猶予の継続が認められる。
都市農地に関しては、特定貸付の対象外の地域にあるため、現段階においては、営農困難時貸付けを受けられない場合、農地の地方公共団体や第三者への貸付けは納税猶予の打切り事由に該当してしまう。
このような事態を避けるために、前述したように「都市農業基本計画」において税制面の手当がされるよう記載されている。また、平成28年度の税制改正大綱の検討事項においても次のような記載がある。
都市農業については、今後策定される「都市農業振興基本計画」に基づき、都市農業が継続される土地に関し、市街化区域外の農地とのバランスに配慮しつつ土地利用制限等の措置が検討されることを踏まえ、生産緑地が貸借された場合の納税猶予の適用など必要な税制上の措置を検討する。
要するに、相続発生時において農地を相続した相続人が地方公共団体や第三者に農地の賃貸等を行った場合において納税猶予を受けられる措置を検討するということである。さらに、納税猶予を受けている相続人が第三者に農地の賃貸等を行った場合、納税猶予の打ち切りの対象にしない措置も検討されていくと考えられる。
* * *
以上、連載第1回となる今回は、農業を取りまく現況と将来像、特に都市農業に係る税制の今後について簡単に述べてきた。
大きな流れとしては、「地方における農地の集約化」、及び、「都市部における宅地化推進から農地維持への方針転換」が打ち出されているのがわかる。
次回以降は、これらの流れを踏まえた農地に関する税制に関する詳細と、それを理解するための周辺知識について述べていく予定である。
(了)
「税理士業務に必要な『農地』の知識」は、毎月第2週に掲載されます。