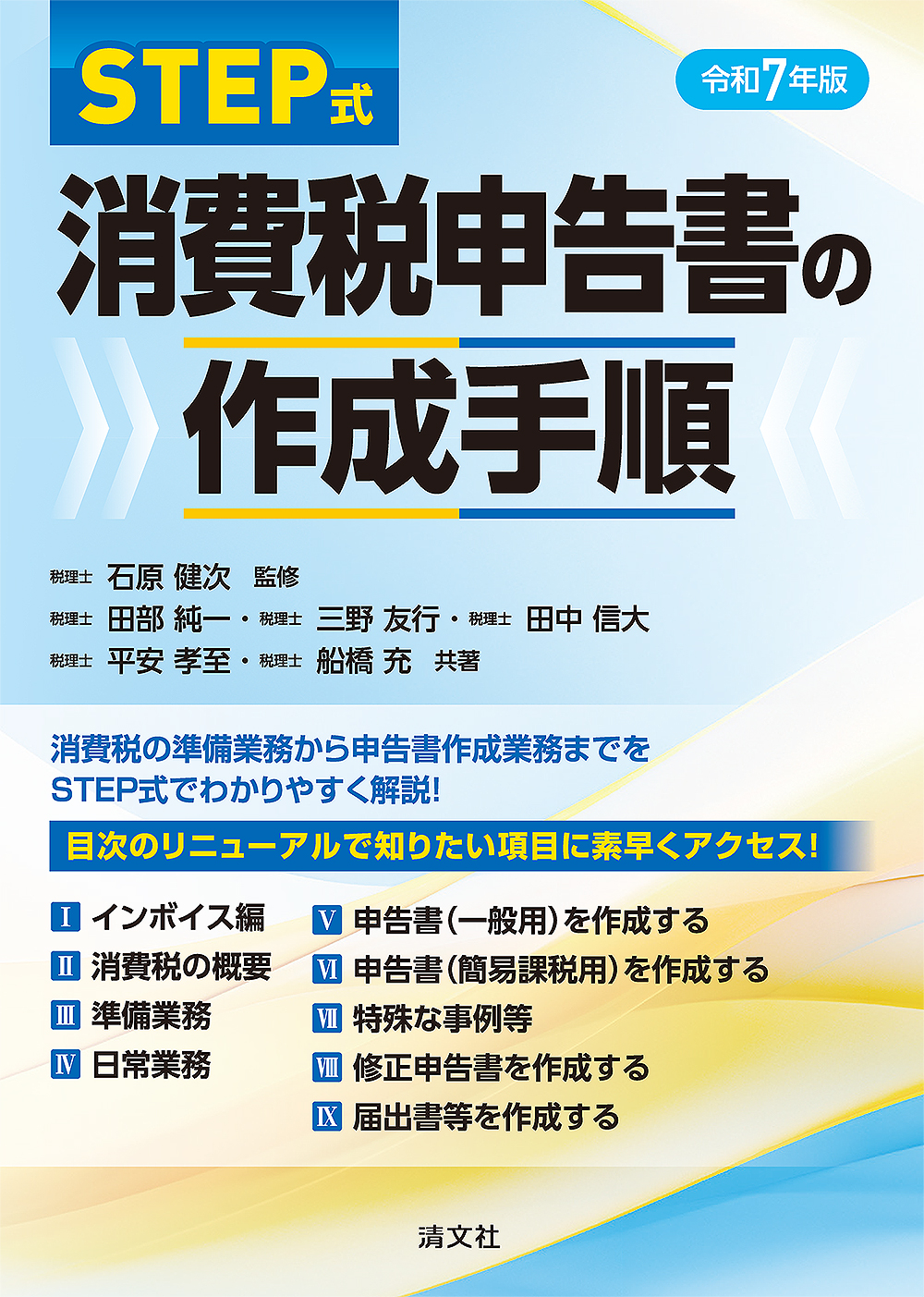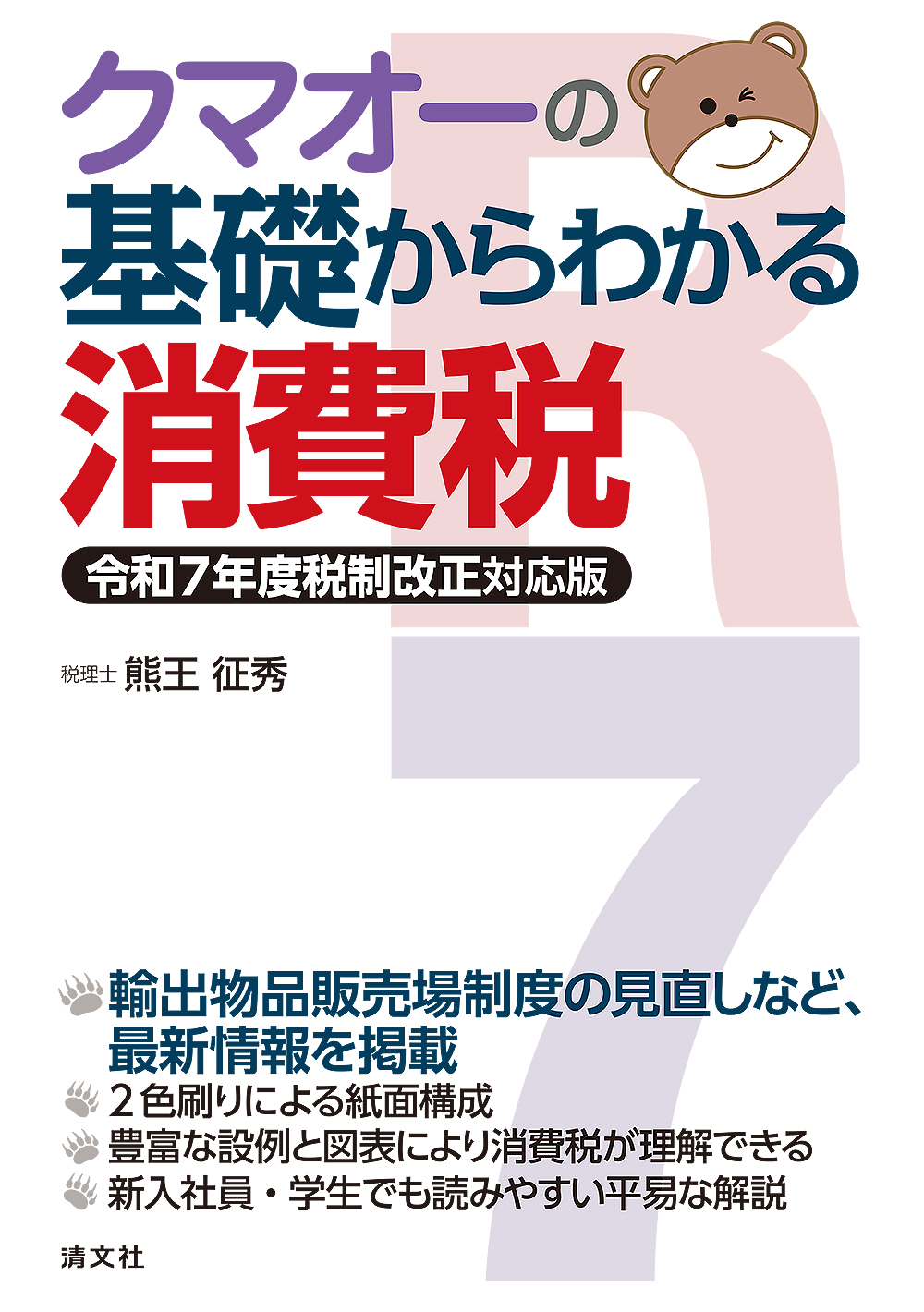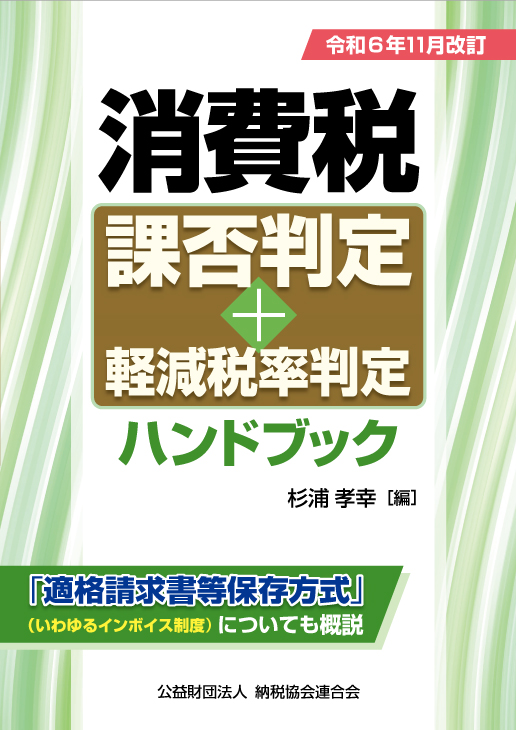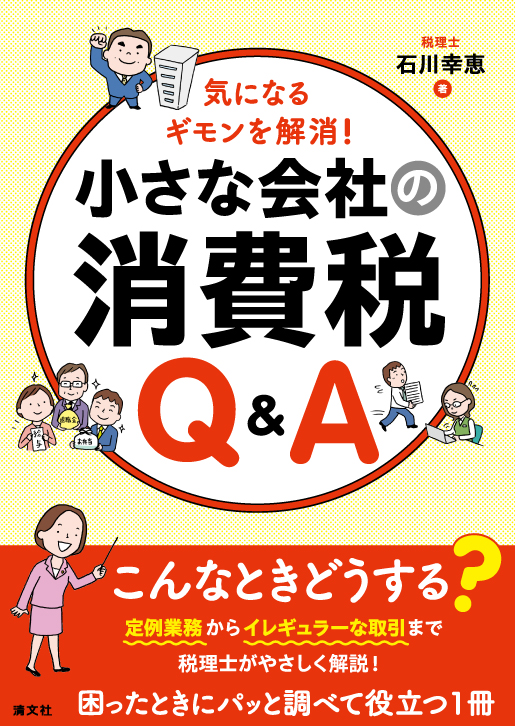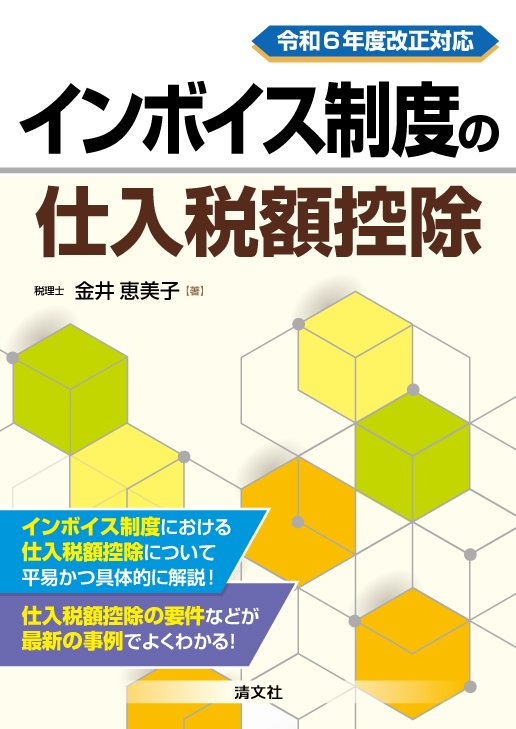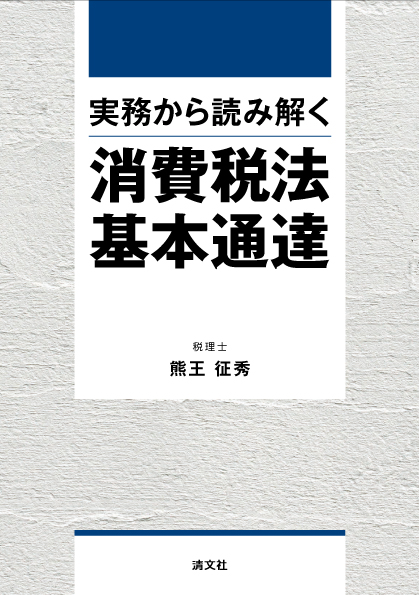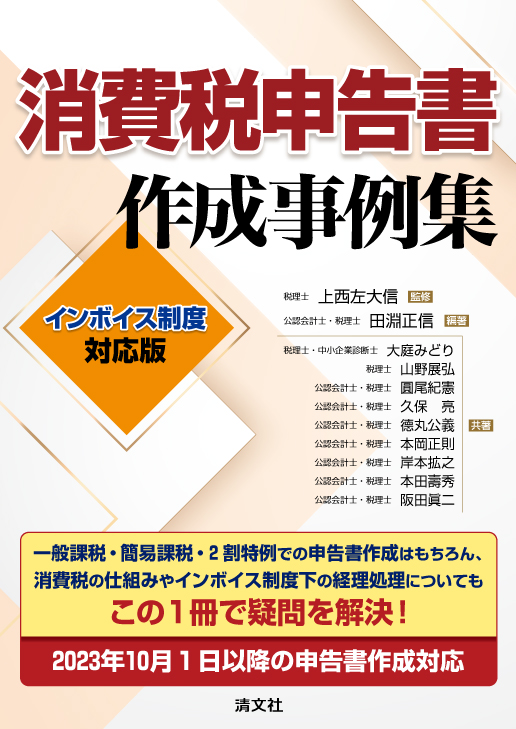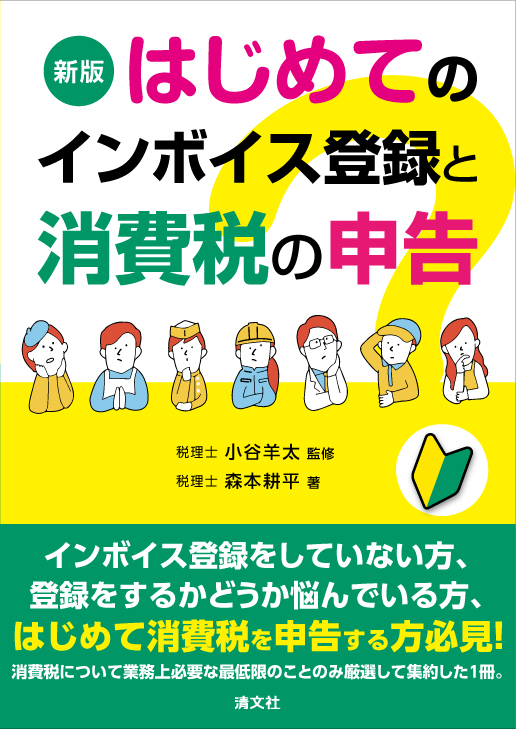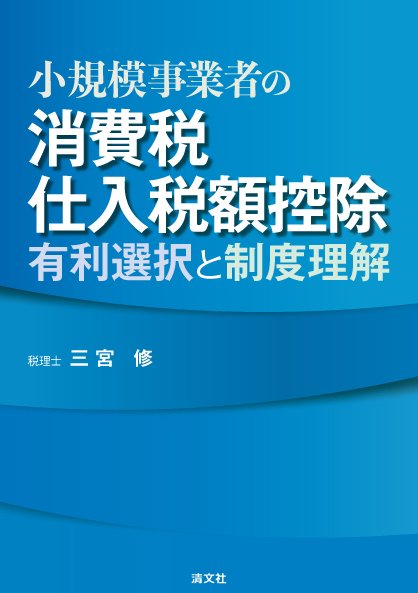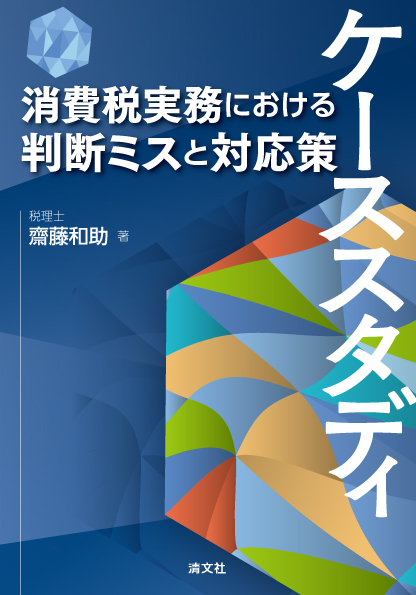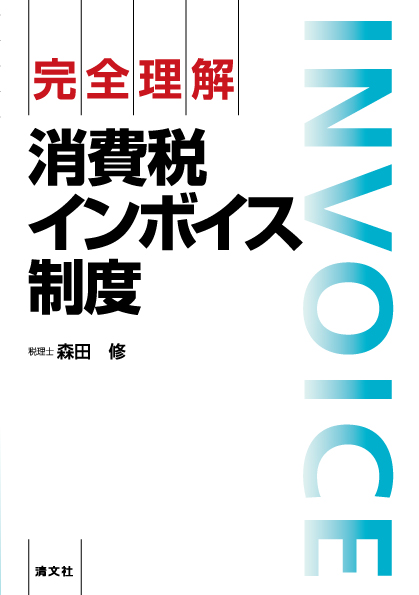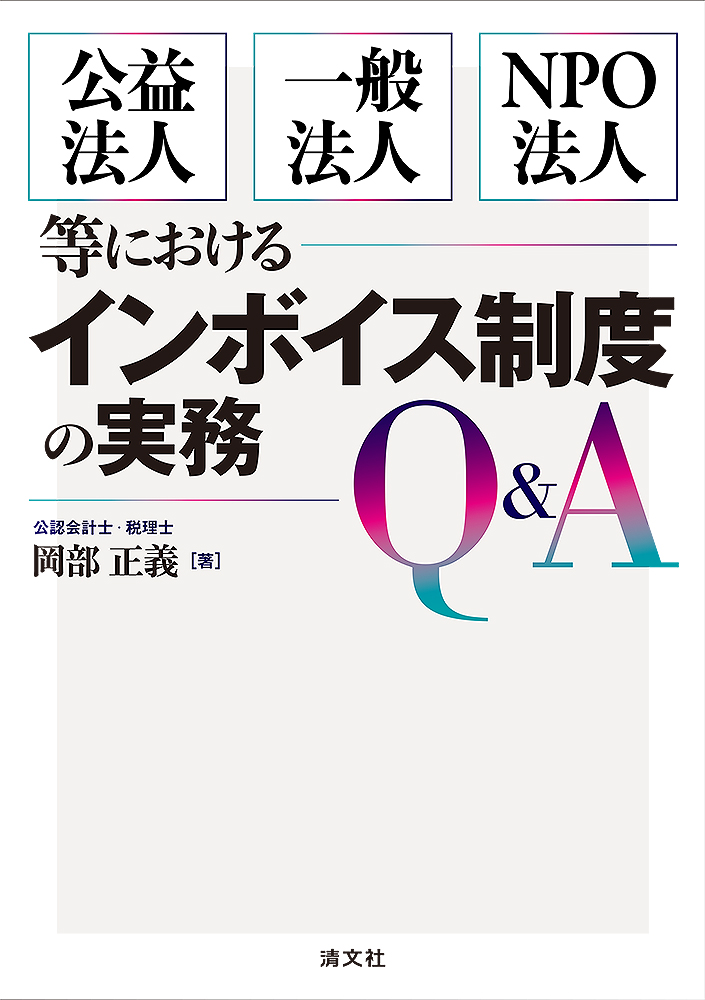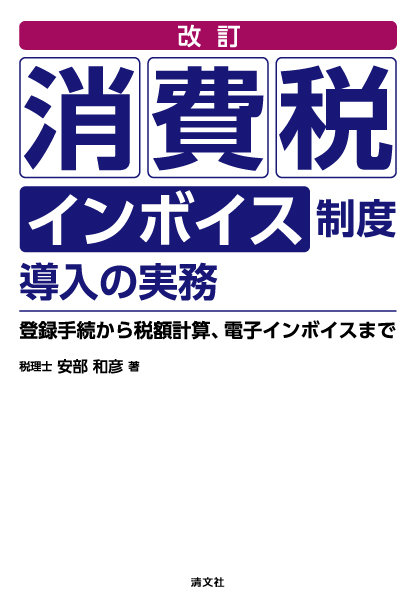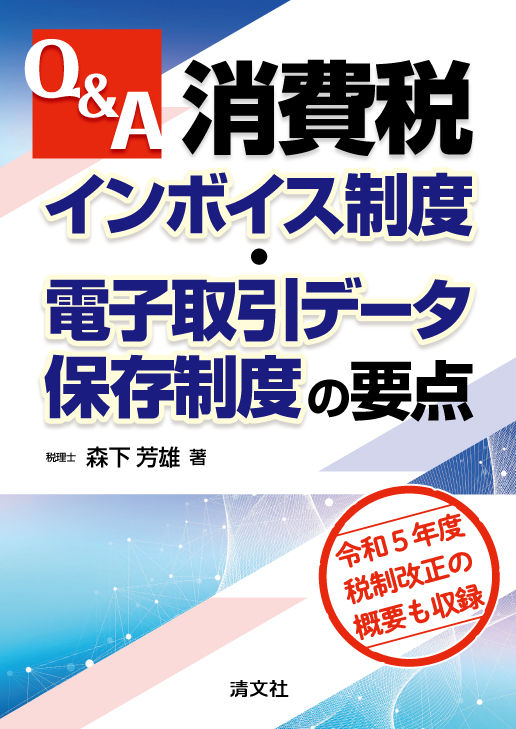〈Q&A〉
消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント
【第1回】
「消費税転嫁対策特措法・下請法の概要と異同」
のぞみ総合法律事務所
弁護士 大東 泰雄
弁護士 福塚 侑也
◇ はじめに ◇
本連載は、施行されて約6年半となる「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特措法」という)が禁止する消費税転嫁拒否等の行為と、「下請代金支払遅延等防止法」(以下「下請法」という)による規制の異同について、両法律が重なり合う範囲に絞ってQ&A方式で横断的に解説し、両法律の内容やこれらを遵守するために留意すべきポイントを、読者の皆様にご理解いただくことを目指すものである。
* * *
【Q】
また、これらの法律の共通点と相違点はどのようなものですか?
【A】
消費税転嫁対策特措法は、消費税の円滑かつ適正な転嫁を図るため、消費税の転嫁を拒む5つの行為を禁止しています。
下請法は、下請取引の適正化を図るため、親事業者に4つの義務を課し、11の行為を禁止しています。
これらのうち、「減額」、「買いたたき」、「商品購入、役務利用又は利益提供の要請」は、両方の法律で禁止されている行為ですが、規制を受ける事業者の範囲や規制内容は大きく異なっていますので、両法律の異同を正しく理解することが重要です。
1 消費税転嫁対策特措法の概要
消費税転嫁対策特措法は、消費税率の引上げに伴って社会で生じることが予想される様々な不都合を解決するために必要な4つの措置を定めた法律であり、平成25年6月5日に成立し、同年10月1日から施行されている。なお、消費税率引上げに適切に対処するための法律であるため、令和3年3月31日限りで効力を失う時限立法とされている。
同法の定める4つの措置の概要は、以下のとおりである。
▷消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
特定事業者が、特定供給事業者に対し、消費税の転嫁を拒否する以下の行為(以下「消費税転嫁拒否等の行為」という)を行うことを禁止するもの。
① 減額
② 買いたたき
③ 商品購入、役務利用又は利益提供の要請
④ 本体価格での交渉の拒否
⑤ 報復行為
▷消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
いわゆる消費税還元セールに関する以下のような表示を禁止するもの。
➤ 「消費税は転嫁しません」
➤ 「消費税は当店が負担しています」
➤ 「消費税率上昇分値引きします」
➤ 「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」
▷価格の表示に関する特別措置
小売店等における総額表示義務の特例を設け、「100円+税」、「100円(税別)」などの表示を可能にするもの。
▷消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
業界が一丸となって消費税転嫁に取り組めるよう、公正取引委員会への届出を条件に、以下の行為を独占禁止法の適用除外とするもの。
➤ 複数の事業者(うち3分の2以上が中小事業者である場合に限る)が、それぞれ自主的に定めた本体価格に消費税額分を上乗せする旨を話し合い、合意すること(転嫁カルテル)
➤ 複数の事業者が、消費税についての表示の方法を話し合い、合意すること(表示カルテル)
※下線は、下請法との交錯が特に問題となるため本連載で取り上げる違反行為。
以上のとおり、4つの措置の内容は、それぞれ全く異なるものである。消費税率の引上げに伴う混乱を回避するために必要な4つの措置が、1つの法律にパッケージとして詰め込まれたと考えると、この法律の全体像をイメージしやすいのではないかと思われる。
本連載が取り上げるのは、上記の4つの措置のうち、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置である。上記措置は、「特定事業者」が、「特定供給事業者」に対し、消費税転嫁拒否等の行為を行うことを禁止するというものである。
2 下請法の概要
下請法は、多数の中小企業に支えられる我が国の産業構造を踏まえ、親事業者が下請事業者に不利益を与える行為等を規制することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正化するとともに、下請事業者の利益を保護することを目的とする法律である。
同法は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という)が禁止する優越的地位の濫用規制を補完する立法であると位置づけられている。もっとも、優越的地位の濫用規制は個別具体的事情に応じた実質判断を重視するのに対し、下請法は事件処理の迅速化・効率化のため形式判断を重視する点に特徴がある。
下請法は、「下請事業者」と取引する「親事業者」に対し、以下の4つの義務を課すとともに、以下の11の行為を行うことを禁止している。
《親事業者の4つの義務》
① 書面(発注書)の交付義務
② 書類の作成・保存義務
③ 下請代金の支払期日を定める義務
④ 遅延利息の支払義務
《親事業者の11の禁止行為》
① 受領拒否の禁止
② 下請代金の支払遅延の禁止
③ 下請代金の減額の禁止
④ 返品の禁止
⑤ 買いたたきの禁止
⑥ 物品の購入・役務の利用強制の禁止
⑦ 報復措置の禁止
⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨ 割引困難な手形の交付の禁止
⑩ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑪ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
※下線は、消費税転嫁対策特措法との交錯が特に問題となるため本連載で取り上げる違反行為。
お気づきの読者も多いのではないかと思われるが、下請法が禁止する11の禁止事項のうち、「下請代金の減額」、「買いたたき」、「物品の購入・役務の利用強制」、「不当な経済上の利益の提供要請」は、消費税転嫁対策特措法においても、消費税転嫁拒否等の行為として禁止されているものである。
つまり、異なる2つの法律において、「買いたたき」の禁止など同じ名称の規制が設けられていることになるため、コンプライアンスの徹底のためには、これらの異同を正確に把握しておく必要があるということになる。
3 2つの法律の大まかな異同
消費税転嫁拒否等の行為が禁止されるのは、事業者がお金を支払って物を購入したり、サービスを利用したりする場面であり、その点では下請法の適用場面と重なるが、対象となる取引の範囲は下請法と比較して極めて広範にわたる。下請法の規制対象となる「親事業者」及び「下請事業者」の意義、消費税転嫁対策特措法の規制対象となる「特定事業者」及び「特定供給事業者」の意義については、本連載の第3回で詳しく述べることとしたい。
次に、2つの法律に含まれる同じ名称の規制であるが、名称は同じであっても、規制の内容や留意すべき場面はかなり異なっている。「買いたたき」については第4回及び第5回、「減額」については第6回、「商品購入、役務利用又は利益提供の要請」については第7回で、それぞれ詳しく述べることとしたい。
そして、次回の第2回では、これらの具体的な規制の異同や留意すべきポイントを述べるに先立ち、消費税転嫁対策特別措置法及び下請法における当局の調査・勧告等の状況について述べることとする。
(了)
「〈Q&A〉消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント」は、毎月第3週に掲載されます。