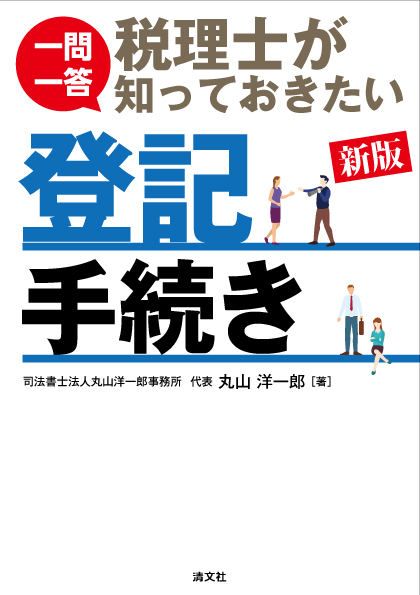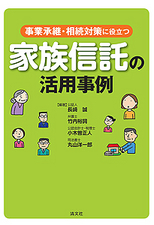〔相続実務への影響がよくわかる〕
改正民法・不動産登記法Q&A
【第1回】
「民法・不動産登記法の改正及び相続土地国庫帰属法成立の背景」
司法書士 丸山 洋一郎
弁護士 松井 知行
◆ ◆ ◆ はじめに ◆ ◆ ◆
所有者不明土地の問題を解消するため、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立した(同月28日公布)。成立した法律の中には、相続の登記を義務化し、義務を怠った場合には10万円以下の過料に処せられるという社会的にインパクトの強い内容も含まれている。
そこで、本Web情報誌の中心的読者であり、かつ相続実務に関わることが多いと思われる税理士、公認会計士、企業の実務担当者にとっては改正法の知識を習得することは不可欠といえる。
本連載は、上記の読者を対象に改正法が実務にどのような影響を与えるのか、できるだけ簡潔に、かつ、分かりやすく解説することを目的とする。
【Q】
今回の民法・不動産登記法改正及び相続土地国庫帰属法成立の背景について教えてください。【A】
所有者不明土地の発生予防と、すでに発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的な見直しがなされた。-《解説》-
人口減少等に伴い土地利用のニーズも減っている。使われない土地が増えると、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は、判明しても所有者の所在が不明で連絡が付かない土地(所有者不明土地)や、管理されず放置される土地(管理不全土地)も増えていく。
この所有者不明土地や管理不全土地の増加により、土地の取引、防災等のための公共事業、森林や農地の管理など様々な点で支障が生じている。古くからあった問題だが、東日本大震災の復興の際に、高台の所有者が不明のために災害復興住宅が建設できなかったことで一般に広く知られるようになった。
このような必要性を踏まえて、所有者不明土地の発生予防と、すでに発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が令和3年4月21日に成立、同月28日に公布された。
① 民法の主要な改正項目
- 所有者不明土地・建物の管理制度の創設
- 共有者が不明である場合の共有地の利用の円滑化
- 長期間経過後の遺産分割の見直し
② 不動産登記法の主要な改正項目
- 相続登記・住所変更登記の申請義務化
- 相続登記・住所変更登記の手続きの簡素化・合理化
③ 相続土地国庫帰属法
- 相続等により土地を取得した者が法務大臣の承認を受けてその土地(一定の要件を満たすものに限る)の所有権を国庫に帰属させることを可能とする制度の創設
両法律の施行日を大まかにまとめると、以下のようになる。
❶ 民法等の一部を改正する法律は原則として令和5年4月1日
❷ 不動産登記法のうち相続登記義務化関係の改正については令和6年4月1日
❸ 不動産登記法のうち住所変更登記義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日(政令は本稿執筆時点(令和3年12月22日)で未制定)
❹ 相続土地国庫帰属法は令和5年4月27日
このように改正法は、段階的に順次施行することとされている。詳細な施行期日は、本連載の中で個別に触れていく。
1 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
● 相続登記・住所変更登記の申請義務化
● 相続登記・住所変更登記の手続きの簡素化・合理化 など
▶ 発生予防
2 土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
● 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
▶ 発生予防
3 土地利用に関連する民法の規律の見直し
● 所有者不明土地・建物の管理制度等の創設
● 共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化
● 長期間経過後の遺産分割の見直し など
▶ 土地利用の円滑化
(※) 法務省資料をもとに筆者作成。
(了)
「〔実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A」は、毎月最終週に掲載されます。