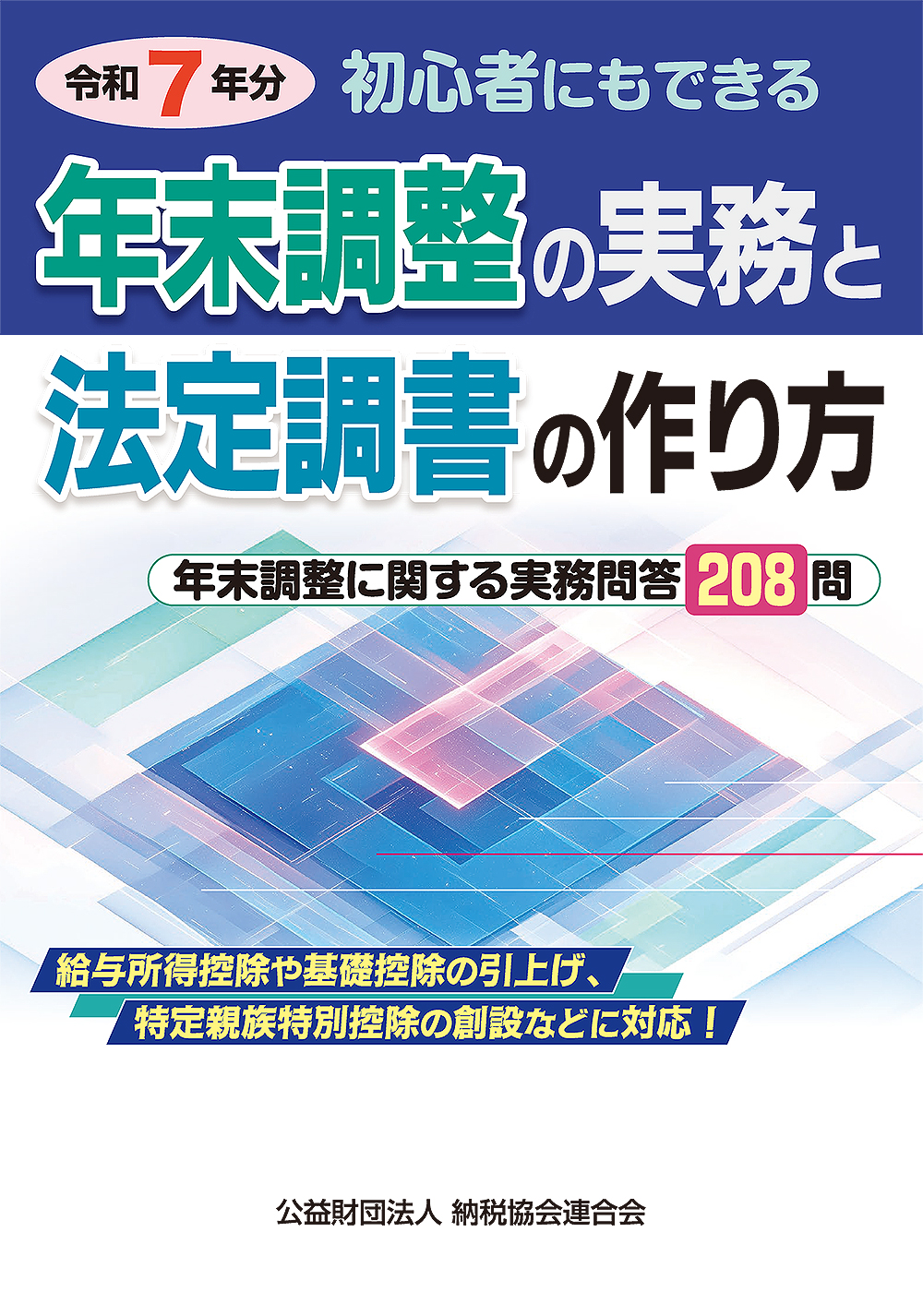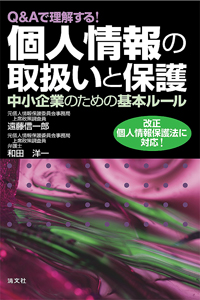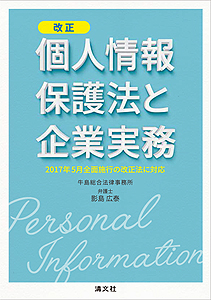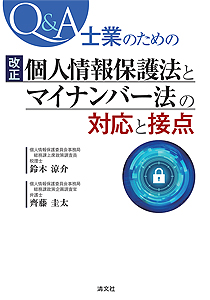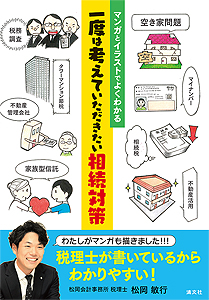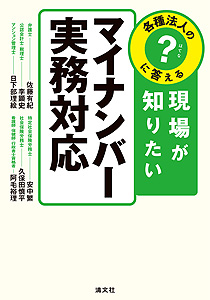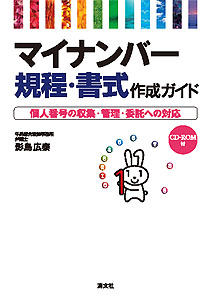企業における
『マイナンバー導入プロジェクト』の
始め方&進め方
【第1回】
「企業内の“旗振り役”となる構成メンバーを集める」
仰星監査法人
公認会計士 岡田 健司
はじめに
~マイナンバーへの企業対応は順調か~
2015年も2月に入ったが、読者の勤務する企業、あるいは読者が関与する企業でのマイナンバーの導入準備は、順調に進められているだろうか。
筆者の印象では、政省令等、ガイドライン、各種Q&Aあるいは法定調書の様式案等が順次公表されてはいるものの、社会全体としては依然認知度合いは低く、急いで取り組まなければならないというトーンにまでは至っていないのが実態と思われる。
「なかなか準備が進まない理由」としては、指針となる情報が最近になって矢継ぎ早に公表されていること、「本人確認」をはじめとする実務がほとんどの会社にとって初めてであることから、その手続き等、手探りにならざるを得ない状況であることも推測される。
また、着手にすら至っていない企業においては、マイナンバー制度自体の認知度の低さに加え、その実務への影響が十分に浸透していないことから、何から着手したらよいか分からないこともその理由に挙げられるのでないだろうか。
マイナンバー制度への対応について、まず何より、『旗振り役となるコアメンバー』の存在が不可欠である。
次に、このコアメンバーを中心として実務への影響を検討し、実際に実務への落とし込みを進めていく『導入プロジェクト』の存在が必要となる。
そこで本連載では、どのようにこのプロジェクトを立ち上げ、どのような役割分担で、どのように進めていけばよいかを解説していきたい。
本連載は計3回シリーズとし、およそ次の内容を予定している。
第1回 「企業内の“旗振り役”となる構成メンバーを集める」(本稿)
第2回 「メンバーの役割とプロジェクトの全体像」
第3回 「プロジェクトをどう進めるか(まとめ)」
なお、2015年におけるマイナンバーへの対応については、本誌に掲載した下記の拙稿をご覧いただきたい。
【参考記事】
〔2015年からできる!〕企業が行うマイナンバー制度への実務対応
1 マイナンバー制度が企業実務へ与えるインパクト
企業がマイナンバー制度へ対応するにあたって、まず、実務への影響度を認識する必要がある。
詳細は上記の拙稿にてご理解いただけると思うが、およそ次の2点が特徴として挙げられる。
① 企業の規模(※1)、業種(※2)、人事システムあるいは給与計算システムが標準パッケージ製品かどうか等によって、実務への影響が極めて広範囲に及ぶこと。
② 企業に重い責任が課されていること。具体的には、番号法には個人情報保護法以上に厳しい罰則(直罰、刑事罰を含む)が規定され、特定個人情報等の情報漏えい等には情報漏えいを起こした本人だけではなく、企業にもその罰則が及ぶ可能性があること。また、企業自体に特定個人情報保護委員会の検査が行われる可能性があること。
(※1) ここでいう「規模」とは、売上高や資本金ではなく、従業員数、支店などの拠点数、株主数、契約数、源泉徴収票の発行数などをイメージされるとよい。
(※2) 本連載において後述するが、影響の大きい業種に、金融業、派遣業、運送業、小売業などが挙げられる。なお、本連載では、金融業は取り上げない。
マイナンバー制度への実務対応にあたっては、この2点を考慮に入れた慎重な対応が求められる。
1点目については、まさに本稿で説明するプロジェクトの進め方と直結する点である。
2点目については、プロジェクトの進め方とも関係するが、どちらかといえば実務的に対処すべき課題である。今まで以上に組織全体、組織の細部に至るまで情報管理の重要性を浸透させる必要がある。また、不要な個人番号を入手しないよう従業員教育を行うことが重要になる。この点は、制度が運用されるまでの残り1年弱の期間にかけてじっくりと、また制度が運用された以降も継続して取り組むべき事項である。
2 企業規模や業種等による影響度合い
(1) 企業規模からみた影響度
マイナンバー制度の導入が企業実務へ与える影響の大きさは、その企業の売上高や資本金等におおむね連動することになると思われる。その他、番号法の実務への影響度合いを計る指標となるものとして、従業員数、支店などの拠点数、株主数、契約数、源泉徴収票や支払調書の発行枚数などが挙げられる。
これらの指標が多ければ多いほど、実務に与える影響は大きいといって間違いない。つまり、これらの指標が多いということは、企業で入手し管理すべきマイナンバー(個人番号)自体の数が多く、入手元である個人の種類も多様になると考えられるためである。
(2) 影響の大きい業種は?
業種からみた企業実務への影響度としては、総合商社、人材派遣業、介護・福祉、小売業、給与計算などのアウトソーシングを受けるサービス業などの業種においては、実務に与える影響が他の業種と比べて相対的に大きいといえる。その他の業種でも、運送業、塾や専門学校、出版社、不動産賃貸業、建設業などでも影響は大きいと考えられる。
これらの業種では、一般的に従業員数(アルバイトやパートタイマーを含む)が多く、事業拠点も全国に多数あるものと思われる。また、個人への業務委託、個人からの不動産賃借含め個人との関わりも深いと思われる。つまりは(1)と同様、マイナンバーの入手及び本人確認を行うべき対象となる個人が多種多数になると考えられるためである。
(3) 人事システム・給与計算システムが標準パッケージ製品か?
人事システムあるいは給与計算システムが標準パッケージ製品でない場合には、番号法への対応を機能面(マイナンバーの入力、新たな様式の帳票の表示や出力、マイナンバーの削除など)、情報管理面(マイナンバーへのアクセス制限、マイナンバーの非表示機能、出力ログの記録など)の両面にわたってシステム改修しなければならないことから、実務に与える影響は極めて大きいと考えるべきである。
(4) 導入に向けた『プロジェクト』が必要となる
マイナンバー制度への実務対応の進め方を考えるにあたり、後述するとおり自社の業務を棚卸して影響度合いを分析するのが理想であるが、まずは上記(1)~(3)を照会することで、自社への影響度合いがおおまかにも把握できる。
影響度が大きいと考えられる企業については、できるだけ早期に対応を進めることはもちろん、影響範囲は広範に及ぶものと考えられることから、以下に示すように『プロジェクト』として対応を進めることが望まれる。
3 構成メンバーは『どの部署』から選ぶか?
プロジェクトの発足にあたり、まずは関係する、あるいは関係しそうな部署の選定が必要となる。
この場合、「総務部」あるいは「人事部」が中心になると考えられるが、上述したようにマイナンバー制度は企業実務の広範囲に影響を及ぼすことから、関係する部署は多岐にわたるという認識が必要である。
例えば、
「『マイナンバーを入手すべき個人』と関連する部署」はどこか
という切り口で考えれば、「総務部」あるいは「人事部」以外にも、「法務部」「経理部」などとも関係がある。
また、番号法やガイドラインで求められる安全管理措置を企業全体で達成しようとすると、「法務部」や「情報システム部」の協力は必要不可欠である。
そこで次の表は、
① 「『マイナンバーを入手すべき個人』と関連する部署」はどこか?
② 「『番号法やガイドライン上求められる対応』を担う部署」はどこか?
という2つの視点で、関係する部署とその役割について、筆者が想定するもので例示としてまとめたものである。
各部署の役割は企業の規模や業種で異なるため一概にはこのとおりに整理されないこともあると思われるが、実務上の影響をおおまかに把握し、各部署からメンバーを招集する際の参考にされたい。
『人事部』
① 当該部署が関係するマイナンバーを入手すべき個人
- 従業員及びその扶養親族
- 個人の社会保険労務士
- 子会社等の給与計算の委託を受けている場合には当該子会社の従業員及びその扶養親族
② 番号法及びガイドライン上、求められる対応
- 従業員の入社時など、各種の業務フローの見直し
- 給与計算のアウトソーシング先の管理監督
- 源泉徴収票等の作成と提出
- 給与支払報告書等の法定調書等の作成と提出
『総務部』
① 当該部署が関係するマイナンバーを入手すべき個人
- 個人の地主、賃貸人
- 個人でデザインやコンテンツ等の製作を請け負う者
- 個人で社内研修を請け負う者
- 株主
② 番号法及びガイドライン上、求められる対応
- 業務委託先との契約フローの見直し(法務部と分掌)
- 地主等との契約フローの見直し(法務部と分掌)
- 源泉徴収票等の作成と提出
- 株主との折衝、株主管理
『法務部』
① 当該部署が関係するマイナンバーを入手すべき個人
- 個人の顧問弁護士
- 個人の弁理士
② 番号法及びガイドライン上、求められる対応
- マイナンバー法の遵守体制の構築、他部署への指導
- 業務委託先との契約フローの見直し(総務部と分掌)
- 地主等との契約フローの見直し(総務部と分掌)
- マイナンバーを含む特定個人情報管理体制の構築と情報管理ポリシーの見直し
- 特定個人情報保護委員会からの命令等への対応、検査への対応
『経理部(あるいは財務部)』
① 当該部署が関係するマイナンバーを入手すべき個人
- 個人の税理士
- 個人の公認会計士
② 番号法及びガイドライン上、求められる対応
- 源泉徴収票等の作成と提出
『情報システム部』
① 当該部署が関係するマイナンバーを入手すべき個人
- 個人で情報システムの製作や保守等を請け負う者
② 番号法及びガイドライン上、求められる対応
- 情報システム(プリンタ等のハードも含む)の改修更新の企画設計及び各課とりまとめ
- 情報システムの改修更新作業
- 外部ベンダーとの折衝
『監査室』
② 番号法及びガイドライン上、求められる対応
- 法令の遵守状況、コンプライアンスに関する状況の監査
- 内部統制評価報告制度への対応(変更後の業務フローの整備評価と運用評価)
- 独立監査人との協議
『広報部』
② 番号法及びガイドライン上、求められる対応
- マイナンバーを含む特定個人情報管理体制の広報
なお、上記に『営業部』の記載がないが、営業部も業種によっては番号法遵守上、極めて重要な位置づけに置かれることもある。例えば、不要な個人番号の提示を顧客に求めたり、提示を受けた個人番号カードの写しや個人番号の記録を不用意にとることは、番号法上認められない。
そのため、営業部に在籍する従業員に対し、番号法上認められない事項や留意事項について十分な社内教育を行うことが、業種によっては重要になる。
なお、これらの対応はすべて、企業内の『誰か』が、プロジェクト化の重要性と、早期にプロジェクト化して取り組む必要性を問うてはじめて実現されうるものであり、繰り返しとなるが、やはり「旗振り役となるメンバー」の存在が極めて重要となるのである。
4 本稿のまとめ
本連載では、「企業における『マイナンバー導入プロジェクト』の始め方&進め方」と題し、企業全体として取り組むべき番号法への実務対応の進め方に焦点を当て解説していきたい。
初回となる本稿では、マイナンバー制度の実務上の影響度合いを概括的に把握するとともに、プロジェクトに関係があると考えられる部署はどこか探ってみた。
本連載の読者の一人でも多くの方がマイナンバー対応の事務局として旗振り役となり、組織に一石投じられることを心から期待している。
(了)