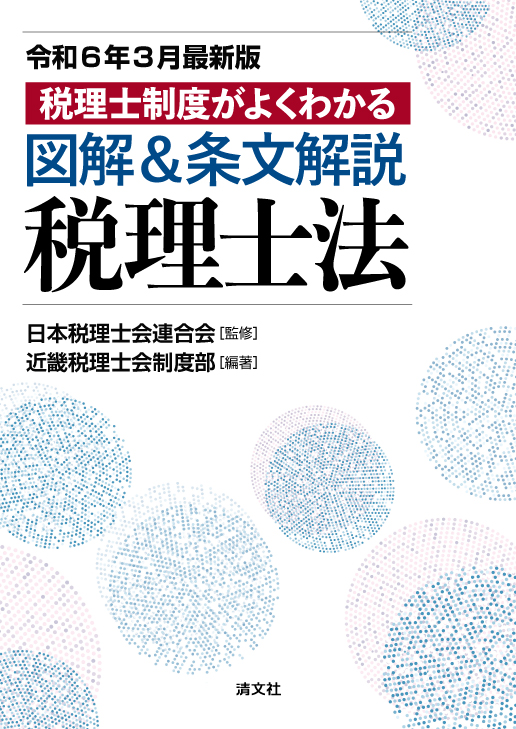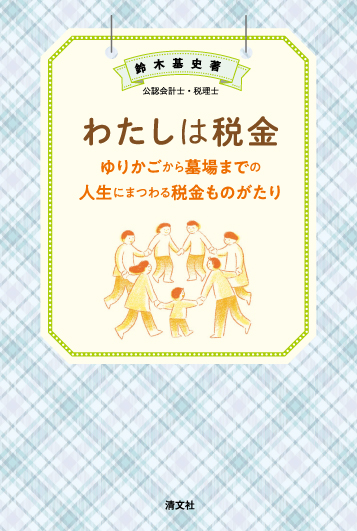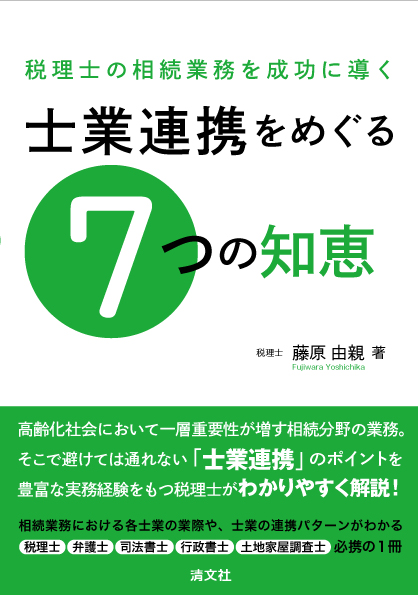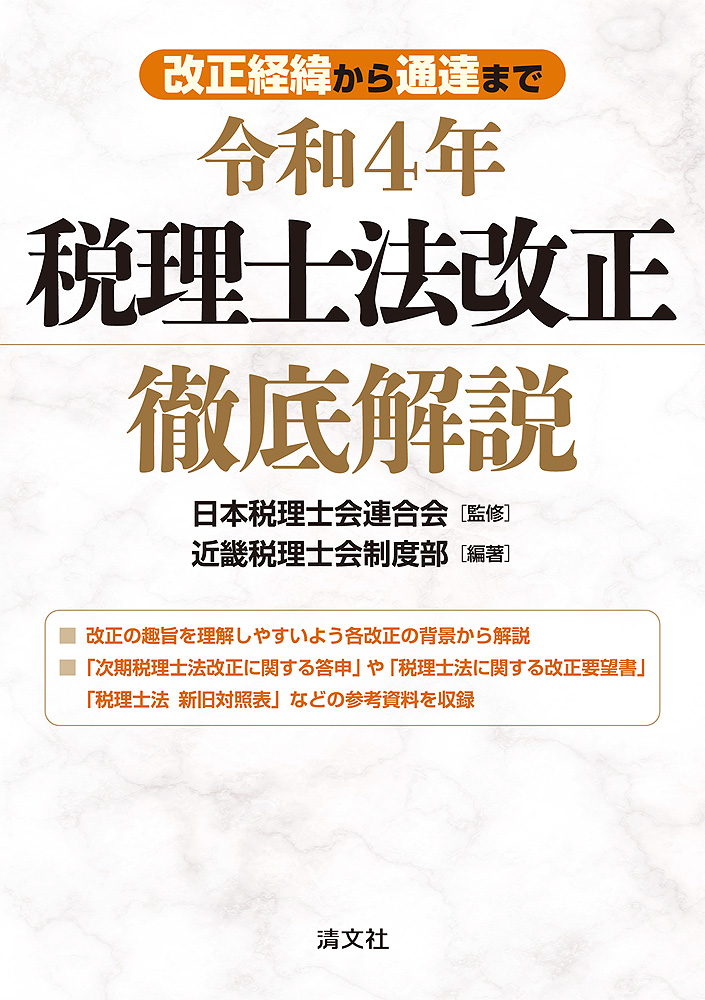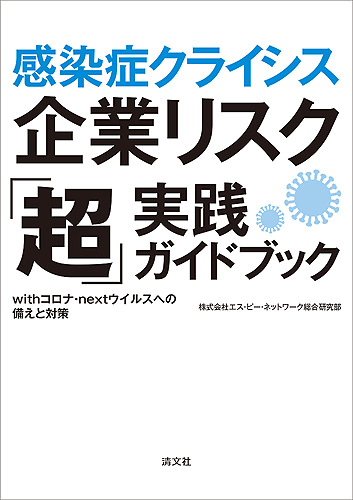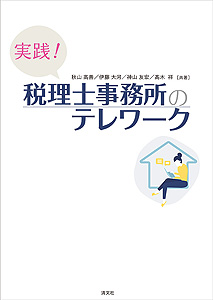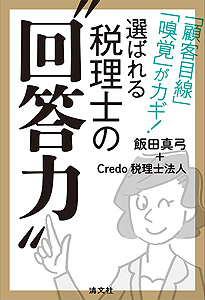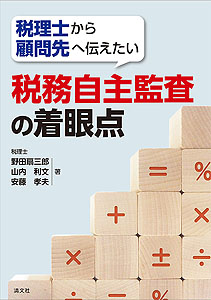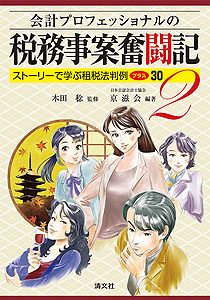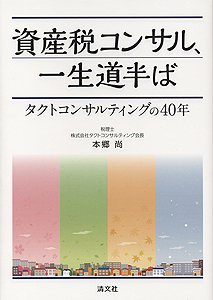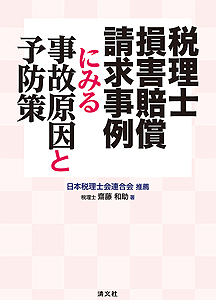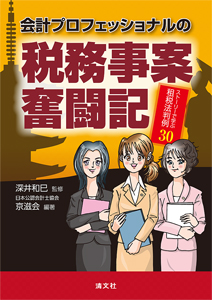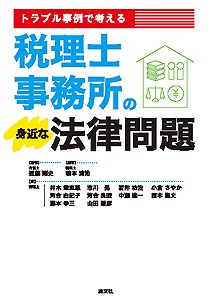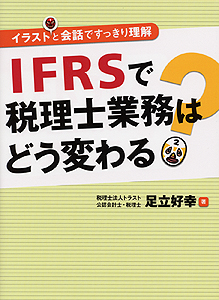改正『税理士法』の検証と今後への期待
【第1回】
「資格取得に関する改正事項」
弁護士 木村 浩之
はじめに~税理士法の改正趣旨~
平成26年度税制改正では、納税環境整備の一環として、税理士法の改正がなされ、課税の実務において重要な役割を担う税理士制度の見直しがなされた。
本稿は、今回の税理士法改正を一つの契機として、税理士がより一層、社会から信頼される存在として高く評価されるために、どのようなことが期待されているかということも踏まえて、改正の内容について解説するものである。
税理士は、税務に関する専門家として、国家財政の基盤である申告納税制度そのものを支え、納税義務の適正な実現を図るために必要不可欠な存在である。
このような税理士の公共的使命に照らせば、個々の税理士が十分な能力及び人格を備えた上で、その能力を遺憾なく発揮し、社会からの信頼を得ることが極めて重要である。
今回の改正では、
① 入り口(税理士資格の取得)の段階で、税理士としての適格性を有すること
② 業務遂行の段階で、十分にその能力を発揮することができる環境が与えられること
③ 業務遂行の前提として、社会からの信頼が得られる態勢を整えること
という「3つの観点」から、税理士制度の質的向上が図られたものといえる。
改正の主な内容については、上記「3つの観点」から次のとおり整理される。以下、順次解説する。
1 税理士資格の取得に関する改正
⇒資格付与の見直し、登録拒否事由の見直し
2 税理士業務に関する改正
⇒補助税理士制度の見直し、調査の事前通知
3 税理士の信頼性確保に関する改正
⇒税理士に係る懲戒処分の適正化など
1 税理士資格の取得に関する改正
(1) 資格付与の見直し
① 現在の資格制度
税理士資格は、税理士法(以下「法」という)3条によって定められており、税務の専門家として適正な職務を遂行することができるだけの能力を担保するものである。能力を図るのにもっとも明快な指標が試験であり、その意味では、試験合格者(法3条1号)が税理士資格のもっとも正当なルートであるといえる。
ところが、これには広く例外が定められており、法7条によって試験が免除された者(いわゆる「大学院ルート」)、法8条によって試験が免除された者(いわゆる「OBルート」「教授ルート」)が税理士となる資格を有している(法3条2号)。
大学院ルートでは、税法と会計学の各分野に属する科目につき、1科目でも合格すれば、残りの科目が免除されることになる。また、教授ルートでは、大学教授などの専門職にある者が当該専門分野の科目を免除されることになる。
重要なのがOBルートであり、これによって国税等のOB職員には、試験免除の途が与えられている。例えば、国税職員の場合には、一定の業務に10年以上従事すれば税法科目が免除され、さらに、23年以上従事した上で、会計に関する指定研修を修了すれば会計科目も免除され、税理士の資格が与えられることになる。
以上のほか、第4のルートとして、弁護士・公認会計士については、無条件で税理士となる資格が認められていた。
【参考条文(改正後)】
※下線筆者
(税理士の資格)
第3条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年(筆者注:今回の改正によって従前の3年から短縮されている)以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
(試験科目の一部の免除等)
第7条 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
2 税法に属する科目・・・(略)・・・に関する研究により修士の学位・・・(略)・・・を授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
3 会計学に属する科目・・・(略)・・・に関する研究により修士の学位・・・(略)・・・を授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
4・5 略
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
一 大学等(略)において税法に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあった期間が通算して3年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目
二 大学等において会計学に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあった期間が通算して3年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目
三 公認会計士法第3条に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第10条第2項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に属する科目
四 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
五 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
六~九 略
十 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目
イ 第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して23年以上になる者
ロ・ハ 略
2 略
② 今回の改正
以上の現状に対して、日本税理士会連合会(以下「日税連」)では、弁護士・公認会計士については、その資格のみでは税務という専門職としての業務を遂行するには不十分であるとして、一定の要件(弁護士については会計科目の試験、公認会計士については税法科目の試験)を課すように意見を述べていた。これに対して、日本弁護士会連合会や日本公認会計士協会からは反対の意見が出され、これらの間で繰り広げられる論戦は社会的にも注目を浴びていた。
今回の改正では、最終的には、政治的な決着が図られ、日税連の意見を一部採り入れる形で、公認会計士に係る資格付与については、全くの無条件というわけではなく、一定の税法に関する研修を受講する必要があるものと変更されることになった。
ただし、経過的な措置として、この改正については、平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について適用されることになる。
なお、これに対して、弁護士に係る資格付与については、今回の改正では特に変更がなされておらず、無条件での資格付与が残される形となった。
この点は議論の余地があり得るが、昨今の国税通則法改正などにおける納税者の手続保障を重視する観点からは、不服申立ての前段階である調査手続の段階から法律の専門家である弁護士が関与する機会が与えられ、税理士との協働が図られることは、納税者にとっても有益である場合が多いということは指摘できよう。
(2) 登録拒否事由の見直し
税理士となるためには、税理士となる資格を有する者であることに加えて、税理士会で税理士の登録を受ける必要がある(法18条)。
税理士法は、たとえ税理士となる資格を有していたとしても、税理士としての職務を果たすのに不適当である場合を「登録拒否事由」として定めている(法24条)。
昨今、税務職員による不祥事が相次いでおり、なかでも課税情報の漏えいなど、申告納税制度全体への信頼を揺らがしかねない事件を起こした職員について、退職後に税理士業務を行うことを認めるとすれば、税理士に対する社会的信頼が失われるおそれがある。
もちろん、欠格条項に該当する者は税理士となる資格を有しないとされており、懲戒免職に処せられた公務員については、処分から3年を経過するまでは税理士となる資格を有しない(法4条8号)。
ただし、それでも3年が経過すれば、特段の障害なく税理士の登録を受けることが可能であった。
今回の改正では、そのような年数経過によって欠格条項には該当しないようになった場合でも、なお税理士業務を行わせることに適正を欠くおそれがあるときには、税理士会において税理士登録を拒否することが可能になった。
あわせて、一定の刑に処せられた者や税理士法に基づく懲戒処分で業務禁止となった者(いずれも欠格条項該当者)についても同様に、年数経過によって欠格条項には該当しないようになった場合でも、なお税理士業務を行わせることに適正を欠くおそれのあるときは、登録を拒否することが可能になっている。
これにより、形式的には税理士となる要件を満たす場合であっても、諸般の事情を総合考慮した上で、税理士としての適格性を判断し、実質的な観点から不適当と認められる場合には登録を拒否することができるようになった。
(了)
次回は7月31日(No.80)に掲載されます。