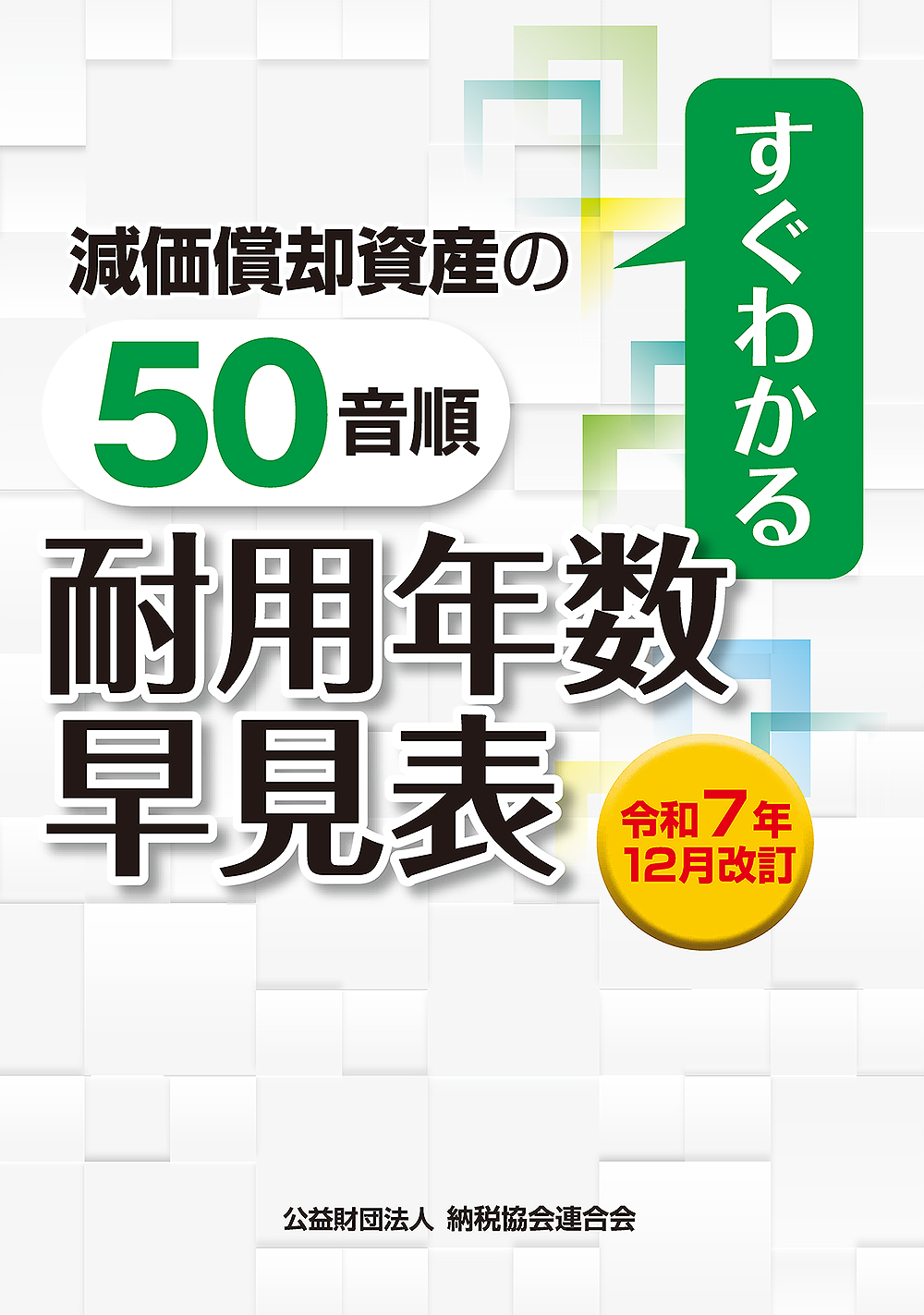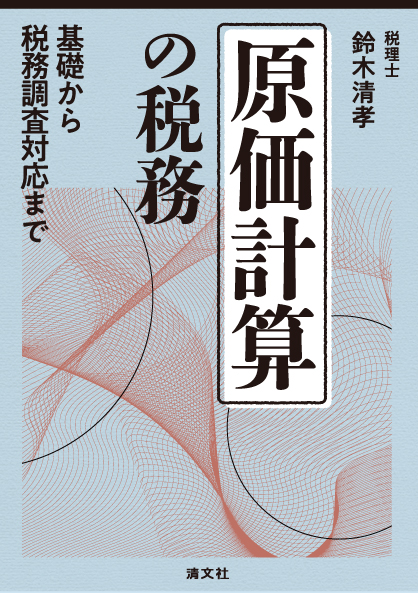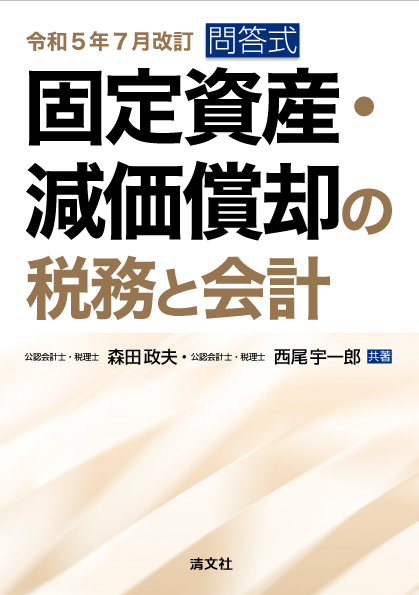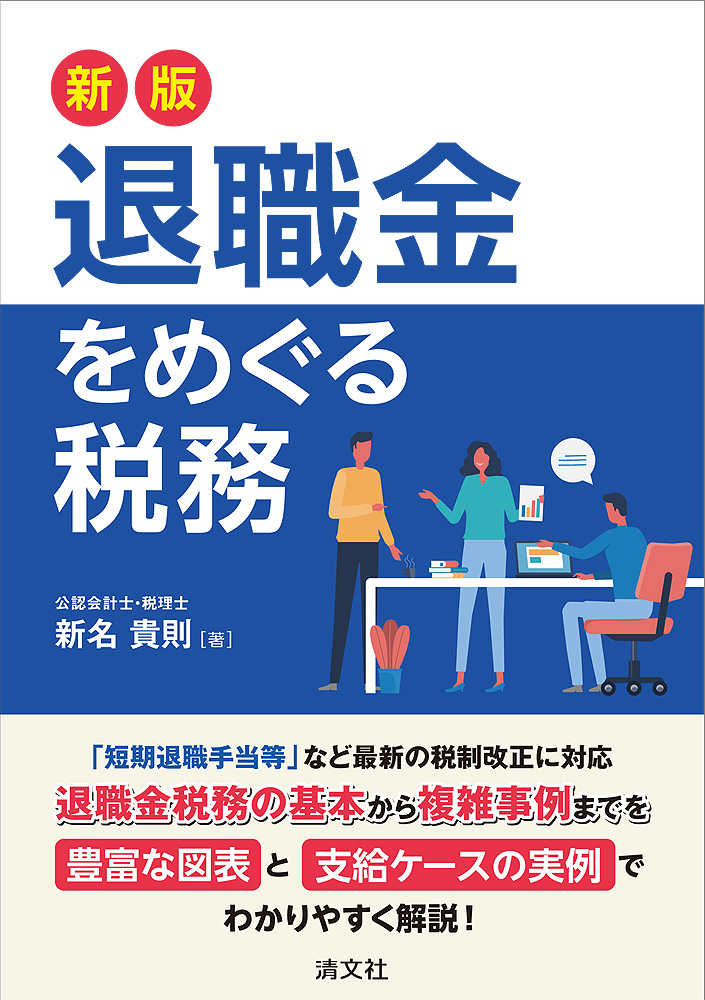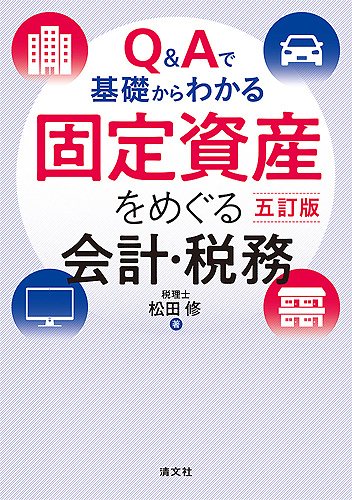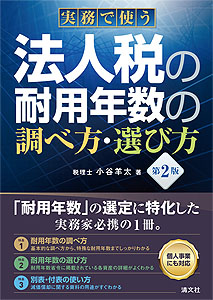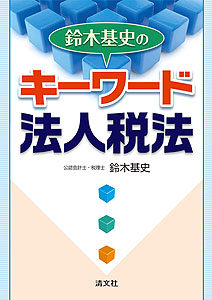税効果会計における
「繰延税金資産の回収可能性」の
基礎解説
【第6回】
「解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異の取扱い」
仰星監査法人
公認会計士 永井 智恵
1 はじめに
前回の連載【第5回】では、タックス・プランニングの実現可能性に関する取扱いについて解説を行った。会社の分類によっては、タックス・プランニングの実現可能性が、繰延税金資産の回収可能性の判断に大きく影響してくるということを説明した。
さて、今回は「解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異の取扱い」について説明する。
重要な用語である「将来減算一時差異」(連載【第1回】)や「一時差異等加減算前課税所得」(連載【第2回】)の意味や、「スケジューリング」(連載【第2回】)及び会社の「分類」(連載【第3回】・【第4回】)の考え方をしっかりと理解したうえで、読み進めていただきたい。
2 解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異とは
連載【第2回】で解説したように、将来減算一時差異や将来加算一時差異が税務上でどのように認容されていくか、つまり、どのように解消されていくかを検討することを「スケジューリング」という。
そのスケジューリングの結果、企業が継続する限り、長期にわたるが将来解消され、将来の税金負担額を軽減する効果を有する一時差異のことを「解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異」という。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。