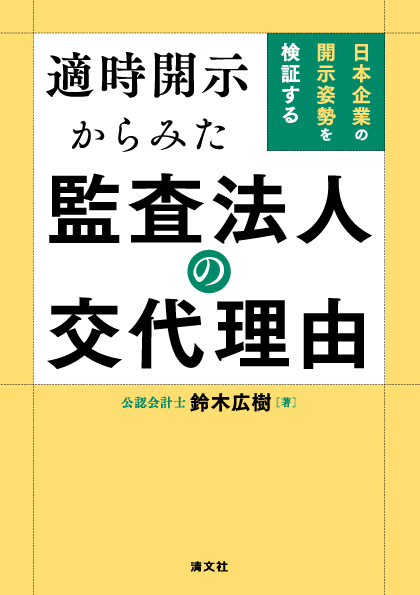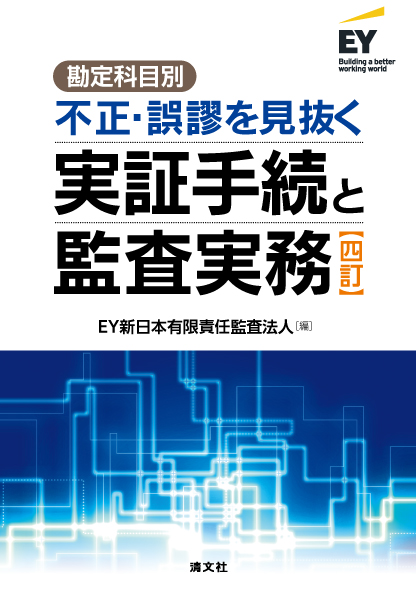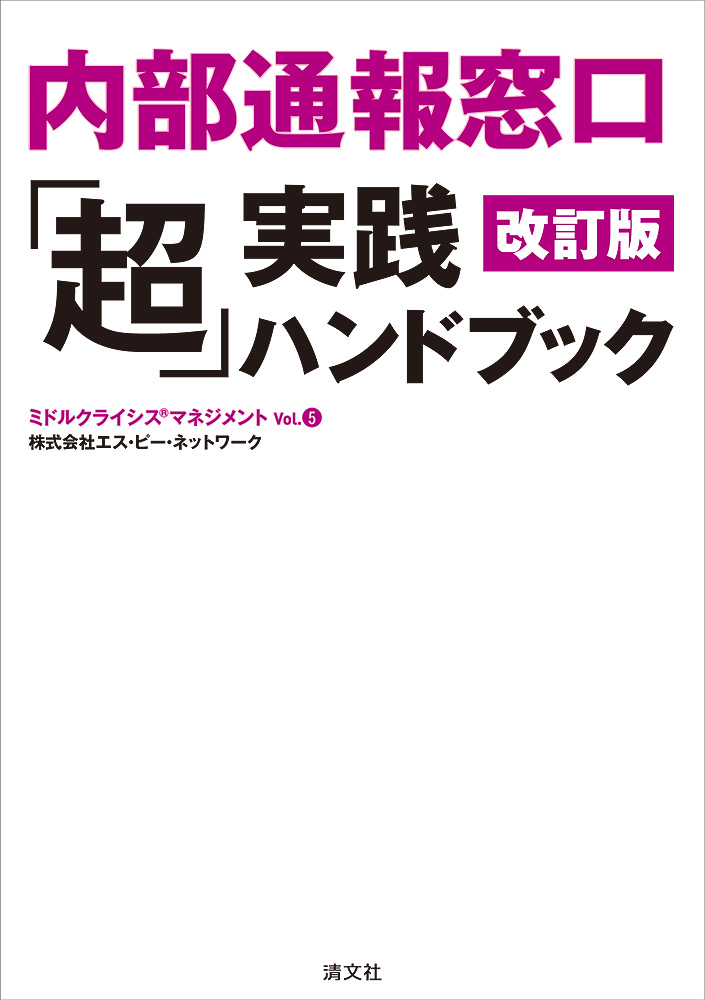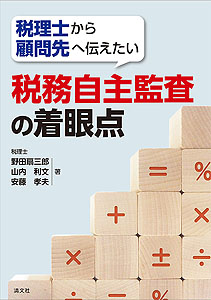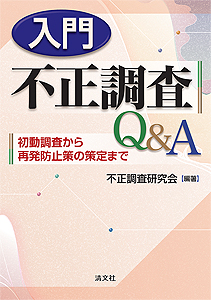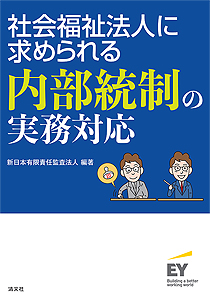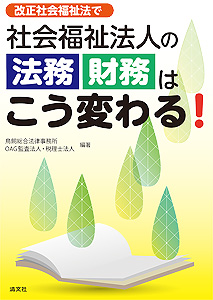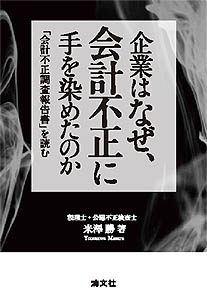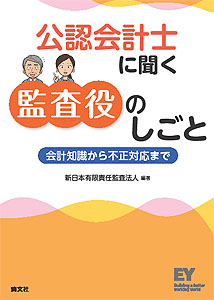事例で学ぶ内部統制
【第1回】
「5年目の内部統制報告制度、
各企業が抱える課題とは?」
株式会社スタンダード機構
代表取締役 島 紀彦
はじめに
筆者が代表を務める株式会社スタンダード機構は、内部統制報告制度が踊り場に差し掛かった3年目にあたる平成22年6月から定期的に、企業で内部統制を担当されている部課長に参集いただき、内部統制報告制度をどうやって有効かつ効率的に運用するべきかを考える交流会を行ってきた。交流会では、毎回、内部統制をめぐり企業の現場で起こっている実務課題と解決策を持ち寄る。
参加企業は、年商100億円程度の中堅企業から数兆円程度の大企業にまでわたり、業種も、電機、食品、卸、重工業、建設、商社、情報通信など、多種多様である。また、交流会には監査法人は参加しておらず、企業の実務担当者による意見交換となった。
本稿では、交流会で交わされた内容を振り返り、「内部統制の現場で何が問題となっているのか」、「その解決として各企業がどういう知恵を絞っているのか」という視点で、今後の内部統制の運用に役立つ事例を紹介していく。
5年目に入った内部統制報告制度
内部統制報告制度は、平成24年4月から5年目に入った。金融庁が実施基準を公表したのが平成19年2月、内部統制報告の開始が平成21年3月決算からであるから、企業に与えられた準備期間は2年余りであった。経理部門に限らず、企業のさまざまな部門を巻き込んで取り組む制度としては、極めて急ピッチで対応が進められたことになる。
参加企業Aは、「正直、導入2年目までは、監査法人が何をどのレベルまで対応するのかという基準を持ち合わせていなかったし、私たちには知識も経験もなかったので、監査法人からの場当たり的な要望の内容を斟酌しながら対応を進める手探り状態だった」(食品メーカー)と、導入当時を振り返った。
金融庁によれば、初年度の内部統制報告制度で、開示すべき重要な不備があると報告した企業の比率は2.4%、その後もこの比率は低位で推移している。そこで、制度4年目を迎えた平成23年3月、金融庁は早々と実施基準の簡素化案を公表した。
各社で簡素化案をどのように自社に取り込むべきかという議論が交わされる中、平成23年末にオリンパスや大王製紙の巨額会計不正が絡む内部統制の不備が発覚し、現在に至っている。
参加企業Bは、「従来の実施基準は抽象的だったため、わが社が他社よりも過剰な対応をしていないかどうかを検証したくても、物差しがなかった。基準が改定されて簡素化に向けた方法が提示されたが、この簡素化案を他社はどの程度採用しているのだろうか、という新たな疑問も出てきた」(建設会社)と、簡素化案の公表後も依然として基準の適用に悩む実情を吐露した。
参加企業Cは、「日本は米国に比べて内部統制の重要な不備の報告が少ないというが、実態を表しているのだろうか。日本では、内部統制の重要な不備を外部に公表するのは恥を晒すことに等しいと考える企業が多いのではないか。わが社はまさにその思想で、内部統制評価部門が合格を出すまで評価を何度も繰り返すとか、評価される側の部門が、事前にすべての伝票を全件チェックして、不備があれば修正して評価に臨み、不備の発覚を防ぐという対応をしていた。簡素化案に踏み切ることは、わが社の場合は拙速だと思う」(商社)と話し、簡素化の適用には懐疑的だった。
このように、内部統制の開始からこれまでの企業の対応状況は悩ましく、紆余曲折を経ている。
制度がもたらした便益とは
他方、内部統制報告制度が企業に良い効果をもたらした面もある。
参加企業Dは、「株式を公開している企業にとって財務報告の信頼性が重要だということに、経理部だけでなく、経理部以外の従業員が理解を示すようになった」(精密機器メーカー)と、全社的な活動としての内部統制の効果を認めた。
参加企業Eは、「財務諸表監査も含めて、監査法人との付き合い方が変わった。内部統制報告制度が導入される前は、私たちはいわば丸腰で、監査法人に言われるままだった。導入後は、リスクとかアサーションとか、監査法人の思考パターンが分かり、監査法人とのコミュニケーションに必要な武器を持つことができた。そのうち、監査法人の言うことを丸呑みするのではなく、他社の事例も踏まえて監査法人と協議する姿勢が生まれ、効果的な監査につながった」(電機メーカー)と話した。
参加企業Fは、「内部統制に対する理解が高まることで、取引先との関係が健全になった。顧客が上場企業の場合、顧客側が購買業務の内部統制を整備する過程で、わが社に対して無理難題のある取引条件を強いることがなくなり、商売がしやすくなった。他方、わが社の仕入先に対して特別な条件や無理な条件で取引することがなくなり、取引条件の透明性が高まり、業務の効率化が実現できた」(食品メーカー)と話した。
いずれも、当初から内部統制に期待された便益である。
山積する実務上の課題
それでも、参加企業の声を聞くにつけ、依然として企業の現場では、制度全般と個別具体的課題の両面で課題が山積しており、どの指摘も、これからの内部統制の課題として正鵠を射ていると感じる。
参加企業Gは、「内部統制も5年目に入り、現場は監査慣れしてしまった。均一化されたルーティーン運用を続けていて、本当に役立つのだろうか、という悩みや疑問が尽きない。もっと効果のある運用をしたい。でも、監査法人はなかなかメリハリのある評価の方法や簡素化の方法を教えてくれない」(情報通信会社)と、制度全般に対する課題を漏らした。
個別具体的な実務課題は次のようなものだ。
まず、「内部統制評価は、毎年同じ作業の繰り返しだが、どの作業をいつごろから開始すればよいのか」という年間スケジュールの問題がある。
監査組織上の実務課題は数多いが、
「社内の内部監査部門の人員が削減される中、少ない人員で内部監査部門の独立性を保つための工夫は何か」
「そもそも内部監査部門の負荷として、1名あたりいくつのコントロールの評価を担当するのがちょうどよいのか」などだ。
評価の手法をめぐる実務課題としては、
「全社レベルの内部統制で、実施基準はCOSOモデル42項目となっているが、企業の実情に応じて追加した評価項目の事例はあるのか」
「プロセスレベルの内部統制で、評価の対象となる重要なコントロールを絞り込むため、キーコントロールと呼ばれる概念を使う場合、その比率は何%ぐらいか」
「決算プロセスの内部統制の評価は専門性が高く、リスクも高いと言われるが、そもそも、どのようなリスクとコントロールを認識しているのだろうか。また、リスクコントロールマトリクス(RCM)を使わない企業があると聞いたが本当か」
などが挙げられた。
運用評価のあり方は、今回の簡素化に大きく関係しており、
「効率化のために、どのように評価対象となるコントロールの絞込みをするのか」
「効率化のために、どのように評価対象部門の集約をするのか」
「運用テストの対象期間とサンプル数は、本当に各社で同じなのか」
「エラーが発生したときの再評価の方法を工夫したい」
などの重要な実務課題が多い。
今回は、内部統制報告制度の開始からこれまでを振り返り、交流会に参加した各企業が制度の便益を認めながらも、より有効かつ効率的に運用するための実務上の悩みや課題を抱えている実情を紹介した。
次回以降では、交流会で交わされた個別具体的な実務課題と解決に向けた取組みの事例を順次紹介していく。
(了)