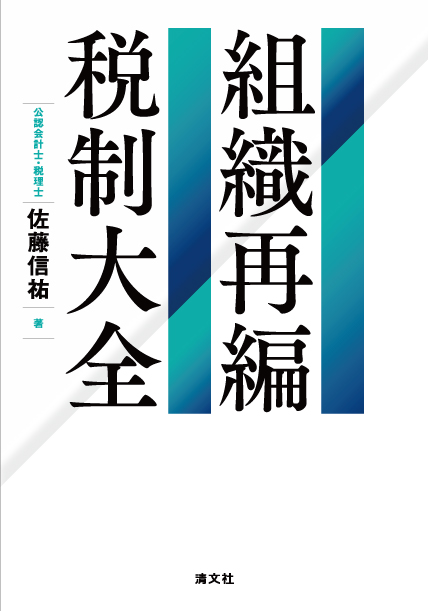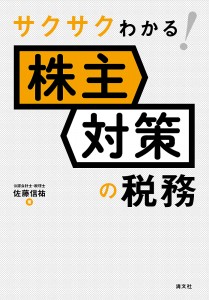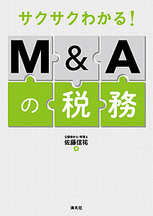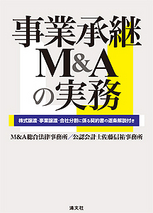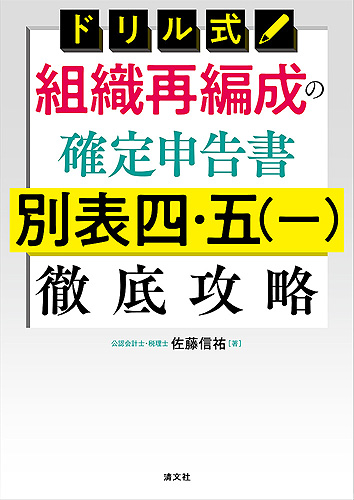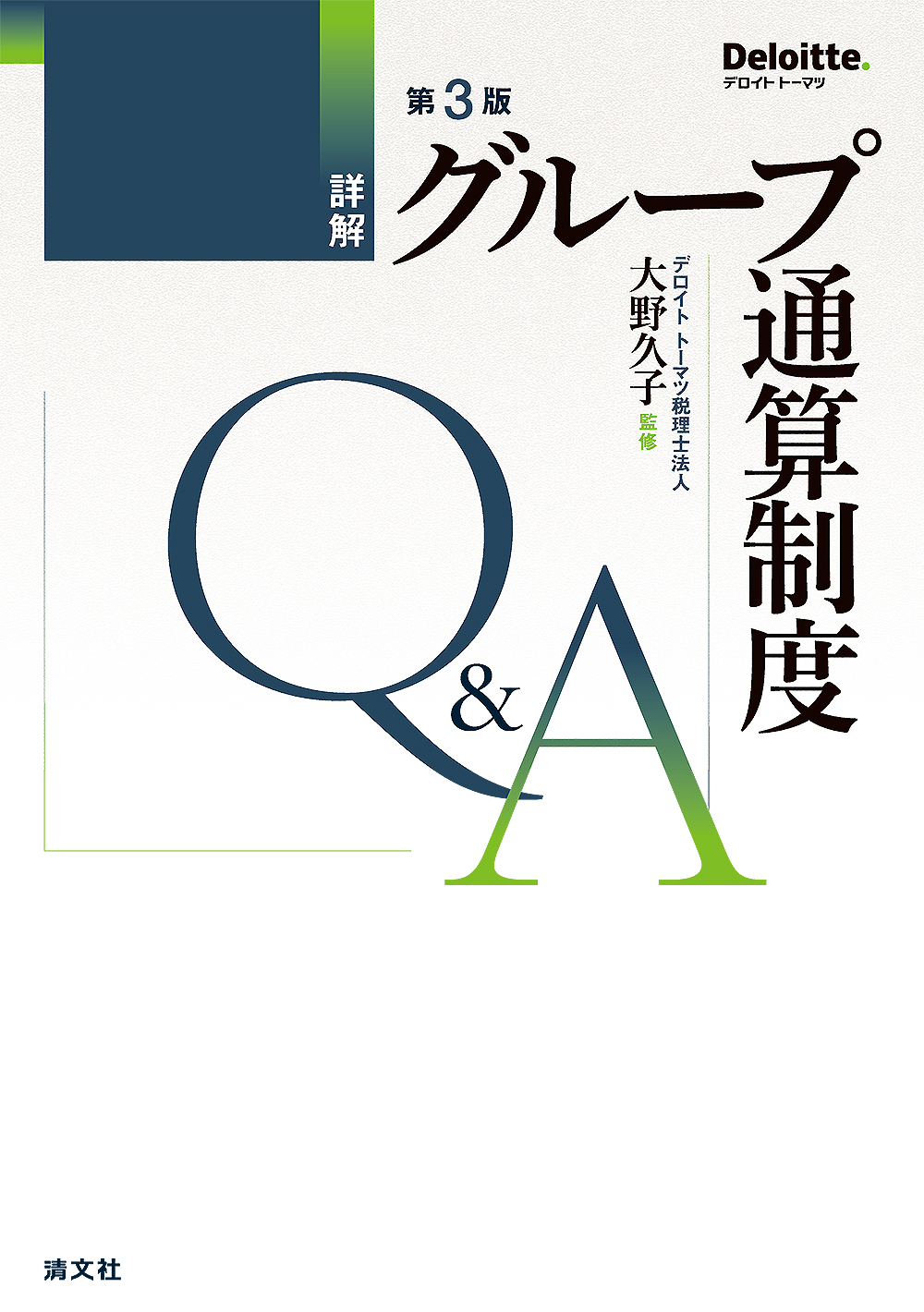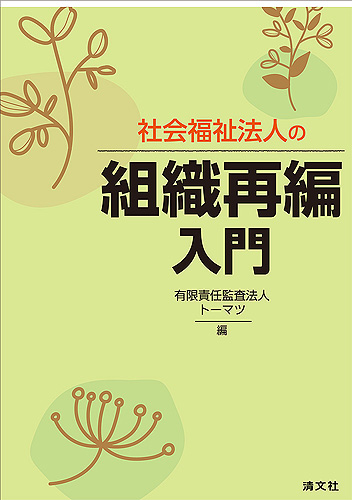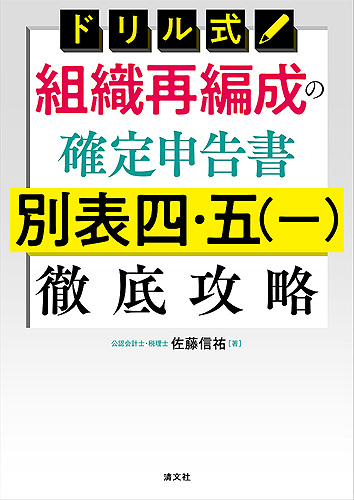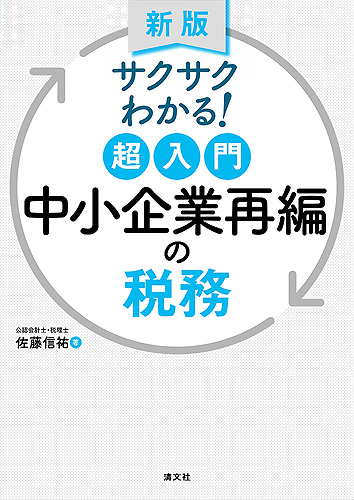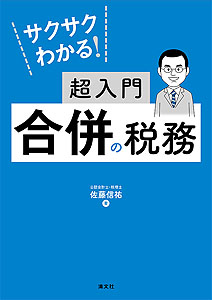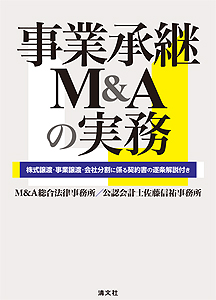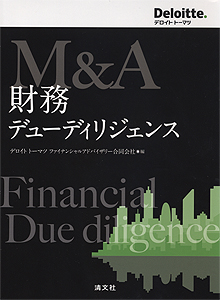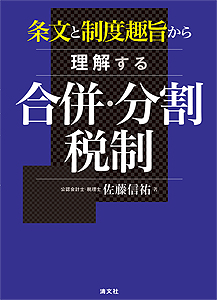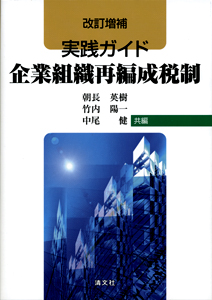〔平成29年度税制改正大綱からみた〕
組織再編税制の改正内容と実務への影響
【前編】
公認会計士 佐藤 信祐
1 概要
平成28年12月8日に平成29年度与党税制改正大綱が公表された。税制改正大綱が公表される前はスピンオフ税制のみが報道されていたが、実際に公表されてみると、平成18年度税制改正(会社法への対応)、平成22年度税制改正(グループ法人税制)に匹敵する大改正であったということが言える。
その概要は以下の通りである。
① スピンオフ税制
② スクイーズアウト税制
③ 支配関係継続要件の見直し
④ 株式継続保有要件の見直し
⑤ 2段階組織再編成の見直し
⑥ 資産調整勘定の償却の見直し
⑦ 繰越欠損金、特定資産譲渡等損失の見直し
このうち、②から⑤までの改正は、平成29年10月1日の施行が予定されており、それ以外は、平成29年4月1日の施行が予定されている。
詳細な内容については、政省令を確認しないと分からないが、本稿では、税制改正大綱から読み取れる実務上の留意事項について解説を行う。
2 スピンオフ税制
現行法人税法では、支配株主の存在しない新設分割型分割や子会社株式の現物分配は、グループ内の組織再編にも該当せず、共同事業を営むための組織再編にも該当しないことから、非適格組織再編として取り扱われている。このような取扱いが企業の円滑な組織再編を妨げているという批判から、スピンオフ税制が導入された。
スピンオフ税制の対象となる組織再編は以下の通りである(なお、具体的な税制適格要件は、平成29年度税制改正大綱(p68-69)を確認されたい)。
① 単独新設分割型分割
② 100%子会社株式を対象とした現物分配
③ 単独新設分社型分割又は単独新設現物出資後に、分割承継法人株式又は被現物出資法人株式の現物分配が行うことが見込まれている場合における当該単独新設分社型分割又は単独新設現物出資
これらはいずれも、他の者(※)による支配関係がないことを前提としていることから、非上場会社で適用されることは稀であり、実務上、上場会社がbad事業を切り離す場合にのみ適用される手法であると思われる。
(※) 「他の法人」としていないことから、個人による支配関係がある場合についても含まれると推定。正確なことについては、改正後の条文を確認する必要がある。
このようなニーズがあることは否定しないが、約3,500社存在する上場会社のうち、スピンオフ税制を適用する会社は極めてわずかであろう。
そのため、多くの税務専門家にとっては、スピンオフ税制の存在を知っておくことは重要かもしれないが、実際に関与することはそれほど多くはないと思われる。
3 スクイーズアウト税制
(1) 対価要件の見直し
平成29年度税制改正大綱を見て、多くの税務専門家が注目したのは、スピンオフ税制ではなく、スクイーズアウト税制であったと言われている。
まず、吸収合併及び株式交換に係る適格要件のうち対価に関する要件について、合併法人又は株式交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式の3分の2以上を有する場合におけるその他の株主に対して交付する対価を除外して判定することになった(p70)。
これは極めて大きな改正であり、発行済株式の3分の2以上を支配した後に、現金交付型合併又は株式交換を行ったとしても、適格合併又は適格株式交換に該当するということを意味している。
しかし、平成29年度税制改正大綱の文言を形式的に読むと、合併法人又は株式交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式の3分の2以上を直接に有する場合に限定されており、間接保有は認められていない可能性があり得る。さらに、同一の者によって、発行済株式の3分の2以上を有する場合については適用されないようにも読める。この点については、2月に公表される改正法案を確認する必要があろう。
そして、税制改正大綱から読み取れないが、発行済株式の3分の2以上を支配した後に、無対価合併又は株式交換を行った場合の取扱いについても注目すべきであろう。この点については、法人税法施行令に規定する支配関係が成立しているかどうかの要件の一つとなっているため、本改正の影響を受けない可能性はあり得る。
なお、例えば、発行済株式の90%を支配している場合に、10%の少数株主に対して現金交付型合併又は株式交換を行った場合には、立法論としては、10%だけ譲渡損益を課税するという考え方もあり得る。平成29年度税制改正大綱を読む限り、そのような考え方は採用されなかったと予想されるが、この点については、念のため、改正法案を確認する必要がある。
さらに、現金交付型合併又は株式交換を行った場合における株主課税の問題、合併法人又は株式交換完全親法人の純資産の部の取扱いについても確認する必要がある。
現金交付型株式交換を行った場合には株式譲渡損益課税になると予想されるが、現金交付型合併を行った場合も同様の取扱いになるのか、みなし配当課税の対象になるのかは、今のところ明らかではない。そして、交付した現金について、合併法人又は株式交換完全親法人における資本金等の額の減額要因になると推定されるが、この点についても、政省令を確認する必要があると考えられる。
なお、現行法上、支配関係が成立しているかどうかは、合併又は株式交換の直前とその後の継続見込みで判断するため、発行済株式の3分の2を取得してから合併又は株式交換を行う場合には、支配関係での組織再編に該当することから、事業継続要件や従業者引継要件を満たせば、税制適格要件を満たすことができる。
この考え方が平成29年度税制改正後も踏襲された場合には、発行済株式の3分の2を取得してから現金交付型株式交換を行うという手法が採用される可能性があり得る(現金交付型合併については、繰越欠損金の引継制限、使用制限、特定資産譲渡等損失の損金不算入の問題があることから、それほど利用されないと思われる)。
(後編(2016/12/22)に続く)