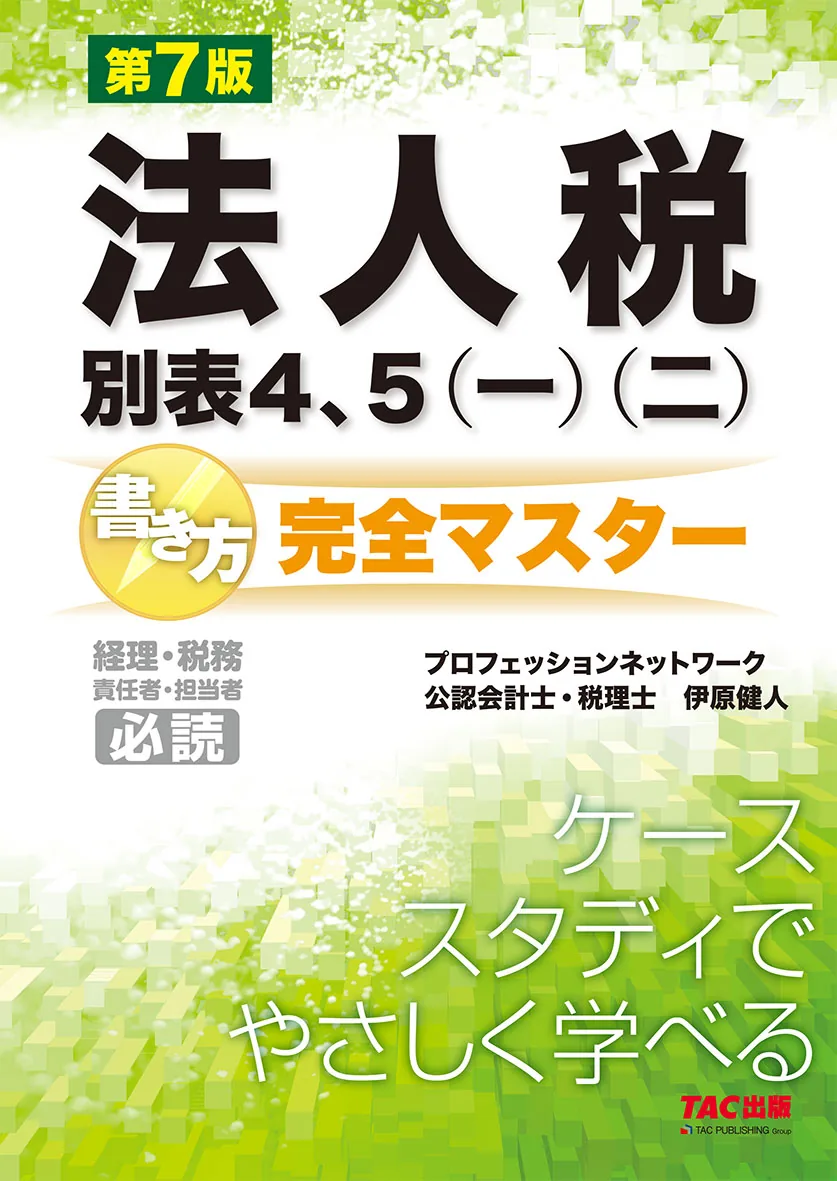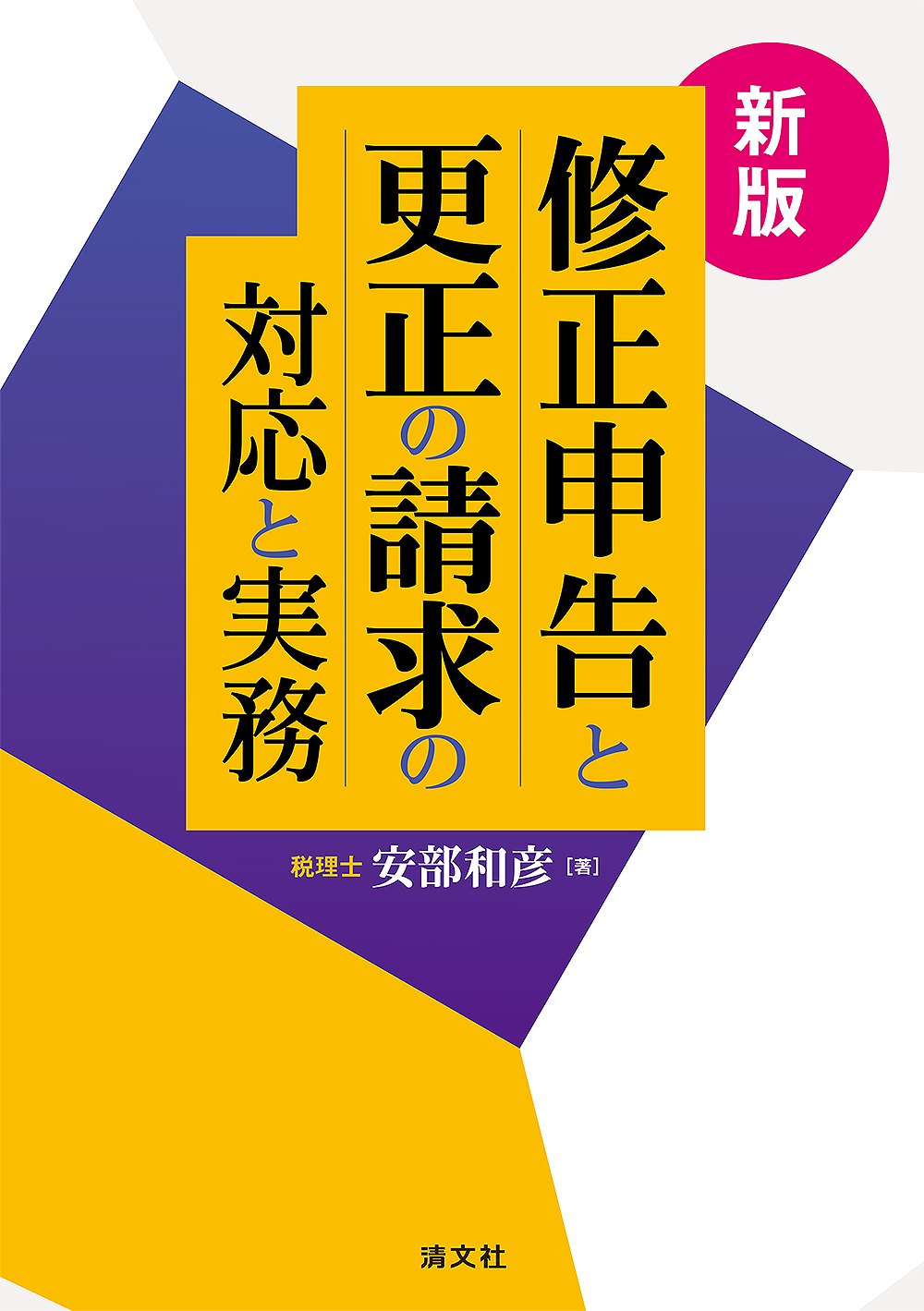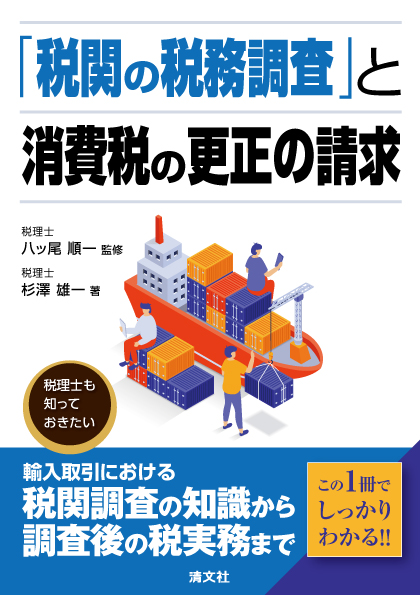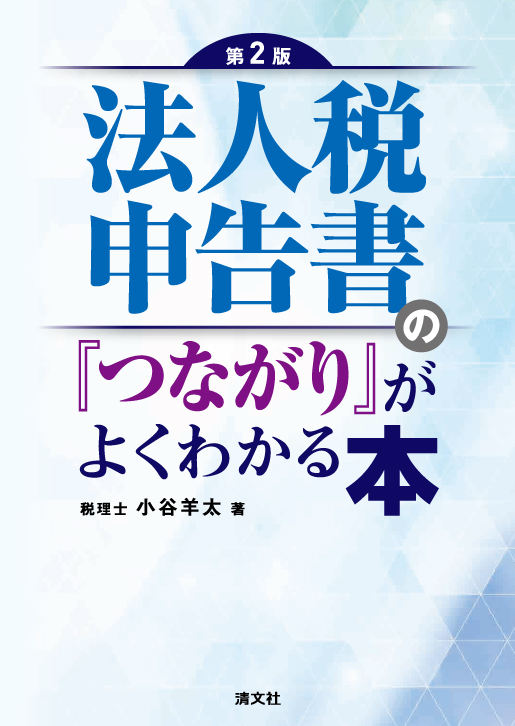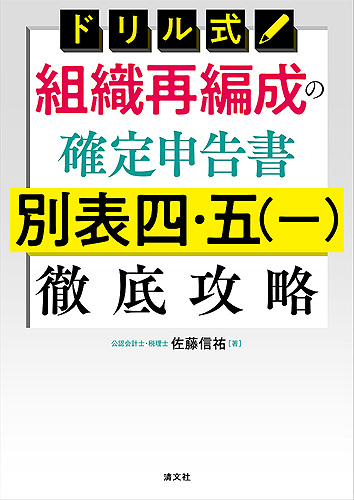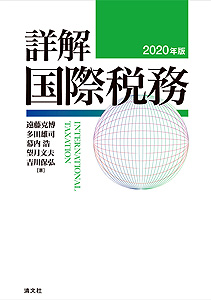法人税における当初申告要件等と
平成29年度税制改正
【第1回】
税理士 谷口 勝司
連載の目次はこちら
-はじめに-
法人税の所得金額や税額等の計算を行う際、例えば、受取配当等の益金不算入、外国税額控除、試験研究費の特別税額控除等、その制度の適用を受けるには、申告書等への所定書類の記載・添付等や証拠書類の保存など、一定の手続が必要とされるものがある。
これらの手続のうち、当初申告である確定申告書に計算明細書の記載・添付等が必要とされるものを、一般に「当初申告要件」と呼んでいる。
この当初申告要件等については、平成23年12月に抜本的な改正が行われ、また、平成29年度税制改正において更にその一部が改正されている。
当初申告要件等は、税務調査等で修正申告や更正が行われる場合や、更正の請求等に当たって、追加的・事後的に制度の適用を受けられるかどうか等を決することになるため、その取扱いを理解しておくことが実務上重要であると思われる。
そこで本稿では、当初申告要件等の取扱いと平成29年度税制改正について、その内容を説明することとしたい。
なお、本稿中意見にわたる部分は、私見であることをあらかじめお断りしておきたい。
1 当初申告要件等の概要-平成23年12月改正-
当初申告要件等については、平成23年12月に抜本的な改正が行われ、その基本的な枠組みや考え方等はこの平成23年12月改正に基づいている。
そこでまず、平成23年12月改正の内容等を紹介するとともに、平成29年度税制改正前の取扱いを説明したい。
(1) 法人税法
平成23年12月改正前の法人税法では、確定申告書等(確定申告書及び仮決算をした場合の中間申告書をいう。以下同じ)にその適用を受けるべき金額など一定の事項を記載した場合又は一定の書類を添付した場合に限り適用し、確定申告書等において制度の適用を受けていない場合には、修正申告や更正の請求によって新たに制度の適用を受けることができないという「当初申告要件」が設けられている制度があった。
これらの制度のうち次の①②のいずれにも該当しないものについては、平成23年12月改正において当初申告要件が廃止され、更正の請求範囲が拡大(請求期間も5年に延長)された。
① インセンティブ措置
② 利用するかしないかで、有利にも不利にもなる操作可能な措置
当初申告要件が廃止された代表的な制度としては、受取配当等の益金不算入、所得税額控除、外国税額控除等が挙げられる(注1)(注2)。
(注1) 平成23年12月改正では、次の(イ)~(ヲ)の12の制度について廃止され、また、その後の税制改正により、(ワ)~(ヨ)といった制度についても当初申告要件は設けられていない。
(イ) 受取配当等の益金不算入(法23⑦)
(ロ) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法23の2③)
(ハ) 国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入(法37⑨)
(ニ) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(法59④)
(ホ) 協同組合等の事業分量配当等の損金算入(法60の2)
(ヘ) 所得税額控除(法68③)
(ト) 外国税額控除(法69⑩⑪)
(チ) 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例(令73の2②)
(リ) 引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例(令113②⑥)
(ヌ) 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制限の5倍要件の判定の特例(令113の2⑭)
(ル) 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の対象外となる資産の特例(令123の8③五)
(ヲ) 特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例(令123の9②⑧)
(ワ) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金繰越しにおける更生手続や再生手続開始の決定等があった場合の特例(法57⑫)
(カ) 青色申告書を提出しなかった事業年度の災害損失金の繰越し(法58②⑤⑦)
(ヨ) 適格合併等による欠損金の引継ぎにおける譲渡等損失額の損金不算入の対象外となる資産の特例(令112⑥三ロ)
(注2) 前記①②のいずれかに該当する制度については、当初申告要件は存続されていることに留意する必要がある。代表的なものとして、国庫補助金等、保険差益、交換等の圧縮記帳、貸倒引当金・返品調整引当金などがある。
上記により当初申告要件が廃止された制度であっても、課税当局側での制度の適用要件確認のため、確定申告書等、修正申告書(注3)又は更正請求書に、所要の事項の記載をした書類又は所要の書類の添付が必要とされた。
(注3) 修正申告時に新たに制度の適用を受けることにより課税標準又は税額が減少する一方、他項目の所得加算等により最終的には課税標準又は税額が増加する場合があることから、ここに修正申告書が掲げられている。
しかし、当初申告である確定申告書で制度の適用を受けていない場合であっても、その後、修正申告書や更正請求書に記載・添付等をすることによって新たに制度の適用を受けることができるという点で、改正前までの記載・添付等とはその意味合いは異なるものであり、平成23年12月改正はそれまでの取扱いを大きく変更するものであった。
また、当初申告要件が設けられている制度の中には、その制度の適用を受ける金額(控除等の金額)について、確定申告書等に記載された金額を限度とするという「適用額の制限」が設けられている制度があった。
例えば、平成23年12月改正前の所得税額控除では、控除をされるべき金額は確定申告書に控除を受けるべき金額として記載された金額を限度とする、と規定されていたことから(平23.12改正前の法68③)、確定申告書に記載した控除金額がいわば絶対的な上限額として取り扱われていた。
このため、確定申告後に控除漏れの所得税額が判明したとしても、確定申告書等に記載された金額を超えて控除金額を増額させることは一切できなかったが、この点についても平成23年12月で改正(見直し)が行われた。
すなわち、所得税額控除、受取配当等の益金不算入といった制度については、確定申告書等だけでなく、修正申告書又は更正請求書に添付された書類に適用を受ける金額として記載された金額を限度とする、と改正され、修正申告書や更正請求書に記載・添付等をすることによって適用額(控除等の金額)を増額させることができるようになった(注4)。
(注4) 平成23年12月改正で「適用額の制限」の見直しが行われたのは、次の制度である。
(イ) 受取配当等の益金不算入(法23⑦)
(ロ) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法23の2③)
(ハ) 国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入(法37⑨)
(ニ) 所得税額控除(法68③)
(ホ) 外国税額控除(法69⑩⑪)
なお、適用額(控除等の金額)の記載を一切不要としなかったのは、課税当局側に金額の立証責任が転換しないようにするためと趣旨説明がされている(財務省HP「平成24年度税制改正の解説」163頁参照)。
以上のとおり、平成23年12月の法人税法の改正は、それまで厳格に取り扱われていた当初申告要件や適用額の制限について、多くの制度についてこれを緩和するという大きな改正であった。
なお、その後の税制改正においても、平成23年12月改正の枠組みや考え方等は維持されている。
(2) 租税特別措置法
平成23年12月では、租税特別措置法(以下「措置法」という)についても改正が行われた。
平成23年12月改正前の試験研究費の特別税額控除制度や中小企業者等が機械等を取得した場合の特別税額控除制度等については、確定申告書等にその控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、その控除を受ける金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り適用することとされていた。
このため、確定申告書等において制度の適用を受けていない場合には、修正申告や更正の請求によって新たに制度の適用を受けることはできないこととされていた。これを「措置法における当初申告要件」という。
また、措置法における当初申告要件が設けられている制度の中には、その適用額(控除等の金額)について、確定申告書等に記載された事項を基礎として計算する場合に控除を受けることができる正当額を限度とするものがあった。例えば試験研究費の特別税額控除により控除される金額は、試験研究費の額や法人税額など確定申告書等に記載された全ての事項を基礎として計算された税額控除額(正当額)が適用限度額とされていた。
このため、確定申告書等に記載されたこれらの金額(例えば試験研究費の額や法人税額)が変動する場合であっても、修正申告や更正の請求によって、確定申告書等に記載された金額を是正して適用額(控除等の金額)を増加させることはできなかった。これを「措置法における適用額の制限」という。
平成23年12月改正では、措置法における適用額の制限の見直しが行われ、控除を受けることができる正当額を計算するに当たって基礎とする事項が、確定申告書等に記載された全ての事項から、確定申告書等に添付された書類に記載された特定の事項(試験研究費の額、資産の取得価額等)と改正された。換言すれば、確定申告書等に記載された試験研究費の額(又は資産の取得価額等)だけを基礎として(固定して)適用額(控除等の金額)を計算することになった。
このため、確定申告書等に記載された特定の事項以外の事項として記載された金額(例えば法人税額)に変動がある場合には、修正申告や更正の請求によってその金額を是正して適用額(控除等の金額)を増額できることとなった。
他方、措置法における当初申告要件は、確定申告書等に添付される書類に特定の事項(試験研究費の額、資産の取得価額等)を記載する必要があることされ、法人税法における当初申告要件とは異なり、引き続き存続することとされた。
当初申告要件の存続理由としては、措置法における特別税額控除制度等は、元々、研究開発促進、投資促進といった政策目的によるインセンティブ措置であることが考慮されたものと考えられる。
* * *
以上のとおり、平成23年12月では、法人税法、措置法のいずれも改正されたが、両者では異なる改正内容であったことに留意しておきたい。
〔凡例〕
法・・・法人税法
令・・・法人税法施行令
規・・・法人税法施行規則
措置法・・・租税特別措置法
(例)令123の8③五・・・法人税法施行令123条の8第3項5号
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。