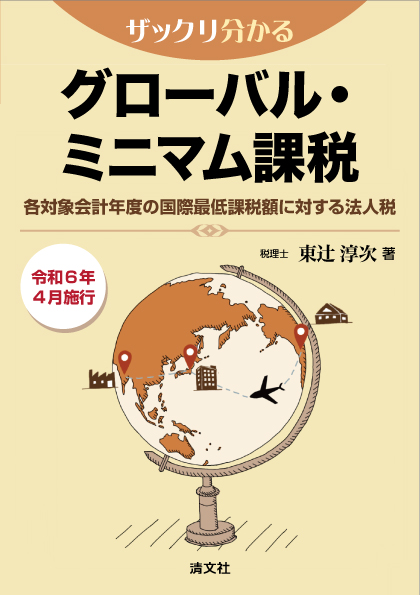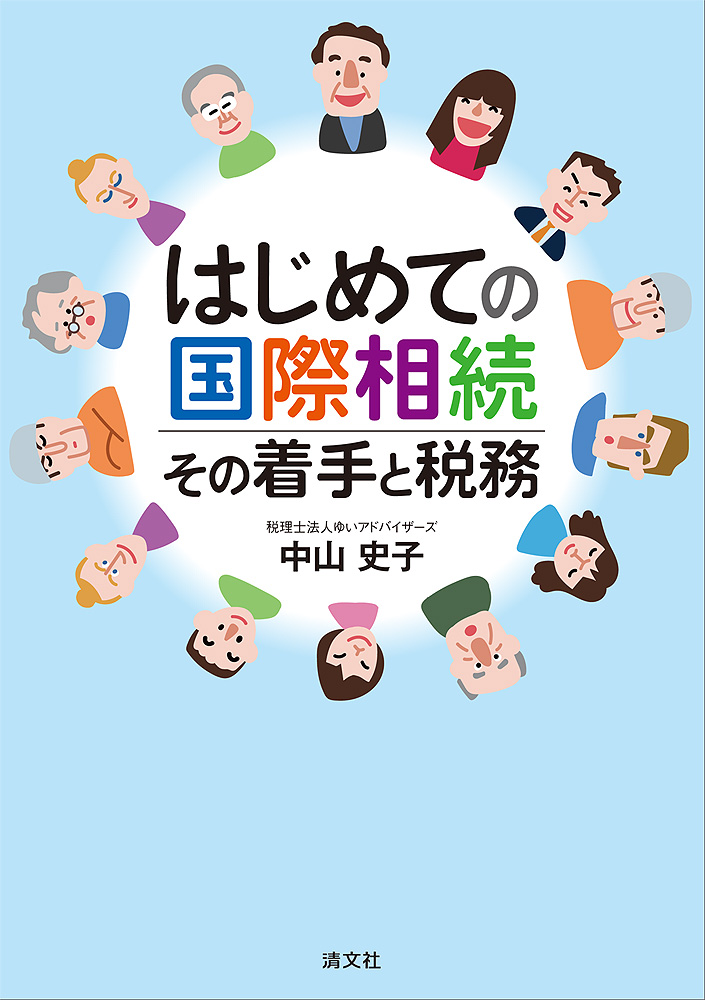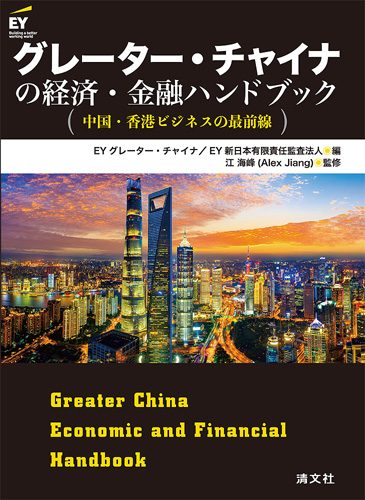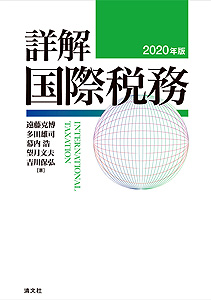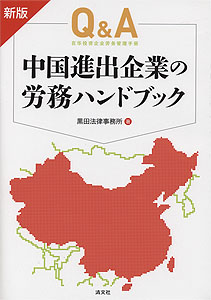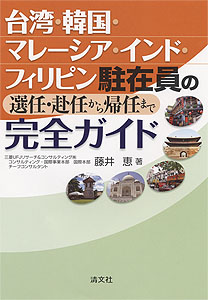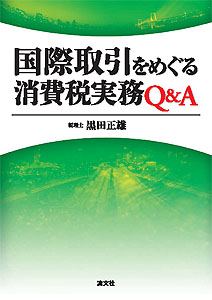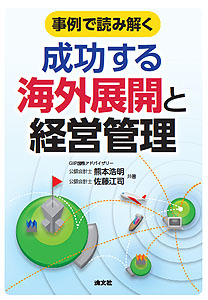〔ケーススタディ〕
国際税務Q&A
【第1回】
「地域統括会社の設置に係る課税関係」
弁護士 木村 浩之
[Q]
日本のメーカーである当社は、世界各国で自社製品を販売しています。各国には販売子会社がありますが、今般、経営の最適化のためにグループ再編を実施し、アジア、ヨーロッパなどの地域ごとに統括会社を設置して、子会社管理機能と物流機能を集約することを検討しています。
どの国に地域統括会社を設置するかを検討するに当たって、税務上の観点から留意すべき点について教えてください。
[A]
地域統括会社の設置に当たっては、関係する各国における課税関係について総合的に検討することが重要です。
具体的には、次のような観点からの検討が重要です。
① 地域統括会社の所在地国での課税関係
② グループ子会社の所在地国での課税関係
③ 親会社の所在地国(日本)での課税関係
・・・[解説]・・・
1 地域統括会社の所在地国での課税関係
地域統括会社は、子会社管理機能と物流機能を有することになるため、それに応じた所得を有することになる。そこで、当該所得に対して適用される税制、つまり法人税制について検討することが重要となる。
具体的には、所在地国の法人税率や優遇税制の有無などのほか、販売子会社からの配当や(将来的における)子会社株式の譲渡益がどのように課税の対象になるか(あるいは課税の対象から除かれるか)を検討する。
例えば、国によっては、一定の持株割合要件を満たした子会社からの配当や子会社株式の譲渡益について課税が免除されることがある(これを「資本参加免税」という)。こういった制度の有無や適用要件について検討する。
また、地域統括会社の性質上、国外に関連会社が複数存在し、関連会社間での取引も多くなるため、CFC税制(国外の関連会社の所得を合算する制度)や移転価格税制などの有無及び適用要件について検討することも必要になる。
さらに、地域統括会社から、本国における親会社その他の関連会社に対して、配当その他の支払がなされる際に、どのように源泉徴収されるかも重要な考慮要素となる。この場合、国内法と租税条約の双方を検討することが必要であり、国内法における源泉徴収の有無について検討した上で、関連する租税条約において課税の減免が受けられるかを検討することになる。
2 グループ子会社の所在地国での課税関係
一般に、グループ子会社は、その性質上、地域統括会社との間でグループ間取引をすることが多い。そこで、グループ子会社から地域統括会社に対して、配当その他の支払がなされる際、その支払に対して、どのような課税(源泉徴収)がなされるかを検討する。ここでも、子会社の所在地国の国内法のほか、関係する租税条約による課税の減免について検討することになる。
この点、配当、利子、使用料などの支払については、その支払をする子会社の所在地国において源泉徴収がなされることが多いといえる。これに対して、地域統括会社の所在地国と子会社の所在地国との間で締結されている租税条約によっては、課税の減免を受けることができる。
また、将来において、地域統括会社がグループ子会社の株式を譲渡することもあり得るが、子会社の所在地国によっては、譲渡されたのが自国の法人であることを理由に、その譲渡益に課税する場合がある。これに対しても、租税条約によっては、そのような課税について免除を受けることができる。
このように、租税条約によって、子会社の所在地国における課税の減免を受けることができるため、地域統括会社の拠点を選定するに当たって、グループ子会社の所在地国との間でどのような租税条約が締結されているかを検討することが重要である。
3 親会社の所在地国(日本)での課税関係
地域統括会社の所在地国での税負担率が低い場合、日本の親会社において外国子会社合算税制が適用される可能性がある。これが適用されると、地域統括会社の所得が親会社の所得に合算されることになるため、その適用の有無を検討することが特に重要となる。
例えば、地域統括会社の所得に対して、その所在地国で課せられる税の実効税率が20%未満の場合、一定の適用除外要件を満たさない限り、その全所得が親会社の所得に合算されることになる。また、適用除外要件を満たす場合であっても、一定の受動性所得については、なお合算の対象となり得る。この税制の適用要件は毎年のように税制改正の対象となっており、平成29年度税制改正でも大幅な見直しがなされた。常に最新の適用要件を確認した上で検討することが必要である。
なお、地域統括会社から日本の親会社に対して支払われる配当については、その多くが日本では課税されない所得となる。すなわち、日本の国内法では、25%以上の株式(又は議決権)を6ヶ月以上保有する外国子会社からの配当については、子会社の所在地国で配当が費用として控除されるものでない限り、配当所得の95%を課税所得から除外することが認められている(外国子会社配当益金不算入制度)。
まとめ
地域統括会社の設置に当たっては、その所在地国での課税関係(課税所得の範囲や税率)のみならず、グループ子会社の所在地国での課税関係(特に配当等の支払に対する源泉徴収)について租税条約を含めた検討をするとともに、日本での外国子会社合算税制の(最新の)適用要件について検討することが重要である。
(了)
「〔ケーススタディ〕国際税務Q&A」は、毎月第3週に掲載されます。