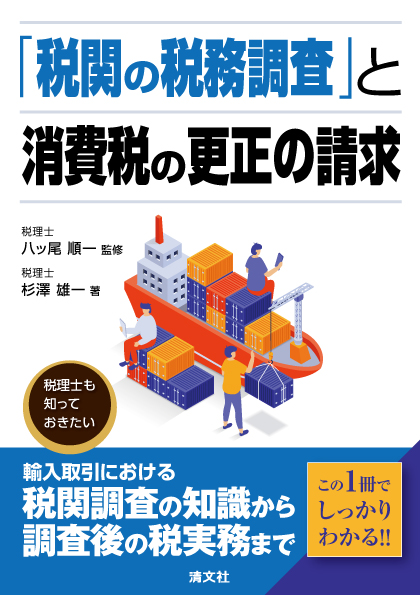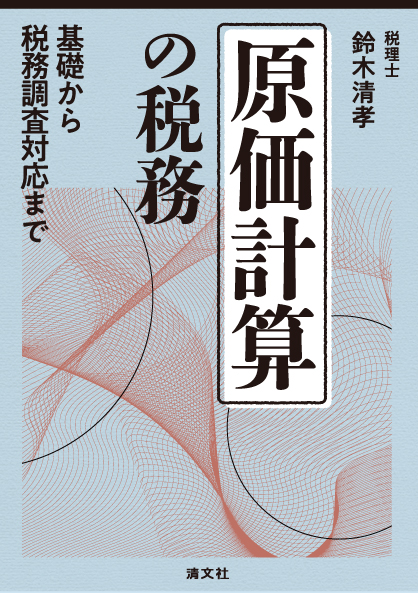〔弁護士目線でみた〕
実務に活かす国税通則法
【第1回】
「国税通則法を学ぶ意味」
弁護士 下尾 裕
1 はじめに
本誌読者の皆様は、「国税通則法」という法律名を耳にすると、どのようなイメージを持たれるであろうか。
税理士試験の受験にあたっては、各試験科目に共通して国税通則法が出題範囲に含まれてはいるものの、実際のところ、実務で活躍されている税理士である読者の中にも、国税通則法を苦手とされている方が一定程度いらっしゃるのではないだろうか。
また、税務調査に対応されている企業の財務経理担当者である読者におかれては、そもそも国税通則法を本格的に勉強する機会がなかった方も多くいらっしゃるものと思われる。
本連載は、様々な理由で国税通則法を苦手とされている又はこの機会に理解を深めたいという実務家を対象に、税務に携わる弁護士目線で重要と思われるポイントを解説するものである。
2 国税通則法を学ぶ意味はどこにあるか
(1) 国税通則法が苦手になる背景
国税通則法を苦手とする実務家が一定程度おられる理由は、まずもって国税通則法が一見して無味乾燥であり、興味が湧きにくいということもあると思われるが、私見では、以下の事情も大きく影響しているものと推測される。
① 国税通則法の多くは“国税当局側”が遵守すべき手続を定めるものである
国税通則法の条文をななめ読みすると、もちろん「更正の請求」といった納税者側の手続も定められているものの、その多くは国税当局側の手続等を定めるものである。
そのため、税務調査の手続等は、事前に国税当局側が整理した実務運用に従って進められており、その是非について税理士側が異論を述べる機会が少なく、また、ハードルも高くなっている。
② 国税当局による国税通則法の違反は課税処分の違法性に直結しない
もう1つ見逃せない事情として、仮に国税当局が国税通則法に違反した税務調査を行って調査資料を収集し、当該資料を前提に課税処分を行ったとしても、こうした調査手続の違法が課税処分の取消し等に直結しないという点がある。
1つの比較として、刑事手続においては、“違法収集証拠排除法則”という考え方により、手続の違法がある捜査により収集された証拠は証拠として使えず、その結果、被告人が無罪になることがありうる。
例えば、尿に覚せい剤が含まれていたという鑑定結果の裏付け証拠として、覚せい剤使用の罪で起訴された被告人につき、尿の差押手続に違法があった場合に、尿が証拠として採用されず、被告人が無罪となるというケースなどである。
これに対し、課税処分については、(査察の事案を除けば)証拠等は納税者から任意に提出されるものであることもあり、仮に税務調査手続に違法があったとしても、納税者が税務調査官に恫喝され、その結果として任意性が認められないなどの特段の事情がある場合を除いては、収集された調査資料が使用できないということにはなりにくい。
こうした背景事情から、実務家においても、時間をかけて国税通則法に精通してまで、その違反を指摘するイニシアチブが働きにくく、個別税法に関する知識獲得を優先してしまうということがあるかもしれない。
(2) 国税通則法を学ぶ意味
では、上で述べたような事情を踏まえても、なお国税通則法を学ぶ意味はどこにあるのであろうか。
あくまで私見であるが、税務に携わる読者の皆様が国税通則法に精通することには、以下のようなメリットがあるものと考えられる。
① 税務調査担当者に対するけん制を効かせることができる
税務調査担当者からすれば、たとえ国税通則法違反が課税処分の適法性に影響しないとはいっても、手続違反を犯すことは国税当局内部ではご法度であり、避けなければならないものであることは明白である。
税務調査官としても、安易に手続違反を犯すことはないと思われるが、それでも税理士が国税通則法に精通し、その点を税務調査官に示すことで、無理な調査を抑制し、かつ、心理的にも対等にやりとりを行うことが可能になる。
② 重加算税や過少申告加算税等、国税通則法の規定が課税根拠となるもの等について、税務調査担当者に対する実効的な反論が可能になる
重加算税や過少申告加算税といった付帯税の課税根拠は、国税通則法にあるところ、重加算税の課税要件である「納税者」、「隠蔽」及び「仮装」の解釈(同法第68条第1項)や過少申告加算税の除外要件である修正申告が「更正があるべきことを予知してされたものでない場合」(同法第65条第5項)の解釈等を正しく理解していなければ、税務調査等において有効な反論ができない。
また、国税通則法には「再調査制限規定」(同法第74条の11第1項)が存在するが、再調査制限規定との抵触を国税当局に指摘するにあたっては、再調査制限がどの範囲で生じるのか(すなわち、調査の範囲はどのように把握されるか)、再調査を許容する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」とはどのような場合なのかを理解していなければ、やはり有効な反論ができない。
逆に税理士において、こうした内容を正しく理解することにより、税務調査官に対し、付帯税の課税に関する対等かつ実効的な反論を行うことが可能になり、また、取るべき対応を看過することによる税務過誤を防止することができる。
3 今後の連載
以上を前提に、次回からは、いよいよ本論として、実務上の重要性が高いと思われる調査、修正申告、更正処分、更正の請求、過少申告加算税、重加算税、更正期限、不服申立て及び犯則事件について、関連する議論・裁判例に言及しつつ、順次取り上げていくこととする。
(了)
「実務に活かす国税通則法」は、毎月最終週に掲載されます。