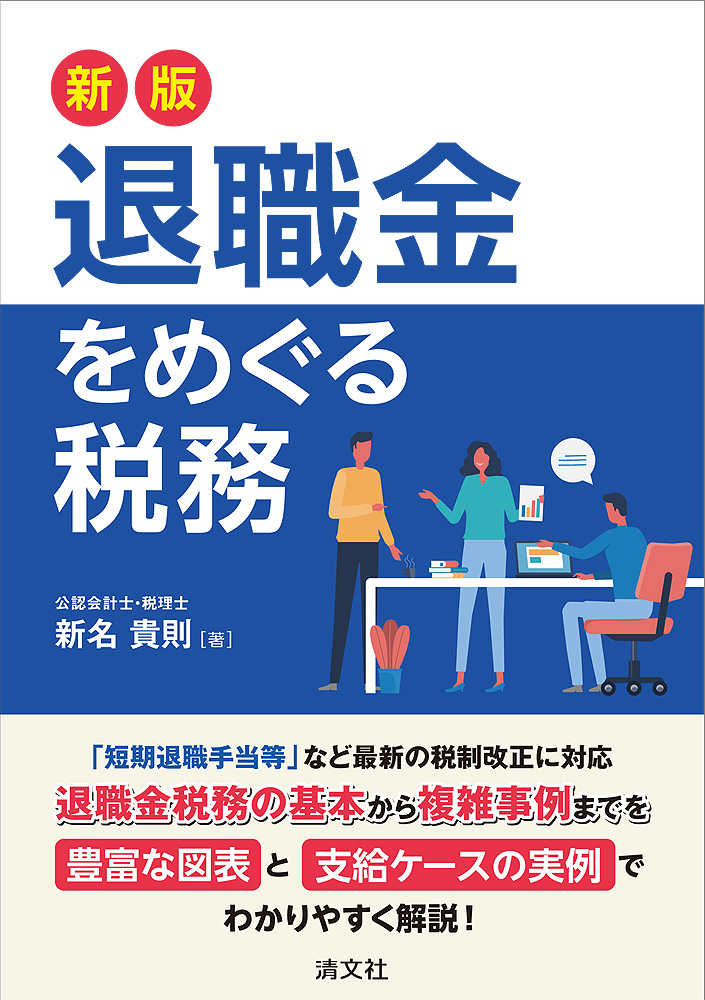退職金制度の作り方
【第1回】
「退職金制度の現状」
なりさわ社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 成澤 紀美
中小企業の8割近くで制度あり
退職金制度はどこの企業にもあるものと思われるかもしれないが、中小企業では必ずしも制度があるとは限らない。
従業員数10人~300人未満の東京都内の中小企業のみを対象とした「中小企業の賃金・退職金事情(平成24年版)」(東京都産業労働局)によると、「退職金制度がある」と回答した企業が77.7%、「退職金制度がない」と回答した企業が21.1%となっている。
調査結果より、中小企業の80%近くで制度が導入されているが、労働基準法では退職金制度を必ず導入するよう求めているものではなく、退職金制度がなくても、労働法令上は特段の問題はない。労働基準法が求めているのは、退職金制度を設けた時点で賃金債権となり得るため、就業規則に規定をし支給ルールを明確にすることである。
一度制度として設けた退職金は、経営者の義務となり、労働者の権利となる。
特に注意が必要なのは、就業規則を労働者側に不利な内容に変更をする場合は、労働者側の同意を要する点である。退職金制度の見直しについても同様で、労働者側に不利益な内容となる場合は、労働者側の同意が必要であり、経営者側が一方的に変更することはできない。
退職金制度は、企業が独自のルールを設け、任意に定めることができるものではあるが、一度定めた内容を変更する際には、労働者の権利も十分に考慮しながら運用をしていかなければならないものとなるため、様々な不都合が生じてしまうケースが多々あるといえる。
支払方法は7割以上が一時金方式
前述の調査結果では、「退職金制度がある」と回答した企業の72.2%が「退職一時金制度のみを採用」、23.7%が「退職一時金と退職年金を併用している」となっている。
これは退職金の支払方法であり、一時金制度は退職時点に一括して支払うものであり、退職年金は、退職後の一定期間にわたり定額で支払う方法をいう。
定年前の中途退職時に退職金を支給する際は、勤続年数に応じて「一時金制度」又は「一時金制度+退職年金」を併用し、定年退職時は「退職年金」として一定期間支払う場合が多い。
退職金の計算方法は、算定基礎額×支給係数が多い
調査結果によると、退職一時金の算出方法としては「退職金算定基礎額×支給率」と回答した企業が49.1%で最も多く、次いで「勤務年数に応じた一定額」と回答した企業が21.1%となっている。
「退職金算定基礎額×支給率」の算出方法は、一般的には勤続年数×退職時点での支給給与額に、退職理由(自己都合・会社都合)に応じた支給係数を乗じて計算される。
「勤務年数に応じた一定額」での算出方法は、勤続年数に応じた確定支給額をあらかじめ定めておく方法となる。
* * *
次回は、退職金制度の種類についてお伝えしたい。
(了)