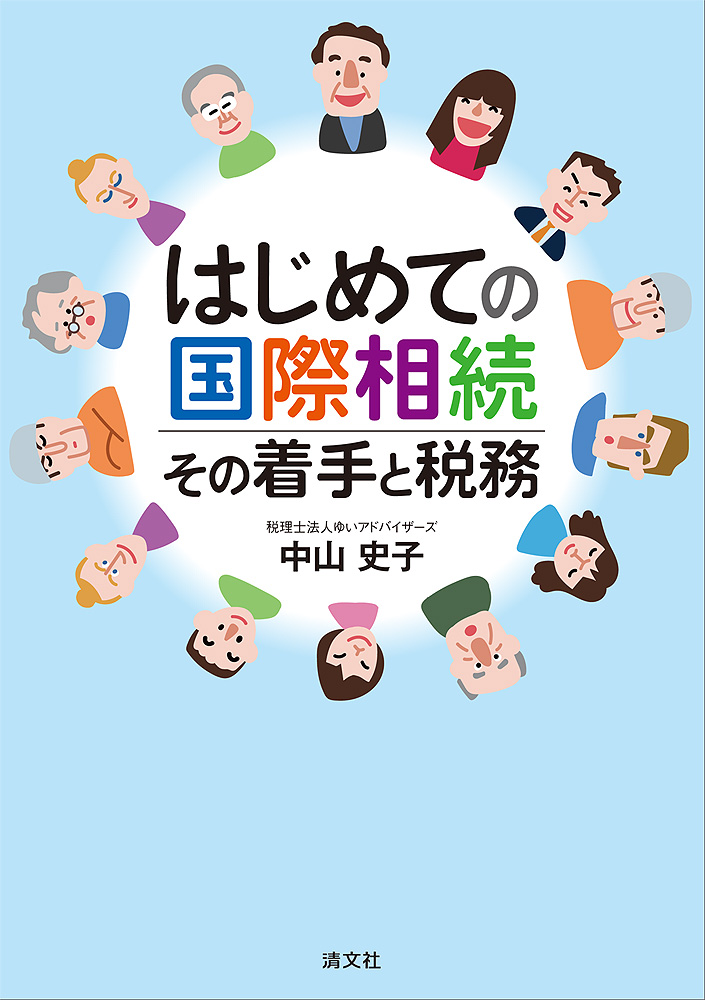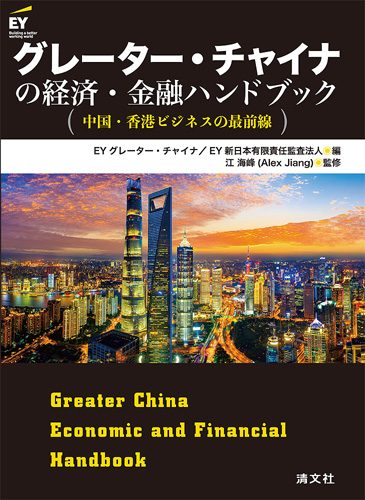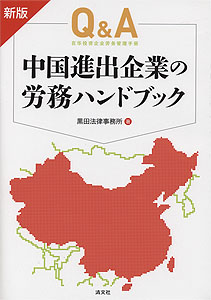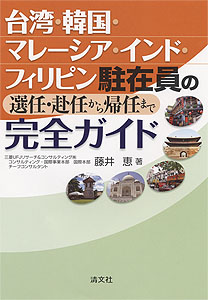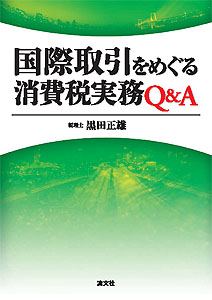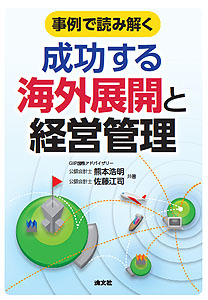法人税に係る帰属主義及び
AOAの導入と実務への影響
【第1回】
「改正の趣旨と背景」
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
《本連載の構成》
1 はじめに
2 改正の趣旨と背景
2-1 総合主義から帰属主義へ
2-2 AOAの導入
3 改正の内容
3-1 外国法人の法人税
3-2 内国法人の法人税
3-3 外国法人の所得税
4 企業活動への影響
5 適用開始日(平成28年4月1日以降開始事業年度)までに準備すべき事項
1 はじめに
平成26年度税制改正において、外国法人及び非居住者(以下「外国法人等」という)に対する課税原則が、総合主義から帰属主義に大きく変わるとともに、帰属主義の適用方法として、OECDモデル条約が採用しているAOAが導入された。
AOAとは、帰属所得の計算に関するOECD公認アプローチ(Authorized OECD Approach) の略称である。その内容は、まず、本店と支店を別々の分離した法人と擬制して、機能分析を行って内部取引を認識する。次に、機能分析の結果に基づいて、本店及び各支店への資産と資本の帰属を確定する。その上で、本支店間の取引価格を移転価格税制と同様の方法で算定し、それに基づいて本店及び各支店の帰属所得を計算する、というものである。
今回の改正の影響を最も大きく受ける者は、わが国に恒久的施設(以下「PE」という)を有する外国法人であるが、国外にPEを有する内国法人や個人の居住者も、外国税額控除の計算に関して影響を受ける。また、所得計算の方法の改正だけでなく、本支店間取引について移転価格税制と同様の文書化義務が課された点が実務的に大きな影響を伴う。
今回の改正の結果、国内法の課税原則をOECDで認められた国際課税原則に合わせたことにより二重課税や二重非課税の発生をある程度防止できることが期待されるというメリットがある。しかし、企業にとって次のような点から、コンプライアンス・コストがかかるという問題がある。
◆外国法人の日本PEにとっては、課税所得計算方式が、資本配賦の計算をはじめとして多くの点で変更されていること
◆内国法人で外国にPEを有する法人は、外国税額控除を適用する場合、本支店間内部取引を認識したうえで、PEの帰属所得の算定と文書化について移転価格税制と同様の対応が必要になること。また、海外支店の所在地国がAOAを導入している国か否かで計算方法が異なること
こうしたことから、わが国に支店を有する外国法人だけでなく、外国に支店を有する内国法人にとっても税務コンプライアンス・コストが相当の規模で増加することが予想される。
今回の改正は、平成28年4月1日以降開始事業年度に適用される。
大幅な改正であるため、準備期間を考慮して適用開始まで2年の猶予を見込んでいる。
内容が大幅に変わっただけでなく、改正条文の数からみても膨大な量の改正であるため、影響を受ける納税者にとって相当な準備期間を要する。対象となる企業は、早期に影響を評価し適時に対応策の検討を開始する必要がある。
本連載では、改正の趣旨・概要をできるだけ分かりやすく解説するとともに、実務への影響について考察する。
なお、今回の改正は個人の居住者・非居住者にも影響があるが、本稿では法人についての説明となっていることに留意されたい。
また、本稿の意見にわたる部分は筆者の私見であり、筆者の所属する団体の見解ではないことをお断りしておく。
2 改正の趣旨と背景
2-1 総合主義から帰属主義へ
外国法人や非居住者の課税の範囲については原則として国内源泉所得のみに課税するのが国際的に確立した課税ルールであり、わが国の税法もそれに従っている。国内源泉所得のうち、PEに帰属する所得のみに課税するのが「帰属主義」であり、PEがあればPEに帰属しない所得も含めてすべての国内源泉所得に課税するのが「総合主義」である。
例えば、米国本店が日本の顧客との直接取引によって得た利益は、日本支店に帰属しているとは言えないので、帰属主義の下ではわが国で課税されない。しかし、総合主義の下では、日本に支店があれば支店が関与していない所得でも日本で課税されることになる。
わが国の国内法における外国法人課税の規定は、昭和38年に総合主義を採用して以来、ずっとこれを維持してきた。しかし、世界の趨勢は圧倒的に帰属主義であり、わが国の締結している租税条約は最後の総合主義の条約であったパキスタンとの条約が帰属主義に変更されたことにより、すべてが帰属主義となった。
わが国は国内法と租税条約が乖離する状態が長い間続いてきたが、今回の改正で帰属主義に統一されることになった。
2-2 AOAの導入
帰属主義は国際課税ルールとして確立した原則であり、OECDモデル条約7条がそれに当たる。帰属主義とは、外国法人等の事業所得の課税範囲をPEに帰属する所得に制限する原則である。
帰属主義は一見シンプルだが、2010年にOECDがAOA(OECD公認アプローチ)を導入するまでは、国によって「帰属する」という文言の解釈の違いが存在した。ひとつは支店と本店を全く別個の法人と擬制して本支店間の取引も取引として認識したうえで所得計算をする方法である。これをOECDの議論においてはSeparate entity approachと称していた。欧州諸国の多くはもともと支店を独立した会計単位として会計処理を行う慣例があったという歴史的背景もあって、この解釈を採用すべきと主張した。
これに対立する解釈が、Single entity approachであった。これは、支店の所得は、法人全体の活動による所得のうち、支店が関与した活動による部分として計算されるべきという解釈である。主に米国とわが国が主張していた。
両者の違いが顕著に現れるのは、法人全体が赤字のときに支店だけが黒字になることがあり得るかという命題に対する答えである。
Separate entity approachでは法人全体が赤字でも支店は黒字ということはあり得る。一方、Single entity approach ではひとつの取引から得られる法人の所得を本店と支店で分けるという発想なので、法人全体が赤字のときに支店だけが黒字ということはあり得ない。
Separate entity approachの結論は、移転価格算定方法のTNMMの帰結と同じである。TNMMではグループ取引による合算利益が赤字でも、子会社が単純な機能しか果たしていない場合には黒字であってもおかしくないという結果になる。Separate entity approachは移転価格課税と親和性の高い課税方式である。これに対してSingle entity approachはオール・オア・ナッシング課税と親和性が高い。
例えば、外国法人による商品の輸入販売の場合、棚卸資産の販売地がわが国であれば売買益の総額が我が国の国内源泉所得として課税された。本支店間で利益を分け合うという考え方は、わが国の支店課税方式においては無かった。AOAが導入されると、このような場合には本支店間で所得を配分することになる。したがって、根本的に国際取引の課税に関する考え方が違ってくることになる。
そうした意味において、今回の改正は非常に大きな改正といえる。
AOAが導入された背景には、世界経済のグローバル化がある。
ある企業グループ内部では、関連者間取引と本支間あるいは支店・支店間取引が交錯して取引が行われることも少なくない。このような状況において、グループ内で所得配分を行う場合、関連取引には移転価格課税原則が、本支店間取引には支店課税独自の原則が適用されると、二重課税や二重非課税が生じやすくなる。この不都合を回避することがOECD租税委員会に求められていたのである。
なお、BEPSとの関係であるが、AOAの議論は過去20年以上にわたり行われてきたものであるのに対して、BEPSの議論は最近取沙汰されるようになったものである。AOAはどちらかといえば二重課税防止に力点がある。これに対してBEPSは租税回避防止が目的である。
「国際課税ルールの見直し」という点では共通点もあるが、目的が異なるので、相互に関係する部分は少ないといえるだろう。
2-3 改正の概要
2-3-1 外国法人の日本支店の課税所得計算の見直し(概要)
わが国に所在するPEを通じて事業を行う外国法人に対して、本店とPEが分離・独立の企業であると擬制した場合にPEに帰属する所得を算定し、これに課税することとした。
関連する主な改正点は以下のとおりであり、多岐にわたる。
(1) 国内源泉所得の分類・定義の見直し・・・「恒久的施設帰属所得」という新たな国内源泉所得の類型を設けた。(見直し)
(2) PEの課税標準その他の課税方法の見直し・・・上記(1)に伴いPEの有無に応じた課税方法を大幅に見直した。「恒久的施設帰属所得」とそれ以外の国内源泉所得は互いに損益通算しない。(見直し)
(3) 内部取引による損益の認識・・・本支店内部取引を原則認識する。ただし、内部保証と内部再保険は認識しない。旧条約適用の場合は使用料、利子、無形資産の償却費は認識しない(法基通20-5-7)。(新設)
(4) 内部取引の価格に移転価格税制と同様の独立企業原則を適用(新設)
(5) 単純購入非課税原則の廃止・・仕入活動しか行わないPEについても所得発生を認識することとした。(廃止)
(6) 内部取引に関する文書化(新設)
(7) 内部寄附金の損金不算入(新設)
(8) 外国保険会社等のPEに帰せられるべき投資資産に係る収益の益金算入(新設)
(9) PEに帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入(新設)
(10) PE帰属資本を超える負債利子に係る支払利子の損金不算入(新設)
(11) 外国銀行等のPEに帰せられるべき資本に対応する負債性資本に係る利子の損金算入(新設)
(12) PEの外国税額控除制度(新設)
(13) 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認(法法147の2)(新設)
なお、法令解釈通達が平成26年7月9日付けで発遣されている(「課法2-9他2課共同」)。
2-3-2 内国法人に影響する改正点(概要)
内国法人については、支店形態で海外進出している場合に、外国税額控除の控除限度額の計算が変わるとともに、文書化を行う義務が新たに課された。外国税額控除を適用しない場合には影響がない。
主な改正点は以下のとおり。
(1) 国外源泉所得の定義(見直し)
改正前は国内源泉所得以外の所得との定義であったが、改正後は、「国外事業所等帰属所得」、国外資産の運用保有所得、国外資産の譲渡所得等積極的に定義することにより明確化した。
(2) 国外事業所等帰属所得(見直し、新設)
国外事業所等帰属所得(以下「国外PE帰属所得」という)の計算は、外国法人のPE帰属所得の計算に準じて行う。つまり、国外PEが内国法人と独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外PEが果たす機能、使用する資産、内部取引その他の状況を勘案して認識する。
ただし、以下の点については外国法人のPEの計算とは異なる。
① 国外PEへの資本配賦及び帰属所得の加減算(新設)
(イ) 国外PEで計上された支払利子総額のうち、国外PEの自己資本相当額がPE帰属資本配賦計算により算定された額に満たない部分に対応する金額は、国外PE帰属所得に加算する。これにより外国税額控除限度額が増加する。
(ロ) 銀行又は証券業を営む内国法人については、規制上の自己資本のうち負債に相当するものがある場合には、その負債に係る利子のうち国外PE帰属資本に対応する部分の金額は、国外PE帰属所得から減算する。これにより、外税控除の控除限度額が縮小する。
② 国外PEの閉鎖時の時価評価(新設)
PE閉鎖時の時価評価の計上及び繰り延べた損益の計上は行わない。
③ 国外PE帰属所得に係る繰越欠損金(新設)
外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる当期の全世界所得及び当期の国外所得金額は、現行制度と同様、繰越欠損金控除前の金額とする。
④ 保険会社である国外PEへの投資資産及び投資収益の帰属(新設)
保険会社の国外PEが計上した投資収益の額が、国外PEの責任準備金等に応じて国外PEに帰属されるべき投資収益の額を超える場合には、超える部分に応じた投資収益を国外PEの帰属所得から減算する。
(3) 国外PEの帰属資本の額(新設)
国外PEへの帰属資本の計算方法は、資本配賦法又は同業者比準法のいずれかを選択できる。いったん選択した方法は、特段の事情がない限り継続適用が必要になる。
帰属資本の配賦計算は外国税額控除の控除限度額の計算のためにのみ必要なので、銀行及び証券会社を除く内国法人は、外国税額控除を適用しない場合には行わなくてよい。
外国税額控除を適用する場合には、銀行・証券以外でも資本配賦計算が必要になる。
銀行等が国外PE帰属資本の算定上リスクウェイト資産を計算する場合、信用リスクが全リスクの80%を超えており、かつ貸出債権に係る信用リスクがその50%を超えるときには、貸出債権の信用リスクのみに基づいて計算ができる(法規28の10)。
(4) 国外PEの範囲(新設)
国外PEの範囲は、租税条約相手国所在のものは条約の規定により、それ以外はわが国の国内法による。積極的な定義はなく、「国外にある恒久的施設に相当するものその他法令で定めるものをいう。」(法法69④一)とある。
(5) 外国税額控除の対象とならない外国法人税(新設)
国外PEから本店等に対する内部利子等の支払いに対して課された源泉税は、わが国の外国税額控除の対象とならない(法令142の2⑦四)。その外国法人税の課税標準である支払金額が、わが国の法人税の課税標準として認識されるからである。
(6) 国外PE帰属所得に関する文書化(新設)
外国税額控除の適用を受けるためには、国外PEの外部取引に関する書類のほか、本店等との内部取引について文書化し、調査の際に要求があった場合には遅滞なく提示、提出しなければならない。内部取引の価格算定については、移転価格税制と同様の算定方法が適用され、文書化も必要になる(法法69⑲、法規30の2)。
(注) 行為計算の否認規定
内国法人の国外PEについては、行為計算の否認に関しては、外国法人のPEのような特段の規定は設けられなかった。
〔凡例〕
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
法規・・・法人税法施行規則
法基通・・・法人税基本通達
(例)法法138①一・・・法人税法138条1項1号
(了)
「法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響」は、隔週で掲載されます。