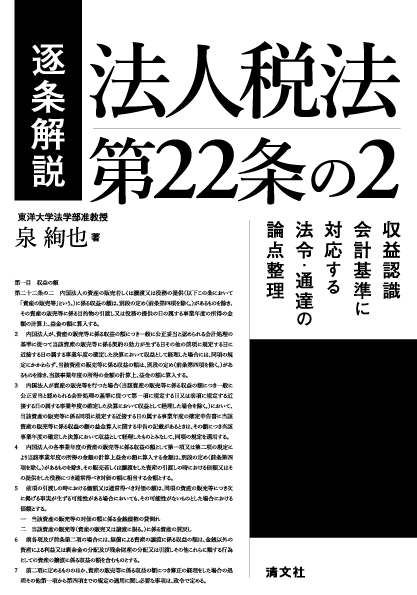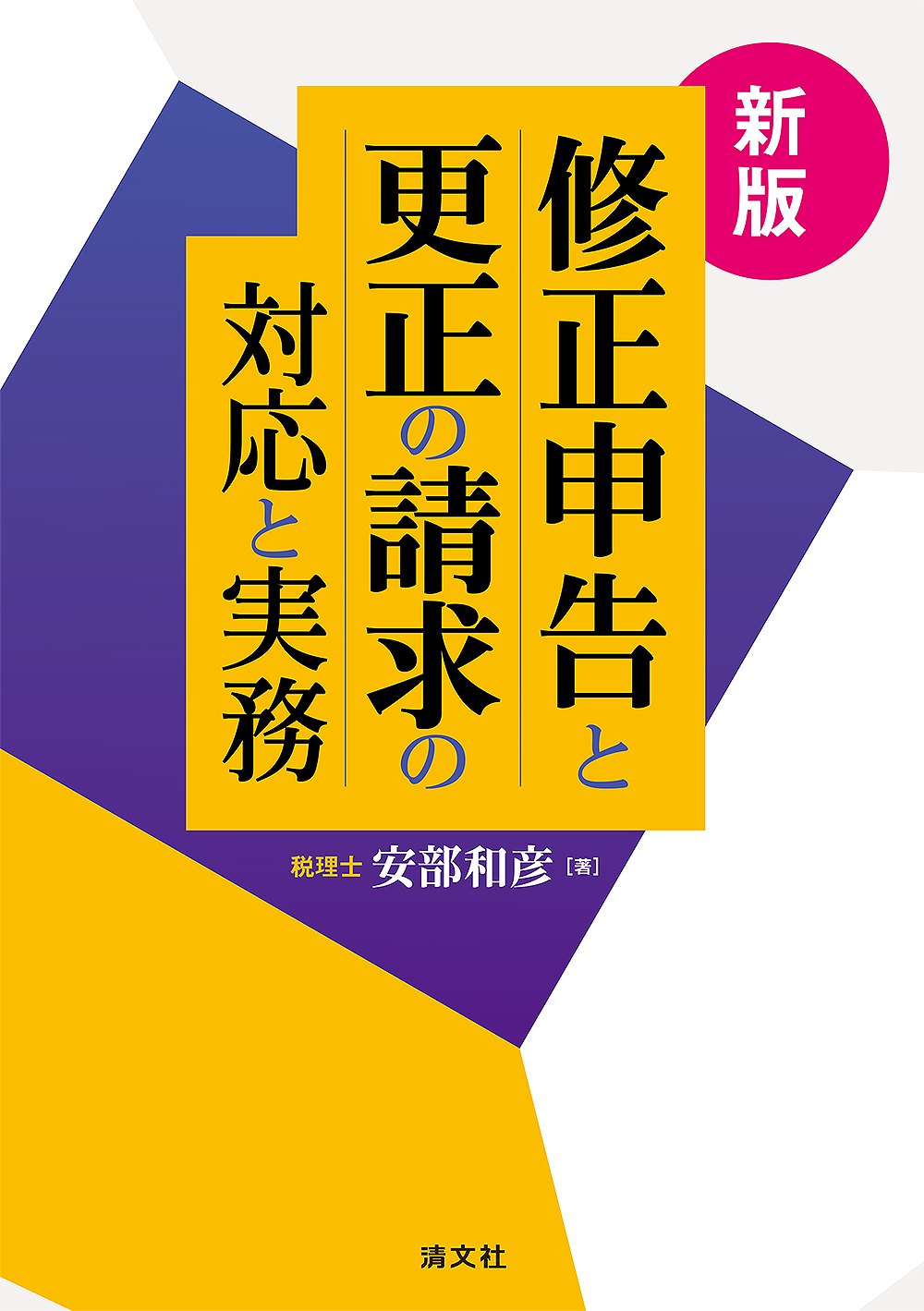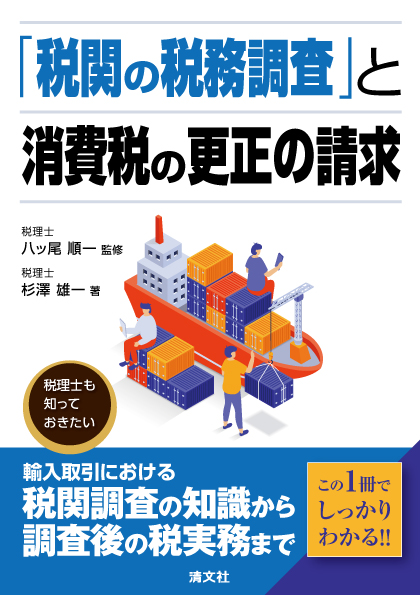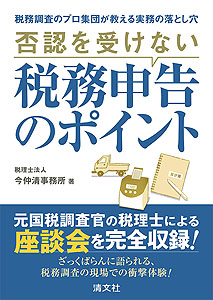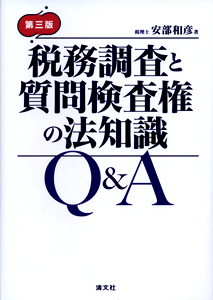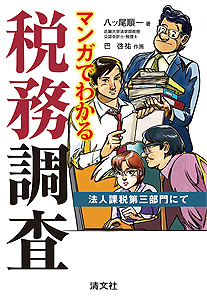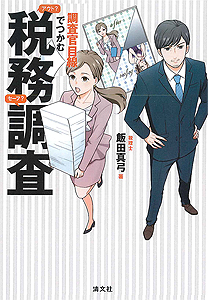理由付記の不備をめぐる事例研究
【第1回】
「理由付記制度及び判例法理等の概観」
中央大学大学院商学研究科 博士後期課程
(酒井克彦研究室所属)
泉 絢也
1 本連載の趣旨
平成23年12月の税制改正により、課税庁は、原則として国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分(更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知、青色申告承認申請の却下などの処分)や不利益処分(更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの処分)を行う場合には、処分の通知書に処分の理由を付記(注)しなければならないこととなった(国税通則法74条の14第1項、行政手続法8条、14条)。
理由付記制度に関して注目すべき点は、課税処分の内容自体に取り消されるべき瑕疵がないとしても、理由付記を欠いていたり、あるいは、理由の記載はあるものの、法が要求する理由付記の記載の程度に照らして十分な内容ではない場合には、課税処分が取り消されることである。しかしながら、理由付記に当たり、どの程度の記載をすべきであるかを定める条文は存在しない。
そのため、実際の事案において、具体的にどの程度の記載がなされていないと、理由付記が不備であるとして処分が取り消されることになるのかについては、必ずしも明らかではなく、議論や事例の集積が待たれるところである。
そこで、本連載では、理由付記の不備を巡る議論や争訟の発展に資するべく、実際の裁判例・裁決例を素材として、更正の理由付記の不備についての事例研究を行う。
(注) 本連載では、判決文等の引用部分を除き、「理由附記」ではなく「理由付記」と表記する。
2 本連載の検討対象
青色申告書に係る更正については、法人税法130条2項又は所得税法155条2項により、理由付記が求められることは、改正前後で変わりはない。そして、この青色申告書に係る更正処分とそれ以外の処分等に係る理由付記において要請される理由の記載の程度は異なる面もあろうが、これまでの議論や事例の蓄積状況及び法人の9割以上が青色申告を行っている現状などを踏まえ、本連載においては、法人税の青色申告書に係る更正の理由付記(法人税法130条2項)の十分性が問題となった裁判例・裁決例を中心に取り上げることとする。加えて、青色申告承認の取消処分の通知書(同法127条4項)に係る理由付記についても、若干、取り上げてみたい。
法人税法130条2項(青色申告書等に係る更正)
税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。
法人税法127条4項(青色申告の承認の取消し)
税務署長は、第1項又は第2項の規定による取消しの処分をする場合には、第1項又は第2項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となった事実が第1項各号又は第2項のいずれに該当するかを付記しなければならない。
3 連載の進め方
本連載の進め方としては、まず本稿(第1回)において、判例によって示された理由付記の十分性の判断基準等を確認し、【第2回】及び【第3回】において、最近の注目裁判例等を紹介し、その注目すべき点を指摘する。
そして、【第1回】から【第3回】の内容を踏まえた上で、【第4回】以降において、裁判例等を素材とした事例研究を行うこととする(具体的な連載予定項目については、論末の連載目次をご覧いただきたい)。
ただし、どの程度、理由を付記すれば十分であるかは、条文に明記されておらず、かつ、極めて個別的な問題であるから、具体的事例において理由付記が十分であるか否かは必ずしも一義的明確になるものではない。
このようなこともあって、事例研究においては、素材とした裁判例等における理由付記の十分性の判断と、私見における理由付記の十分性の判断に相違が生じる場合があることをお断りしておく。
4 最高裁昭和60年判決が示した理由付記の十分性の判断基準
青色申告書に係る更正の理由付記を巡っては多くの裁判例・裁決例が存在するが、ここでは、最高裁昭和60年4月23日第二小法廷判決(民集39巻3号850頁。以下「最高裁昭和60年判決」という)の判示を確認しておこう。
同判決は、理由付記の記載の程度に関する一般論として、次のとおり判示している。
① 理由付記(法人税法130条2項)の趣旨
「法が、青色申告制度を採用し、青色申告にかかる所得の計算については、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨にかんがみ、更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものというべきであ」る。
② 帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合の付記すべき程度
上記趣旨からすれば、「帳簿書類の記載自体を否認して更正をする場合において更正通知書に附記すべき理由としては、単に更正にかかる勘定科目とその金額を示すだけではなく、そのような更正をした根拠を帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示することによって具体的に明示することを要する〔下線筆者〕」
③ 帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合の付記すべき程度
「帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合においては、右の更正は納税者による帳簿の記載を覆すものではないから、更正通知書記載の更正の理由が、そのような更正をした根拠について帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示するものでないとしても、更正の根拠を前記の更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由の附記として欠けるところはないと解するのが相当である。〔下線筆者〕」
上記を要約すると、最高裁昭和60年判決は、【1】帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合の付記すべき程度について、更正をした根拠を帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示することによって具体的に明示することを要するとし、【2】帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合の付記すべき程度について、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示することを要する、としている。
5 若干の留意点
最高裁昭和60年判決が示した上記のような理由付記の十分性の判断基準は、これまでに蓄積された判例法理の1つの到達点ともいえる重要なものであり、その後の裁判例も、基本的にこの基準に従って、理由付記の十分性を判断している。
したがって、本連載においても、最高裁昭和60年判決をたびたび引用し、同判決が示した理由付記の十分性の判断基準に従って、理由付記の十分性を検討する。
しかしながら、次のような留意点があることを指摘しておく。
① 帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合であるか、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合であるかは、具体的な事例に落とし込んでみると、その判断が難しいこともある。
② 最高裁昭和60年判決は、帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合の付記すべき程度について、更正をした根拠を帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示することによって具体的に明示することを要するとしている。このような資料の摘示がある場合には、通常、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記の趣旨目的も充足されることになると考える。
この点、本連載においては、根拠資料の摘示さえあれば当然に理由付記が十分なものであると評価されるわけではないという理解に基づいて、根拠資料の摘示がある場合でも、理由付記の趣旨目的に照らしてその十分性を判断すべきであると解している。
③ 訴訟等において、納税者が理由付記の十分性を争う場合には、単に、「更正処分庁の恣意抑制又は不服申立ての便宜という理由付記の趣旨に照らして、理由付記が十分なものではない」と主張するのではなく、「仮に、この程度の理由付記で十分なものであるとした場合には、更正処分庁において、〇〇〇のような恣意的な処分を行うことができてしまう、あるいは納税者が不服申立てを行う際に〇〇〇のような不都合が生じる」と具体的に主張した方が説得的である。
6 その他の重要な裁判例等
理由付記の不備に関して、最高裁昭和60年判決以外の重要な裁判所の判断等を以下に示しておく。
① 理由付記に不備がある場合には、課税処分自体が違法なものとして取り消される。
⇒最高裁昭和38年5月31日第二小法廷判決・民集17巻4号617頁
② 理由を付記させることは、単に納税者に更正の理由を示すために止まらず、漫然たる更正のないよう更正の妥当公正を担保する趣旨をも含むものと解すべきであるから、更正の理由は、更正通知書の記載自体において法が求める程度に記載されていることを要し、その理由を納税義務者が推知できると否とにかかわりのない問題である。
⇒最高裁昭和38年12月27日第二小法廷判決・民集17巻12号1871頁
③ 理由付記の不備がある場合には、不服申立ての段階(異議決定書又は審査裁決書)で、十分な理由が付記されたとしても、その違法は治癒されない。
⇒最高裁昭和47年3月31日第二小法廷判決・民集26巻2号319頁、最高裁昭和47年12月5日第二小法廷判決・民集26巻10号1795頁
④ 複数の更正項目があり、その一部の理由付記のみが不備である場合に、更正はその理由に対応する税額の部分についてのみ違法であると解すれば十分である。
⇒東京高裁昭和50年6月27日判決・民集33巻3号424頁、東京地裁平成5年3月26日判決・行集44巻3号274頁
⑤ 一般的に青色申告書に係る更正処分の取消訴訟において、課税庁が、更正の理由とは異なるいかなる事実をも主張すること(いわゆる理由の差替え)ができると解すべきかどうかはともかく、争訟段階で、課税庁側に更正の理由とは異なるような追加主張の提出を許しても、当該更正処分を争うにつき納税者の側に格別の不利益を与えるものではない場合には、上記のような追加主張の提出をすることも認められる。
⇒最高裁昭和56年7月14日第三小法廷判決・民集35巻5号901頁参照
また、裁判例は、基本的な課税要件事実の同一性が認められる範囲内で、いわゆる理由の差替えを認める傾向にある。
⇒徳島地裁平成5年7月16日判決・訟月40巻6号1268頁、東京高裁平成10年4月28日判決・税資231号866頁など参照
⑥ 理由付記から、更正処分の理由が、帳簿の記載に誤りがあるという趣旨であるか、法令を適用した結果であるのかなどを読み取ることができない場合には、理由付記に不備があるとされ得る。
⇒最高裁昭和47年3月31日第二小法廷判決・民集26巻2号319頁
⑦ 裁判例は、理由付記に根拠条文の記載がされていない場合でも、理由付記から根拠条文が容易に判明することなどを理由に、根拠条文の記載がないことのみをもって直ちに理由付記が不備であるとは解さない傾向にある。
⇒東京地裁昭和55年10月28日判決・訟月27巻4号789、名古屋地裁平成8年3月22日判決・税資215号960頁など参照
このほか、今後、裁判所の判断として定着するか否かは明らかではないが、次のような判断も示されている(東京地裁平成8年11月29日判決・判時1602号57頁)。
「理由附記においては、更正処分庁の判断過程を具体的に明示するとともに、その判断が課税行政庁の把握した事実に基づく場合には、その事実認定が単なる推測、憶測に基づくものではなく、相応の根拠を有するものであることを示し得る程度に、右認定を裏付ける資料を摘示すべきものである。そうすると、青色申告書における帳簿書類の記載を否認して更正をする帳簿否認の場合においては、附記理由において、そのような更正をした根拠を具体的に明示し、かつ、右認定に至る過程で収集された、帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示する(帳簿記載事実に反する事実について信憑力ある資料を摘示する)ことを要するものというべきであり、帳簿記載事実又は帳簿記載において前提とする事実に基づいて、単にその評価のみを否認する場合には、そのような評価判断に至った過程自体を、また、更正処分庁の把握した事実を加えて異なる評価をしたときは、その事実の根拠について、やはり、更正処分庁の恣意の抑制及び相手方の不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨に適う程度に具体的に説明又は摘示する必要があるものと解すべきである。
これに対し、被告新宿税務署長は、帳簿否認の場合でも、複数の間接事実をもって帳簿記載事実を否認する場合には、その間接事実を基礎づける間接資料と帳簿書類の記載との信憑力の比較ができないから、右の理は妥当しない旨主張する。確かに、帳簿に記載された事実を直接否定する更正ではない場合には、複数の間接事実による推認によらざるを得ないことは、指摘のとおりである。しかしながら、その場合であっても、更正の理由とされた事実については事実的資料を摘示すべしとする理由附記制度の趣旨からすれば、公知又は顕著な事実以外の事実については、その資料が一般的に明らかであったり、又は当然に推定されるものを除き、事実認定の根拠となった資料を摘示したうえ、それらの間接事実から帳簿記載の事実を否認したことに信憑性があると判断できる程度に判断過程を記載すべきものであって、事実に関する資料の摘示又は理由の信憑性が問題とならないわけではない。〔下線筆者〕」
* * *
次回から2回に分けて、理由付記に関する最近注目の裁決例・裁判例を取り上げることとする。
(了)
「理由付記の不備をめぐる事例研究」は、隔週で掲載されます。