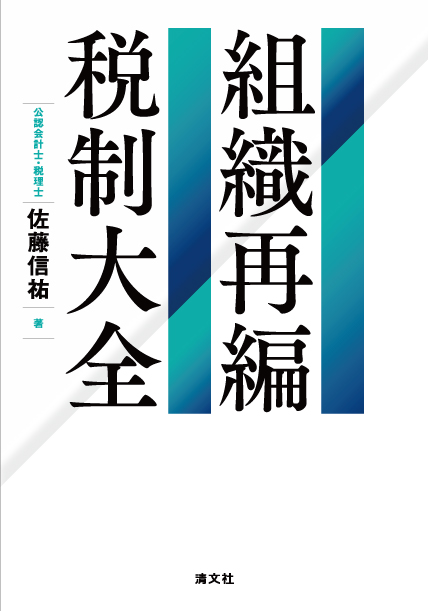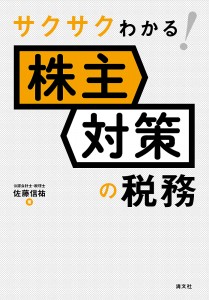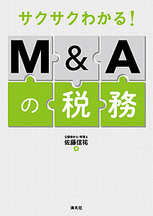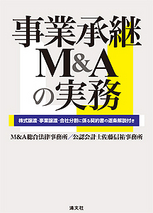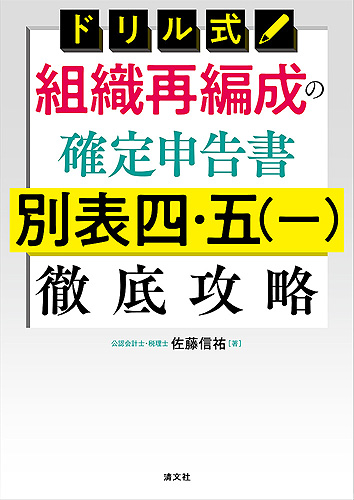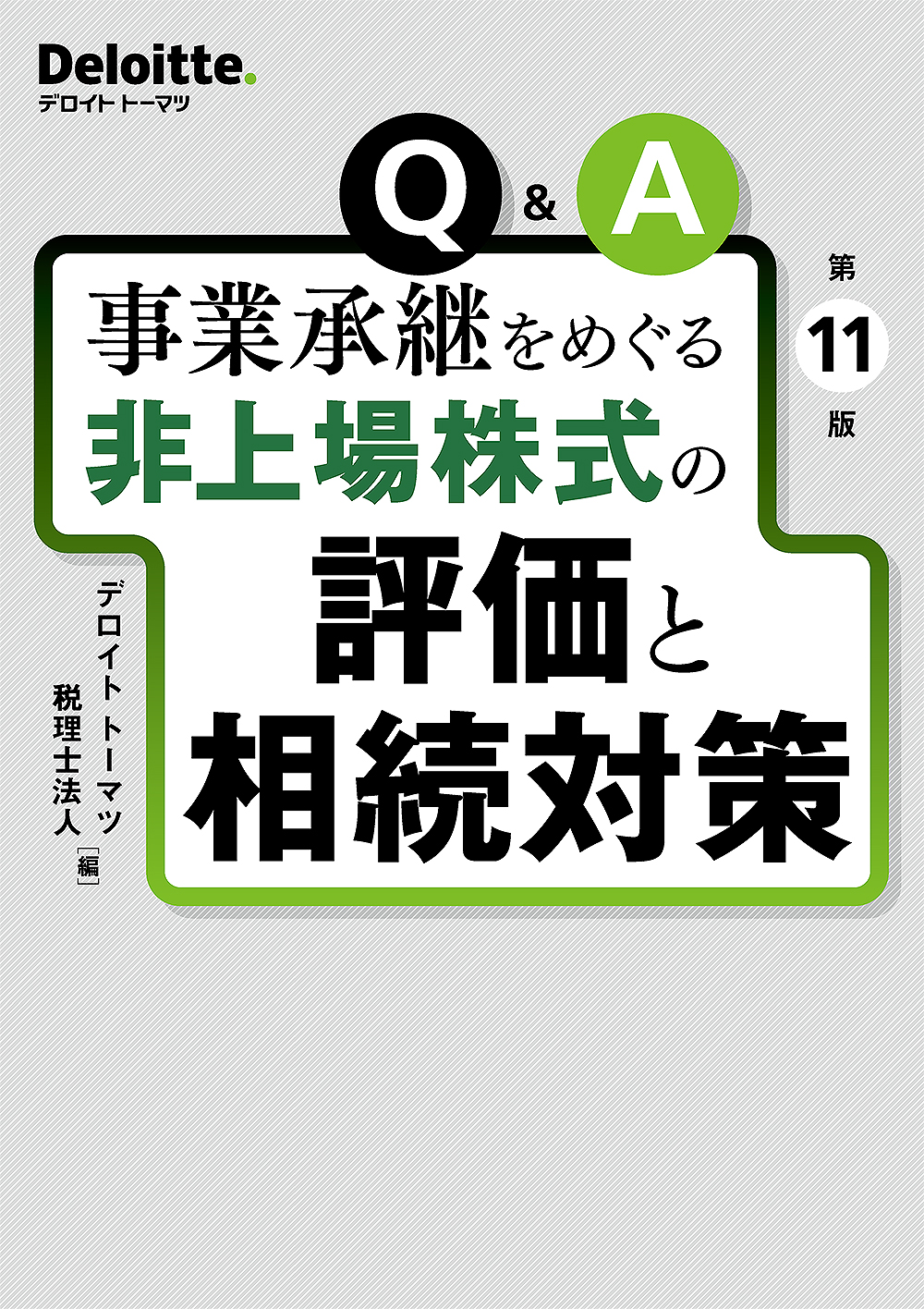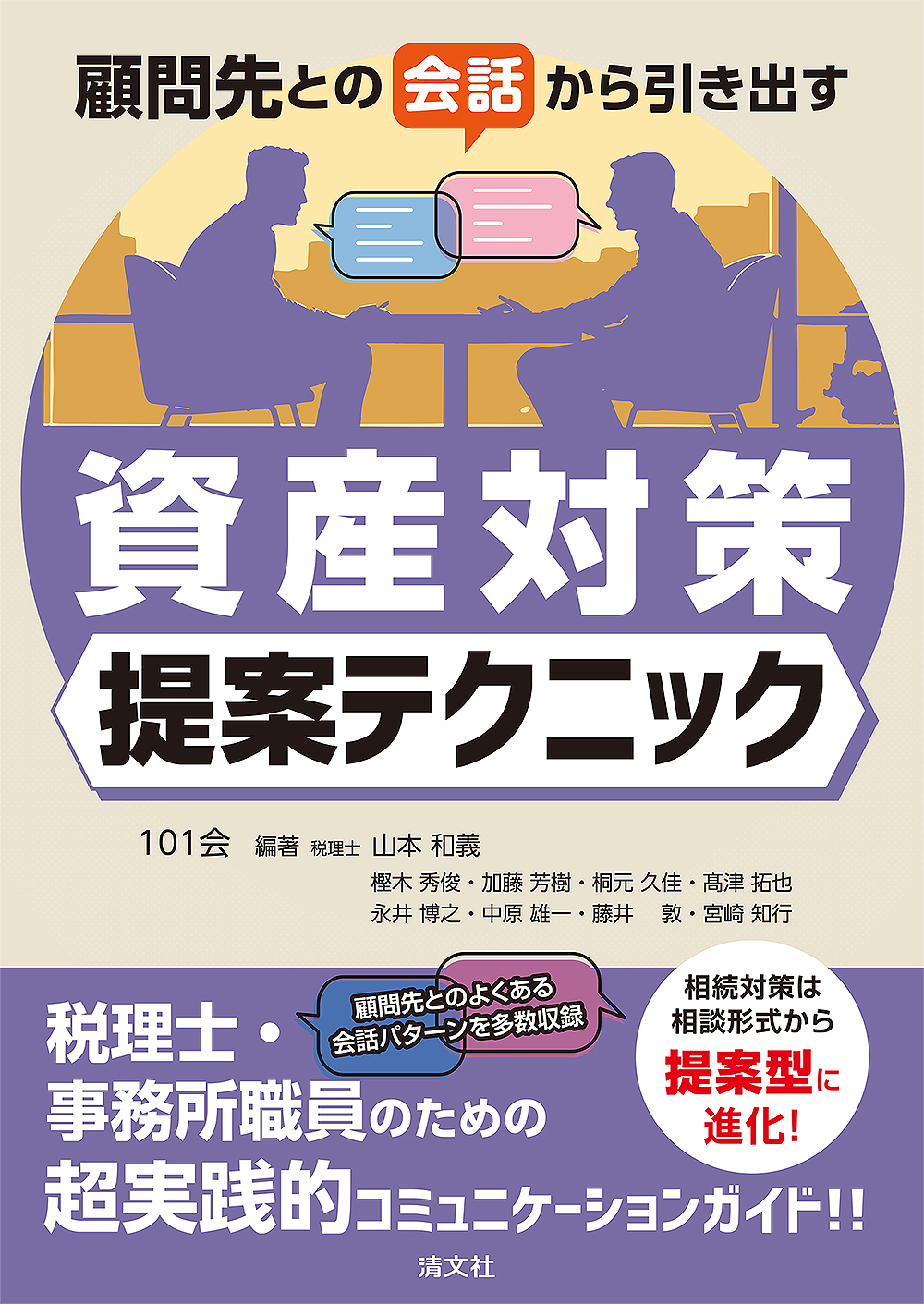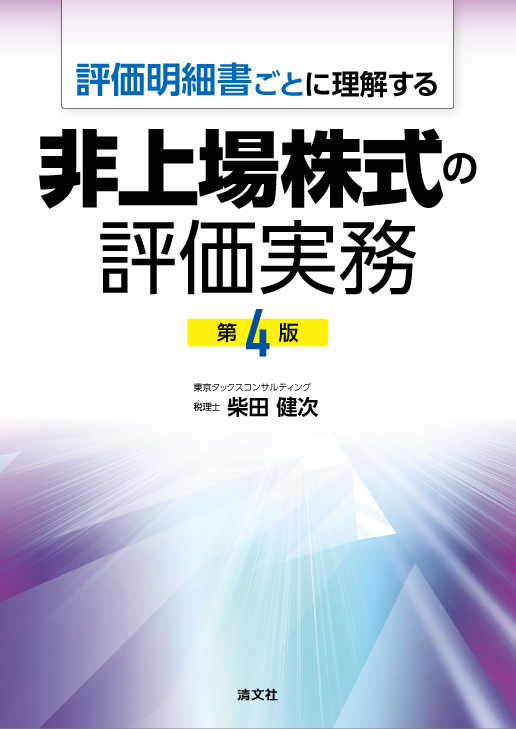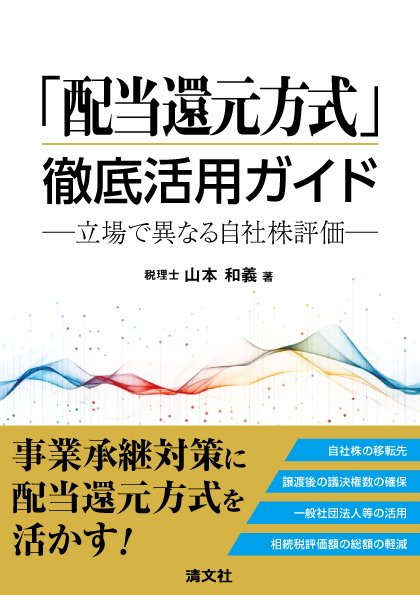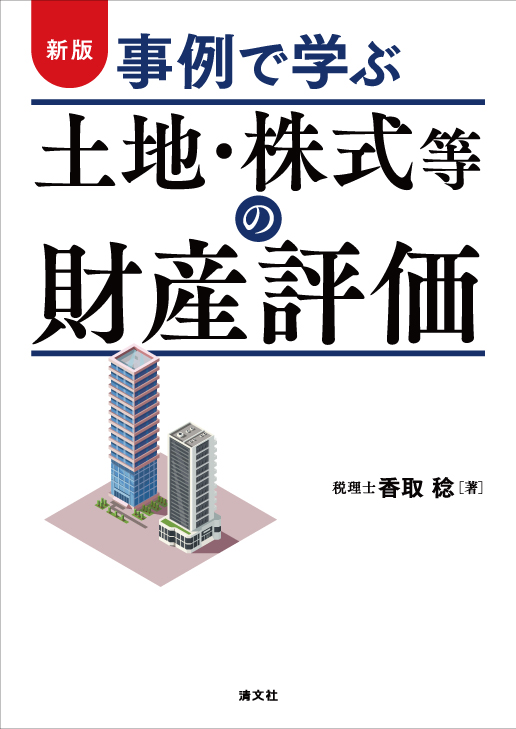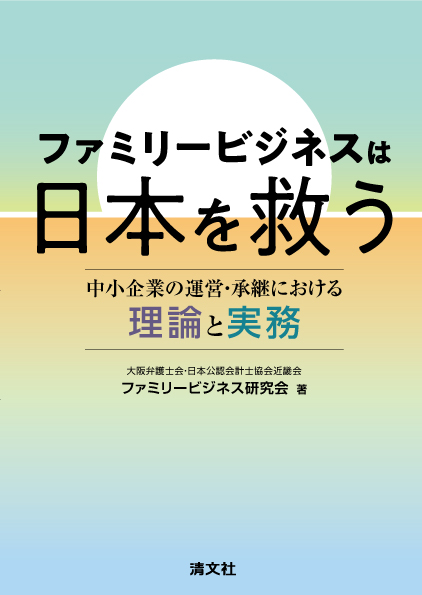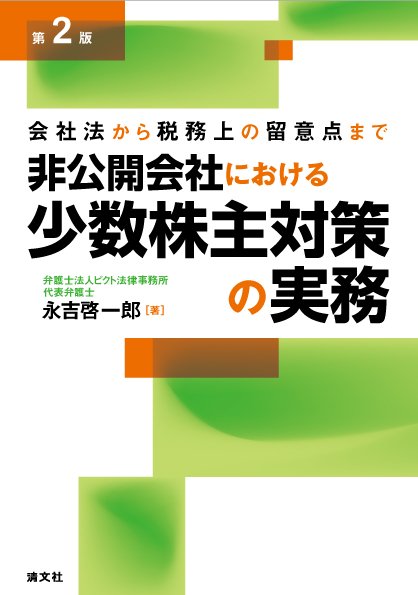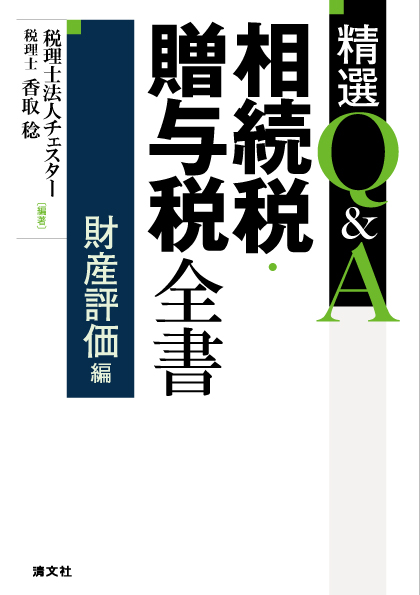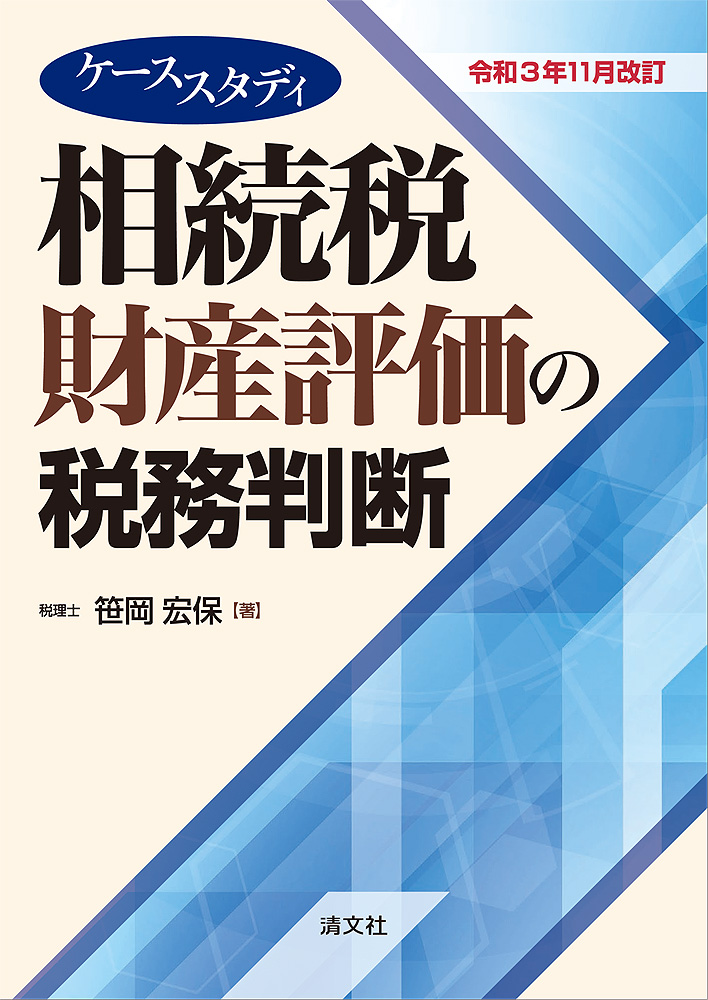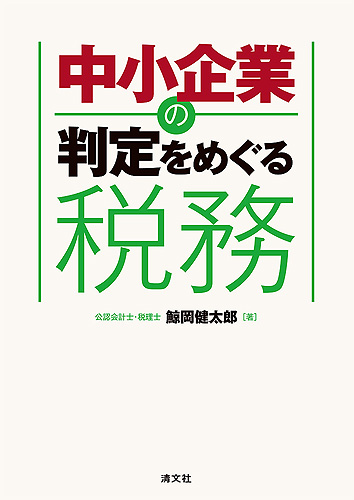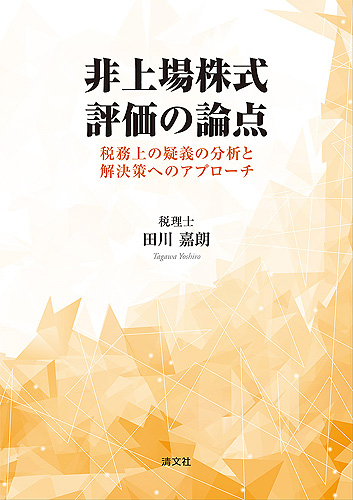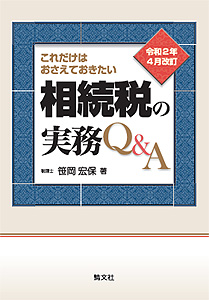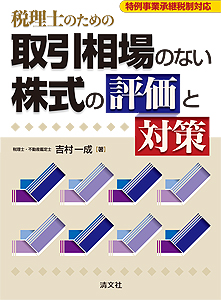裁判例・裁決例からみた
非上場株式の評価
【第1回】
「論点分析」
公認会計士 佐藤 信祐
連載の目次はこちら
税務専門家の立場からすると、「非上場株式の評価」と言われると財産評価基本通達を思い浮かべてしまうが、実務においては、会社法からの分析も必要である。
【第1回】にあたる本稿では、会社法、租税法の両面からの論点について解説したい。
1 論点分析
(1) 会社法の観点からの分析
会社法上、非上場株式の評価が問題となる場面として、以下のものが挙げられる。
- 譲渡制限株式の譲渡についての売買価格決定の申立て
- 有利発行に該当する募集株式の発行等の差止請求
- 組織再編における反対株主の買取請求
- スクイズアウトにおける価格決定の申立て
- 所在不明株主からの株式の買取り
- 相続人等に対する売渡請求
- その他、取締役の損害賠償など
なぜならば、価格決定の申立ては非訟事件に該当することから、裁判所の裁量により決定される。そのため、上場株式については顕著であるが、統計学的手法を用いた分析もなされていたり、プレミアムを20%とするといった大雑把な算定がされていたりするものも少なくない。
これに対し、例えば、取締役の損害賠償責任を追及する訴訟事件では、損害の額を認定しなければならないため、裁判所の裁量により大雑把な算定をすることは許されない。そのため、非訟事件に比べて、取締役に有利な判決が下されることも少なくない。
さらに、会社法の観点からの分析は、それぞれの事件の目的により異なる価格になることがあり得るという点に留意が必要である。例えば、組織再編やスクイズアウトでは、マイノリティ・ディスカウントや非流動性ディスカウントが認められない可能性が高いのに対し、譲渡制限株式の譲渡では、マイノリティ・ディスカウントや非流動性ディスカウントが認められる余地があるからである。
(2) 租税法の観点からの分析
租税法の観点では、非時価取引に該当するか否かという点が問題となる。この場合、贈与をした者、贈与を受けた者が自然人なのか、法人なのかにより、所得税、法人税、贈与税のいずれに該当するのかが異なるが、それぞれの税目の目的に応じた分析が必要となる。
さらに、財産評価基本通達により評価を行うにしても、原則的評価方式により評価を行うのか、特例的評価方式により評価を行うのかをまずは検討する必要があるという点に留意が必要である。
例えば、贈与税では、贈与を受けた者の贈与後のポジションにより、これらの評価が決定される(相続税法22条)。これに対し、譲渡所得税では、贈与をした者の譲渡をする直前のポジションにより、これらの評価が決定される(所得税法基本通達59-6)。
これらの評価方法は、会社法と目的が異なるため、当然に評価方法が異なる場合も考えられる。
(3) 本稿の目的
これらを踏まえ、本稿では、非上場株式の評価につき、会社法の裁判例、租税法の裁判例、裁決例をそれぞれ分析することを目的にしている。
非上場株式の評価についての筆者の平成26年度の研究実績は、「特例的評価方式による少数株主の締出し」税務弘報62巻12号73-79頁、「配当還元方式により現金交付型合併を行った場合」税務QA2014年9月号 36-39頁であり、平成27年度の研究実績は「非上場会社の少数株主の締出しにおける公正な価格」法学政治学論究106号133-165頁である。
これらは、少数株主の締出しについての研究であるため、租税法の観点からの分析は、原則的評価方式によるものが多く、わずかに売り手側の少数株主の譲渡所得税の計算において特例的評価方式を採用する余地が認められた。これに対し、会社法の観点からの分析は、支配株主にとっての株式価値により評価を行う必要があり、さらに、非流動性ディスカウントが認められないものと結論づけた。そして、少数株主の締出しにより将来フリー・キャッシュ・フローが増加する場合には、増加するフリー・キャッシュ・フローに基づいて株式価値の算定をすべきであると結論づけた。本稿では、さらに踏み込んで、募集株式の発行等や譲渡制限株式の譲渡などの裁判例について触れるとともに、租税法の観点から、より細かな分析をしていきたい。
本稿の目的は、学術的な研究を行うことではなく、裁判例、裁決例から、実務上の問題点を抽出していくことにある。そのため、裁判所、国税不服審判所の見解と筆者の見解が異なる場合であっても、あえてその点については触れず、裁判所、国税不服審判所の見解を中心に解説していきたい。
本稿の構成は、まずは会社法の分析をひと通り行った上で、租税法の分析を行い、そこから導き出される実務上の留意事項をまとめていく予定である。
次回以降は、募集株式の発行等の裁判例について触れていく予定である。なお、平成17年改正前商法では、新株の発行と自己株式の処分はそれぞれ分けて規定されていたが、会社法の施行により、両者は募集株式等の発行として1つの条文にまとめて規定されることになった。裁判例の多くは平成17年改正前商法に基づくものであるが、現行会社法でも同様に解されるかどうかについて、検討が必要になるものもあり得るという点にご留意されたい。
(了)
「裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価」は、隔週で掲載されます。