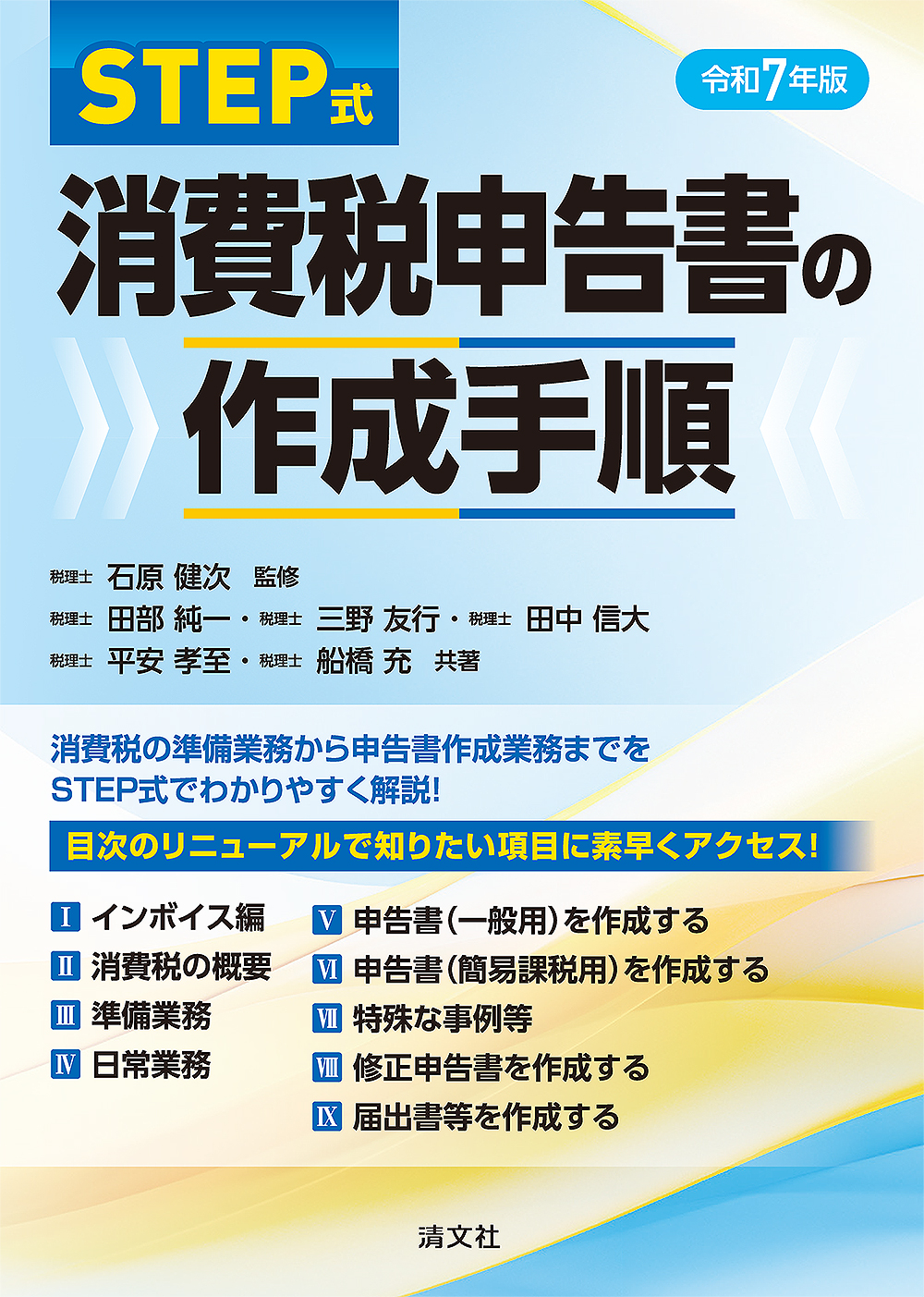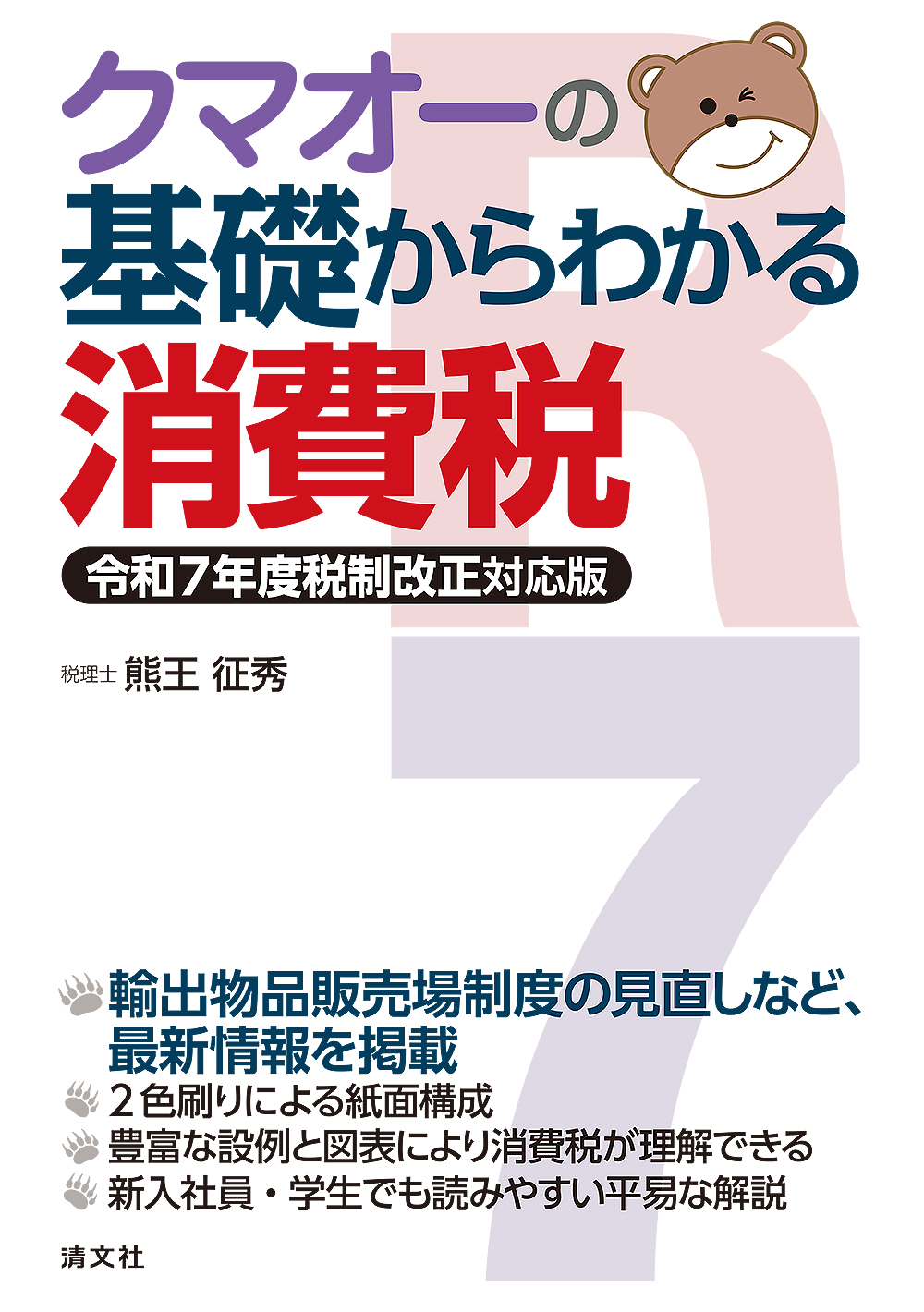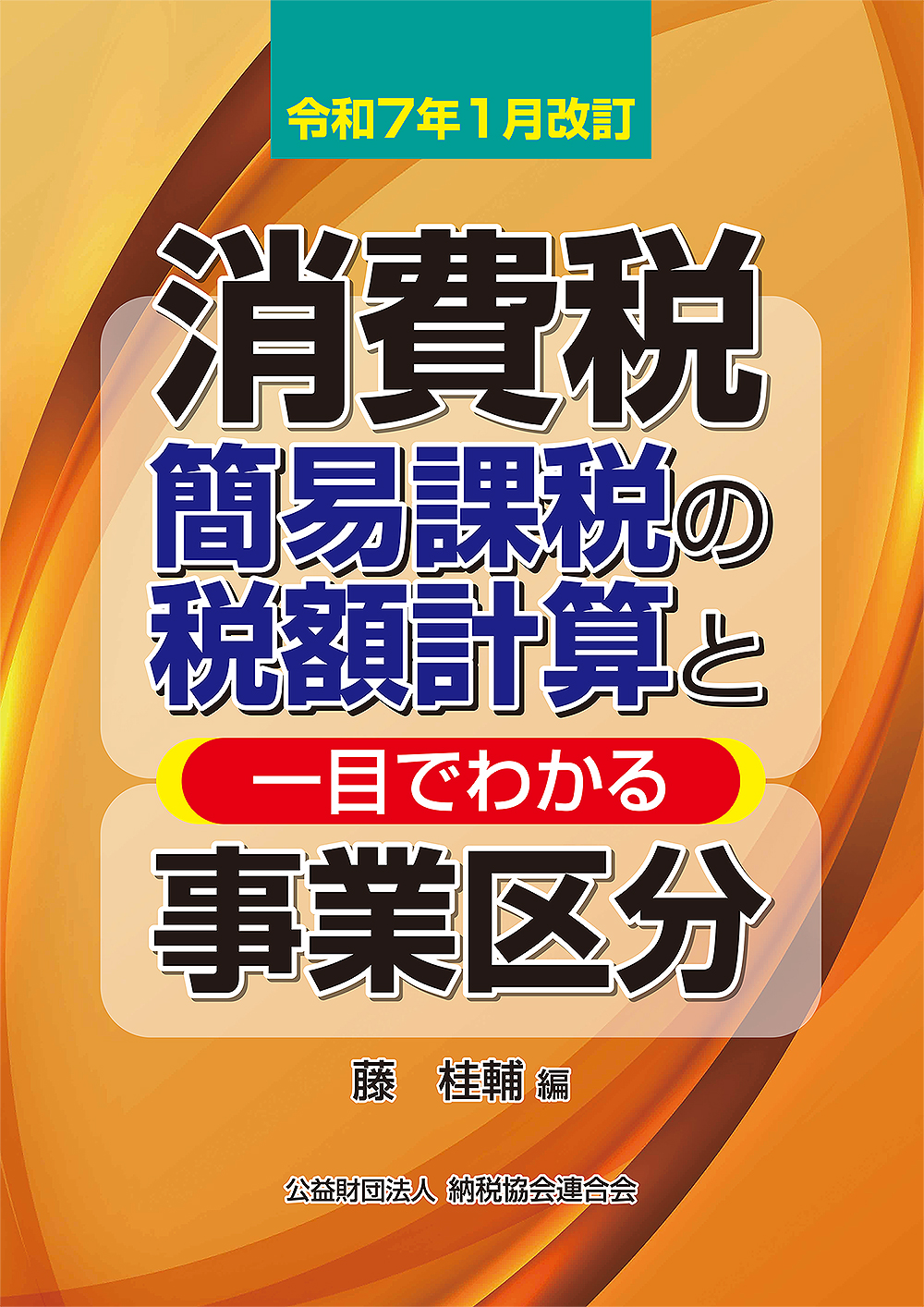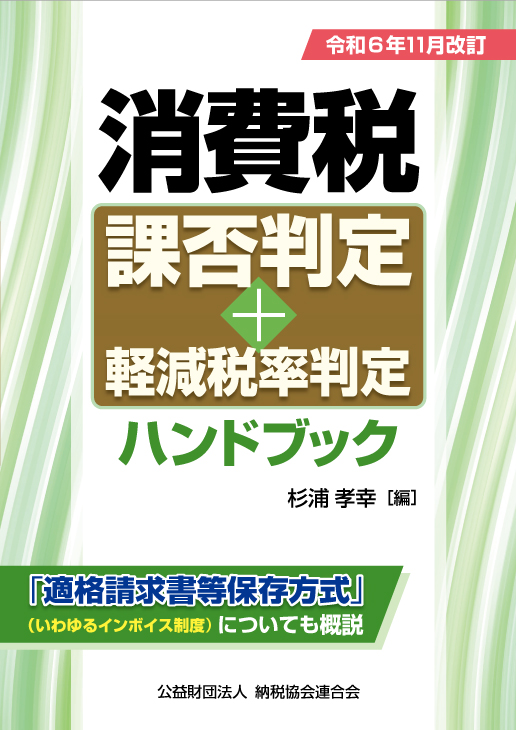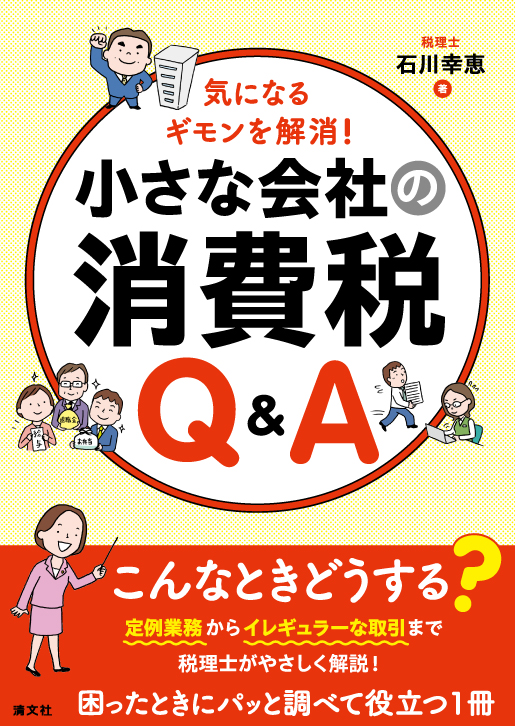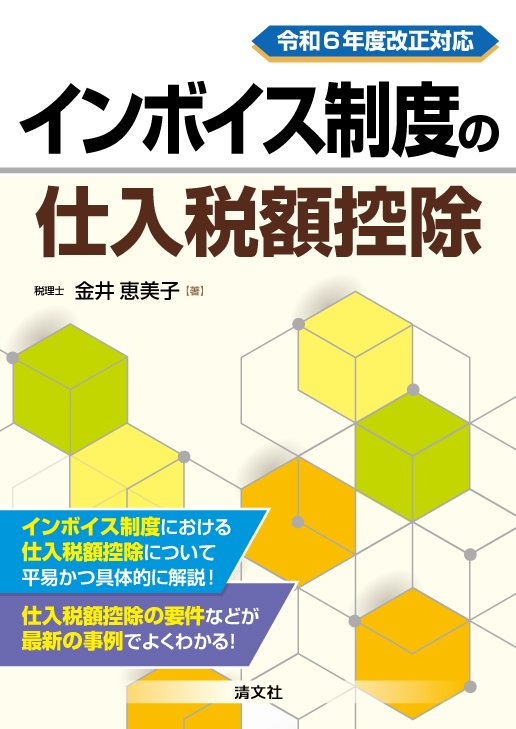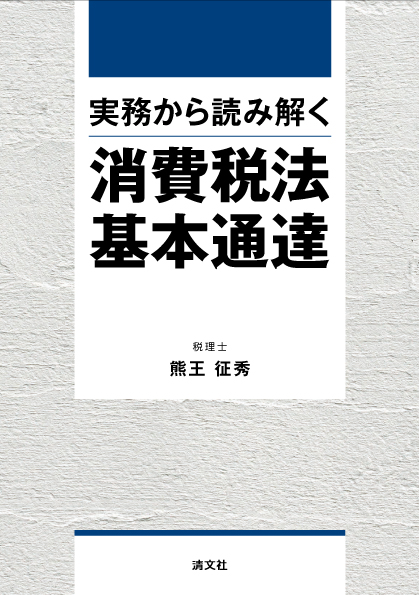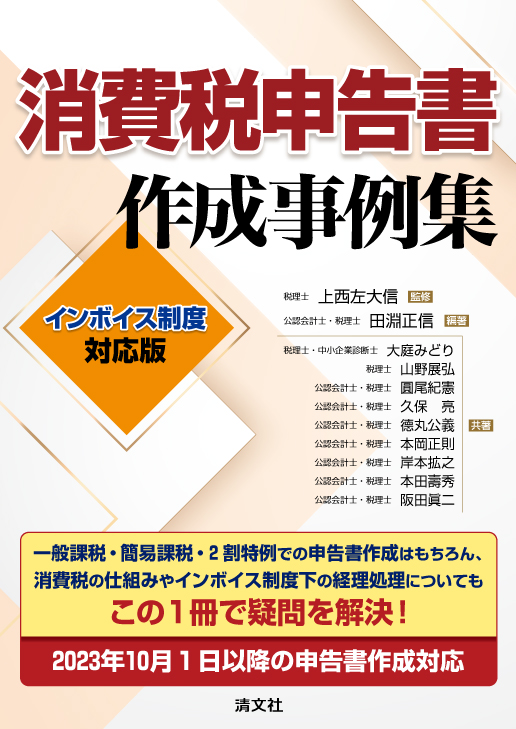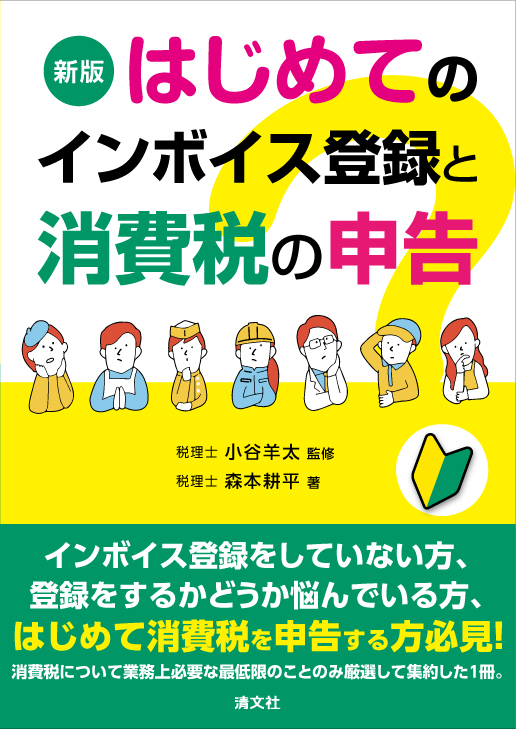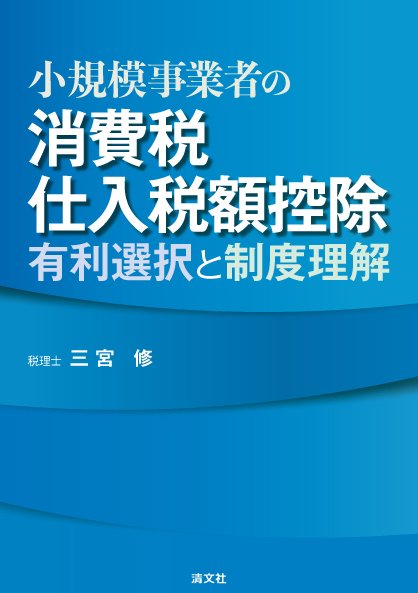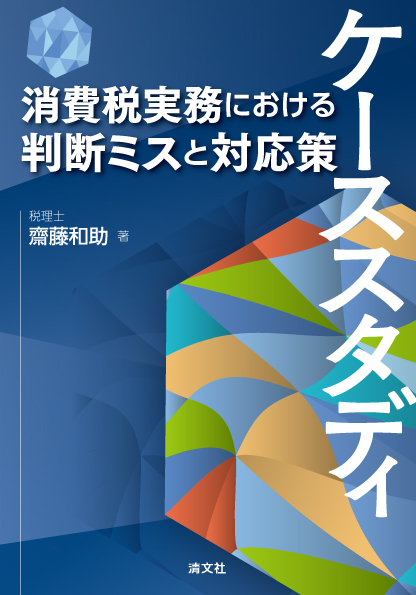5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順
【第1回】
「一般課税の申告書・付表作成の流れ(前編)」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩 (監修)
税理士 小嶋 敏夫(執筆)
平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられたことで、施行日以後に終了する課税期間については旧税率と新税率が混在することとなり、経過措置用の付表を作成する等、これまでの申告実務とは異なる対応が必要となる。
そこで本連載では、一般課税と簡易課税による申告書及び付表の作成方法について、具体例を交えつつ確認していくこととする。
1 施行日以後に作成する確定申告書及び付表について
施行日以後に作成する消費税の申告において提出しなければならない帳票は、以下のとおりである。
(1) 一般課税用の確定申告
① 経過措置の適用がない場合
② 経過措置の適用がある場合
確定申告書に控除不足還付税額の記載がある場合には、「消費税の還付申告に関する明細書」も併せて提出しなければならない。
- 消費税及び地方消費税確定申告書(一般用)
⇒様式はこちら(同上) - 付表1(旧・新税率別、消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕)
⇒様式はこちら - 付表2-(2)(課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕)
⇒様式はこちら
(2) 簡易課税用の確定申告
① 経過措置の適用がない場合
② 経過措置の適用がある場合
- 消費税及び地方消費税確定申告書(簡易課税用)
⇒様式はこちら(同上) - 付表4(旧・新税率別、消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕)
⇒様式はこちら - 付表5-(2)(控除対象仕入税額の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕)
⇒様式はこちら
2 一般課税における申告書及び付表の作成手順
(1) 申告書及び付表の作成手順
施行日以後に終了する課税期間で、消費税の確定申告(一般課税)を行う場合には、旧税率と新税率が混在することが考えられ、従来の付表2ではなく、複数税率の計算をするための付表1及び付表2-(2)を作成し、確定申告書に添付することとなる。
具体的には、以下の手順で作成することとなる。
《確定申告書作成の流れ》
税率毎に課税売上げや課税仕入れを区分
付表2-(2)の作成
付表1の作成
確定申告書の作成
各付表及び確定申告書を作成するためには、まず、その課税期間における課税売上げや課税仕入れを税率ごとに区分して計算することとなるが、具体的には、以下のような数値が必要になる。
① 課税売上割合の計算
- 5%適用分の課税売上高(税込み)
- 5%適用分の課税売上げに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 8%適用分の課税売上高(税込み)
- 8%適用分の課税売上げに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 輸出免税売上高
- 非課税資産の輸出等の金額及び国外移送した資産の価額の合計額(注1)
- 非課税売上高(注2)
(注1) 国内で譲渡すれば非課税売上げとなる資産等を輸出した場合には、その金額を免税売上げとみなして課税売上割合の計算を行うこととなっているが、その具体例は以下のようなものがある。
・身体障害者用物品等の輸出売上げ
・外国債の利子
・非居住者からの受取利息
また、海外で自ら使用する備品等や海外支店で販売する商品等を輸出した場合にも免税売上げとみなして課税売上割合の計算を行うこととなり、その場合における対価の額はその商品等を移送する際の本船甲板渡し価格(FOB価格)となる。
(注2) 課税売上割合の計算上、一定の有価証券等を譲渡した場合における非課税売上げとして計上する対価の額は、譲渡対価の5%相当額となる。また、平成26年4月1日以後に行った金銭債権の譲渡(資産の譲渡等の対価として取得したものを除き、リサイクル預託金等の譲渡を含む)についてもその譲渡対価の5%相当額を非課税売上げとして計上することと改正されたので注意が必要である。
② 全額控除方式及び一括比例配分方式を採用する場合の仕入税額控除
- 5%適用分の課税仕入れの合計額(税込み)
- 5%適用分の課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 8%適用分の課税仕入れの合計額(税込み)
- 8%適用分の課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 5%適用分の課税貨物に係る消費税額及び還付を受けた消費税額
- 8%適用分の課税貨物に係る消費税額及び還付を受けた消費税額
③ 個別対応方式を採用する場合の仕入税額控除
- 5%適用分の課税売上げにのみ要する課税仕入れの合計額(税込み)
- 5%適用分の課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 8%適用分の課税売上げにのみ要する課税仕入れの合計額(税込み)
- 8%適用分の課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 5%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れの合計額(税込み)
- 5%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 8%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れの合計額(税込み)
- 8%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 5%適用分の課税売上げにのみ要する課税貨物に係る消費税額及び還付を受けた消費税額
- 8%適用分の課税売上げにのみ要する課税貨物に係る消費税額及び還付を受けた消費税額
- 5%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税貨物に係る消費税額及び還付を受けた消費税額
- 8%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税貨物に係る消費税額及び還付を受けた消費税額
④ その他の項目
- 5%適用分の棚卸資産等に係る消費税額の調整額(注1)
- 8%適用分の棚卸資産等に係る消費税額の調整額(注1)
- 5%適用分の調整対象固定資産に係る消費税額の調整額(注2)
- 8%適用分の調整対象固定資産に係る消費税額の調整額(注2)
- 5%適用分の課税売上げに係る貸倒金額(注3)
- 8%適用分の課税売上げに係る貸倒金額(注3)
- 5%適用分の貸倒回収額(注4)
- 8%適用分の貸倒回収額(注4)
(注1) 納税義務の免除を受けないこととなった場合又は納税義務の免除を受けることとなった場合には、棚卸資産等に係る消費税額を調整することとなる。
(注2) 課税売上割合が著しく変動した場合には、調整対象固定資産に係る消費税額を調整することとなる。また、調整対象固定資産を課税業務用から非課税業務用に転用した場合又は非課税業務用から課税業務用に転用した場合には、その調整対象固定資産に係る消費税額を調整することとなる。
(注3) 課税売上げに係る売掛金等が貸し倒れた場合には、その貸倒れに係る消費税額を税額控除として処理することとなる。
(注4) 前課税期間以前において、貸倒れに係る消費税額として処理したものが当課税期間において回収できた場合には、その回収できた金額に係る消費税額を課税資産の譲渡等とみなして課税標準額に対する消費税額に加算することとなる。
(2) 付表2-(2)の作成
付表2-(2)は、課税売上割合や仕入税額控除の計算を行うために作成するのであるが、旧税率と新税率が混在している場合には、それぞれの税率を基に計算をしていくこととなるが、具体的には、以下のようになる。
〈①欄〉 課税売上額(税抜き)
【4%適用分①B欄】
税込課税売上高×[100/105]-売上対価の返還等(税込)×[100/105]
【6.3%適用分①C欄】
税込課税売上高×[100/108]-売上対価の返還等(税込)×[100/108]
【合計①D欄】
①B欄+①C欄
〈②欄〉 免税売上額
輸出免税売上げの金額を記載。
〈③欄〉 非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価額
非課税資産の輸出があった場合又は海外支店等へ移送した資産があった場合に記載。
〈④欄及び⑤欄〉 課税資産の譲渡等の対価の額
①D欄+②D欄+③D欄
〈⑥欄〉 非課税売上額
非課税売上げの金額を記載(上記参照)。
〈⑦欄〉 資産の譲渡等の対価の額
⑤D欄+⑥D欄
〈課税売上割合の欄〉
④D欄/⑦D欄
(※) 上記割合の端数処理については、原則として行わないが、任意の位で切り捨てることも認められる。
〈⑧欄〉 課税仕入れに係る支払対価の額
【4%適用分⑧B欄】
税込課税仕入れの金額-仕入対価の返還等(税込)の金額
(※) なお、仕入対価の返還等の金額が大きい場合には、マイナスで表示する(以下同じ)。
【6.3%適用分⑧C欄】
税込課税仕入れの金額-仕入対価の返還等(税込)の金額
【合計D欄】
⑧B欄+⑧C欄
〈⑨欄〉 課税仕入れに係る消費税額
【4%適用分⑨B欄】
税込課税仕入れの金額×[4/105]-仕入対価の返還等(税込)の金額×[4/105]
(※) なお、仕入対価の返還等の金額が大きい場合には、マイナスで表示する(以下同じ)。
【6.3%適用分⑨C欄】
税込課税仕入れの金額×[6.3/108]-仕入対価の返還等(税込)の金額×[6.3/108]
【合計⑨D欄】
⑨B欄+⑨C欄
〈⑩欄〉 課税貨物に係る消費税額
【4%適用分⑩B欄】
引取りの税額(国税分)-引取りの還付税額(国税分)
(※) なお、引取りの還付税額が大きい場合には、マイナスで表示する(以下同じ)。
【6.3%適用分⑩C欄】
引取りの税額(国税分)-引取りの還付税額(国税分)
【合計⑩D欄】
⑩B欄+⑩C欄
〈⑪欄〉 納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額
【4%適用分⑪B欄】
棚卸資産等の金額(税込)×[4/105]
【6.3%適用分⑪C欄】
棚卸資産等の金額(税込)×[6.3/108]
【合計⑪D欄】
⑪B欄+⑪C欄
〈⑫欄〉 課税仕入れ等の税額の合計額
【4%適用分⑫B欄】
(前課税期間が免税事業者の場合)
⑨B欄+⑩B欄+⑪B欄
(翌課税期間が免税事業者の場合)
⑨B欄+⑩B欄-⑪B欄
【6.3%適用分⑫C欄】
(前課税期間が免税事業者の場合)
⑨C欄+⑩C欄+⑪C欄
(翌課税期間が免税事業者の場合)
⑨C欄+⑩C欄-⑪C欄
【合計⑫D欄】
⑫B欄+⑫C欄
〈⑬欄〉 課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合
全額控除方式を採用する際に記載するが、上記⑫の欄をそのまま転記する。
〈⑭欄〉 個別対応方式:⑫のうち課税売上げにのみ要するもの
個別対応方式を採用する際に記載するが、課税売上げにのみ要するものを抜き出して、以下のように計算する。
【4%適用分⑭B欄】
税込課税仕入れの金額 ×[4/105]-仕入対価の返還等(税込)の金額×[4/105]
+課税貨物に係る消費税額-課税貨物に係る還付税額
【6.3%適用分⑭C欄】
税込課税仕入れの金額×[6.3/108]-仕入対価の返還等(税込)の金額×[6.3/108]
+課税貨物に係る消費税額-課税貨物に係る還付税額
【合計⑭D欄】
⑭B欄+⑭C欄
〈⑮欄〉 個別対応方式:⑫のうち課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの
個別対応方式を採用する際に記載するが、課税売上げと非課税売上げに共通して要するものを抜き出して、以下のように計算する。
【4%適用分⑮B欄】
税込課税仕入れの金額×[4/105]-仕入対価の返還等(税込)の金額×[4/105]
+課税貨物に係る消費税額-課税貨物に係る還付税額
【6.3%適用分⑮C欄】
税込課税仕入れの金額×[6.3/108]-仕入対価の返還等(税込)の金額×[6.3/108]
+課税貨物に係る消費税額-課税貨物に係る還付税額
【合計⑮D欄】
⑮B欄+⑮C欄
〈⑯欄〉 個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額
個別対応方式を採用する際に記載するが、以下の算式に従って計算する。
【4%適用分⑯B欄】
⑭B欄+⑮B欄×課税売上割合
【6.3%適用分⑯C欄】
⑭C欄+⑮C欄×課税売上割合
【合計⑯D欄】
⑯B欄+⑯C欄
〈⑰欄〉 一括比例対応方式により控除する課税仕入れ等の税額
一括比例配分方式を採用する際に記載するが、以下の算式に従って計算する。
【4%適用分⑰B欄】
⑫B欄×課税売上割合
【6.3%適用分⑰C欄】
⑫C欄×課税売上割合
【合計D欄】
⑰B欄+⑰C欄
〈⑱欄〉 控除税額の調整:課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整(加算又は減算)額
課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に係る消費税額の調整額を記載するが、課税売上割合が著しく増加した場合は加算、著しく減少した場合は減算することとなる。
〈⑲欄〉 控除税額の調整:調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用)に転用した場合の調整(加算又は減算)額
調整対象固定資産を課税業務用から非課税業務用に転用した場合又は非課税業務用から課税業務用に転用した場合にその調整額を記載することとなるが、課税業務用に転用した場合には加算、非課税業務用に転用した場合には減算することとなる。
〈⑳欄〉 差引:控除対象仕入税額
この欄は、以下の算式により計算した金額がプラスの場合に記載する。なお、プラスなのかマイナスなのかの判定は税率区分ごとにそれぞれ判定することとなるので注意が必要である。
(全額控除方式の場合)
【4%適用分⑳B欄】
⑬B欄 ± ⑱B欄 ± ⑲B欄
【6.3%適用分⑳C欄】
⑬C欄 ± ⑱C欄 ± ⑲C欄
【合計⑳D欄】
⑳B欄+⑳C欄
(個別対応方式の場合)
【4%適用分⑳B欄】
⑯B欄 ± ⑱B欄 ± ⑲B欄
【6.3%適用分⑳C欄】
⑯C欄 ± ⑱C欄 ± ⑲C欄
【合計⑳D欄】
⑳B欄+⑳C欄
(一括比例配分方式の場合)
【4%適用分⑳B欄】
⑰B欄 ± ⑱B欄 ± ⑲B欄
【6.3%適用分⑳C欄】
⑰C欄 ± ⑱C欄 ± ⑲C欄
【合計⑳D欄】
⑳B欄+⑳C欄
〈(22)欄〉 貸倒回収に係る消費税額
前課税期間以前において、貸倒れに係る消費税額として処理したものが当課税期間において回収できた場合には、以下の算式で計算した金額を記載する。
【4%適用分(22)B欄】
貸倒回収の金額×[4/105]
【6.3%適用分(22)C欄】
貸倒回収の金額×[6.3/108]
【合計(22)D欄】
(22)B欄+(22)C欄
この付表2-(2)を上記に従って作成し、各欄の中に「付表1へ」と記載がある部分は、そのまま付表1に記載することとなる。
次回は付表1と確定申告書の作成の流れを確認する。
(了)