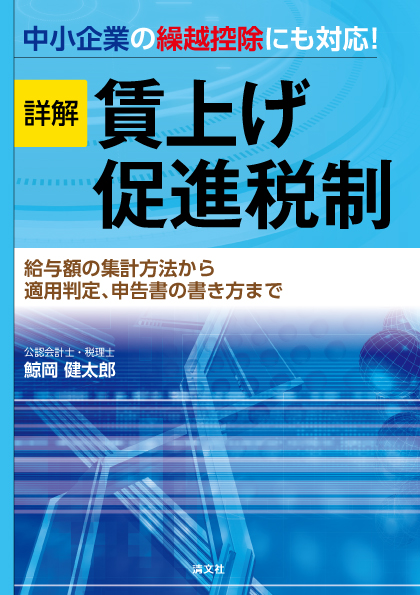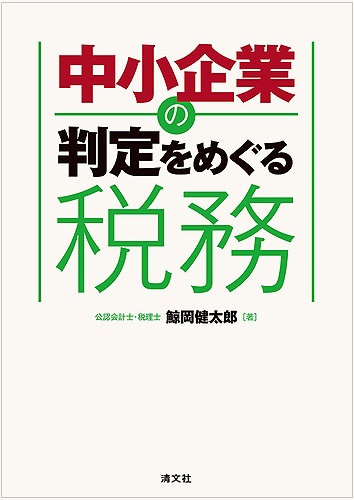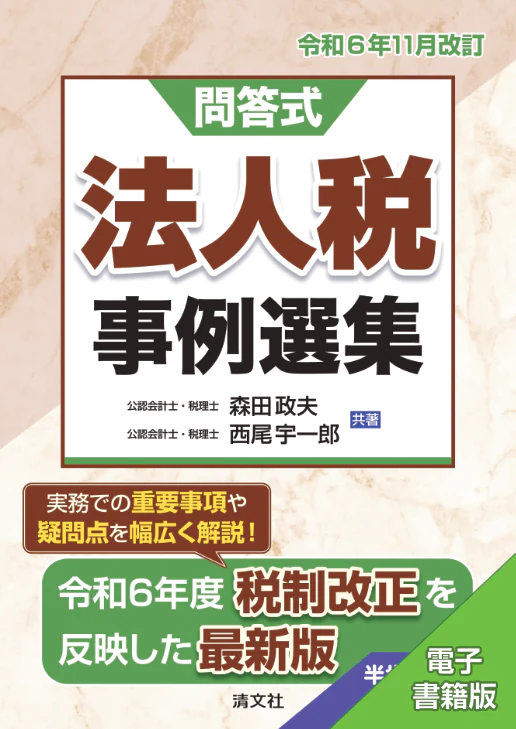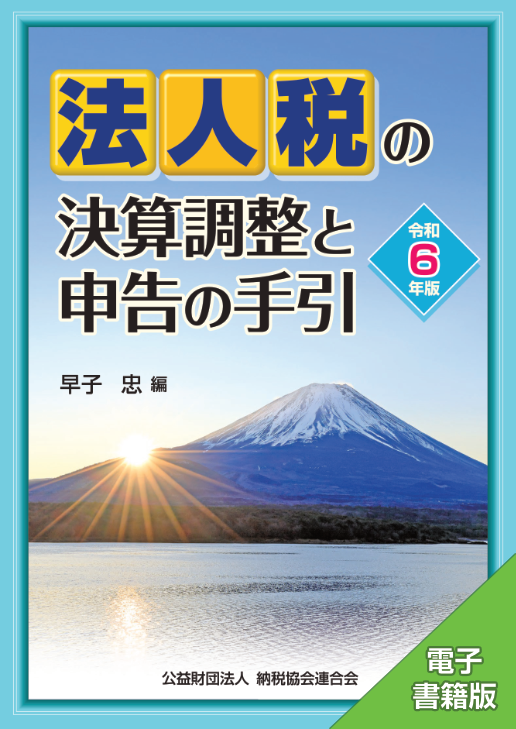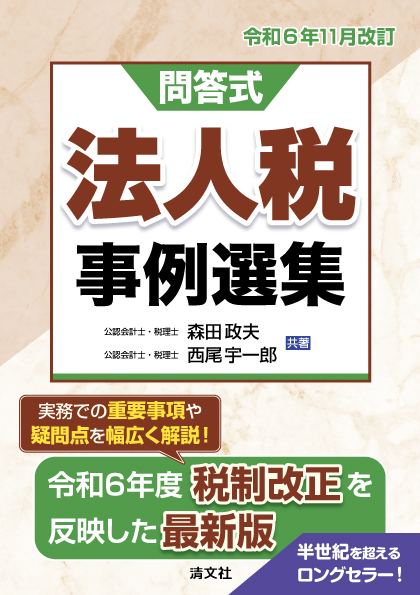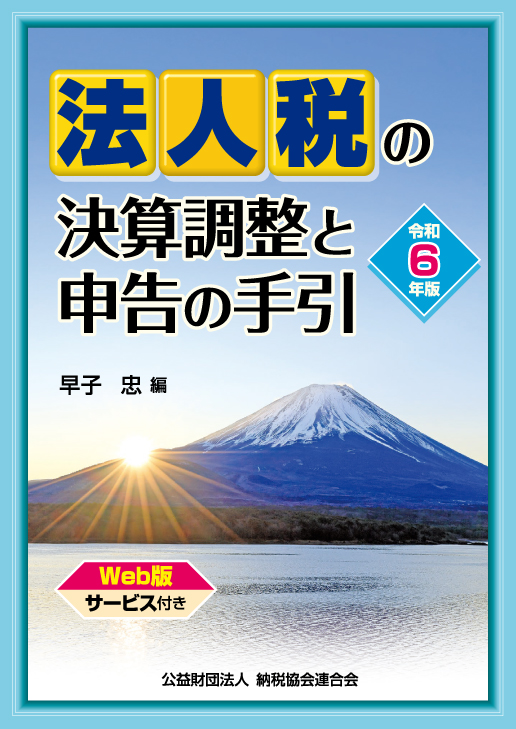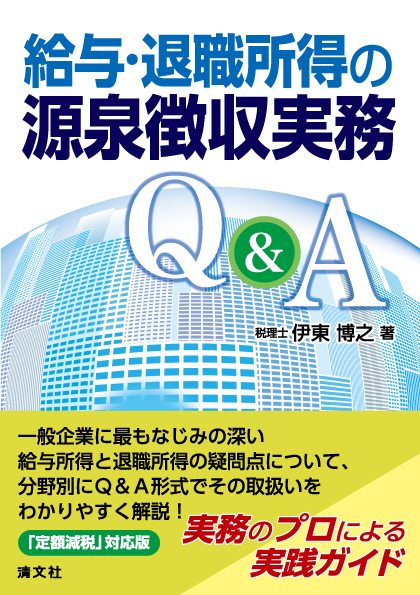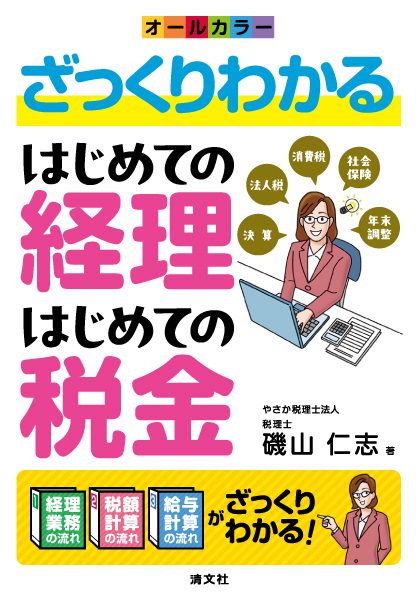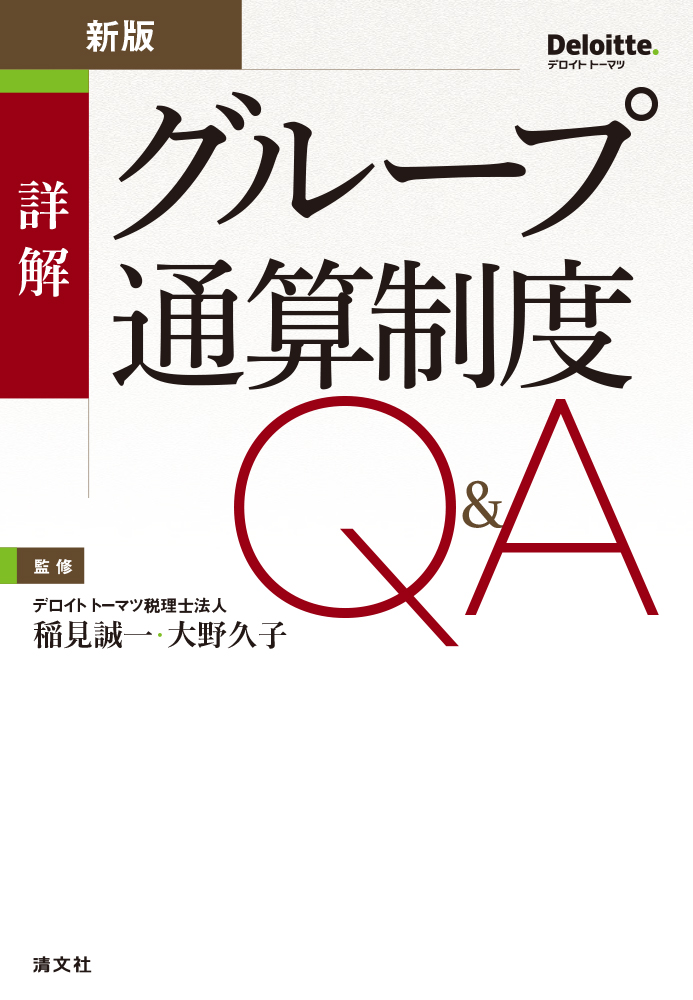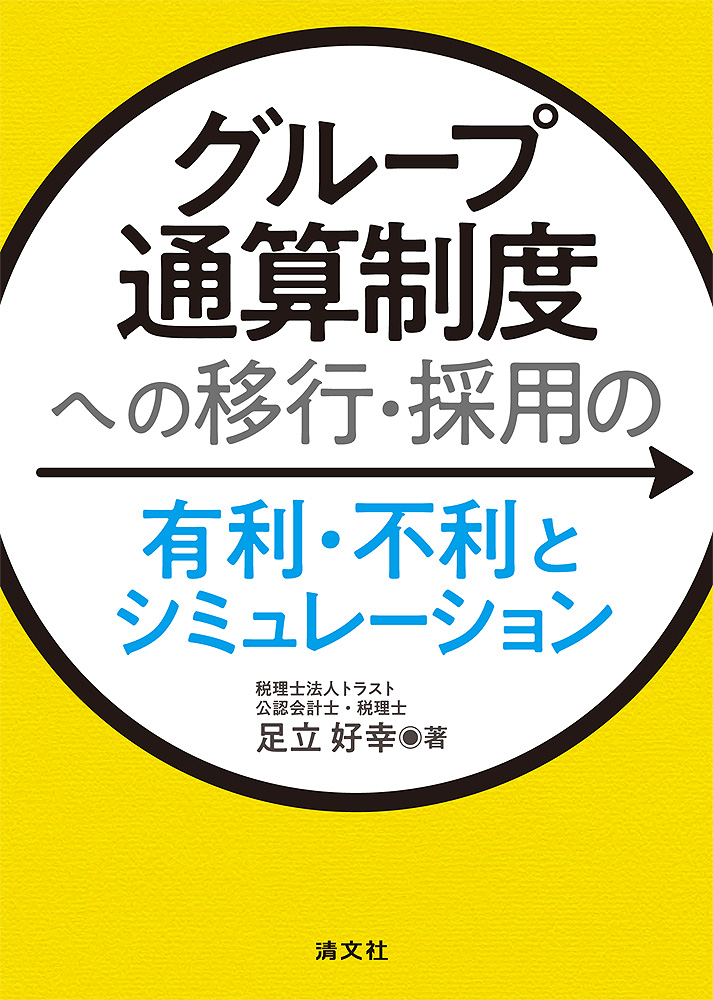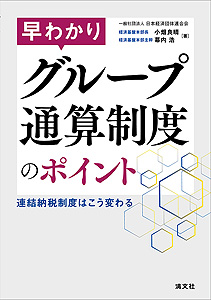〔令和4年度税制改正における〕
賃上げ促進税制の抜本的見直しについて
【第3回】
(最終回)
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
4 上乗せ控除のための要件
改正後の賃上げ促進税制においても、一定の要件を満たした場合に税額控除率の引上げ措置が設けられている。具体的には下表のとおりである(措法42の12の5①②)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。