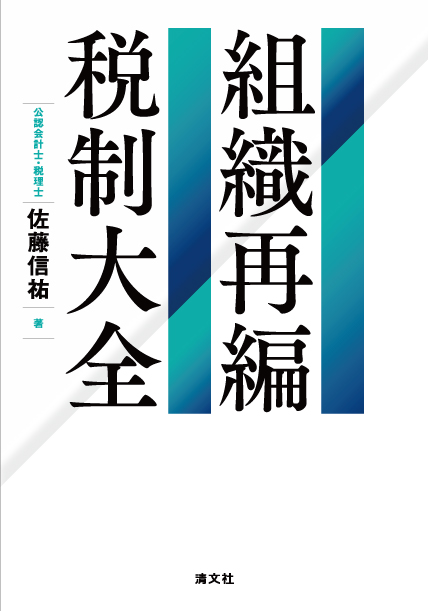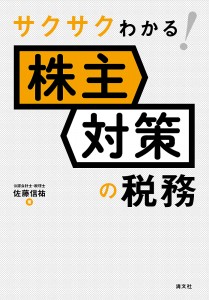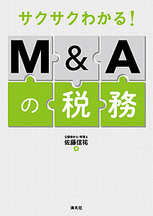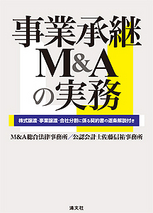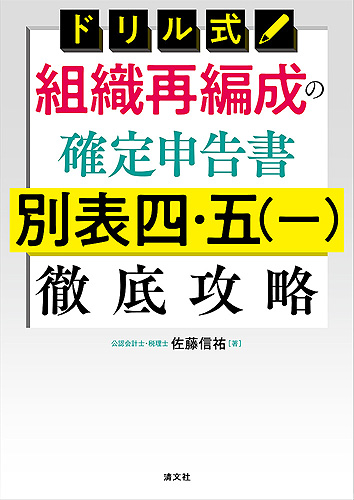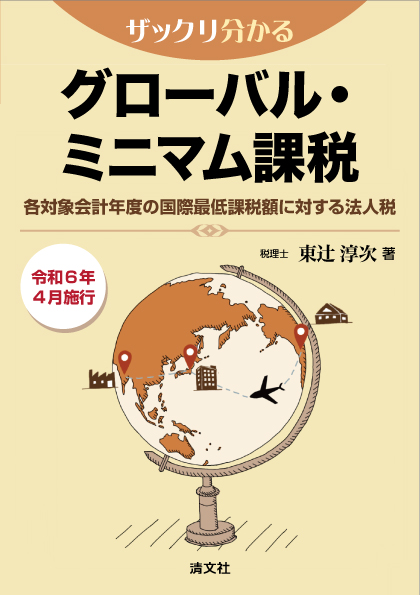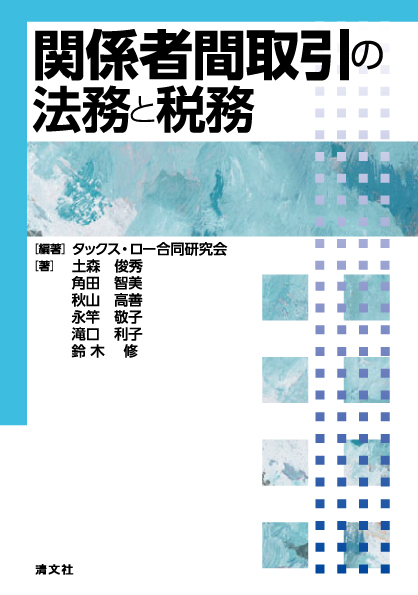〈徹底分析〉
租税回避事案の最新傾向
【第1回】
「はじめに」
公認会計士 佐藤 信祐
1 はじめに
令和4年4月19日、同月21日と最高裁判決が立て続けに下された。平成28年2月29日の最高裁判決(ヤフー・IDCF事件)を含めると、租税回避に対する最高裁の考え方が概ね示されたと考えられる。令和4年4月19日及び同月21日の最高裁判決に係る調査官解説もいずれ公表されると思われるが、今後、クライアントからの節税の相談に応じる際には、これらの最高裁判決を理解しておく必要がある。
平成28年2月29日の最高裁判決を参考にすると、組織再編成に係る包括的租税回避防止規定(法法132の2)の適用については、①法人の行為又は計算が不自然なものであるかどうか、②税負担減少目的以外の事業目的が十分に認められるかどうか、③税負担減少の意図があったかどうか、④制度趣旨に反するかどうか、の4点により検討されることになる。その後のTPR事件(東京高判令和元年12月11日)及びPGM事件(国税不服審判所令和2年11月2日裁決)でも同様の検討がされていることから、上記4点により包括的租税回避防止規定の適用が検討されるという理解で差し支えがないと思われる。
ここで問題となるのが、③の「税負担減少の意図」である。最近の税務調査では、メールを閲覧したり、反面調査をしたりすることで、税負担減少の意図を探ろうとする試みが見受けられる。ただし、「税負担減少の意図」を「税負担が減少することを知っていた」と解するのであれば、組織再編成を行うに際し、租税法上の検討を行わないということはあり得ないため、法人税の負担が減少する組織再編成のすべてに「税負担減少の意図」があるといえてしまう。このようなものについてまで、「税負担減少の意図」があったことを理由に租税回避として認定すべきでない。
「組織再編成を行うに際し、税負担を減少させようとした」と解するのであれば、租税回避に該当する余地があるのかもしれない。ただし、例えば、不採算の子会社を清算する場合において、当該子会社の清算により、親会社において子会社整理損失が計上されたり(法基通9-4-1)、子会社の繰越欠損金が引き継がれたりすることがある(法法57②)。不採算の子会社であれば、事業を廃止し、会社を清算することに、十分な事業目的が認められるはずであるが、親会社の法人税の負担が減少することが分かれば、それを意識した子会社の清算にならざるを得ない。このような場合であっても、「税負担減少の意図」があるものと考えるべきなのだろうか。
広辞苑によると、「意図」とは、「あることを(実現)しようと考えること。また、考えた事柄。もくろみ。ねらい。」と定義されている。すなわち、上記のような子会社の清算については、法人税の負担を減少させることが主目的だったとはいえないものの、日本語を素直に読めば、「税負担減少の意図」があったと解さざるを得ない。そのため、税務調査においても、税負担減少の意図があったと認定しようとしてくるのかもしれない。
ただし、平成28年2月29日の最高裁判決では、①法人の行為又は計算が不自然なものであるかどうか、②税負担減少目的以外の事業目的が十分に認められるかどうか等の事情を考慮したうえで、「当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否か」を検討すべきであるとしている。
すなわち、「組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したもの」とは、不自然な行為又は計算が行われ、かつ、税負担減少目的以外の事業目的が十分に認められないことが前提となっている。そして、調査官解説でも「組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであること(租税回避の意図)」(※1)と表記されていることから、最高裁判決における「税負担減少の意図」は「租税回避の意図」のことを意味し、一般的な「税負担減少の意図」とは明らかに異なるものである。本稿では、一般的な用語としての「税負担減少の意図」と区別するために、租税回避に該当する「税負担減少の意図」のことを「税負担減少の意図(租税回避の意図)」と表記するものとする(※2)。
(※1) 徳地淳・林史高「判解」法曹時報69巻5号300頁(平成29年)。
(※2) 本稿公表前における著者の文献及び講演資料では、一般的な用語としての「税負担減少の意図」をそのまま使用してしまったため、「税務調査において税負担減少の意図を否定することは難しい」と説明していたが、ここでいう「税負担減少の意図」とは「税負担減少の意図(租税回避の意図)」とは異なるものである点にご留意されたい。すなわち、組織再編成を行うに際し、租税法上の検討を行わないということはあり得ないことから、税務調査において「税負担減少の意図」を否定することは難しいが、経済合理性や事業目的が十分に認められることを説明すれば、「税負担減少の意図(租税回避の意図)」を否定することはできるのである。
このように、「税負担が減少することを知っていた」という程度では租税回避と認定することはできず、「組織再編成を行うに際し、税負担を減少させようとした」としても、事業目的が十分に認められるのであれば、租税回避として認定することはできない。すなわち、前述のように、法人税の負担が減少する組織再編成のすべてに「税負担減少の意図」があると認められるものの、事業目的も十分に検討したうえで組織再編成を行うことから「税負担減少の意図(租税回避の意図)」も認められる事案は稀である。
換言すると、法人の行為又は計算が不自然なものであり、かつ、税負担減少目的以外の事業目的が十分に認められない場合に限り、「税負担減少の意図(租税回避の意図)」があったといえることから、包括的租税回避防止規定の検討では、(A)法人の行為又は計算が不自然なものであるかどうか、(B)税負担減少目的以外の事業目的が十分に認められるかどうか、(C)制度趣旨に反するかどうかの3つを中心に、包括的租税回避防止規定の適用を検討すべきであり、一般的な意味としての「税負担減少の意図」があったかどうかについては、さほど重要ではないはずである。
2 租税法律主義
前述のように、最近の税務調査や税務訴訟では、過度な節税に対して厳しい対応がなされているが、これは時代の流れであるように思われる。かつては認められていたものが、法律や慣習の変化により認められなくなってくることは様々な産業で起きており、最近の事案だと節税のための保険商品が挙げられる。
租税法律主義についても同じことがいえる。もともと、租税法律主義は、国王が法律に基づかずに税を徴収することを防ぐために、西洋諸国で導入されたものである(※3)。我が国でも、日本国憲法において租税法律主義が定められており(憲法84)、租税回避の範囲を安易に広げることは、法的安定性の観点から問題がある。
(※3) 下村芳夫「現代における租税の意義について-租税法律主義の歴史的考察を中心として-」税大論叢5号1-31頁(昭和47年)参照。
これに対し、令和4年4月19日の最高裁判決では、「本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する」と判示された。すなわち、節税のために税理士に高い報酬を支払うことのできる富裕層とそれができない中間層との間に著しい不公平があることから、過度な節税に対して厳しい対応をすべきであるということだと思われる。
自由主義国家という観点からは、明確な法律の規定に基づかずに、租税回避であることを理由として更正処分を行うことは望ましくはないのかもしれない。これに対し、福祉国家という観点からは、富裕層が税理士に高い報酬を支払って、税負担を減らそうとすることも望ましくはないはずである。本最高裁判決を見る限り、自由主義国家の観点からではなく、福祉国家の観点から租税法律主義を捉えようとしており、従来の租税法律主義の考え方とは異なる可能性がある。
そうなると、租税法規が予定していたものなのか、制度趣旨に反してはいないのかという点を常に検討せざるを得ないし、もし、租税法規が予定したものではなく、かつ、制度趣旨にも反しているものの、経済合理性や事業目的が十分に認められる場合には、それを税務調査及び税務訴訟で説明できるようにしておく必要があるということがいえる。
〔凡例〕
法法・・・法人税法
法基通・・・法人税基本通達
(例)法法57②・・・法人税法57条2項
(了)
「〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向」は、毎月第2週に掲載されます。