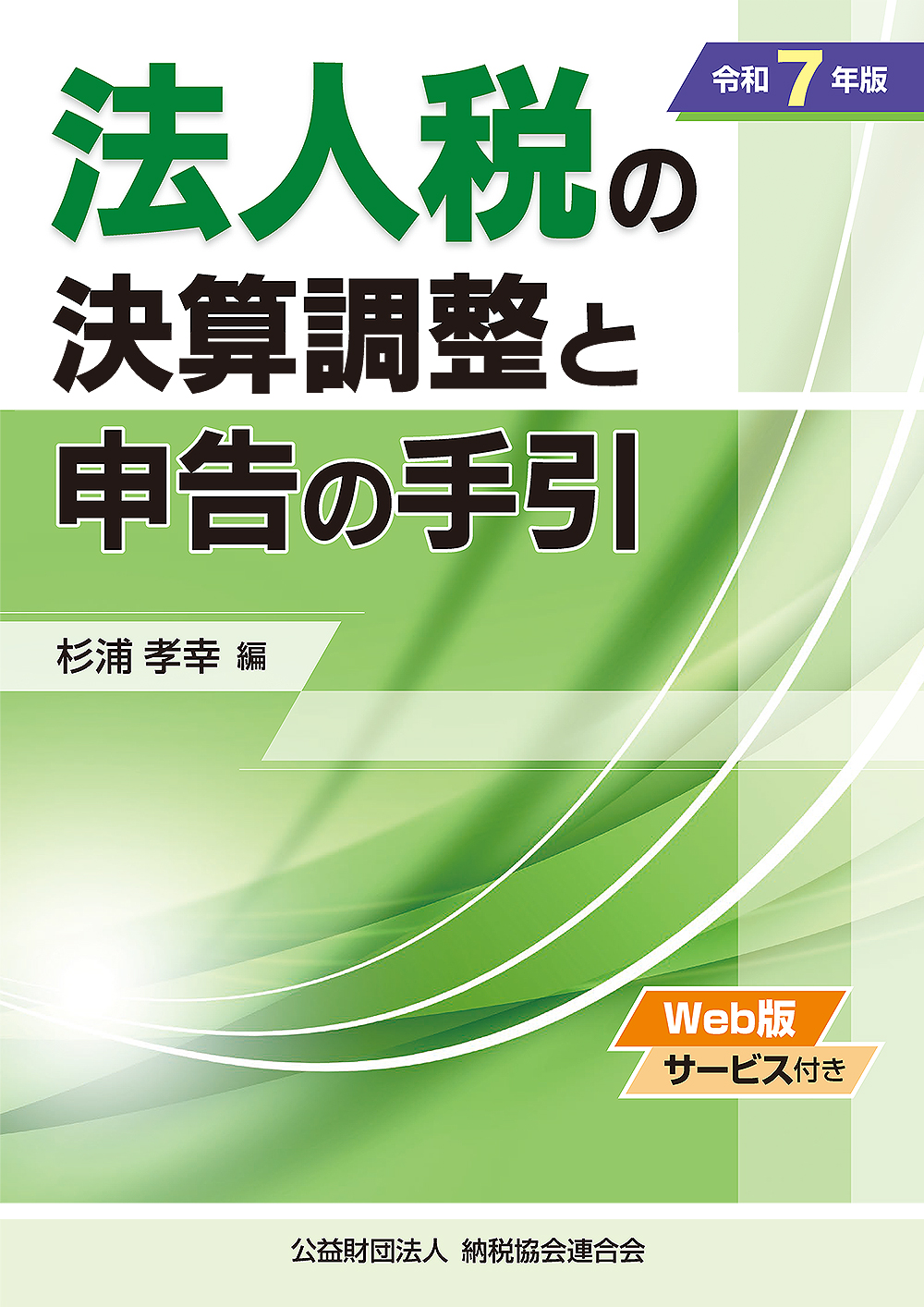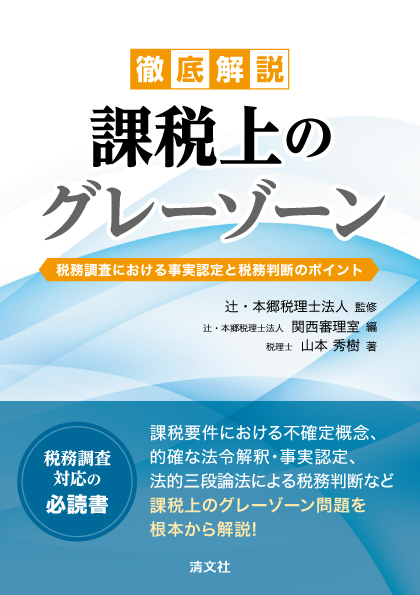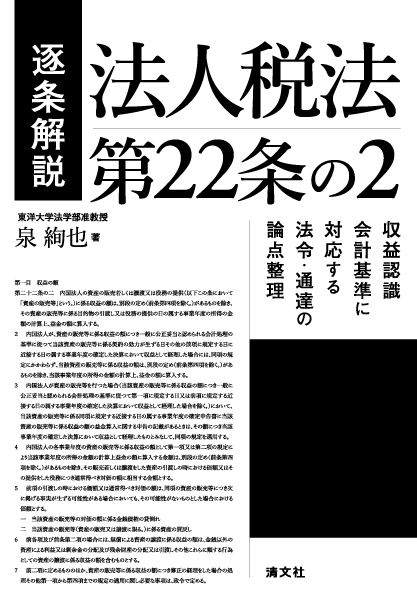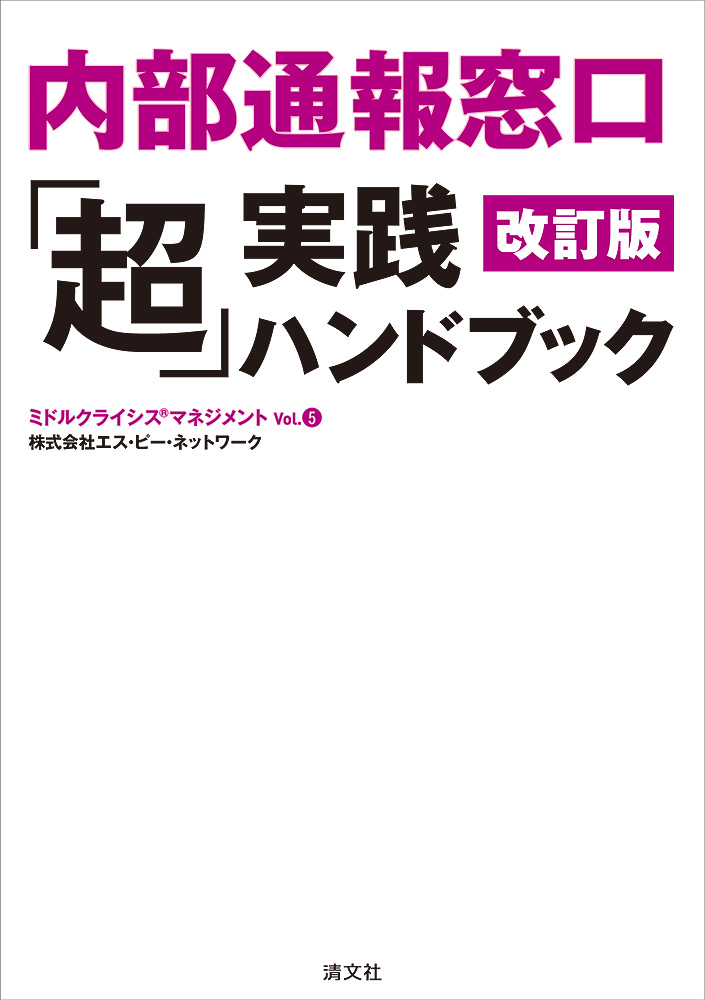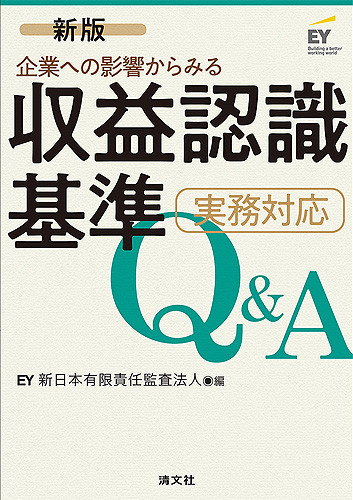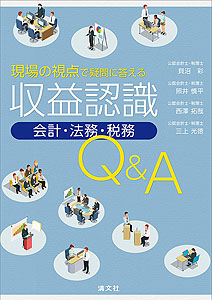法務・会計・税務からみた循環取引と実務対応
【第3回】
「会計からみた循環取引」
弁護士・公認不正検査士 下尾 裕
1 会計からみた循環取引の問題点
企業会計(財務会計)は、経営者・株主・債権者等に対し財務会計の利益計算を報告することで、これら関係者の利害調整機能を果たすとともに、特に上場企業又は有価証券報告書提出会社(上場企業等)においては、投資家に対する情報提供機能を果たしている。
よって、企業は、財務諸表ないし決算書の作成に際しては、当該企業の経済活動実態を正確に反映する必要があり、仮に財務諸表等に記載された企業の財務状態とその実態に大きな齟齬があれば、借入に際し自社の財務諸表又は決算書を提出しているであろう金融機関等の債権者、さらに、特に上場企業等については株主・投資家との関係で、それぞれ大きな問題が生じることになる。
この点、例えば、企業が物品の売買により循環取引を行っている場合、当該企業は、自らの直前の売主との売買契約に基づき「資産」としての棚卸資産(商品・製品等)を取得し、その後、当該棚卸資産の買主との売買契約に基づき売上を認識するという会計の流れを繰り返すことになるが、上記で述べた企業会計の機能に鑑みれば、このような会計処理を通じて計上された収益(さらにはその前提となる棚卸資産の取得等)は、前提となる取引に経済合理性がない限り、原則として、収益等として取り扱われるべきではないという結論になろう。
そこで、本稿においては、循環取引において主に問題となる収益の認識(計上)について理論的な整理を行った上で、実際に循環取引が発覚した場合に、実務上しばしば問題となる過年度決算修正(循環取引が複数事業年度にわたり継続された場合における会計処理の修正方法)等について解説を行う。
2 循環取引に基づく収益の認識に関する理論的整理
(1) 企業会計における収益認識の考え方
企業がいつの時点で収益を認識すべきかという問題については、現行の企業会計原則においては、実現主義、すなわち、以下の2点が充足された時点で収益を認識すべきものと考えられている(企業会計原則「第二 損益計算書原則」「三」「B」本文)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。