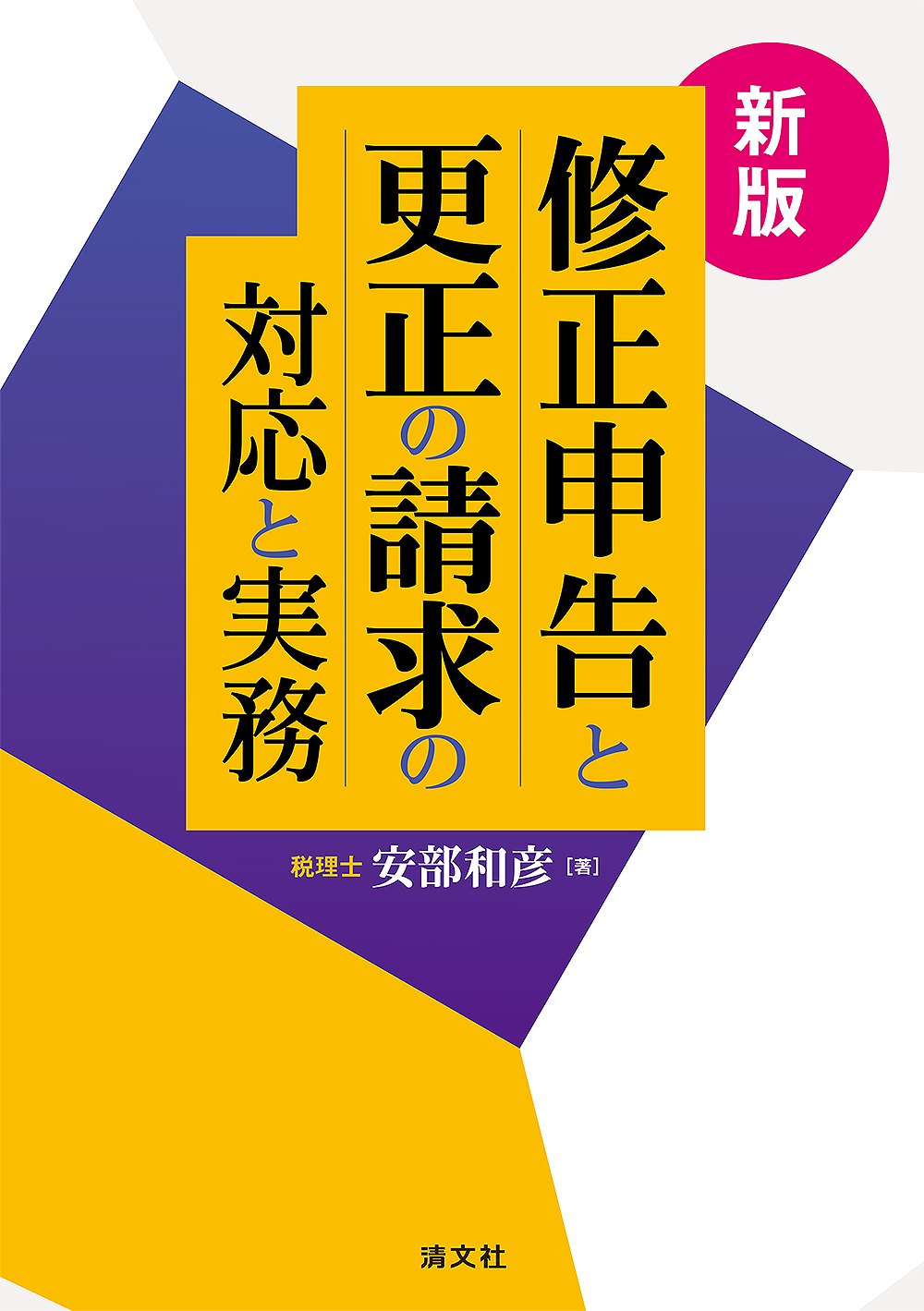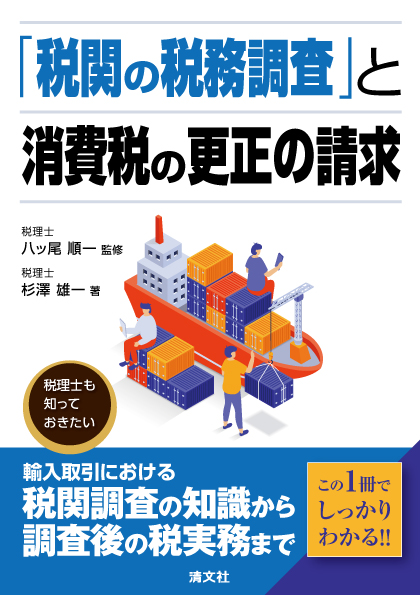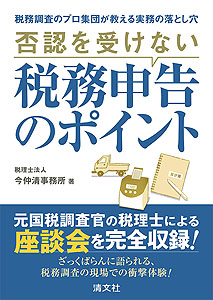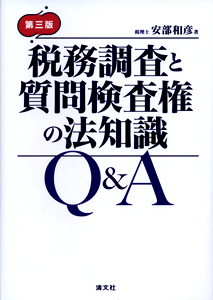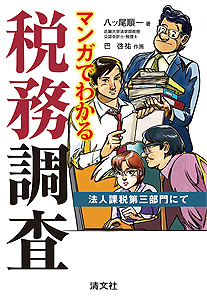「更正の予知」の実務と
平成28年度税制改正
【第1回】
税理士 谷口 勝司
連載の目次はこちら
-はじめに-
過少申告加算税、重加算税等の加算税は、延滞税や利子税とともに「附帯税」と称され(通則法60~69)、その名が示すとおり、法人税や所得税等の本税に附帯するものである。
加算税は、法人税等の本税ほどその取扱いが問題となることはないものの、修正申告、更正、税務調査といった場面で、加算税固有の疑義が生ずることがある。
本稿の主題である「更正の予知」は、修正申告書提出に伴う過少申告加算税について、例外的にこれを免除する取扱いである。
平成28年度税制改正において、税務調査に係る事前通知から更正の予知までの間に提出された修正申告書について、新たに5%の過少申告加算税を賦課するという、実務上重要な改正が行われている。また、法定化された税務調査手続が平成25年1月以降実施され、加算税や更正の予知の取扱い実務にも影響を与えていると思われる。
そこで本稿では、以上のことを踏まえつつ、「更正の予知」に関し、その実務上の取扱いと平成28年度税制改正について、順次説明していくこととしたい。
なお、本稿中意見にわたる部分は、私見であることをあらかじめお断りしておきたい。
1 過少申告加算税と更正の予知の制度概要
(1) 過少申告加算税
過少申告加算税は、申告納税方式をとる法人税、所得税、消費税、相続税等の期限内申告書が提出された場合等において、その後修正申告書の提出又は更正があったときに、その修正申告又は更正に基づき納付すべき税額(以下「追加本税額」という)に対し、原則10%の割合で、賦課課税方式により課される加算税である(通則法65、16)。
要するに、過少申告加算税は、期限内申告を行った後に追加本税額が生じた場合にいわば自動的に賦課される加算税である。ただし、追加本税額が生じない修正申告又は更正(例えば、法人税の欠損金額を減少させるもの)の場合には、当然賦課されることはない。
加算税には、他にも無申告加算税、不納付加算税又は重加算税があるが、過少申告加算税は最も一般的なものといえよう。
10%の加算税割合には、いくつかの例外がある。一つは、いわゆる二段階制であり、追加本税額が、期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超える場合は、その超える部分については5%加重されて15%の割合となる(通則法65②③)。また、もう一つは国外財産調書又は財産債務調書に関するもので、5%加重又は5%軽減の措置が講じられている(国外送金等調書法6、6の3)が、詳しくは割愛する。
さらに、後述する平成28年度税制改正では、調査に係る事前通知後は5%の割合で新たに賦課されることになった。
(2) 更正の予知
過少申告加算税の賦課が例外的に免除される規定として、「更正の予知」がある。
すなわち、国税通則法第65条第5項では、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る事前通知がある前に行われたものであるときは、過少申告加算税を賦課しない旨を規定している(下線部分は平成28年度改正箇所)。
平成28年度改正後の規定はやや読みにくいところがあるが、ごく簡単にいえば、更正の予知・事前通知のいずれもない場合において提出された修正申告書(換言すれば、納税者からの自発的な修正申告書で、実務上は自主修正とも呼ばれる)については、過少申告加算税を賦課しないとするものである。
なお、無申告加算税には「決定の予知」という軽減規定があるが、その規定振り等は更正の予知とほぼ同じであり、さらに、不納付加算税には「納税の告知の予知」という軽減規定がある。
2 平成28年度税制改正
今般の平成28年度税制改正において、加算税制度について何点かの改正が行われた。
その改正点の中で、更正の予知に関するものとして、
調査対象税目、調査対象期間及び実地の調査において質問検査等を行う旨(事前通知を要しない場合には実地の調査を行う旨)の通知以後、かつ、その調査があったことにより更正があるべきことを予知(更正の予知)する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(改正前:0%)については、5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とする。
という改正が行われた(通則法65①②⑤、通則令27③)。
改正前は、更正の予知がある前に提出された修正申告書については過少申告加算税が賦課されなかった(免除されていた)ところ、改正後は、更正の予知がある前に提出された修正申告書であっても、調査に係る事前通知以後に提出されたものである場合には、新たに原則5%の過少申告加算税の賦課を行うというものである。
なお、無申告加算税についても、上記と同様に、調査に係る事前通知から決定の予知までの間は、原則10%(改正前:5%)の割合とする改正が行われたが、源泉所得税に係る不納付加算税についてはこのような改正は行われていない。
これらの改正は、いずれも、平成29年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用される(改正法附則54③)。
平成25年1月以降、法定化された調査手続規定に基づき、実地の調査(国税の調査のうち、当該職員が納税義務者の支配・管理する場所(事業所等)等に臨場して質問検査等を行うものをいう。以下同じ)については、納税者(税務代理人を含む)に対して事前通知が原則行われているが(通則法74の9①)、今回の改正は、この事前通知の直後に多額の修正申告等を行うことにより(更正の予知がないとして)、加算税の賦課を回避している事例が散見されたことが背景にあったと趣旨説明がなされている(下記参照)。
当初申告のコンプライアンスを高める観点から行われた今回の改正は、自身の申告が過少申告であることを知っている納税者が事前通知を受けてから修正申告書を提出する、あるいはあえて過少申告をしておいて事前通知を受けてから修正申告書を提出する、といった不誠実・悪質な行為を抑制するものであって、後述する加算税制度の趣旨に沿うものであろう。
なお、実地の調査であっても、国税当局が保有する情報等から、事前通知を行うことにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、法令上事前通知を要しない(通則法74の10)こととされている(※)。また、実地の調査以外の調査(この点は後述)についても、事前通知を行うことが法律上義務付けられておらず(通則法74の9①)、これらの調査は実務上、いわゆる事前通知は行われていない。
(※) 事前通知を行うことなく実地の調査を実施する場合には、実務上、臨場後速やかに、調査対象税目、調査対象期間、実地調査を行う旨等を納税者に説明することが通達(平成24年9月12日付 課総5-11ほか「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(以下「調査運営通達」という))に定められている。
これらの調査と今回の税制改正との関係について現時点で明らかにされているものはないが、事前通知や後述する更正の予知に関するこれまでの税務執行・取扱いに変更がないことを前提にすれば、これらの調査に係る過少申告加算税の取扱いについては、今回の税制改正による影響はないと見込まれる。
また、次の①及び②の修正申告等については、今回の改正による加算税の対象外となることが、今後通達等において示される予定である、と説明されている(前掲「平成28年度税制改正の解説」874頁参照)。
① 次のように調査対象が区分される場合において、調査通知がされる調査の対象となっていない部分についての修正申告
イ 調査通知の際に納税者の同意の上、移転価格部分とそれ以外の部分に区分して調査が行われる場合
ロ 一部の連結子法人の調査を行わないこととした場合
② 次のように調査通知の時期に関わらず、一定の時期に提出が予定されている修正申告等
イ 他の税目における更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目において必要となる修正申告又は期限後申告
ロ 相続税又は贈与税について、遺産分割が確定するなどして任意に行う修正申告又は期限後申告
上記①について若干敷衍すると、現行の法人税の調査実務では、納税者の事前の同意がある場合には、法人税調査を「移転価格調査」と「それ以外の部分の調査」に区分して別々の調査として実施するという運用が行われている。これは、移転価格調査は通常長期間にわたることが多いこと等の理由から、1つの納税義務ではあるものの、納税者の負担軽減策のため、調査を区分して別々の調査として実施しようというものである。
この納税者の区分の同意を得て、例えば、「移転価格調査」を行うため事前通知を行った後、移転価格以外の部分に関して修正申告書が提出されたとしても、移転価格以外の部分について調査及び事前通知は行われていないため、28年度税制改正後においても、この修正申告について過少申告加算税は賦課されないことになるということであろう。また、このことは、連結納税の調査において、複数の連結子法人のうちの一部を調査対象として事前通知を行った場合に、調査対象以外の連結子法人に関して修正申告書が提出されたときも、同様である。
いずれにせよ、上記①及び②については、今後通達等で示される予定とのことなので、具体的な内容は通達発遣等を待つこととしたい。
ところで、今回の税制改正を契機に、例えば更正の予知とは具体的にいつの時点なのか等、改めて「更正の予知」とはどういうものか、調査などの税務執行において実務上どのように取り扱われているか等を理解しておくことが重要になってくると思われる。
そこで、次回以降、法人税の過少申告加算税に関する「更正の予知」を中心に、その取扱いを説明していくこととする。
〔凡例〕
・通則法・・・国税通則法
・通則令・・・国税通則法施行令
・国外送金等調書法・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
・法人税過少通達・・・法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)
・調査解釈通達・・・国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)
・調査運営通達・・・調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
(例)通則法74の9①一・・・国税通則法第74条の9第1項第1号
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。