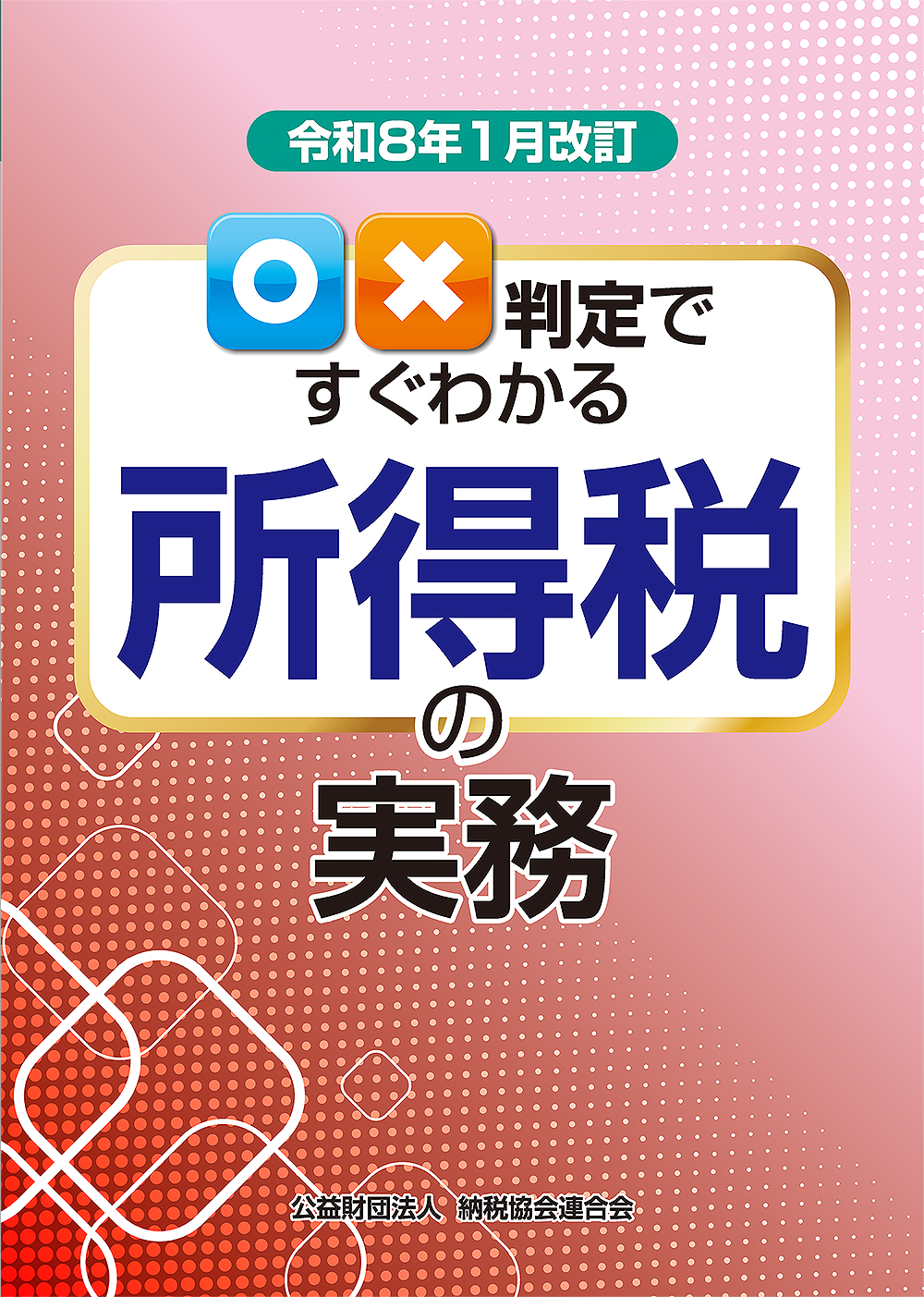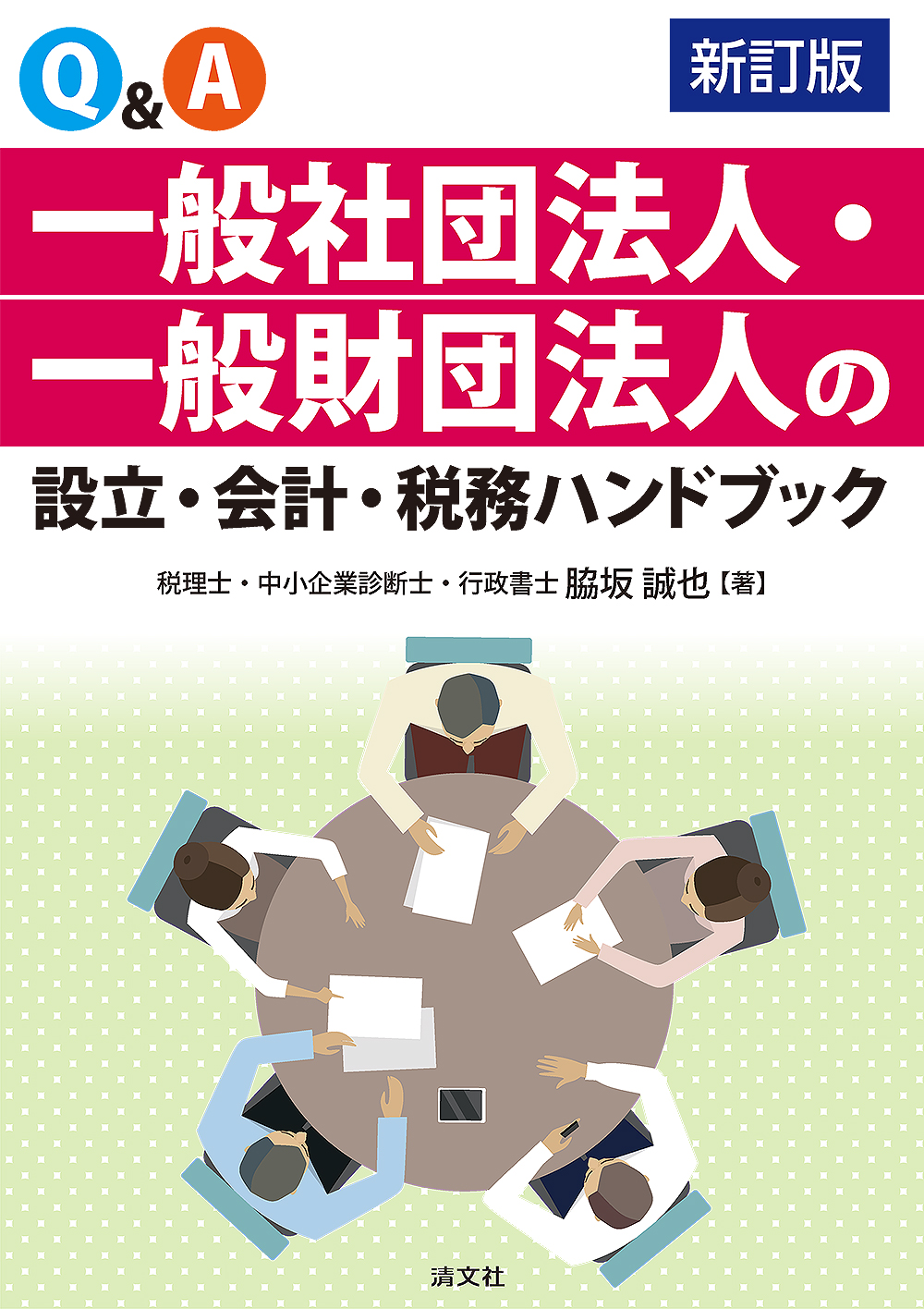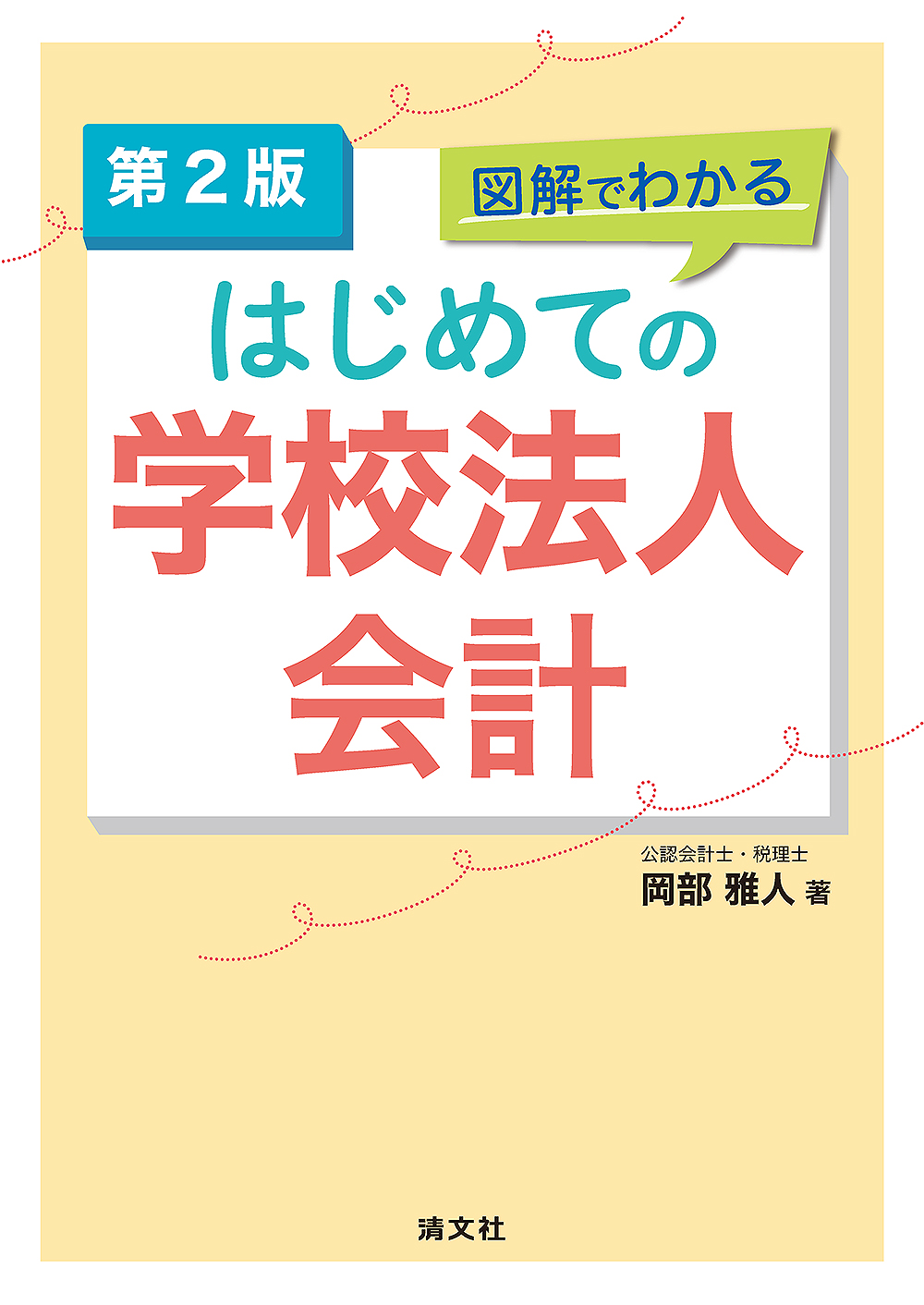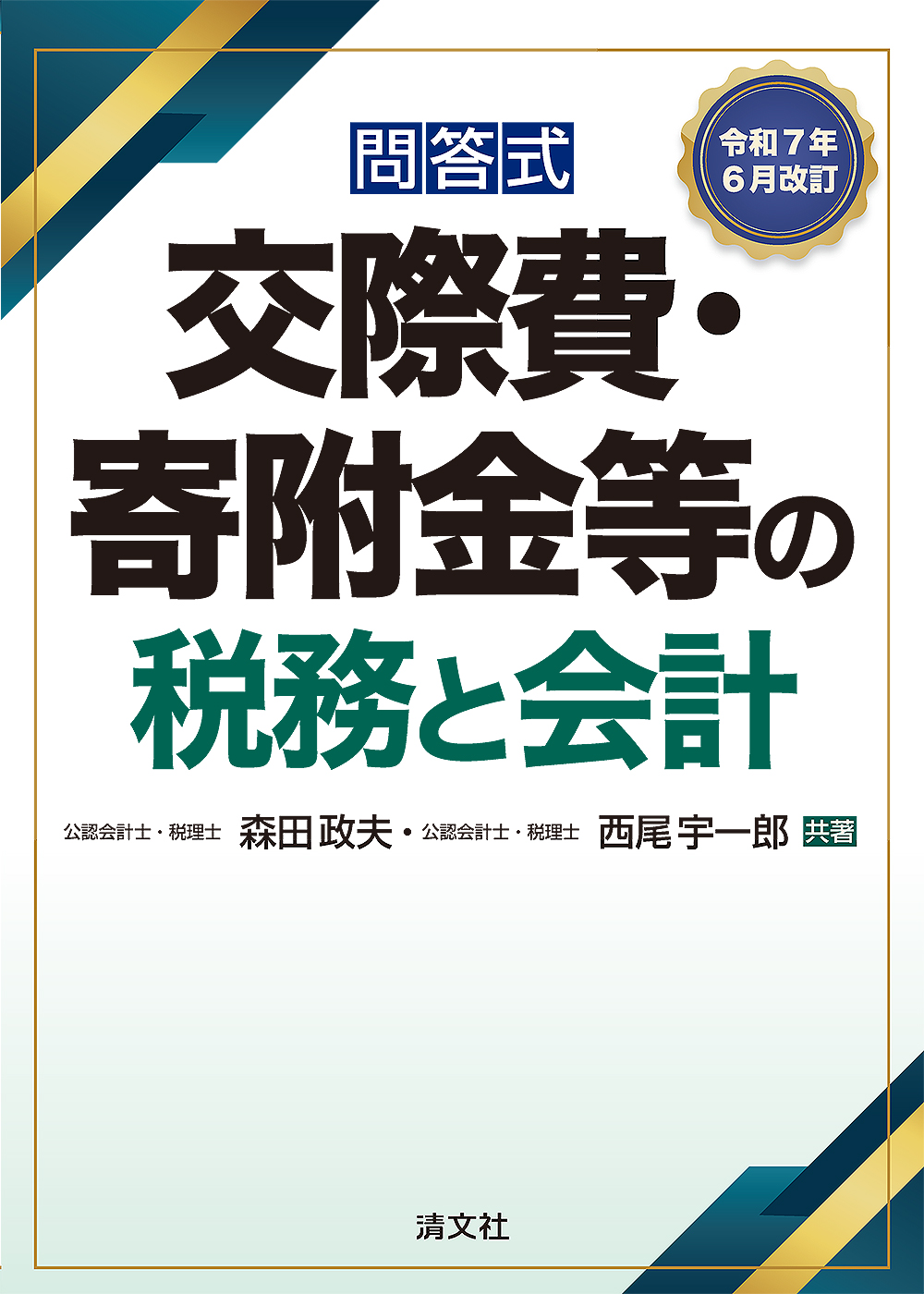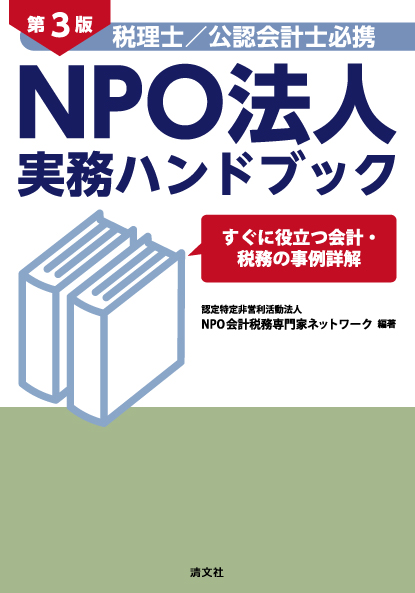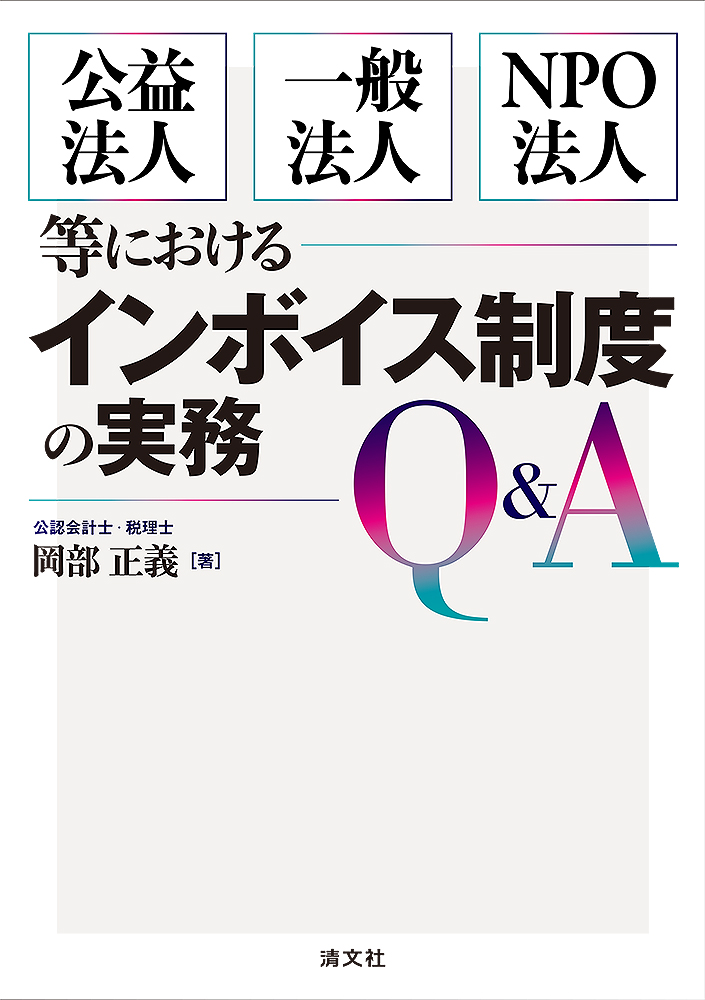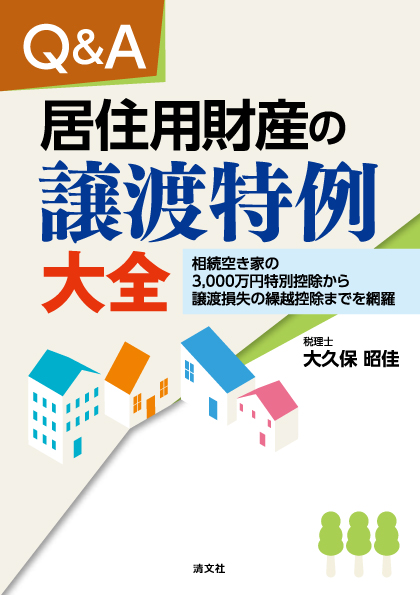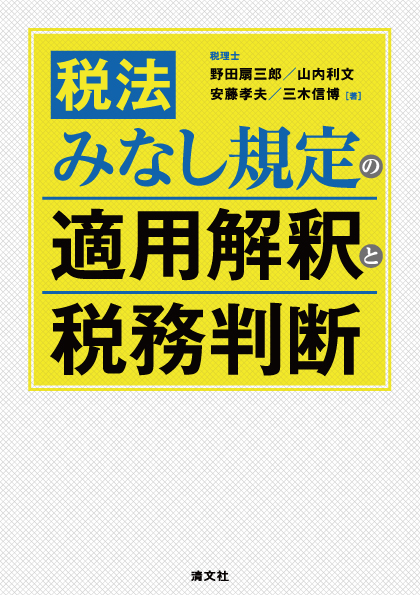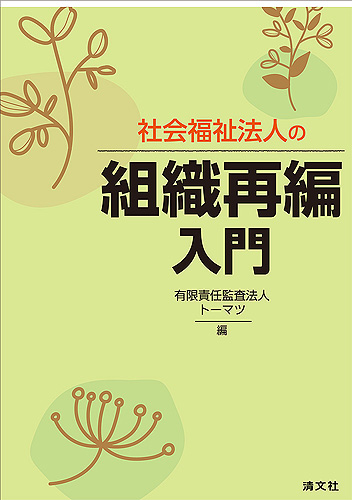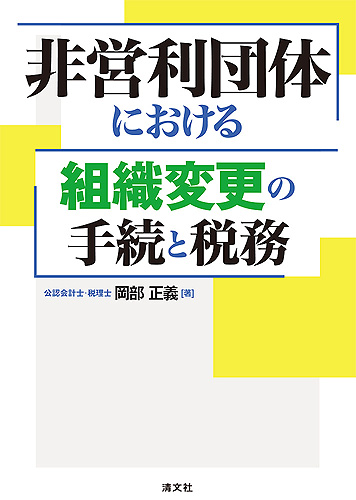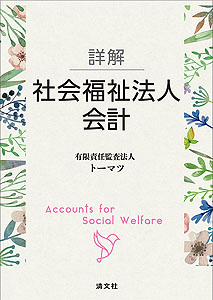措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の
譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント
【第1回】
「非課税措置の概要と承認特例の改正」
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
- 質 問 -
公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置とはどのようなものですか。また、その手続の簡素化が図られた承認特例制度について教えてください。
- 回 答 -
通常、無償で財産を寄附した場合、寄付者の個人に対しては時価で譲渡したものとみなされ譲渡所得税が課税されます。ただし、寄附の相手が公益法人等であり、その寄附が一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときには、当該所得税について非課税とする制度(以下「非課税措置」という)が設けられています。
また、手続きが簡素化された承認特例制度(以下「非課税承認特例」という)もあり、こちらの制度では、承認申請書を国税庁長官に提出した場合で、その提出した日から1ヶ月以内(株式の場合は3ヶ月以内)に、その申請について国税庁長官の承認がなかったとき、又は承認しないことの決定がなかったときは、その申請について承認があったものとみなされることになっています。
○●○◆ 解 説 ◆○●○
1 制度の概要
個人が、土地、建物などの財産を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課されます(所法59①一)。
ただしその寄附が公益法人等へのもので、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他の公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、当該所得税について非課税とする制度が設けられています(措法40①後段)。
2 非課税措置の承認要件
非課税措置に係る国税庁長官の承認を受けるには、その公益法人等に対する財産の寄附について、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります(措令25の17⑤)。
〈一定の要件〉
当該寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること
寄附財産が、寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該寄附を受けた法人の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること
当該寄附が寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること
3 非課税承認特例の制度
公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人に対する現物寄附、かつ、以下の要件がすべて満たされる寄附において、国税庁長官に承認申請書を提出した日から1ヶ月以内に、その申請について国税庁長官の承認がなかったとき、又は承認しないことの決定がなかったときは、その申請について承認があったものとみなされ、所得税は非課税とされます(措令25の17⑦⑧)。
〇寄附をした人が寄附を受けた法人の役員等及び社員並びにこれらの人の親族等に該当しないこと
〇寄附財産について、寄附を受けた法人の区分に応じ、必要な事項が定款に定められていること又は基本金に組み入れる方法により管理されていること
〇寄附を受けた法人の理事会において、寄附の申出を受け入れること及び寄附財産について不可欠特定財産とすること又は基本金に組み入れること等が決定されていること
なお、平成30年度税制改正により、次の場合も非課税承認特例の対象となりました。
➤国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人、国立高等専門学校機構又は国立研究開発法人(法人税法別表第一に掲げる法人に限る)に対する贈与等で、その贈与等に係る財産が一定の手続の下でこれらの法人の行う研究開発の実施等の業務に充てるための基金に組み入れられるもの
➤国立研究開発法人(法人税法別表第二に掲げる法人に限る)、公益社団法人又は公益財団法人に対する贈与等でこれらの法人の理事、監事、評議員その他これらに準ずるもの(その親族等を含む)以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が一定の手続の下でこれらの法人の行う研究開発の実施等の業務等に充てるための基金に組み入れられるもの
ただし、国立大学法人等については、寄附者が寄附を受けた法人の役員等及び社員並びにこれらの人の親族等に該当しないこと、の承認特例の要件は不要です。
また、株式についても新たに非課税承認特例の対象となりましたが、申請書の提出があった日から1月以内ではなく、3ヶ月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかった場合に、その承認があったものとみなされます。
〔凡例〕
所法・・・所得税法
措法・・・租税特別措置法
措令・・・租税特別措置法施行令
(例)所法59①一・・・所得税法59条1項1号
(了)
「措置法40条を理解するポイント」は、毎月最終週に掲載されます。