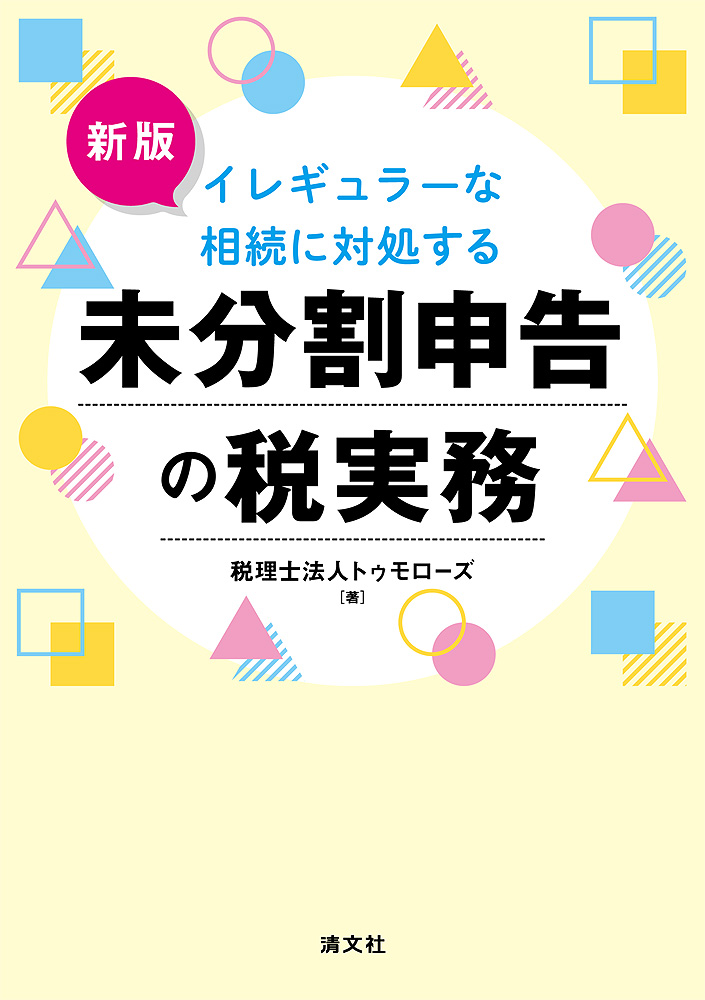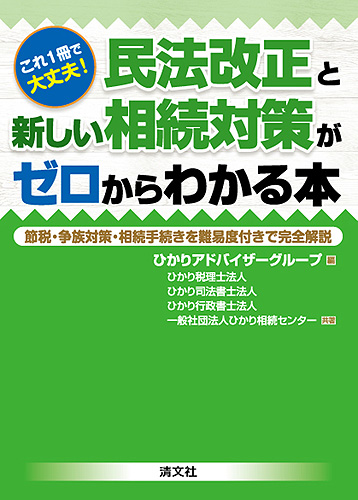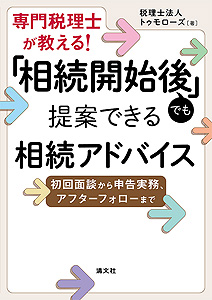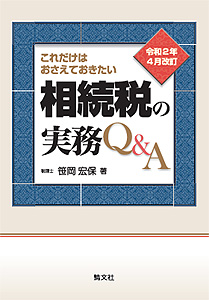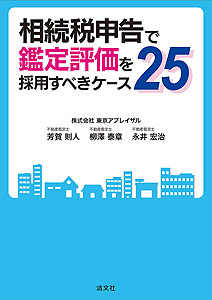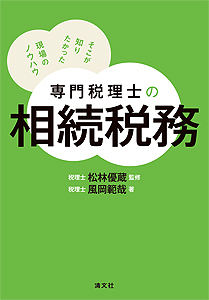〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第1回】
「申告業務に必要なこと」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
◆連載開始にあたって◆
平成25年度税制改正において、平成27年1月1日以降に発生する相続については、基礎控除が現行より4割引き下げられることが決定された(以下「相続税増税」という)。
国税庁統計年報によると、平成23年中の相続について、相続税が発生した相続税申告数は全国合計で51,559件となっている(この数値には、相続税がゼロの場合の相続税申告数は含まれていないため、税額が発生しない相続税申告数も含めた相続税申告数は、この数よりも多いことになる)。
相続税増税が行われると、相続税申告数が1.5倍程度に増加すると一般的には言われており、今後、相続税申告案件は増えることが予想されている。
そこでこの連載では、増えることが予想される相続税申告業務に備えて、理解しておくべき知識や実務上の注意点を、相続税増税時期までに、段階を踏んで説明していきたい。
〔はじめに〕
相続税申告業務には、「相続」という法律(民法)の基礎知識、「相続税」という税法の基礎知識のいずれもが必要となる。
加えて、相続税の財産評価を行う際に、土地(借地権を含む)の法令(建築基準法や借地借家法など)の基礎知識も必要となる場合がある。
細かなケースを含めてすべてを理解しようとすると、理解するまでにかなりの時間が必要となるため、相続税申告業務を専門にする方は別として、一般的なケースに限定し、まず必要な基礎知識を理解し、実際の実務で直面した問題についてはその都度、書籍や他の専門家に確認しつつ、業務を進めていく、ということが現実的な対応策となるだろう。
このため、「はじめての相続税申告業務」では、この一般的なケースに限定して、最低限、必要な知識を、相続の法律(民法)、相続の税金(相続税)の2つについて、理解していくことを目的としたい。
〔相続税申告業務の流れ〕
どのように相続税申告業務を獲得するか、また、報酬はいくらにすべきかという点は営業戦略の話となるため、この連載では省略するが、相続税申告業務を請け負った場合、どのように業務を進めていくのか、全体の流れをまず理解しておく必要がある。
その全体の流れに従って、最低限、必要な知識(民法、相続税)を理解していくことが、相続税申告業務を正確に行う最短の距離である。
したがって、まず、相続税申告業務の全体の流れについて学ぶこととする。
〈相続税申告業務の全体の流れ〉
1 相続人の確定
↓
2 相続財産の範囲・評価の確定
↓
3 相続財産の分割協議
↓
4 相続税申告書作成
↓
5 相続税納税準備
上記1から5の手続は、通常、他界した日から10ヶ月以内に完了させることになる。
これは相続税申告期限が、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められており(相続税法27条1項)、通常は、相続の開始があったことを知った日は、他界した日となるからである。
また、相続税は、原則、現金で一括して申告期限までに納付することになっている(相続税法33条)。
したがって、相続税申告業務を進めるにあたって、相続税申告期限は重要な日となるため、どのように算定すべきか、しっかりと理解しておく必要がある。
ここは重要なポイントとなるので、具体例を用いて説明したい。
【ケース1】
他界した日:平成24年4月1日(日)
相続税申告期限:平成25年2月1日(金)
平成24年4月1日に他界した場合、他界した日の翌日(平成24年4月2日)を起算日として10ヶ月を計算すると、平成25年2月1日となる。
つまり、相続税申告期限は、他界した日の10ヶ月後の応当日になる。
【ケース2】
他界した日:平成24年4月2日(月)
相続税申告期限:平成25年2月4日(月)
平成24年4月2日に他界した場合、他界した日の10ヶ月後の応答日は平成25年2月2日となる。
ただし、応当日が土日祝日の場合には、土日祝日に該当しない翌日(応当日が土曜日の場合、翌々日の月曜日になる)が相続税申告期限になる(国税通則法10条2項)ので、このケースでは他界した日の10ヶ月後の応当日である平成25年2月2日は土曜日であるため、土日祝日ではない翌々日である平成25年2月4日が相続税申告期限となる。
上記で述べた相続税申告業務の全体の流れのうち、1から3は相続税申告が必要か否かにかかわらず、相続を完了させるためには行わなければならない手続である。
一方、相続税申告業務の全体の流れのうち、4及び5は相続税に特有の手続となる。
別の観点からいえば、相続税申告業務の全体の流れのうち、1から3は相続の法律(民法)上、必要とされている手続であり、4及び5は、相続の税金(相続税)上、必要とされている手続といえる。
「3 相続財産の分割協議」で、財産分けの合意ができないまま(「未分割」という)、相続税申告を行うこともあるが、その場合には、当初申告時においては、小規模宅地特例や配偶者税額軽減など特例が適用できず、結果として相続税の納税額が大きくなる(*)ので、通常は、この3を完了させ、財産分けの合意をした上で、相続税申告を行うことが大半である。
次回は、相続税申告業務の全体の流れについて、その内容の概略について見ていきたい。
(*)未分割の状態で相続税申告を行った場合でも、当初申告で「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、申告期限から3年以内に分割できた場合、更生の請求を行うことで、特例の適用を行い、相続税を還付することができる。ただし、その場合でも、当初申告時には、特例の適用ができないため、特例の適用がない状態で相続税申告を行い、その計算に基づいて算定された相続税を、原則として、申告期限までに現金で一括して納付する必要がある。
(了)
「〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務」は、隔週の掲載となります。