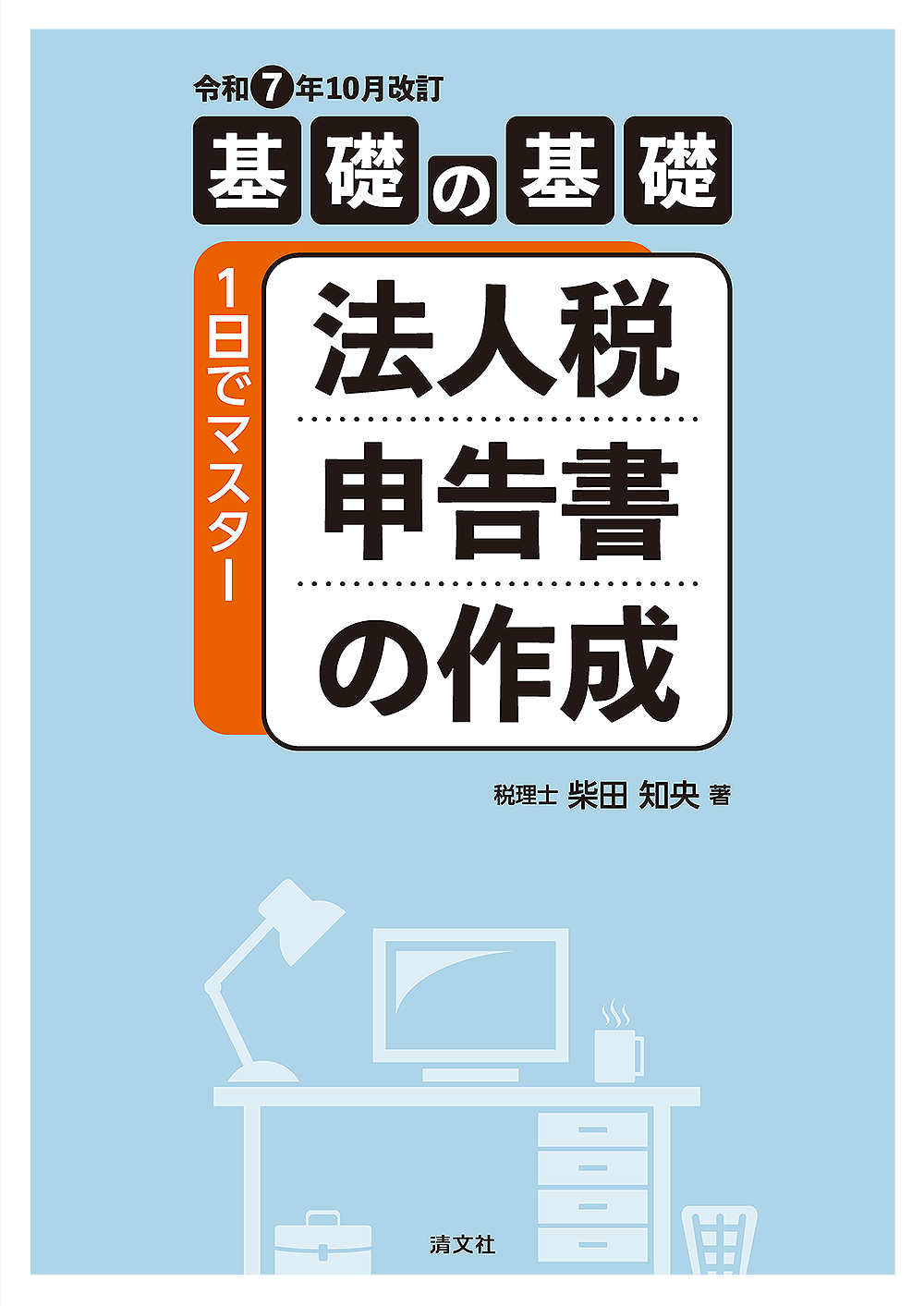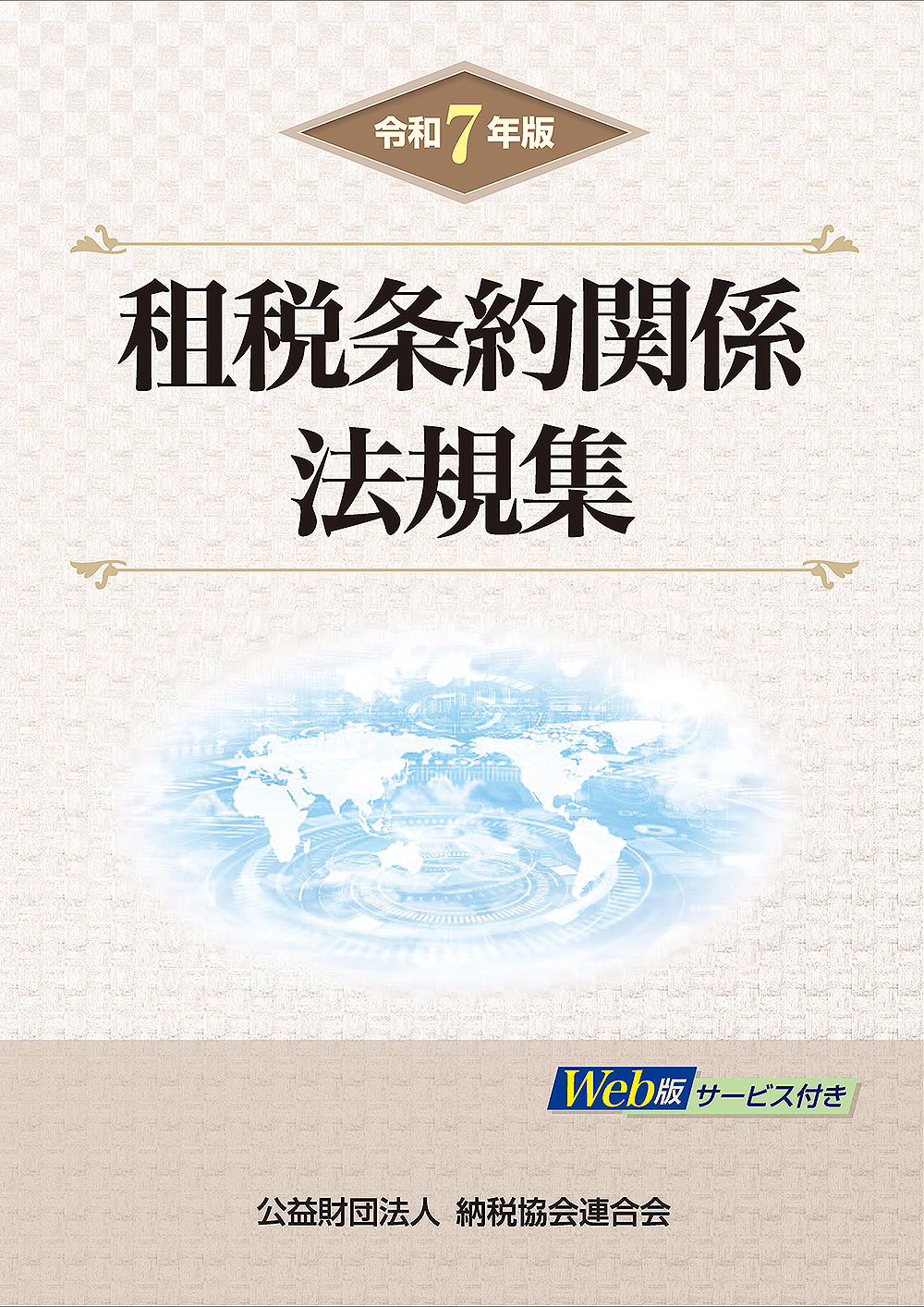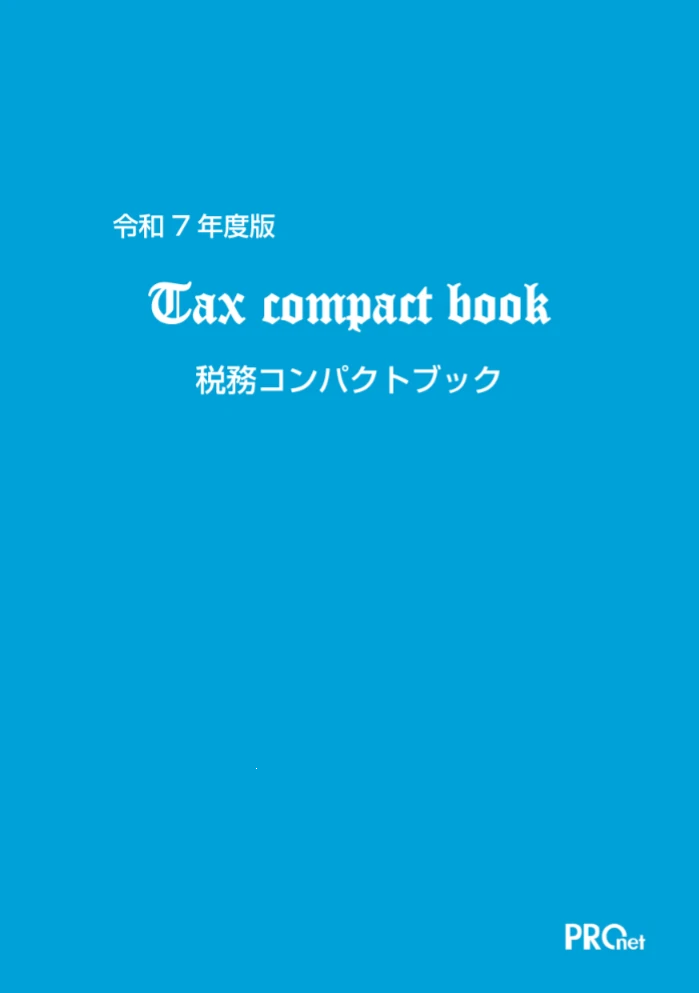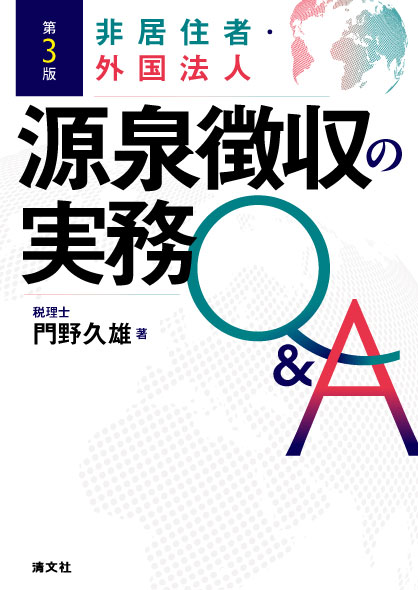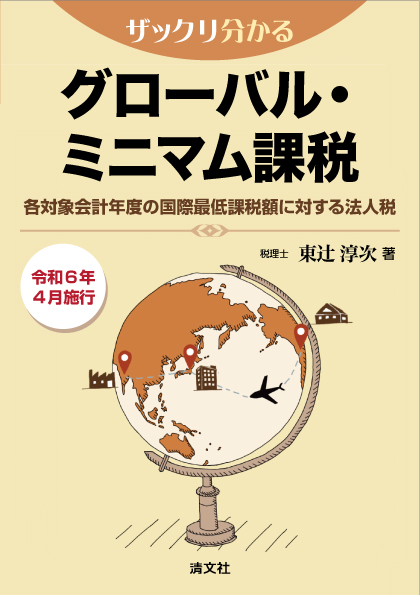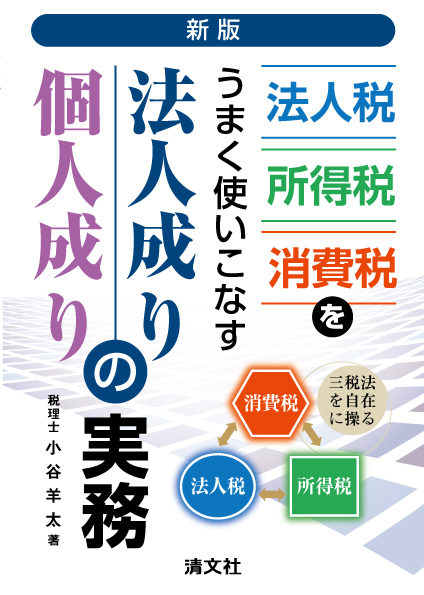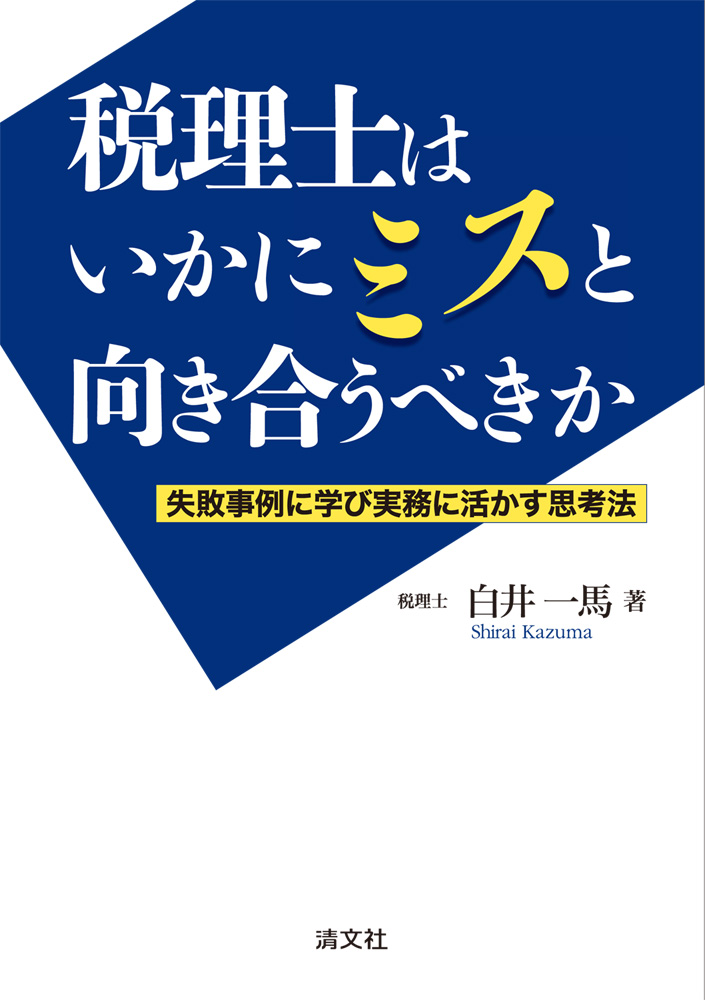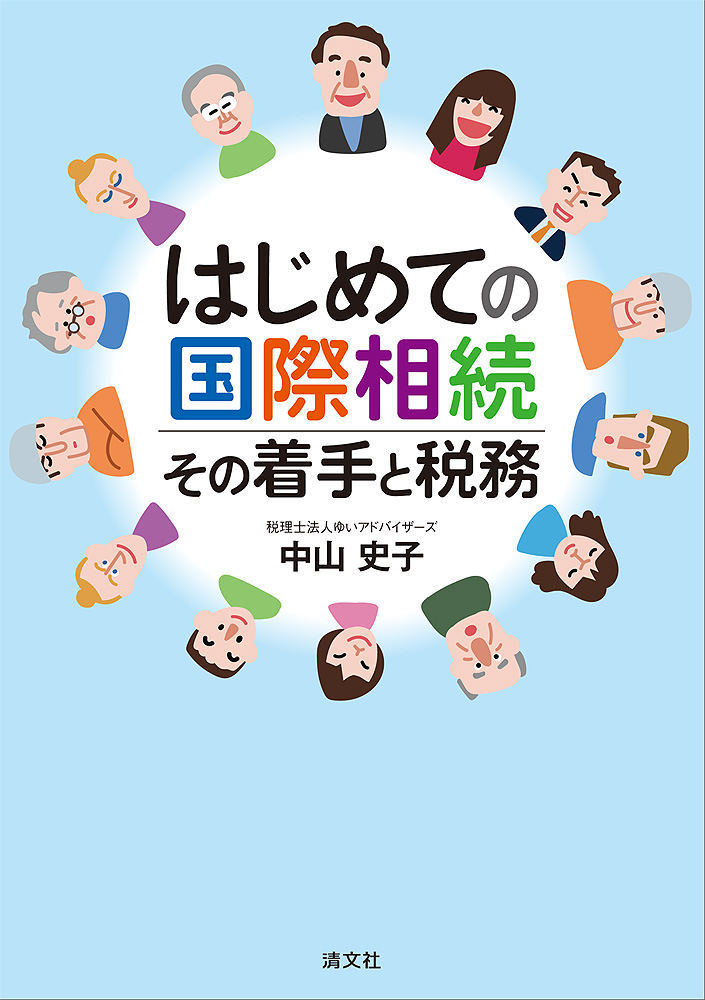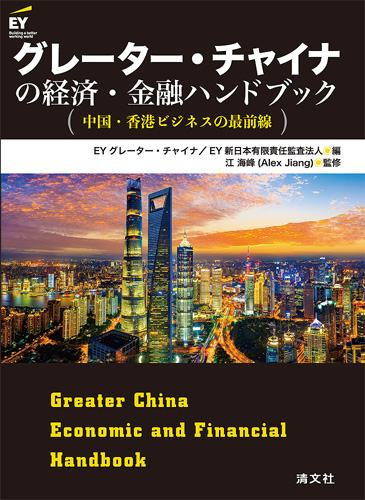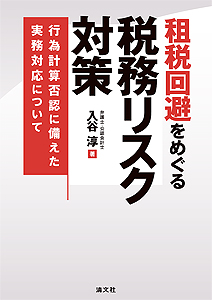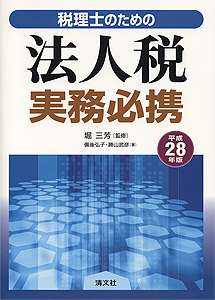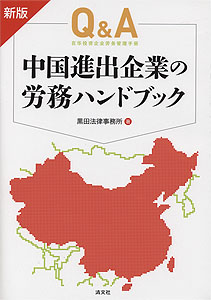国際課税レポート

【第1回】
「実施段階を迎えたOECD国際課税改革のゆくえ」
税理士 岡 直樹
(公財)東京財団政策研究所主任研究員
グローバルミニマム課税(国内法)とAmount A(多国間条約)
令和6年4月以降に開始する事業年度から、令和5年度の税制改正で導入された「国際最低課税額に対する法人税」(グローバルミニマム課税)のうち「所得合算ルール」が適用される。これは、子会社の実効税率が15%未満の巨大多国籍企業に対し、税負担率が15%に達するまで追加課税を行う制度だ。子会社の利益を親会社で合算して課税する点で、タックスヘイブン対策税制に似ているが、目的(法人税率引下げ競争に下限を設ける)や仕組み(税率は法人税23.2%・地方法人税10.3%などでなく、15%までの追加課税を行う)が異なる。
グローバルミニマム課税は、2021年10月にOECDで140ヶ国あまりが合意した「2つの柱による国際課税改革」(いわゆるBEPS 2.0)の第2の柱の措置で、連結売上が7.5億ユーロを超える多国籍企業が対象だ。日本では約900社が該当する。各国が国内法を立法して施行される。
国際合意のもう1つの柱は、契約締結権や物理的な拠点がなくても、多国籍企業の連結利益の一部(10%を超える部分の1/4)を定式配分し、市場国で課税することを可能にする「新課税権」(Amount A)の創設だ。売上高200億ユーロを超える巨大多国籍企業が対象で、グローバルに約100社が該当すると言われている。
こちらは新しい多国間条約の締結が必要だ。署名時期は2度延期されたが、OECDは昨年12月に2024年3月までに条文を確定し、6月までに署名式を行う予定であると発表している(その後、3月末の期限までに公表はない)。
これらの新しい制度の特徴は、課税所得を連結ベースで捉える点だ。これは、グループ企業を個別のエンティティとして扱う従来の制度と異なる。
デジタル経済における課税権の配分
デジタル経済の下、多国籍企業や知的財産の存在感が増している。また、情報化及びIT化の進展により、格差や競争など、市民にとって身近な問題に構造的な変化が引き起こされている。
2013年に開始されたBEPS(Base Erosion and Profit Shifting)プロジェクトの背景にはこうした変化があった。デジタル経済から生じる税務上の課題への対応策についての検討は、解決が最優先されるべき課題だったはずだ。
しかし、デジタル経済で成功している多数の巨大テクノロジー企業を擁する米国にとっては、課税ルールの現状変更は自国企業への税負担増に直結するため、消極的だった。一方、ユーザーや市場を有する欧州諸国は、市民の声もあり、制度がデジタル経済に追いついていないことから生じる課税もれを放置するわけにはいかない。
意見の隔たりが大きいため、2015年のBEPS最終報告書では、デジタル経済における税務上の問題を2020年までの課題として残し、各国が既存のルールに反しない範囲で独自の措置を導入することを容認する形で終わらざるを得なかった。
デジタルサービス税の広がりと2つの柱による対応策
国際合意を巡る議論が進展しないことに業を煮やしたフランス(2019年)、イギリス(2020年)を含む欧州各国はデジタルサービス税(DST)の導入を開始した。この税は2~3%の税率で、原価や費用控除を考慮せずに売上全額に課税する売上税である。国際的な合意に基づかないので、内容は各国バラバラだ。
一方、OECDは、デジタル経済における課税権の配分問題に対応するため、2018年に中間報告書をまとめ、その後「2つの柱による対処案」(BEPS 2.0とも呼ばれる)の検討を開始した。
政治的な焦点となったのは、市場国での課税を可能にする「新課税権」(Amount A)の設計だった。アメリカの立場を考慮し、テクノロジー企業だけを対象としないよう、消費者向けビジネスや自動化されたデジタルビジネス(例えばクラウドサービス)を対象にするなど、工夫が凝らされ、2020年の合意を目指して精力的な議論が行われたことと思う。
しかし、2019年12月、トランプ政権当時の米国のムニューシン財務長官は、多国籍企業に対する連結利益の定式配分を強制する「新課税権」(Amount A)については、納税者の広い支持(米議会での承認を指すだろう)を得ることができないため、企業の選択制(セーフハーバー)で導入すべきだと提案した。
この提案は、条約が米国議会の承認を受けなければ効力を持たないという現実を踏まえたものであり、一理あるが、欧州諸国はこの提案を受け入れなかった。セーフハーバー制度では多国籍企業への課税の決め手にならないと見ていたためだろう。
米国議会の反発
2021年1月に発足したバイデン政権は、インフラ投資等に必要な財源を確保するために法人税の増税を含む政策を打ち出し、OECDにおける国際課税議論でもリーダーシップをとるようになった。政権はグローバルミニマム課税を推進し、法人税率引下げ競争に終止符を打つことで、国内での増税のための環境を整えようとしたためと推察する。
しかし、現時点において、多国間条約も、米国におけるグローバルミニマム税の導入も、米国議会の承認が得られる見通しは立っていない。背景には、2022年の中間選挙後に下院の多数派となった共和党と、国際交渉にあたっている民主党政権下の財務省との間で調整が取れていないことがある。
2023年9月には、下院歳入委員会議員団がOECDやドイツを訪問し、米国はOECDの国際課税改革を支持しないとわざわざ申し入れている。さらに、下院歳入委員会の共和党議員は、グローバルミニマム課税のための3つの措置の1つである「UTPR」を採用する外国の企業や富裕層に対して、税率を最大20%引き上げる報復的な課税を行う法案を提出するなど、強硬な姿勢を示している(日本は現時点でUTPRを導入していない)。
複雑で税収を生まない制度という指摘
米国内で15%のグローバルミニマム税に対する議会の支持が広がらない背景の1つとして、その複雑性(合計数百頁の文書)と税収を生まないことへの批判が挙げられる。
2023年6月に米議会スタッフが公表した試算によると、他国がグローバルミニマム課税の立法を進めた場合、米国が同様の立法を行っても10年間で565億ドルの損失が見込まれ、米国が立法を行わない場合は1,220億ドルの損失になると見積もっている。
日本では、令和5年度の税制改正でグローバルミニマム課税のうち所得合算ルールを導入したが、この改正からの税収増は計上されていない。新しい制度なので技術的に見積りが困難であるほか、各国がグローバルミニマム課税の一類型であるQDMTT(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)を導入することで、日本での合算課税可能な金額が生じないと考えたのかもしれない。
官・民の租税専門家が参加する国際的な集まりであるIFA総会(2023年10月)では、パネリストの弁護士から、税収に結びつかないのに複雑な事務作業の負担を企業が負うことに割り切れない思いを持つ声も聞かれた。
多国籍企業大国日本と2つの柱による解決策の負担
OECDによると、2019年時点で売上が7.5億ユーロを超える巨大多国籍企業は世界で約7,600社存在し、国別に見ると米国が1,759社でトップ、次いで日本が904社、中国が691社、ドイツが419社、英国が399社と続いている。資源や市場が限られている日本は、米国に次ぐ世界第2位の多国籍企業大国でもある。
多国籍企業は既に多くの情報提供義務を負っており、コンプライアンスコストは追徴課税と同等、あるいはそれ以上の影響を競争条件に与えている。米国がグローバルミニマム課税に参加しそうにない現状では、日本企業の事務負担が競争条件に与える影響に対して敏感になる必要があるだろう。
OECDの多国間条約関連文書及びグローバルミニマム課税に関連する文書は、合計1,000ページにも及ぶ巨大な文書だ。正確な執行と納税のためには、これらを理解する必要がある。OECDの議論が簡素化に十分な注意を払っていないと感じられることは、どのような理由があれ、残念というほかはない。
グローバルミニマム課税のための最初の確定申告書提出期限は2026年9月だが、OECDの議論は進行中であり、制度には変更が加えられる可能性がある。新制度が長期的に安定するためには、事務負担の軽減がカギとなりそうだ。
先に述べたように日本は多国籍企業大国だ。事務負担の軽減やコストのデータを制度設計にフィードバックし、制度の簡素化を求めていく責任があるだろう。
(了)
「国際課税レポート」は、毎月第2週に掲載されます。