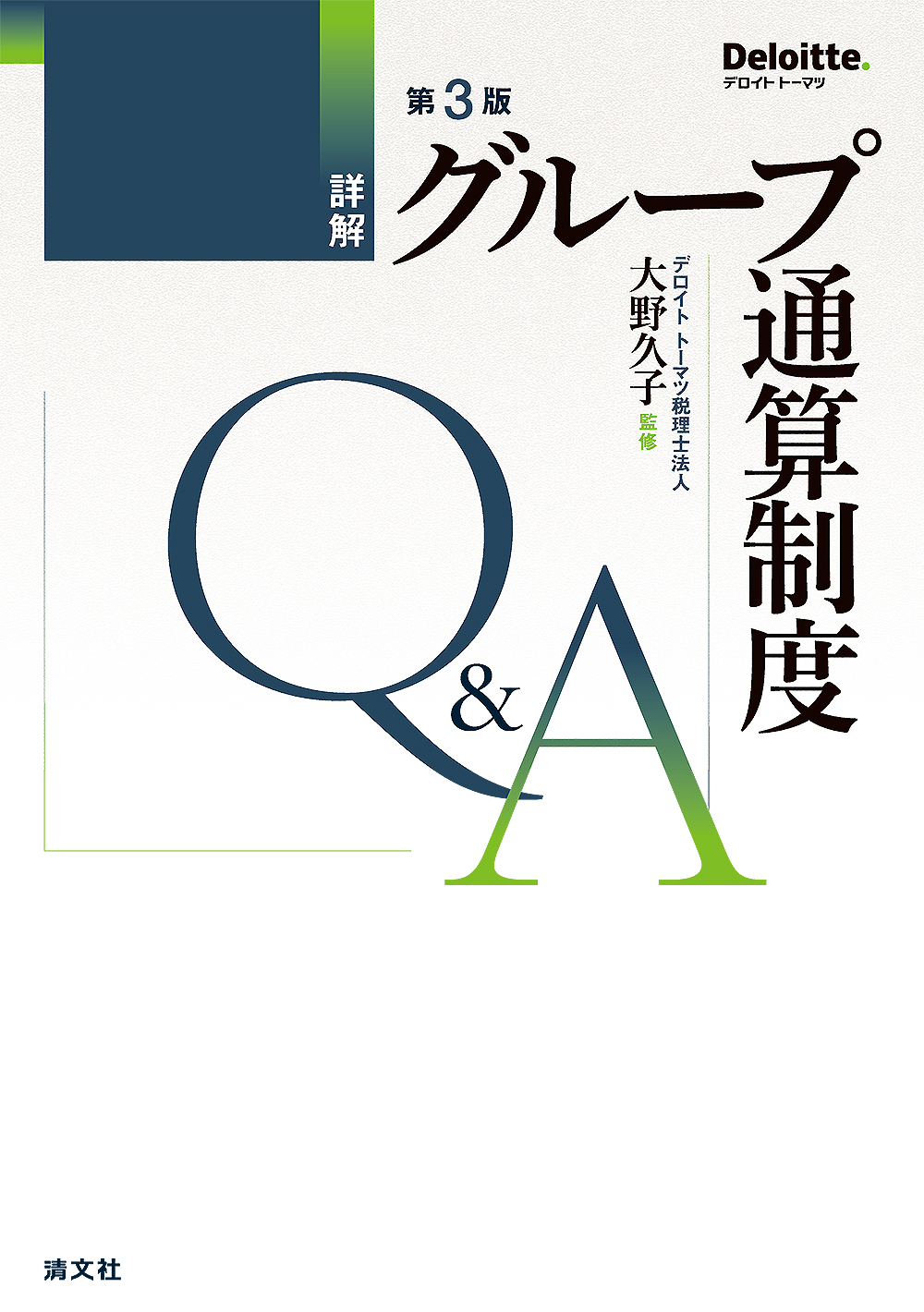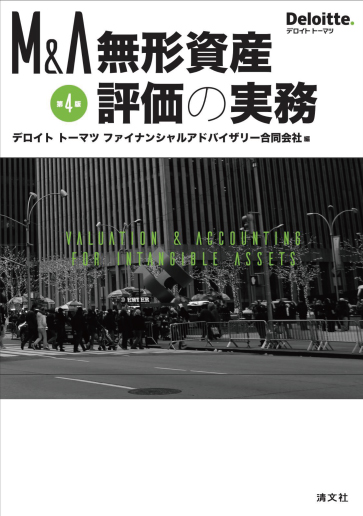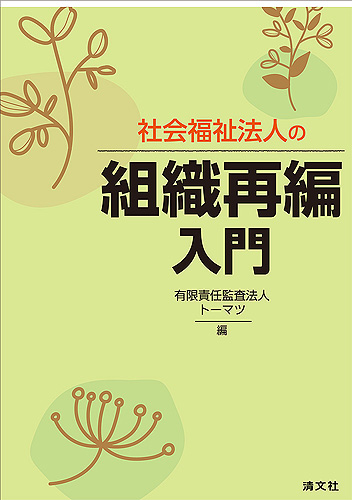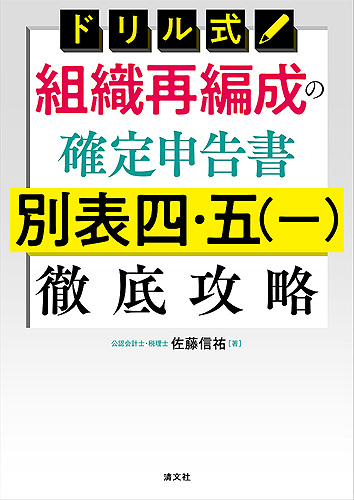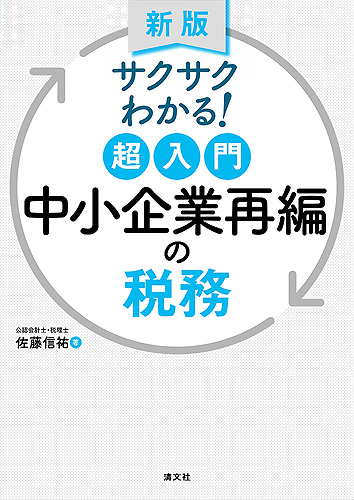組織再編時に必要な労務基礎知識
Q&A
【Q1】
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
【A】
労働契約の承継
株式交換等の労働契約の承継を伴わない組織再編を除き、組織再編後の組織体制を踏まえて、どの労働契約を承継するか、また、労働契約を承継するにあたり法的に必要な手続きはどのようなものがあるかを事前に確認し、整理しておく必要がある。
労働契約の承継を伴う組織再編には、合併、事業譲渡、会社分割があるが、例えば、会社分割のケースでは、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」に基づく手続きが必要となり、その手続きを実施するにあたっては一定の期間が必要になる。
また、例えば、営業エリアが重なる2社が合併するケースでは、営業所等の統廃合が行われ余剰人員が生じる可能性がある。この場合には、組織再編前に人員削減を行う選択も考えられ、いわゆる整理解雇の4要件に照らして早い段階から検討を重ねて準備する必要がある。
このように組織再編時には労働契約の承継に関して実施すべき事項が様々に考えられることから、事前に対応すべき事項を洗い出し、具体的な実行スケジュールを策定して進める必要がある。
組織再編後の労働条件
労働契約の承継を伴う組織再編においては、組織再編後の労働条件をどうするかを検討しておく必要がある。
例えば、2社が合併するケースでは、主に次の3つの対応が考えられる。
① 当面はそれぞれの会社の労働条件をそのまま適用しダブルスタンダードで運用する。
② どちらか一方の会社の労働条件に統一して運用する。
③ 両社の異なる労働条件を踏まえて新しい労働条件を設定して運用する。
上記のうち①を除き、まずは、両社の労働条件を比較し、何がどの程度異なるか、労働条件の差異を分析する必要があり、この差異分析を踏まえて組織再編後の労働条件を検討することとなる。さらに、組織再編後の労働条件をこれまでよりも低下させる場合には、不利益な変更に当たるため、さらなる検討が必要となる。
例えば、所定労働時間が次の通り異なる2社が合併する場合を考えてみよう。
A社 1日の所定労働時間:7時間15分
B社 1日の所定労働時間:7時間00分
合併後の1日の所定労働時間についてA社を基準に7時間15分とする場合、B社の従業員からみると1日の所定労働時間が15分延長されることになり不利益な変更となる。よって、この不利益な変更が可能かどうかの検討が必要となる。
労働条件の不利益変更
労働条件を不利益に変更する方法としては、①個別に合意する方法(労働契約法第8条)、②就業規則を変更する方法(労働契約法第10条)、労働組合がある場合には③労働協約(労働組合と書面で取り決めしたもの)を締結する方法(労働組合法第16条等)があるが、組織再編時には、労働契約法第10条を踏まえて、「労働者の受ける不利益の程度」、「労働条件の変更の必要性」、「変更後の就業規則の内容の相当性」、「労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情」に照らして合理的なものとなるよう対応を検討することとなる。
◆労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
先のB社の従業員の1日の所定労働時間が15分延長される例では、不利益の程度を緩和するため、その延長時間に相当する月例給与の増額や所定休日の追加等の対応が考えられる。
なお、組織再編時には、様々な制度が変更となり、有利に変更される項目と不利益に変更される項目の両者が混在することが多いため、実務的には、ひとつひとつの項目ごとに対応を検討するのではなく、全体的なバランスをみつつ緩和措置等の対応を検討することとなる。
(了)
「組織再編時に必要な労務基礎知識Q&A」は、毎月第3週に掲載されます。