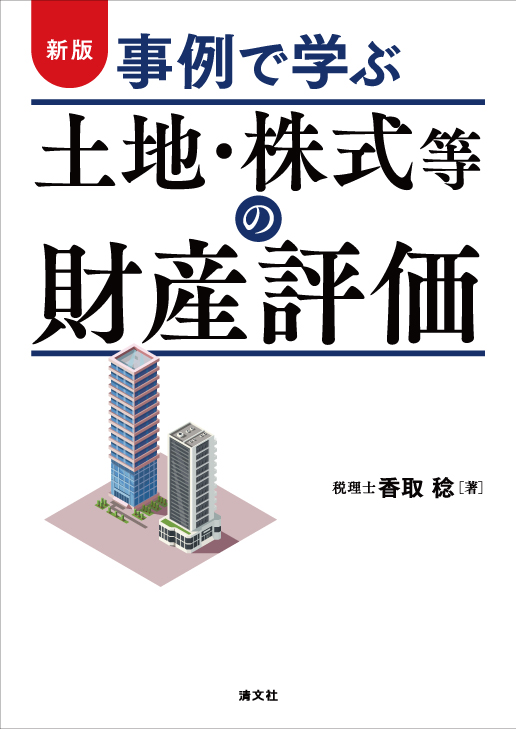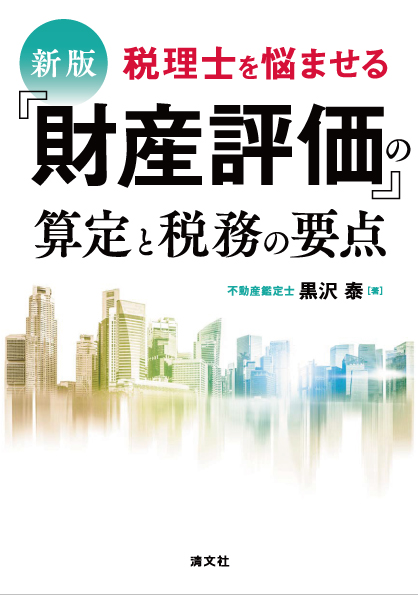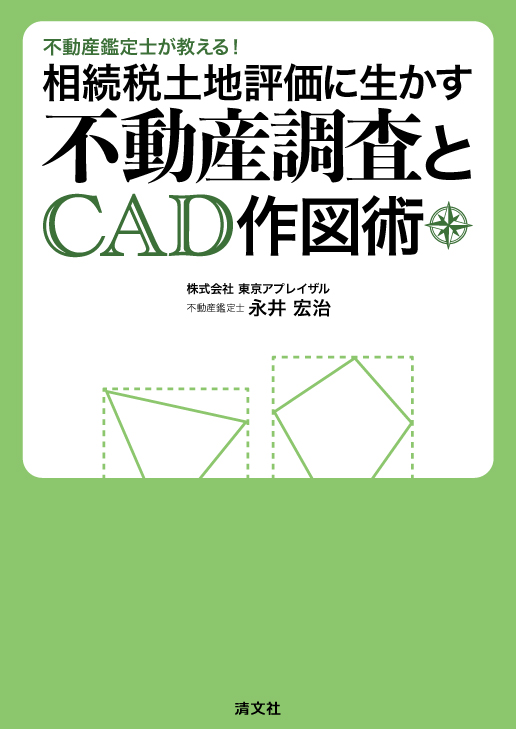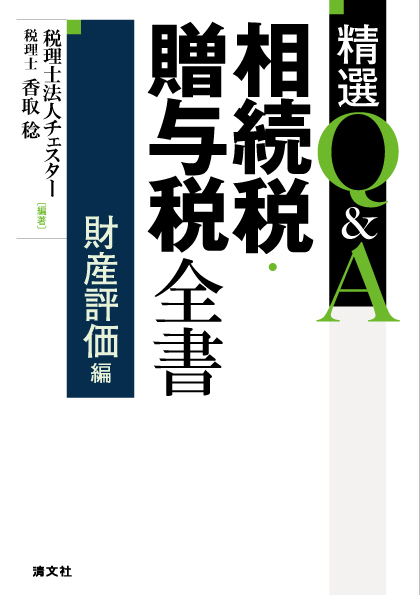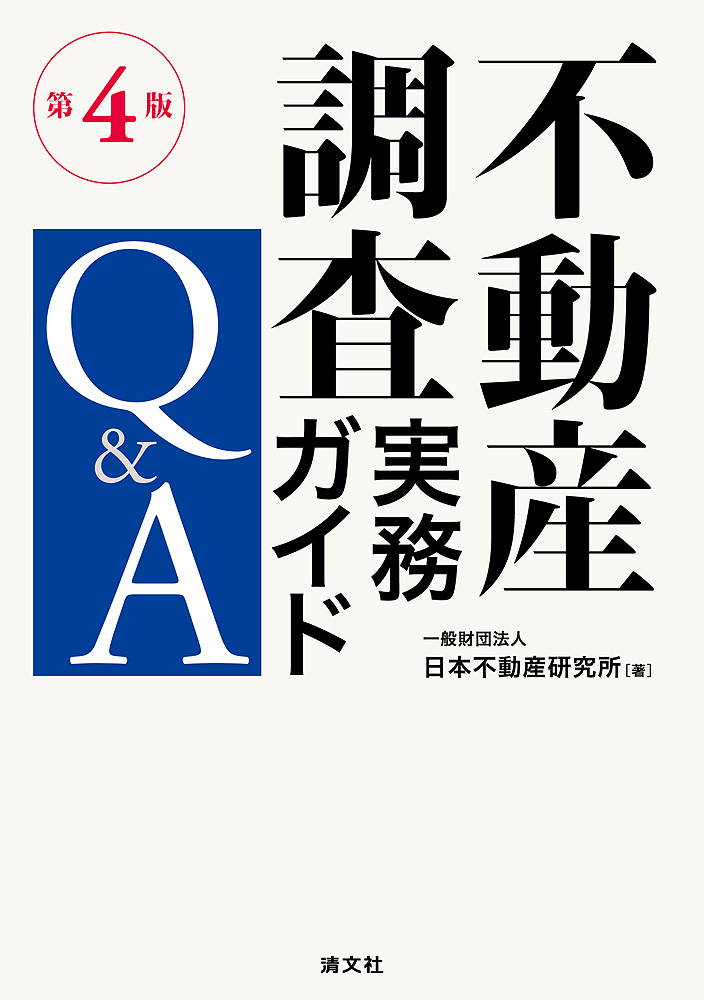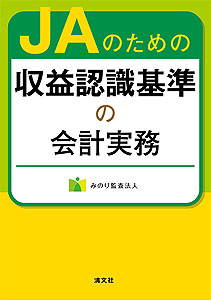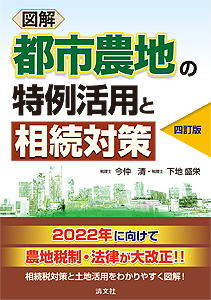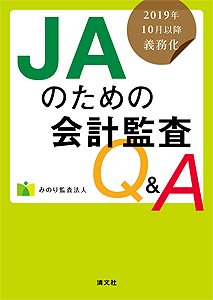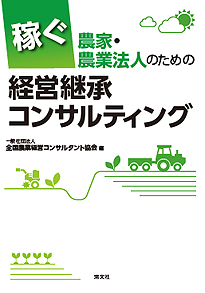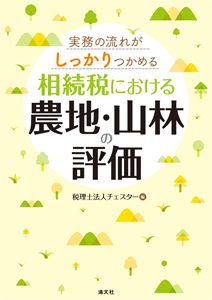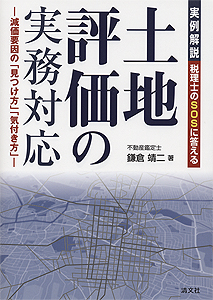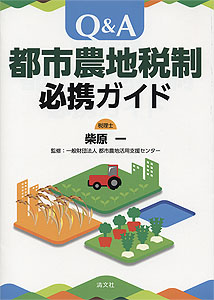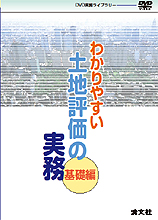税理士業務に必要な
『農地』の知識
【第8回】
「市民農園とその税制」
税理士 島田 晃一
今回は市民農園について、その概略を説明する。市民農園は特に都市部に住む人の農業体験の場として近年需要が高まっている。以下では、市民農園の概略に加え、市民農園として提供した土地の相続税評価などの税務についても解説していく。
1 市民農園とその開設方法
市民農園とは、サラリーマンなどが、レクリエーションとしての自家用野菜・果樹などの栽培、農業体験学習などの目的で利用する区割りされた小規模農地をいう。
市民農園を開設するのは、主として地方公共団体や各地域のJAである。ただし、農地所有者が自ら開設したり、農地を所有していない法人やNPOが開設する場合もある。
市民農園の開設形態は、「特定農地貸付法」による開設、「市民農園整備促進法」による開設、「農園利用方式」による開設の3つがある。平成28年度末の段階では、特定農地貸付法による開設件数は約3,700件、市民農園整備促進法による開設件数は約500件である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。