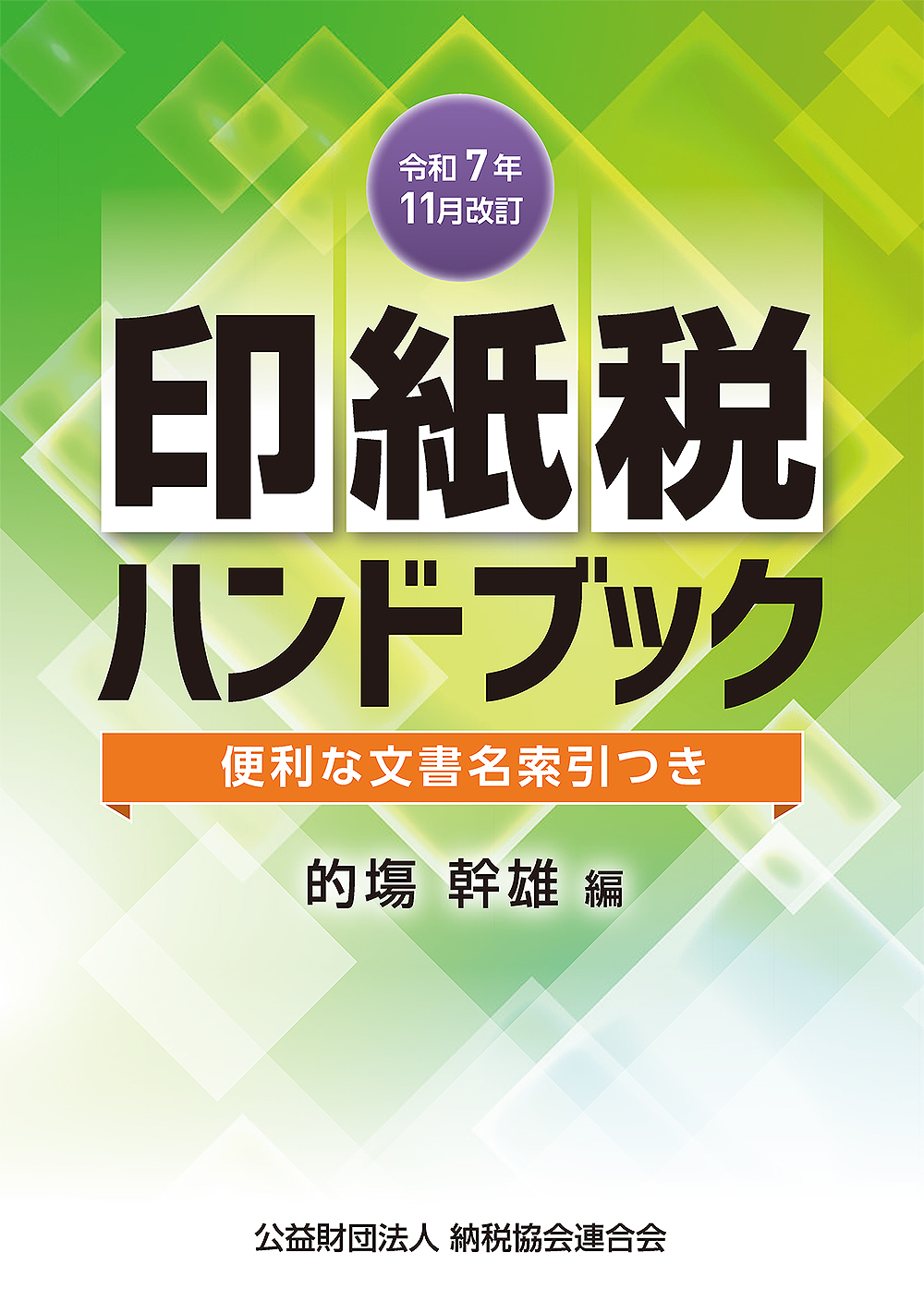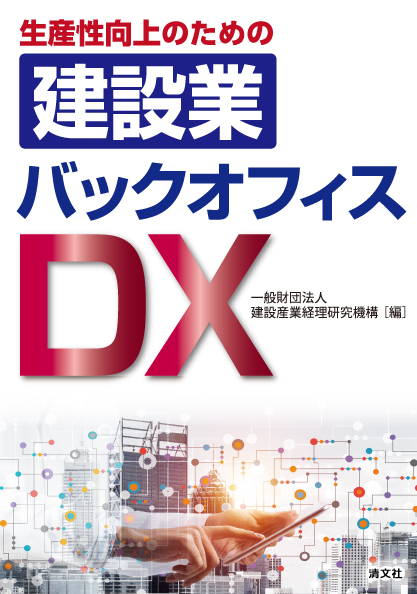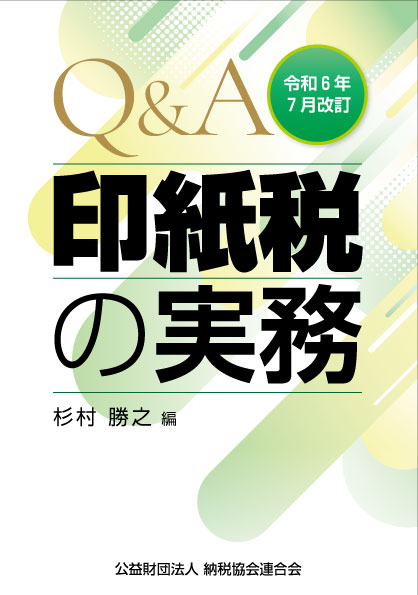不動産の電子契約化に関する改正ポイント
【第1回】
「不動産業界における電子化の現況と改正の概要」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
司法書士 奥村 圭祐
1 はじめに
令和3年5月12日、社会のデジタル化を促進するために関連する法律の改正を行う「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「デジタル改革法」という)が成立し、同月19日に公布された。デジタル改革法では、個人情報の取扱いルールの整備や、マイナンバーを活用した行政手続の効率化、各種の手続において電子化を進めるための押印・書面交付義務の廃止などを改正の内容としている。
原則的な施行日は令和3年9月1日とされているが、不動産契約等の電子化を可能とする宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という)及び借地借家法の改正に関する部分は令和4年5月18日に施行された。本改正は不動産会社や不動産オーナーに与える影響も大きく、顧問を務める税理士・公認会計士としても、内容を把握しておく必要があるだろう。
本稿は、デジタル改革法による宅建業法及び借地借家法の改正を中心に、税理士等が知っておくべきポイントについて、できるだけ簡潔に解説を試みるものである。
2 不動産業界における電子化の取組み
不動産業界では、トラブルを防止する趣旨から、宅建業法等により重要事項説明書や売買契約書などの書面の作成や押印が義務付けられてきた。こうした厳格な取組みが不動産業界の健全性の向上と、取引の安全に寄与してきたことは確かであるといえる。一方、不動産取引の現場では、生活にITの活用が浸透していくなかで、変化に対応していくため、書面や押印を前提とした規律を見直すべきではないかという機運が高まっていた。
例えば、東京在住の会社員が大阪に転勤になり、大阪の賃貸物件を探す場合、インターネットを利用して探すことが大半だと思われる。こうした場合に、関連する手続をインターネット上で完結できれば、顧客の利便性が格段に向上することになる。このような時代の変化を背景に、不動産業界では様々な取組みを進めてきた。
3 IT重説の導入
不動産会社などの宅建業を営む者は、不動産の売買や賃貸の媒介等を行うに際して、重要事項説明書を交付して説明を行う必要があるとされている(宅建業法第35条)。重要事項の説明は、対面によることが原則とされていた。
そこで、不動産業界ではまず対面原則を見直し、オンライン上での重要事項の説明(IT重説)を可能とするために、平成27年から社会実験を実施してきた。賃貸取引に関するIT重説については平成29年10月から、売買取引に関するIT重説については令和3年3月から本格運用されている。
IT重説はあくまで重要事項の「説明」をオンライン上で可能とするものであり、別途書面として「重要事項説明書」を作成し、顧客に交付する必要があった。オンラインによる不動産の取引を促進させるためには、こうした書面の交付や押印義務を見直す必要があり、今回の改正で、不動産取引のオンライン化が促進されることとなった。
4 デジタル改革法による改正点
デジタル改革法による主な改正点について、宅建業法に関するものと借地借家法に関するものに分けてまとめると、次の通りである。
(※1) 実務上、売買契約書や賃貸借契約書に宅建業法第37条で求められる情報を記載している。
(※2) 書面による場合でも押印は不要。
(※3) 書面により媒介契約書を作成した場合には、記名押印は必要となる。
重要事項説明書などを電磁的方法によって作成し提供する場合には、交付を受ける相手方の承諾が必要である。具体的な提供方法や承諾を得る方法については、電子メールやウェブページ上でのやりとりによるなど、国土交通省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」において詳細が示されている。
【借地借家法の主な改正点】

借地借家法の改正は、一般の不動産オーナーにも直接影響が及ぶ改正である。一般定期借地契約など、書面によることが必要とされてきた契約が、電子契約サービスなどの電磁的方法により行うことが可能となった。電磁的方法によることで契約書に貼付していた印紙代の節約にもつながるため、負担が大きい不動産オーナーから相談が寄せられることも考えられる。
定期建物賃貸借契約に際して求められる事前説明書の交付については、宅建業法の各書面と同様に事前の承諾を得て、電磁的方法により提供することができる。
なお、事業用定期借地権(借地借家法第23条)の契約については、今回の改正の対象ではないため、従来通り「公正証書」により作成する必要がある。
次回は不動産契約の電子化を進めていくためのポイント等について解説を行う。
(了)
次回は6/2に掲載されます。